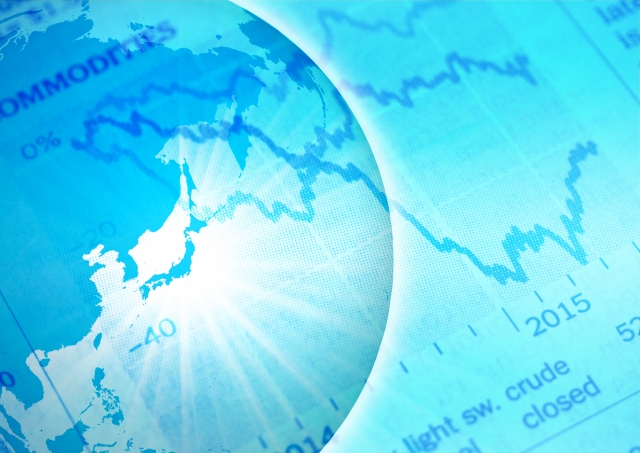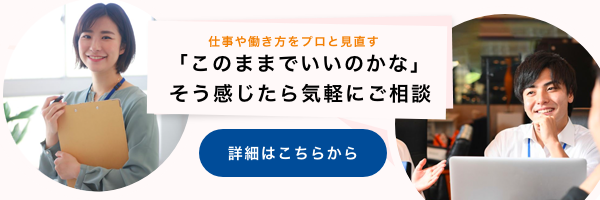ゼネラリストとスペシャリストどっちが有利?今後のキャリアの考え方
入社して2~3年経ち、仕事や会社に一通り慣れてくると、今後のキャリア形成について考えるようになります。その時に、「ゼネラリストとスペシャリスト、将来どちらがいいのだろう?」という悩みがでてくることも。
「スペシャリストのほうが、転職でも『潰し』がきく」「これからは、深い知識を持ったゼネラリストが求められる」など情報は様々です。「結局、どっち?」と迷ったら、こんな視点で考えてみませんか。
「ゼネラリスト」を選んだ場合のキャリアパスは?
ゼネラリストとは、複数の分野での業務経験と、それにまつわる知識を持つ人を指します。2~3年で異動を繰り返す大企業の人材育成制度では、このようなゼネラリストが育成される傾向があります。
会社の意向としてゼネラリストを養成するのではなく、キャリアパスとしてスペシャリストかゼネラリストか選べる企業もあります。いずれにしても、ゼネラリストを選んだ場合は、複数の業務領域で幅広く経験を積んでいくことになります。
たとえば文系職種では「営業→マーケティング→事業企画→新規事業立ちあげ」のように全く異なる領域へ異動を繰り返すようになります。また理系職種では、現場のエンジニアからチームやプロジェクトをまとめる立場になり、技術力よりもマネジメント力・プロジェクト推進力を磨くことを重視していくようになります。
他部署への異動でも、「商品企画→広告宣伝→販売促進」のように、関連する領域で異動を繰り返す場合は、「ゼネラリスト」というよりも「マーケティングのスペシャリスト」と言えるでしょう。同じように法人営業でも、「大企業へのルート営業→中小企業への新規開拓営業→大手企業への新規開拓営業」という場合も、「営業のスペシャリスト」と言えます。
「ゼネラリスト」に向いている人はどんな人?
ゼネラリストは、プロジェクトや事業を成功させるために、若手メンバーや内部・外部の協力者、スペシャリストのまとめる調整役・推進役となります。
複数の関係者をまとめて、プロジェクトや事業を推進するには、幅広い業務経験で培った広い視野と課題発見力、課題解決力、調整力、交渉力、コミュニケーション能力などが必要となります。
そのためゼネラリストは、人と話をしながら問題解決するのが好きな人や、周囲の人を動かして自分の思い描く事業やプロジェクトを推進していきたい人に向いています。一方で、人との交渉や調整が苦手な人や、自分の得意分野に集中したい人には、あまり向いていません。
「スペシャリスト」を選んだ場合のキャリアパスは?
一方スペシャリストとは、特定の分野に高い専門性を持ち、その分野に特化した仕事を行う人のことです。
技術系職種の場合は、いずれも専門性の高いスペシャリスト色が強くなりますが、一般企業の文系職種なら、人事や経理、総務、法務などの管理部門が該当します。これらの部署に配属となった場合、その部署で深い知識を身につけて「事務系スペシャリスト」のキャリアを歩むことが多くなります。
また前述のようにマーケティングや営業、品質管理や生産管理などの限られた職種内で様々な経験を積んだ人も、「スペシャリスト」です。
システムエンジニアは、技術の進化とともに専門性も細分化しているため、得意とする技術(アプリケーション、ネットワーク、データベース、システム管理など)、開発するシステムの内容(販売管理、生産管理、財務会計など)、担当業界(金融業界や製造業、飲食業界など)に特化した経験を積み重ねることで、「●●ならアイツ」というような専門性を身につけていくことになります。
「スペシャリスト」に向いている人はどんな人?
スペシャリストには、「特定分野に関する深い知識と経験」が必要とされ、常に最新の技術や業界動向、他社事例などの情報にキャッチアップしていることが求められます。
そのため、新しい技術や知識を学ぶことが好きな向学心の強い人や、自分の興味のある分野や好きなことを深く追求したいタイプには向いています。専門分野の知識や経験を、周囲にわかりやすく伝えられるコミュニケーション能力もあれば、さらに活躍の場は広がります。
自分の専門知識やスキルを高めることに喜びを感じる場合は、スペシャリストの道を選ぶほうが仕事の満足感を得やすいと言えます。
市場で求められるのはゼネラリスト?スペシャリスト?
「転職を考えるなら、専門性の高いスペシャリストのほうが転職しやすいのでは?」という認識もあるようですが、そのようなことはありません。
専門性の高いスペシャリストはもちろん、ゼネラリストの持つ課題発見力、課題解決力、調整力、交渉力、コミュニケーション能力なども転職市場でも十分評価されます。こうしたゼネラリストは、20代であれば幹部候補生として、30~40代であれば管理職の戦力として求められるのです。
ゼネラリストもスペシャリストもそれぞれに求人ニーズがあります。「転職しやすさで選ぶなら」という視点では、どちらも変わらないのが現実です。
どちらを選ぶかの決め手は市場性よりも自分の志向性
また、管理職はゼネラリストというイメージがあるかもしれませんが、最近ではプレイングマネジャーとしてスペシャリストでもマネジメント業務が付加されることも多くなっています。さらに、スペシャリスト部門を統括する立場になることもあり、スペシャリストも管理職になる可能性はあります。
ゼネラリストかスペシャリストか。どちらを選んでも、自分の目指す方向をきちんと意識して経験を積んできたのなら、転職市場でも企業からも必要とされる人材となります。
「転職しやすいか、潰しがきくか、出世しやすいか」という市場性や、出世や待遇という視点ではなく、ぜひ「どちらの働き方を楽しいと感じ、やりがいを感じるか」というあなたの志向性で決めてください。

上司と合わないのがストレス…楽になる考え方&うまく付き合う方法
合わない上司の下で働き「毎日がストレスの連続…」という方は多いのではないでしょうか。 しかし、考え方や接し方を少し変えるだけで、合わない上司との付き合いが楽になることがあります。 この記事では、上司と合わないと悩んでいる方に向けて、ストレスを軽減させる考え方や上手な付き合い方を解説します。 ストレスになる!合わない上司の特徴 まずは、多くの部下から「合わない」と思われる上司に多い特徴を紹介します。 自己中心的 日や気分で言うことが変わる、嫌な仕事や責任を押し付けてくる、部下の手柄を横取りするなど自己中心的な上司は、部下から合わないと思われても仕方ありません。 自己中心的な上司と一緒に働くと、意味不明な指示や理不尽な叱責はしょっちゅう。部下は上司から日常的に振り回されるため、非常にストレスがたまるでしょう。 また、自己中心的な上司は自分の能力や実績を過大に評価する傾向があり、自分には甘いのに他人に厳しいのも特徴です。 古いやり方や自分のスタイルにこだわる こだわりが強く自分のスタイルを周囲に押し付けるのも、部下から合わないと思われる上司の特徴です。 上司が自分のスタイルにこだわりすぎると、仕事の成果に直結しない作業に膨大な時間が使われたり、あえて非効率なやり方が選択されたりします。業務がスムーズに進まないので部下はストレスがたまり、次第に仕事に対するモチベーションまで失くしてしまうでしょう。 このタイプの上司は考え方がアップデートできておらず、未だに部下に長時間労働や休日出勤を強いるケースも多いです。 結果や個人的感情で部下を評価する 人事評価は、普段の勤務態度や周囲との協調性、努力の継続など、成果以外のポイントにも注目して総合的に判定する必要があります。 結果を数字で表しにくい職業もあるため、数字だけを見て判定を下しても「正しい評価」とはいえません。 しかし、明確な評価基準がない会社や上司の権力が強い会社では、部下が出した数字、もしくは上司の個人的な感情で評価が決まってしまう場合があります。 頑張っているのに上司が正当に評価してくれないとなれば、部下は上司に不満を持ち「合わない」と感じてしまうでしょう。 能力・やる気不足 上司の中には勤務歴の長さだけで出世して、能力が伴っていない人もいます。他にも、もともとは仕事を頑張っていたのに、上司になってからは立場に胡坐をかいて仕事をサボろうとする人も…。 能力・やる気不足の上司の下で働くと、成長に必要な経験を積ませてもらえなかったりトラブルが起きてもサポートしてもらえなかったりするので、部下はストレスを感じます。 また、能力ややる気が低い「かっこよくない上司」が身近にいると、部下は将来に対する希望が持てません。うまくキャリアプランが描けず、仕事を頑張る意味がわからなくなる場合も多いです。 人間性に問題がある 人間性に問題がある上司は、多くの部下から「合わない」と思われるでしょう。 たとえば、些細なことで感情的になる、暴力で部下を従わせる、他人の人格を否定するような発言をするといった上司は、もはや「合う・合わない」を定義する以前にパワハラに該当する可能性が高いです。 たとえ上司の仕事能力が高かったとしても、人間として尊敬できる部分がないため、部下は一緒に働いていて強いストレスを感じます。 明らかなパワハラ行為が認められる場合は、上司と無理に付き合おうとせず、さらに上の上司や然るべき機関に相談することが大切です。 上司と合わないのは自分が悪い可能性も… 自分が原因で、上司との関係が悪くなっている可能性もあります。上司と合わないと感じたら、一方的に上司に不満を募らせるのではなく、一度冷静に「自分にも悪いところはなかったか?」と考えてみましょう。 最低限のビジネスマナーがない 基本となるあいさつやお礼、業務に関する報連相などは、社会人として最低限身につけておきたいビジネスマナーです。このような最低限のビジネスマナーがない場合、上司から苦手意識を持たれ、それが「合わない」と感じる原因になっている可能性があります。 合わない上司を無意識に避けてしまい、あいさつや返事が疎かになるケースは珍しくありません。 しかし、たとえ合わない上司であっても一緒に働く以上は最低限のコミュニケーションが求められるので、一度普段のあいさつや報連相の頻度を見直してみましょう。 仕事のミスが多い 「上司が頻繁に怒ってくる」「小言が多い」と思っている人もいるかもしれませんが、上司が指摘・注意をするのは、あなたが業務上のミスを繰り返しているからではありませんか。もしもミスの繰り返しで上司から怒られているのなら、上司と合わない原因は自分にある可能性が高いです。 もちろん「ミスをした部下にはどんな怒り方をしてもいい」というわけではないため、注意の仕方によっては上司に原因がある場合もあります。 しかし、ミスが原因で上司との関係がギクシャクしているのなら、ミスをなくせば怒られなくなるので、上司との付き合い方を模索する前にミスを減らす努力が必要でしょう。 社内で上司の愚痴を言っている 上司に対する「合わない」という感情は自然と湧き上がることも多く、無理になくそうとしても難しいです。一緒に働いているとストレスがたまるので、たまには誰かに愚痴を聞いてもらいたいときもあるでしょう。 しかし、愚痴のはけ口に社内の人間を選ぶと、噂となって上司の耳にも入る可能性があります。 合わないと思っていることが上司に知られると、関係が悪化してより一緒に働きにくくなるので、社内で上司の愚痴は言わないほうが無難です。 合わない上司がストレスなら考え方を変えよう 合わない上司と一緒に働くとストレスがたまりますが、少し考え方を変えるだけで負担を感じにくくなる場合もあります。ここからは、合わない上司と働くときに大切にしてほしい考え方を紹介しましょう。 上司と仲良くなる必要はなし 職場は友達をつくる場ではないため、合わない上司と無理に仲良くなる必要はありません。「強い信頼関係を築かないと」のように思い詰めると、悪いプレッシャーとなってさらにストレスを感じてしまいます。 そもそも、異動や退職によって上司または自分が職場を去る可能性もあり、合わない上司との関係はあくまで一時的なもの。「仲良くならなくていい」「いつか離れられる」と考えると、少しは気が楽になるはずです。 反面教師にする 上司から嫌なことを言われた・された際には、反面教師にして学びを得るのもおすすめです。合わない上司を反面教師にすると、上司という「人」ではなく「行動」に目が向くようになります。 「人」に注目してしまうと「上司はひどい人だ!絶対合わない!」と感情がかき乱され、精神的負担になりやすいです。しかし、「行動」に注目すると「こんなことをしたら周囲の信頼をなくすんだな」のように俯瞰的視点を持ったまま冷静でいられるので、ストレスを感じにくくなります。 そもそも上司に期待しない 仕事ができて、人格者で、頼りがいがあって…のように上司に高い理想を持つと、ちょっとしたことで理想が打ち砕かれてストレスになります。 よって、合わない上司にはあえて「期待しない」と割り切るのも効果的。そもそも、上司といっても所詮は「自分より少し早く入社しただけの人」に過ぎず、人間なのでミスもすれば人間性が未熟なこともあります。 期待していないからと上司の存在を無視するのはいけませんが「上司なら~してくれるだろう」と期待を持たないようにするだけでも、ストレスから解放されることは多いです。 合わない上司とストレスフリーで付き合う方法 合わない上司とうまく付き合っていくためには、接し方にも工夫が必要です。ここでは、合わない上司との付き合い方を解説します。 笑顔で丁寧に接する 合わないからといって露骨に嫌悪感を出すのは、人として正しい行動とはいえません。また、嫌悪感を出されれば上司側も良い気持ちはしないので、さらに関係がこじれて悪化する恐れがあります。 合わない上司と接する際は、他の人と接する際と同様に、笑顔で丁寧な対応を心掛けましょう。 なお、後々「言った・言ってない」で上司とトラブルになるのを避けるため、大切な業務連絡は口頭で伝えるだけでなくメールのような証拠が残る形でも送っておくと安心です。 報連相を欠かさない 部下から合わないと思われる上司の中には、頼りがいのない上司もいます。「報告・連絡・相談をしても、大した答えは返ってこないかも…」と予想できてしまう上司には、報連相を省略したくなるかもしれません。 しかし報連相を怠ると、何かミスがあった際に「独断で動いたあなたが全て悪い」と判断される可能性があります。 実のある回答が得られないとしても、「一度は上司の判断を仰いだ」という実績をつくっておくことが大切です。 仕事はできるだけ正確にこなす 仕事でミスをすれば、合わない上司への報告や謝罪が必要になります。合わない上司とは一定の距離を保ったほうがストレスにならないので、自分のミスにより距離が近くならないように、仕事はできるだけ正確にこなしましょう。 また、正確性は一つの優れたスキルであり、「正確に仕事をしよう」という意識は自分を成長させます。 正確性を上げられれば合わない上司と良い距離感が保てるだけでなく、仕事の評価も上がる可能性があり、まさに一石二鳥です。 2人きりを避ける 業務上どうしても避けられない場面もありますが、可能な限り合わない上司と2人きりにならないようにしましょう。 2人きりになってしまうと、合わない上司から話しかけられたら絶対に自分が答えるしかありません。2人きりというのも相まっていつもよりも緊張しやすくなるので、そのぶんストレスも大きくなります。 3人以上だと他の人も答えてくれるため合わない上司との関わりが少なく済み、ストレスも軽くなるはずです。 スルースキルを発動させる 合わない上司とうまく付き合っていくためには、スルースキルが必須です。上司から嫌味を言われたり、業務に必要のないこだわりを押し付けられたりした際には、真に受けず受け流すほうがストレスになりません。 優しくてまじめな人ほど、上司の言うことを真剣に聞いて振り回されてしまいますが、理不尽な要求や悪意が込められた言葉などは、真摯に受け止めなくてもいいのです。 スルースキルが低い人は、「情報の取捨選択」を意識してみてください。業務に必要な話か否かを考え、必要ないと判断した場合には、最低限の配慮として相槌だけ打って深く気に留めないようにしましょう。 どうしても上司と合わないときの対処法 考え方や接し方を変えても、やっぱり上司と合わなくて辛い…という場合もあるでしょう。どうしても上司と合わないときはどうするべきか、対処法をお伝えします。 他の部署に異動を希望する どうしても上司が合わないなら、他部署への異動を希望するのも一つの手です。 異動願いは直属の上司に提出するのが一般的なので、その上司に対して合わないと思っている場合は出しにくいと感じるかもしれません。しかし、上司に何も知らせず他の人に異動願いを出すと不要なトラブルに発展する可能性があるので、まずは上司に提出してください。 なお、直属の上司が異動願いの受け取りを拒否するなら、さらに上の上司や人事部に提出して問題ありません。 転職を検討する 合わない上司と働いて毎日ストレスをため続けると、モチベーションの低下や健康を損なうリスクなどが大きくなります。 どうしても上司と合わないうえ、異動できる部署がない場合には、転職を検討してもいいでしょう。 しかし、次の職場でも合わない上司に当たる可能性はあるため、一時の感情で転職をするのは厳禁。また「上司と合わないから」という転職理由は面接官にマイナスイメージを与えやすいので、面接ではポジティブに言い換えてください。 キャリアコンサルティングを受ける 部署異動や転職は決断するのに勇気が必要なため、なかなか答えが出せずに悩んでしまう人も少なくありません。 そんなときは、キャリアコンサルティングを受けてみるのがおすすめです。 第三者に相談することで「上司が悪いのか、それとも自分が悪いのか」を客観的に判断してもらえます。「上司のタイプに合わせた接し方のコツ」「今転職すべきかどうか」などもアドバイスしてもらえるため、具体的な解決策が見つかりやすくなるでしょう。 悩みを話すだけでもストレス解消になるので、ぜひ気軽に相談してみてください。 合わない上司ともうまく付き合ってストレスを減らそう 報連相の相手として頻繁に関わる上司と合わないと、興味のある仕事でも楽しめずストレスを感じてしまいます。 しかし「苦手だ」「嫌いだ」とマイナスな感情にばかり目を向けていても状況は改善しにくいので、「どんな考え方・接し方をすればストレスを軽減できるか」に視点を切り替えましょう。 身に付けたコミュニケーション方法やストレスマネジメントは他の人相手にも使えるので、ぜひこの機に磨いてみてください。

仕事で評価されなくてモチベーション低下!疲れた気持ちを上げる方法
仕事をするうえで避けては通れないのが人事評価。頑張っているのに仕事ぶりを評価してもらえないと次第に精神的疲れを感じ、働くモチベーションも下がってしまいます。 しかし、低いモチベーションのまま仕事をしても成果は上がりにくく、さらに評価を落としてしまう可能性も! 本記事では、仕事で評価されずやる気が出ない方に向けて、モチベーションを上げる方法を解説します。 仕事で評価されないとモチベーションが下がる原因 評価とは本来、仕事ぶりから給与や役職を決めたり、社員のモチベーションを高めて成長を促したりする目的で行われます。 たとえ高い評価でなくても「公平性」や「明確性」があり納得できる内容であれば、そこまでのモチベーションダウンにはならないはずなのです。 ではなぜ、仕事で評価されないことがモチベーションの低下につながるのでしょうか?まずは、仕事で評価されないとモチベーションが下がる原因を解説します。 評価基準が不明確 たとえ低い評価でも、納得できる理由なら「次は頑張ろう」「ここを直していこう」と思えるので、モチベーションは下がるどころかむしろ上がります。 しかし評価基準が明確に示されておらず「なぜ低評価になったのかわからない」という場合は、今後どのように頑張っていけばいいのかがわからず、モチベーションが下がる原因に。 評価制度は会社設立時に整え従業員にも公表するのが一般的ですが、中には評価基準を公表しない、もしくは明確な基準がないという会社もあります。このように評価基準が不明確だと、評価されても結果の信ぴょう性が低く、疑問や不満が生まれてやる気低下につながりやすいです。 数値でしか評価してもらえない 売上など数値で見える結果も大切ですが、仕事はそれだけではありませんよね。 数値だけで評価されると、成果の裏にある手間や努力を見逃されたような気持ちになり、働くモチベーションが下がります。 特に、数値化しにくい仕事をしている人にとっては「どれだけ仕事を頑張っても評価されないんだ」と思うきっかけとなり、働く意欲が低下する原因になるでしょう。 「働く人の本質」ではなく「目に見える表面」だけで評価している印象が強いため、会社への忠誠心も失いやすいです。 頑張っても報われないという精神的疲れ 仕事で評価されない時期が長く続くと、「努力しても報われないんだ」という気持ちになるのも無理はありません。今まで頑張ってきた疲れが急に襲ってきて、「頑張っても無駄」という思考になりやすいので、働くモチベーションが一気に下がってしまうでしょう。 また、精神的に疲れると自己肯定感も下がり、どんどんマイナス思考になります。マイナス思考が目の前の仕事に集中できないほどの悩みへと発展し、さらなるモチベーションダウンを招くケースも多いです。 フィードバックがない、または不十分 評価後は、「なぜその評価になったのか」「今後どうしていくべきか」などをフィードバックしてもらわなくては、改善や成長につながりません。 しかし中には、上司からのフィードバックがなかったり、フィードバックの質が悪かったりする会社もあります。このような会社で働くと、評価に対する疑問や不満が解消されず、徐々にモチベーションが失われていくでしょう。 フィードバックに問題があると、評価を下した上司との関係も悪くなりやすく、そこから労働意欲の低下につながることもあります。 評価者に不信感がある 自分を評価する上司に不信感を持っていると、評価を素直に受け入れられません。「本当に公平に評価したのか」「そもそも部下のことをちゃんと見ているのか」とネガティブな先入観を持っているため、どんな評価であっても価値を見出せないのです。 そうすると「評価なんてどうでもいい」となげやりな考えになりやすいので、モチベーションを維持できなくなるでしょう。 この場合、評価者に不信感を持ってしまった「人間関係の悪さ」もモチベーション低下の一因となっているケースが多いです。モチベーションを上げるには、仕事の評価を上げるだけでなく人間関係の改善も課題となります。 仕事で評価されずモチベーションが下がるとどうなる? 仕事で評価されずモチベーションが下がると、さまざまなデメリットが生じます。どのようなデメリットがあるのかを見ていきましょう。 生産性が下がる 仕事のモチベーションが下がると、やる気が出ずにだらだら働いて作業効率を落としたり、集中できずにミスが増えたりします。 頭では「ちゃんとしないと」と思っていても、無意識の気持ちのゆるみが行動に表れるので、生産性の低下が新たな悩みになるかもしれません。 自分本来の力が出せないため、さらに評価が下がる悪循環にも陥りやすく、精神的疲労やストレスもたまりやすくなります。 受け身で消極的になる 評価されないとモチベーションだけでなく自己肯定感も下がり、「自分は何をやってもうまくいかない」という気持ちになりやすいです。 常に強い不安感があるため自発的な行動やチャレンジ精神が失われ、受け身姿勢になる人も少なくありません。 また、自信がなさそうな人や消極的に見える人には周囲も仕事を頼みにくいので、一緒に働く人から信頼を得られず働きにくさを感じるリスクもあります。 会社への忠誠心がなくなる 正当だと感じている場合は別ですが、仕事で評価されないことに納得できていなければ当然会社への忠誠心もなくなります。 「仕事は好きでモチベーションもあるけど、評価してくれない会社に不満があるからモチベーションが上がらない」という人は多いです。 今の会社で働ける喜びや会社の役に立ちたいという気持ちが薄れていくため、転職や退職を意識する人も増えるでしょう。 上司との信頼関係が悪くなる 評価に疑問や不満を持つと、その評価を下した上司との信頼関係に傷がつきます。 「この上司は自分を評価してくれないんだ」と思うことが敵対心を生み、関係がギクシャクしてしまうのです。 仕事は一緒に働く人とのチームプレーで大きな成果を掴めるケースも少なくないため、上司とうまく信頼関係を築けないと、成功や成長するチャンスも逃してしまう可能性があります。 【短期的】仕事が評価されないときのモチベーションの上げ方 ここからは、すぐにできる仕事のモチベーションの上げ方を紹介します。モチベーションが上がれば仕事のパフォーマンスも良くなり、高評価へとつながっていくはずです。 外部から刺激を受ける 映画や音楽に触れる、自己啓発本を読む、モチベーションが高い人と関わってみるなど、外部からの刺激を自分のモチベーションに変える方法です。 良い刺激を受けると気分転換になりますし、努力する人を見たり、新しい考えを取り入れたりすることで気持ちが前向きになります。 特に映画・音楽・読書は、通勤途中のようなスキマ時間でも取り組めるので、少しモチベーションが下がってきたなと感じたらすぐに実践してみてください。 気心の知れた人に話を聞いてもらう 友人や恋人、家族など、心を許せる相手に愚痴や不満を聞いてもらうのも、下がったモチベーションを上げるのに効果的な方法。 話すだけでも気持ちがすっきりするうえ、共感してもらえるとそれだけで心強く思えます。また、相手の話が良い刺激となり、モチベーションが一気に上がる可能性も。 自分の気持ちを吐き出したり大声で笑ったりすればリフレッシュにもなり、精神的疲れも癒されるでしょう。 「5分だけ」頑張ってみる モチベーションが下がると、仕事をするのが億劫になりなかなか作業に着手できないこともあります。 そんなときは「5分だけ」と制約をつけて、仕事をやってみてください。「今日は一日中この仕事をやらないと…」と思うと気が重いですが、「とりあえず5分だけ」と思えば気楽に取り組めます。 人間には、やる気のない作業でも手をつけると「キリのいいところまでやろう」と自然とやる気になる「作業興奮」という心理現象があるので、一度始めてしまえばきちんと作業を継続できるはずです。 【長期的】仕事が評価されないときのモチベーションの上げ方 ここからは、もう少し時間をかけて仕事のモチベーションを上げる方法を紹介します。長期的に取り組むぶん、上がったモチベーションを維持しやすいので、短期的な取り組みと併せてやってみてください。 小さな目標をいくつも立てる 「昨日より早く仕事を終わらせる」「1日30分は資格の勉強をする」のように、仕事に関する小さな目標をいくつも立てましょう。 こうすると毎日のように何かしらの目標を達成できるので、こまめに成功体験が積めてモチベーションアップになります。 大きな目標を一つ掲げるのも悪くありませんが、それだと達成するまでに時間がかかり、途中でモチベーションが下がってしまう事例も少なくありません。大きな目標を達成したい場合は、その目標を細分化して取り組みやすくする工夫をしてください。 ごほうびを用意する 上記で立てた小さな目標を達成した後は、「プチごほうび」で自分を労ってもモチベーションアップになるでしょう。 「今月の売上が先月より良かったら欲しい服を買う」「今の作業が終わったらお気に入りのドリンクで一息つく」のように、頑張るメリットがあれば自然と意欲も湧いてきます。 目標のレベルに応じたごほうびを用意して、仕事にゲーム感覚をプラスすると、働く面白みも感じやすくなるはずです。 規則正しい生活を送る 仕事で評価されずにモチベーションが下がると、つい夜ふかししてお酒を飲んでしまう、朝ギリギリまで寝てしまうなど生活もゆるみがちに。しかし生活リズムが乱れると、心身にかかるストレスレベルは上がり、本来持っているやる気や集中力が出なくなります。 心身の調子を整えこれ以上モチベーションを下げないためにも、基本である「よく食べよく眠る」を意識し、規則正しい生活を継続しましょう。 キャリアコンサルティングを受ける モチベーションが下がると「このまま仕事を続けてもいいのだろうか」「なぜ会社は評価してくれないのだろう」など、さまざまな悩みや疑問が生まれます。 そんなときは、キャリアコンサルティングでプロの意見を聞いてみるのも一つの手です。専門知識を持ったキャリアコンサルタントと話しているうちに、自分では気づけなかった評価されない理由やモチベーションの上げ方が見つかることもあります。 「今後どうしていけばいいのか」を一緒に考えてくれるので、現状を打開する糸口がきっと見つかるはずです。 仕事で評価されなくてもモチベーションを維持する方法 モチベーションは一時的に上げてもあまり意味がなく、高い水準をキープする必要があります。ここからは、仕事で評価されなくてもモチベーションを維持する方法を解説するので、ぜひやってみてください。 仕事に真摯に取り組む 評価されずにモチベーションが下がると、仕事をサボったり作業の手を抜きたくなったりするかもしれません。 しかし、一度ズルをして楽を覚えると、そこから抜け出せなくなる可能性が高いです。「自分なりに頑張っている」とも思えないので成功体験や自己肯定感が育たず、モチベーションは下がる一方でしょう。 評価されない期間が長引くと気持ちが腐りそうになりますが、ぐっと耐えて目の前の仕事に真摯に取り組んだほうが、結果的にモチベーションを維持できます。 一緒に働く人とコミュニケーションを取る 高いモチベーションをキープしたいなら、周囲の人と積極的にコミュニケーションを図り、連帯感を育てましょう。仕事は一人で頑張るよりも、誰かと一緒に頑張っているという意識を持ったほうがやる気が起きやすいです。 また、チームプレーで仕事ができると、周囲の人から「あの人とは仕事がしやすい」と言ってもらえることがあり、それが良い評価につながる場合もあります。 転職に向けてスキルを磨く 会社の評価制度に問題がある場合は、きちんと評価してくれる会社に転職するのも一つの選択肢です。 そして転職を有利に進めるために、今の会社で経験やスキルを積むというのもありでしょう。 こうすると意識が「社内の評価」から「スキルアップ」に切り替わるので、評価を気にせず高いモチベーションで仕事に取り組めます。 評価に固執しすぎず、高いモチベーションを維持するのが大事 仕事で評価されないと、どうしても気持ちは下向きになってしまうもの。モチベーションが上がらないのも当たり前といえます。 しかし、モチベーションを下がったままにしておくことには、多くのデメリットがあり得策ではありません。仕事のモチベーションはほんの少しの工夫や意識の変化で上がる場合も多いので、評価に固執しすぎずうまくモチベーションをコントロールしましょう。 モチベーションを自分で上げられると仕事のパフォーマンスが安定し、それが今後の良い評価にもつながるはずです。

仕事のモチベーションが全くないときの対処法!モチベなしでもいい場合とは?
仕事において重要だといわれているモチベーション。しかしモチベーションには波があるため、時には「仕事のモチベーションが全くない」ということもあるでしょう。 この記事では、仕事のモチベーションがなくなる原因や全くないモチベーションを高める方法、モチベーションゼロでも問題ないケースを解説します。 「仕事のモチベーションが全くなくてしんどい」「モチベーションが下がって困っている」という方は、ぜひ参考にしてください。 「仕事のモチベーションが全くない」はよくある悩み 仕事のモチベーションが全くないと「自分はやる気のないダメ人間だ…」と落ち込んでしまう人も多いのではないでしょうか? しかし、モチベーションは感情や状況によって変わるものであるため、意外と「仕事のモチベーションが全くない」という社会人は少なくありません。誰にだって、やる気に満ちてどんな仕事も頑張れそう!と思える日がある一方で、働く意欲が低下してしんどい…と思う日があります。 よって、仕事のモチベーションが全くないからといって、自分を過剰に責める必要はないのです。 後ほど詳しくお伝えしますが、場合によっては仕事のモチベーションが全くなくても問題ないこともあります。「モチベーションを気にしすぎない」のも、実は良い対処法の一つです。 仕事のモチベーションが全くない理由 仕事のモチベーションが全くなくなってしまう人は、以下のような理由や問題を抱えていることが多いです。 仕事がつまらない ルーティンワークが多い職種の人や、一通りの業務経験を積んだ30代に多い理由です。 自分に適性がない仕事をしていたり、仕事がマンネリ化していたりすると、働く面白みを感じられません。仕事をしていてもやりがいがなくつまらないため、モチベーションが下がってやがて完全になくなります。 毎日が同じことの繰り返しのように感じて、スキルアップや自分の将来に対する不安も膨らみやすく、それもモチベーションがなくなる一因です。 頑張っているのに評価されない 人事評価の納得性が低く、頑張っているのに評価されないと感じる場合も、仕事のモチベーションは全くなくなってしまうでしょう。 これは、評価システムが不透明、上司の独断・偏見で評価が決まる会社でよく挙げられる理由です。 評価されないと収入アップや昇進にも期待できず、社員はいつしか「この会社で頑張っても意味がない」と考えるように。頑張る意義や目的を失えばモチベーションが上がらないだけでなく、気持ちまで落ち込みやすくなります。 ※仕事で評価されないことへのモヤモヤは、こちらの記事で詳しく紹介しています! https://career-lab.biz/column/work_evaluation/ キャリアビジョンがない キャリアビジョンとは、仕事だけでなくプライベートも含めた将来の理想像のことです。「こうなりたい」というキャリアビジョンを明確に描けると今後の目標や今やるべきことが具体的になり、自然と仕事のモチベーションが高まるでしょう。 しかしこのキャリアビジョンがなかなか見つからないと、自分が何のために働いているのかがわからなくなります。 「今の仕事を続けていいのだろうか」と迷いやすくなるため、目の前の仕事にも集中できず、働くモチベーションがゼロになるケースが多いです。 待遇が悪い 「給料が低い」「労働時間が長い」「休日が少ない」 このような待遇の悪い会社で働くと、会社から正当に評価されていない、自分は搾取されていると感じて不満が溜まるので、モチベーションは全くなくなるでしょう。また、無意識のうちに「仕事=ただ辛いだけ」という認識になりやすく、働くことそのものに嫌気が差す場合も。 給与が低いから生活が苦しい、労働時間が長いからプライベートの時間がないといった状態が長く続けば、疲労が蓄積してネガティブな気持ちが先行しやすくなります。 人間関係に問題がある 仕事はチームで行うことがほとんどだからこそ、職場の人間関係は仕事のモチベーションに大きな影響を与えます。 一緒に働くと苦痛を感じる人との仕事は、どれだけ興味のある内容であっても楽しいと感じにくく、働くモチベーションを激減させるでしょう。 なお、職場の人間関係にトラブルがありお互いにギクシャクしている場合はもちろん、職場に尊敬できる人や信頼できる人がいない場合も、仕事のモチベーションはなくなりやすいです。 プレッシャーが大きすぎる あなたは「前回と同じ失敗は絶対にできない」「自分の責任をしっかり果たさなくては」などと考え、自分で自分にプレッシャーをかけすぎていませんか? プレッシャーは適度であれば仕事に良い緊張感をもたらす効果がありますが、度が過ぎると負担となってモチベーションをなくす原因になります。 また、モチベーションが全くないのに周囲の期待に応えようと自分を追い込んでしまう人も多く、さらに大きなストレスを抱えてしまう場合も珍しくありません。 私生活のストレス ここまで読んでも原因が見つからなかった人は、私生活のストレスにも目を向けてみましょう。 私生活が安定していない、プライベートで悩みがあるなど私的な問題が原因で仕事のモチベーションがなくなるケースも多いです。 仕事と私生活は切り離して考えるべきではあるものの、完全に意識を切り離すことはできません。特に30代以降は、結婚・出産・子育て・介護など、私生活における変化が多く、ストレスを抱えやすいといわれています。 仕事のモチベーションが全くなくても問題ないケースとは モチベーションは大切であるものの仕事において必須ではなく、全くなくても問題ない場合があります。ここからは、モチベーションが全くなくても問題ないケースを解説しましょう。 モチベーションはないけどプロ意識はある 働く上で一番求められるのは、モチベーションではなく成果です。成果が見えにくい職種でも、あなたが働くことで滞りなく業務が遂行されているのであれば、きちんと成果を収めているといえます。 そして、成果はモチベーションが全くなくても、プロ意識があれば出せるもの。 プロはモチベーションに関係なく仕事をするのが当たり前なので、たとえやる気がなくても安定したパフォーマンスで仕事をこなして誰にも迷惑をかけません。 よって、常にプロ意識を持って仕事ができるのであれば、モチベーションは全くなくても問題ないでしょう。 一時的にモチベーションがないだけ モチベーションはその日の気分によっても変動し、特に理由がなくても上がったり下がったりします。また、大きな仕事をやり遂げた際も、一時的に「燃え尽き症候群」のような心理状態になり、モチベーションがなくなりやすいです。 そもそもが同じ高さを維持できないものなので、モチベーションが完全になくなっても数日で復活するようであれば、大きな問題ではありません。 ただし、モチベーションだけに頼って仕事をすると、やる気の増減が激しく成果にもムラが出やすくなるので注意しましょう。 仕事以外のことにモチベーションがある 仕事へのモチベーションが全くなくても、趣味やプライベートに対して高いモチベーションがあるなら、特に対処は必要ないでしょう。 たとえば趣味にモチベーションを注いでいる人も、その趣味だけを毎日やり続けることはできませんよね。趣味を楽しむためにはお金が必要で、お金を得るためには働かないといけません。 そうすると自然に「趣味のためにお金を稼ごう」という思考になり、それが仕事のモチベーションになります。 割り切れて大きな苦痛を感じない 仕事のモチベーションが全くないことを「辛い」と感じるか「まあいいか」と感じるかは、人それぞれです。 お伝えした通りモチベーションは仕事に必須ではないため、全くないからといって絶対に危機感を持たないといけないというわけでもありません。 「モチベーションが全くないけどまあいいか」と割り切れて苦痛を感じない場合は、そのまま過ごすのもアリ。モチベーションは時間の経過とともに上がることも多いので、あえて放っておくのも一つの手です。 全くない仕事のモチベーションを高める方法 なくても問題ない事例もあるものの、多くの人はモチベーションが全くないと「やる気が出なくてしんどい」と感じるでしょう。ここからは、そんなときに試してほしい、「モチベーションが全くない仕事」のモチベーションを高める方法を紹介します。 仕事から離れてリフレッシュする 仕事のことを一切考えない時間を作り、思いきりリフレッシュしましょう。景色のいい場所に行く、趣味を全力で楽しむなど、リフレッシュできるなら時間の使い方は問いません。 仕事のモチベーションが全くなくなると、やる気のなさをカバーするためにより根を詰めて働こうとする人がいます。ですが、ずっと気を張り詰めていても疲労が蓄積するだけでモチベーションは上がらないので、適度に休息を取り自分を労わることが大切。 一度仕事から離れると気持ちがガラッと入れ替わり、モチベーションの高まりを感じるはずです。 モチベーションが全くない理由を考える 仕事のモチベーションがなくなるのは、単なる気分が原因の場合もありますが、ほとんどの場合はこの記事冒頭で挙げたような理由が原因になっています。 明確な原因がある場合は、原因を取り除けばモチベーションが復活する可能性が高いため「なぜ、自分のモチベーションはなくなってしまったのか」についても考えてみてください。 不安や不満、心のモヤモヤなどを紙に書き出して可視化すると、原因を特定しやすいです。また、原因がわかったら、問題解決に向けてアプローチしてみましょう。 環境や待遇の不満は周囲に相談する 仕事のモチベーションが出ない原因が、職場環境や会社の待遇の悪さにある場合は、周囲に相談してみてください。 環境や待遇の悪さは自分一人で改善できるものではないため、人間関係の問題なら人事部、待遇の話なら上司のように、原因ごとに最も頼りになる人や部署を頼るのがおすすめ。すぐに効果的な対処をしてもらえるとは限りませんが、不満や悩みが周知されればそれを取り除く努力はしてもらえるはずです。 また、上司や他部署の人からモチベーションの上げ方をアドバイスしてもらえる可能性もあり、新たな気づきが得られるかもしれません。 業務量や働き方を見直す 仕事のモチベーションが全くないときは、業務量や働き方を一度見直してみましょう。 習慣化して「負担になっていない」と思っていても、実は業務量が多すぎたり働き方が今の生活に合わなくなっていたりする可能性があります。 「どんな業務量や働き方なら、モチベーション高く仕事ができそうか」を意識すると、キャリアビジョンが見つかることもあり、これから何を頑張ればいいのかがわかるかもしれません。 仕事にゲーム性をプラスする 仕事中、急にモチベーションが下がったときは業務に「ゲーム性」を見出してみてください。 たとえばいつもと同じ業務でも、いつもより「早く終わらせる」「きれいに仕上げる」などを意識すると、仕事に遊び心が加わって新鮮味を感じられます。 モチベーションが全くないのに「仕事を頑張らなきゃ」と考えると、よりモチベーションが出にくくなるので、目の前の仕事だけに集中できる環境を作るのがポイント。 どんな仕事でも毎日続けていればマンネリを感じることがあるので、自分なりの楽しみ方を日頃から探しておきましょう。 キャリアコンサルティングで自己分析する モチベーションが全くないときは、自己分析をするのも効果的です。自分の過去や将来の理想をじっくり掘り下げると、自分のモチベーションがどこから出てくるのかを理解できます。理解が深まればモチベーションのコントロールもしやすくなるので、やる気や成果のムラを一定にする効果にも期待できるでしょう。 そして、自己分析をするなら一人よりも、キャリアコンサルタントと一緒に行うのがおすすめ。 キャリアのプロであるコンサルタントと一緒に自己分析すれば、自然と引き出された会話から自分一人では気づけなかった思考の癖やモチベーションの根源が見えてきます。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、オンラインで気軽にキャリアコンサルティングが受けられるので、ぜひ活用してみてください! 仕事のモチベーションが全くないときこそ焦らない! 仕事のモチベーションがなくなると「どうにかしてモチベーションを上げないと」と焦りがち。また、中には「モチベーションが全くないから、もう会社を辞めたい」と考える人もいるかもしれません。 しかし、モチベーションは時々で上下するものだからこそ、モチベーションに突き動かされた衝動的な行動は禁物。 モチベーションが全くないときは自分と向き合うのにちょうどいいタイミングでもあるので、今の自分にできる精一杯の工夫をしながら、仕事やプライベート、将来について考えてみましょう。

仕事で評価されない原因は?低評価が続くと起こるリスクや対処法も解説
「仕事が評価されなくて辛い」「頑張っているのになぜ評価されないんだろう」 このように、仕事で評価されず悩んでいるのではないでしょうか?頑張っているにもかかわらず仕事で評価されないと、これ以上何を頑張ればいいのかわからず、働く意欲まで低下してしまいます。 しかし、あなたが仕事で評価されないのは、何か見落としている原因があるのかもしれません。 この記事では、仕事で評価されない原因や低評価が続くと起きること、評価を上げるための方法について解説します。 仕事の評価が全てではない 仕事で評価されないと、自分という人間を否定されたような気持ちになるかもしれません。「自分なりに一生懸命頑張ったのに…」というやるせなさもあり、ひどくがっかりするでしょう。 しかし、最初に知っておいてほしいのは、仕事の評価はあなたという人間そのものの評価ではないということ。たとえ能力が高くてもすぐには評価されない事例もあるため、今の仕事の評価だけで自分の価値を決めないようにしてください。 仕事の評価はあなたを値踏みするためのものではなく、至らないところを再認識し、良いところをさらに伸ばすためのものです。 働く上では結果が求められ、それに応じた評価も意識する必要がありますが、それだけにこだわると他人の評価ばかり気になって疲れてしまうので注意しましょう。 仕事で評価されない原因 なぜ仕事で評価されないのか、その原因を把握しましょう。ここでは、よくある「仕事で評価されない原因」をお伝えするので、自分や会社に当てはまるものがないかチェックしてみてください。 成果の見えにくい仕事をしている この世にはたくさんの職業が存在しています。そして「〇件の契約を取った」「〇〇円売り上げた」のように、仕事の成果が目に見える職業ばかりではありません。 たとえば総務や経理、組織の管理部門などは成果を数値化しにくく、公正な評価が特に難しい職種だといわれています。成果が見えにくい職業は、評価が難しいからこそ評価制度が曖昧な会社も多いです。 このような職業に就くと、仕事が評価されずに落ち込んだり、低評価を挽回したくても何をどう頑張ればいいのかがわからなかったりして、悩みやすくなります。 会社が求める努力をしていない 「頑張っているのに評価されない」「成果を上げているのに評価されない」 こんな悩みを持っている方もいるかもしれませんが、そもそも仕事は頑張りや成果が必ず評価されるものではありません。いくら頑張って成果を上げても、それが会社の望むものではない場合、仕事で評価される日はこないでしょう。 会社から求められるものは、勤務歴やポジションに応じて変わります。就職直後は「仕事を覚え、成果を上げること」を求められても、数年後には「成果を上げつつ、後輩を育てること」を求められたりするのです。 仕事で評価されないのは、会社からの要求の変化に気づかず、間違った方向の努力をしているからかもしれません。 上司や周囲との関係に亀裂が生じている 周囲とうまく連携を取りながら働くのも、大切な仕事です。「業務に直接関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、良好な人間関係は仕事をスムーズにし、結果的に成果も上がりやすくなります。 よって、上司や一緒に働く人とうまくコミュニケーションが取れないことが、低評価の原因になっているケースも考えられるでしょう。 周囲と良い関係を築けない人は、報告や連絡、相談も遅れがちで、信頼されにくい傾向にあります。また、周囲の人と距離を置くぶん頑張りにも気づいてもらいにくくなり、本来なら評価されるべき努力が見落とされる場合もあるでしょう。 自分を過大評価している 「仕事で評価されない」と感じる原因は、あなたが自分を過大評価しているからという可能性もあります。仕事の評価に不満や疑問を持ったときは、自己評価と他者評価にズレが生じていないか確認するのも大切です。 自己評価を高めることには、自分の行動に自信がつく、仕事にポジティブに取り組めるようになるなど良い面もあります。 しかし、根拠なく自己評価を高めてしまうと「自分が間違うはずがない」という思い込みで仕事を進めて失敗する、他者を見下して人間関係を壊すといった問題行動も増えやすいです。 仕事の評価は、結果だけでなく仕事ぶりや周囲とのコミュニケーションも加味した総合評価なので、普段の自分の言動を振り返ってみましょう。 会社の評価制度に問題がある 仕事で評価されない原因は、会社の評価制度に問題があるからかもしれません。たとえば以下のような会社は、評価制度に問題があるといえるでしょう。 評価基準が曖昧または不明 上司の私的な感情が評価に直結している 年功序列で評価される 評価基準を公表しない会社や、それどころか明確な基準が存在していない会社もあります。 このような会社は、そもそも本当に公平な評価が行われているのかさえ疑問です。業務能力ではなく上司の「好き嫌い」が評価に直結している可能性もあり、会社に対して不信感を抱くでしょう。 また、近年は減少傾向にあるものの、中には年功序列で従業員を評価する会社もあります。働きぶりではなく勤続年数や年齢で評価が決まるため、従業員としては不平不満を感じやすく、モチベーション低下につながりやすいです。 仕事で評価されないと起きること 仕事で評価されないことには、さまざまなリスク・デメリットがあります。どのようなリスク・デメリットがあるのか、一つずつ解説していきましょう。 仕事のやる気が下がる 頑張っているのに評価されない期間が長引けば「何のために頑張っているんだろう」と疑問を持つのは当然のこと。 評価されるためだけに仕事をしているわけではありませんが、やはり努力が認められないと頑張る気力も尽きてしまいます。仕事のやる気が下がるためやりがいや面白みも感じにくくなり、毎日会社に行くのが辛く感じるかもしれません。 仕事のやる気がなくなると、それを理由にさらに評価が下がる可能性もあり、悪循環が生まれやすくなります。 スキル・キャリアアップに悪影響が出る 新しい仕事や重要なポジションは、仕事で評価された人が優先的に任されます。 よって、仕事で評価されないと何年働いても同じ仕事しか任せてもらえず、スキルアップの妨げになるでしょう。そうなると「自分は何もできない」とさらなるマイナス思考に陥りやすくなるほか、仕事中に時間を持て余して会社に居づらくなる可能性もゼロではありません。 さらに、評価されないのを理由に転職を検討する際にも、スキル不足により就ける職業が限られ、キャリアアップに悪影響を与える可能性があります。自分の成長機会が減ってしまうのは、仕事で評価されない大きなデメリットといえるでしょう。 収入が上がらない 収入は、仕事のやりがいを感じる要素の一つです。しかし給与は、仕事ぶりが認められて昇給したり昇進して手当てが付いたりして上がるものなので、仕事で評価されないと大幅な収入アップは見込めません。 収入が思うように増えないと、モチベーションが保てず働く意欲を失う、いつまで経っても生活にゆとりが生まれないなど、さまざまなデメリットがあるでしょう。 収入が少なさが気がかりで結婚・出産に踏み切る勇気も出にくくなるため、人生の選択肢が狭まってしまうリスクもあります。 仕事で評価されないときの対処法 評価されない現状から抜け出すには「把握」と「行動」を積み重ねる必要があります。ここからは、仕事で評価されないと感じたときに試してほしいことを紹介するので、ぜひ取り組んでみてください。 評価基準を把握する 評価を上げたくても「どんな行動が評価されるのか」を正確に把握していないと、間違った努力をしてしまう可能性があります。 仕事で評価されないときは、会社の評価基準や上司が自分に求めていることを再確認しましょう。 なお、誤った自己評価が「仕事で評価されない」と感じる原因になっている場合もあるので、自分を客観視するのも大切。「上司の立場から見た自分」「同僚の立場から見た自分」のように、複数の視点から総合的に判断すると、より自分を客観視できるでしょう。 評価されている人を見習う 仕事で評価されないときは、評価されている他人を注意深く観察してみるのもおすすめです。一見自分と大差がないように感じる相手でも、評価されているということは必ずどこかに違いがあります。 評価されている人の言動から「あんな風に成果をアピールすればいいんだ」と理解できたり、「自分はここができていなかったんだ」と気づいたりするかもしれません。 また、このような姿勢は上司の目に「意欲的」「前向き」と映ることが多く、良い評価につながりやすいです。他人と自分を過剰に比較する必要はないものの、自分にはない他人の良いところは積極的に見習っていきましょう。 気長に成果を出す どれだけ頑張ったところで、仕事は結果が伴わなければ評価されにくいです。そのため、今まで以上に成果にこだわるのも、仕事で評価されないときに試したい方法の一つ。成果が数値化しにくい職業に就いている人でも、業務効率や生産性を上げる、一緒に働く人のサポートに徹するなど、できることはたくさんあります。 ただし仕事の評価は、たった一度好成績を収めただけでは上がらない場合がほとんどです。スピード昇格や大きな成果を狙うと挫折しやすいので、コツコツと気長に成果を積み上げていく感覚のほうがいいでしょう。 すぐには高評価につながらなくても、あなたの頑張りを見てくれている人は必ずいますし、安定的に成果を出せばきっと会社からの評価も上がっていくはずです。 自発的に行動する いくら能力が高くても、指示されたことしかできなければ、仕事で評価されません。受け身な姿勢は、仕事に対する意欲が低いと思われる原因になります。 「やったほうがいいとわかっていたけど、指示されなかったからやらなかった」なんてことが起きる可能性も考えられるため、受動的な人は周囲からの信頼も得にくいです。 仕事で評価されないと働くモチベーションも低下しやすいですが、それでも腐らず自発的に行動してください。常に気を張って先回りするのではなく、自分で考えて状況に応じた行動を取るのがポイントです。 手が空いたときに自ら「手伝おうか?」と周囲に声をかける、他の人が見やすいように自らわかりやすさにこだわって資料作成するなど、小さなプラスアルファの行動はいつか大きな評価につながるでしょう。 周囲と良い関係を築く 一緒に働く人を大切にし、良好な関係を築くのも忘れないようにしましょう。 仕事で評価されないと、評価判定をした上司にネガティブな感情を持ってしまうかもしれません。しかし上司目線で考えると、自分に嫌悪感を持つ部下は「扱いにくい」です。そして扱いづらい部下には大事な仕事を任せられないため、結果として評価も低くなってしまいます。 無理にご機嫌取りをする必要はありませんが、一緒に働くからには相手に敬意を払い、適度なコミュニケーションを取らなくてはいけません。 しっかり挨拶するのはもちろん、報告・連絡・相談を徹底し、周囲から「一緒に働きやすい」と思われる人を目指しましょう。 転職を検討する 上記で紹介した通り、仕事の評価は自分の頑張りによって上げられる場合があります。 しかし、適性のない仕事に就いて自分の強みを活かせない場合や、会社の評価制度に問題がある場合は、努力しても評価は変わらない可能性が高いです。 そんなときは、自分を適切に評価してくれる会社への転職を検討してもいいでしょう。 ただし、自分の強みを活かせる業務内容か、正当な評価基準を設けている会社かなどをよく調べないと再び同じ悩みに直面するので、自己分析と企業研究は必須です。 評価されない悩みはコンサルタントに相談するのもおすすめ 仕事で評価されないと、ついつい自分を責めてしまいがちです。しかし仕事の評価が自分の全てではないため、自責の念を感じるのではなく前を向いて「今の自分に何ができるか」を考えましょう。 また、自分一人ではどうしても客観的視点を取り入れにくいので、第三者の意見を聞いてみるのもおすすめ。キャリアコンサルティングでは、仕事で評価されないと悩む方からの相談にも応じています。 「客観的に見て自分の働きぶりはどうか」「評価を上げるために自分は何をすべきか」などの疑問に的確なアドバイスが欲しい方は、ぜひプロのキャリアコンサルタントに相談してみてください。

仕事に飽きた!つまらない!30代に多い原因とマンネリ解消法
「仕事に飽きた…」「仕事をしても退屈でつまらない」 働いていると、このような悩みに直面することがあります。特に、一通りの業務知識・経験をつけた30代に多く、仕事に飽きたのをきっかけに転職を考えている方もいるのではないでしょうか。 しかし、少しの工夫や働き方の見直しで、つまらない日々から抜け出せるケースも少なくないため、早計な判断は禁物です。 この記事では、仕事に飽きてしまう原因や、つまらなさを解消する対処法を解説します。 仕事に飽きた・つまらないと感じる原因 まずは、よくある仕事に飽きる原因を解説するので、自分に当てはまりそうな理由がないかチェックしてみてください。 毎日同じことの繰り返しに感じる 就職してからの数年間は、どんな仕事にも新鮮味があります。初めての仕事や見たことない世界も多く、好奇心を持って仕事に臨めるでしょう しかし、勤続年数を積んで30代以降になると、仕事の目新しさは減ります。新しいプロジェクトに参加する、新入社員が入社するなど定期的に新しい風は吹くものの、「完全な初体験」ができる機会が減るため、毎日が同じことの繰り返しのように思えてしまうのです。 いわゆるマンネリと呼ばれる状態であり、仕事で充実感を得にくいため「飽きた」「つまらない」と感じやすくなります。 これ以上の成長が見込めない 勤続年数を積んで業務内容を熟知すると、「できなかったことができるようになる経験」が減り、成長している実感は薄れていきます。 そして、新たな発見や吸収できる知識がなくなり、これ以上の成長が見込めないと判断すると、人は飽きやつまらなさを感じるもの。「今の仕事を続けていいのだろうか」という不安にもつながりやすく、働くモチベーションに大きな影響を与えるでしょう。 なお、このように感じるのに成果は関係ありません。思うように成果を上げられないときだけでなく、成果を上げて社内から評価されたときにも「ここが成長の頭打ちだ」と感じて、仕事に飽きてしまうことがあります。 緊張感やプレッシャーがない 仕事に飽きた・つまらないと感じるのは、緊張感やプレッシャーが一切ないからかもしれません。 大きすぎる緊張感やプレッシャーはストレスの原因となりますが、だからといって一切ない状況だと刺激不足に陥ることがあります。まるでぬるま湯に浸かっているようで仕事中も中だるみしてしまい、飽きやつまらなさを感じるでしょう。 慣れない仕事をすると誰でも自然と気を張るので、飽きやつまらなさは成長して仕事に慣れた証拠ともいえます。しかし完全に慣れ切ってしまうと、仕事をする張り合いが抜けてしまい、退屈だと感じやすくなるのです。 トップダウン体制が強すぎる トップダウンとは、上層部が決めた方針や施策を下部組織が実行するスタイルのことで、日本語でいうと「上意下達」です。 確立された経営スタイルの一つであり悪いものではありませんが、トップダウン体制が強すぎる企業は社内の風通しが悪く、多くの従業員には発言や提案をする権利すら与えられません。 そんな状況では、主体性を伸ばせず仕事のやりがいも得にくいため、仕事に飽きた・つまらないと感じるのも無理はないでしょう。 職場の人間関係が悪い 仕事に飽きた・つまらないと感じるのは、職場の人間関係が原因の可能性もあります。 「どんな仕事をするか」も大切ですが、「誰と一緒に仕事をするか」も、働く楽しさを感じるうえでは欠かせません。たとえば、少し仕事にマンネリ感を感じていても、仕事仲間と楽しく働ければ飽きた・つまらないと悩むまでには至らないケースがほとんどです。 職場の人間関係が悪いと会話が少なすぎて仕事中に退屈したり、人間関係のトラブルで悩んで仕事に集中できなかったりします。 飽きた・つまらないという感情は、仕事内容だけでなく職場環境に対しても抱くものなので、人間関係が悪い職場環境に疲れているサインなのかもしれません。 仕事に飽きた・つまらないと感じやすい人の特徴 ここでは、仕事に飽きた・つまらないと感じやすい人の特徴を解説します。 熱しやすく冷めやすいタイプ 熱しやすく冷めやすいタイプの人は、就職直後は仕事に没頭しますが長続きしません。凝り性であると同時に飽き性でもあるため、理想の職業に就いたとしても時間が経つと興味を失い、仕事をつまらないと感じてしまいます。 また、好奇心旺盛なので、他の仕事のほうが面白そうだと思ったら、後先考えずに行動してしまうことも。 このような人は、同じことを繰り返すルーティンワークよりも、状況に応じた判断や行動が求められる非定型業務のほうが向いているでしょう。 きちんと企業研究をせず就職した 企業研究を行わず、自分に合わない職種や企業を選んでしまった人も、仕事をつまらないと感じがちです。 職種や企業が本当に自分に合うかは、実際に働いてみないとわからない部分もありますが、入社前に徹底的に企業研究すれば「合う可能性」は高まります。 また、企業選びの際に通いやすさや給与、その他福利厚生といった条件面だけで判断した場合も、業務内容と自分の適性にミスマッチが起こり、入社後仕事に飽きやすいです。 合わない仕事を、飽きた・つまらないと思いながら続けるのは大きな苦痛が伴うため、自己分析と企業研究をしっかり行い転職するのも一つの手かもしれません。 器用で何でもそつなくこなす 仕事に飽きた・つまらないと感じる人は、器用さを兼ね備えている場合が多いです。器用な人は飲み込みが早く、初めての業務もすぐに習得して難なくこなすため、一見とても魅力的に思えます。 しかし、確かに強みではあるものの、何でも簡単にできてしまうからこそ仕事を面白いと思えず、飽きた・つまらないと感じやすいです。また、これまで苦労して何かを成し遂げた経験が少ないため努力する方法がわからず、集中力が続かない、一つのことを極められないという人もいます。 理想が高く結果を重視する 理想が高く結果重視の人も、仕事に飽きやすいです。 理想を持つのはいいことですが、仕事の結果とはそう簡単に出るものではありません。特に高い理想は実現させるまでに時間がかかるため、思うような結果がすぐには得られず、先にやる気が尽きて飽きてしまいます。そうすると「こんなことをやっていても無駄だ」と感じて仕事に意義を見出せなくなり、つまらないと思うようになるでしょう。 理想や結果だけを追求するのではなく、その途中にある自己成長や小さな成果にも目を向けてくださいね。 他人の影響を受けやすい 仕事に飽きた・つまらないと感じる人は、他人の影響を受けやすいという特徴をもっているケースも多いです。 このような人は、誰かが違う会社で楽しそうに働いているのを見ると転職したくなる、職場内の愚痴を聞くと「自分の会社は悪いんだ」と思い込んでしまうなど、たやすく周囲に流されてしまいます。 この他にも、他人の影響を受けやすい人は、周囲の様子や話に興味を引っ張られ、自分の仕事への興味が薄れてしまう場合も少なくありません。 仕事に飽きた・つまらないときにすべきこと 仕事に飽きた・つまらないと感じたまま何もせずに働き続けても、状況が改善する見込みは薄いです。ここでは、仕事に飽きた・つまらないと思ったときに試してほしい5つの対処法を解説します。 目標を作る 何の目標もないまま働いていると、飽きた・つまらないという感情はより大きくなっていきます。よって、まずは自分の仕事のモチベーションになりそうな目標を立てましょう。 とはいえ、大きすぎる目標を立てると実現するまでに時間がかかって途中で飽きてしまうため、目標は小さめでOK。たとえば「〇〇〇円まで貯金を増やしたい」「この繁忙期を乗り越えたらちょっと良いお店で外食する!」のような、会社には利益がない目標でも問題ありません。 少しの努力は必要なものの実現可能な目標を立てるとやる気が長続きし、仕事に飽きた・つまらないと感じる日々から脱却しやすくなります。 できたことを可視化する 自分の仕事が役立っているという実感がもてないとやりがいを見失い、飽きやつまらなさにつながっていきます。仕事に飽きた・つまらないと感じている人は、やったことや成果を可視化させて、小さな達成感を得てみてください。 仕事効率化の手法の一つに「やることリスト」を作るというものがありますが、これを応用して「やったことリスト」を作るのがおすすめ。 一日の終わりや空き時間を利用して、その日仕事でやったことをまとめてみると「意外と自分の仕事は誰かの役に立っているな」と気づけて飽き解消になったり、「今日の頑張りがいつか必ず結果に結びつく」と思えてやる気になったりするはずです。 オンオフを意識して働く 仕事はメリハリをつけて行わないと、余計な嫌悪感や疲労の原因になります。マンネリを感じて飽きやすくもなるため、オンオフを意識して仕事とプライベートはしっかり分けましょう。 オンの時間をあらかじめ決めておけば、「時間内に仕事を終わらせよう」という気持ちが芽生え、いつもよりも業務に集中できて仕事をつまらないと感じることも減るはずです。 また、オフの時間でこまめにリラックスできるので疲れがたまりにくくなり、仕事のストレスそのものが減るといわれています。 副業を始める 「転職したいわけではないけど、仕事には飽きていて毎日つまらない…」 このような人は、副業で他の仕事を経験してみるのも効果的。今の会社で実績を積んでいたとしても、副業先では新人です。普段は仕事を教える側の人でも教えてもらう立場になるため、新鮮味や良い刺激を得られる可能性があります。 また、副業を行うためには本業をスケジュール通りに終わらせる必要があり、自然と本業にもメリハリが生まれるでしょう。 ただし、会社の規則で副業が禁止されている場合もあるので、行動する前にまずは就業規則を確認してください。 休暇を取ってリフレッシュする 仕事に飽きた・疲れたと感じたら、少し長めの休暇を取って仕事から離れてみるのもおすすめの対処法です。 飽きた・つまらないと感じるのは、多忙により視野が狭くなっているからかもしれません。一度仕事から離れて客観視してみると、「今の仕事がやっぱり自分に向いている」と再認識できる可能性がありますし、休暇明けはどうしてもバタバタするのでマンネリの解消にもなります。 プライベートの充実が仕事のモチベーション向上につながるケースも多いので、仕事に飽きた・疲れたと感じたら思い切って長期休暇を申請してみてもいいでしょう。 「飽きた」「つまらない」で転職するのはアリ? 仕事に飽きた・つまらないと感じたとき「転職して心機一転したい」と考える人も多いでしょう。ここからは、飽きた・つまらないを理由に転職してもいいケース・転職しないほうがいいケースを紹介します。 転職を検討したほうがいいケース 自分の頑張りだけでは改善できない不満や問題がある 職種や環境が合っていない 理想の転職先が明確に決まっている 心身ともに限界に陥っている 自分の力だけではどうにもできない問題を抱えている人や、転職後のビジョンが明確な人、ストレスが限界を迎えている人は、転職を検討するのもありです。 しかし、仕事に飽きた・つまらないと感じた原因を正しく把握しなければ、転職先でもまた同じことを繰り返す可能性があるため、自己分析は徹底してください。 転職しないほうがいいケース 上記の対処法や自分の頑張りで改善できる可能性がある 今の環境を変えたい気持ちだけが先行している 飽きた・つまらないと感じる原因が不明確 同じ理由で過去にも転職したことがある 自分の行動次第でマンネリを解消できる可能性がある人や、環境を変えたい気持ちが強いだけでつまらないと感じる原因を特定できていない人などは、まだ転職しないほうがいいでしょう。 転職は最後の切り札として取っておけるので、まずは今の自分にできることに着手してみてください。 仕事に飽きた・つまらない現状から脱却しよう 毎日働く社会人は「会社に飽きた」「仕事がつまらない」と感じることもあります。 そう感じたときは、つまらないと思う原因を特定し、自分なりの方法でモチベーションの向上や飽きさせない工夫を図ってみてください。 また、もしも考えがまとまらないときや、自分に合う対処法が見つからないときは、キャリアコンサルティングを受けてみるのもおすすめです。キャリアコンサルティングでは「どうすればあなたが気持ちよく働けるのか」にスポットを当てて、丁寧にヒアリングを行い最善の道を探します。 仕事に飽きた・つまらないと感じている人は、ぜひ一度キャリアコンサルタントに心のモヤモヤを相談してみてくださいね!
あわせて読みたい!

40代に多いキャリアの悩みとは?おすすめの相談相手を解説
豊富な仕事経験を積み、これまでのキャリアを振り返ったり、今後のビジョンを練り直したりすることも多くなる40代。 40代は自身のキャリアを見つめる機会が多いぶん悩みを抱えがちですが「悩みをうまく相談できない」「誰に相談すればいいのか」と葛藤してしまう人も少なくありません。 この記事では、40代が抱えやすいキャリアの悩みやおすすめの対処法、適した相談相手を解説します。 40代が抱えやすいキャリアの悩みとは 悩みの内容は、働く人の年代によって異なる傾向にあります。まずは、40代に多いキャリアの悩みを見ていきましょう。 出世できない 40代は出世して役職持ちになる人が増える世代ですが、40代全員が管理職に昇進できるわけではありません。出世は管理職のポストに空きが出ない限り不可能であり、現代では能力の有無に関係なく、40代の3人に1人は管理職になれないといわれています。 しかし、思うように出世できないと「何のために頑張ってきたのか」と大きな喪失感が生まれ、やがてキャリアの悩みへと発展していくでしょう。 仕事に停滞感がある 40代にもなれば、数々の業務をこなしてきた経験から、自分のペースで仕事ができるようになるでしょう。これは自分が成長した証拠でもありますが、一方で体感としては刺激が少なくなるとともに「毎日同じことの繰り返し」のような感覚に陥り、停滞感につながりやすいです。 また、停滞感は希望通りに出世できた人でも感じることがあります。出世は永遠に上があるわけではないため「これ以上は出世が見込めそうにない」とわかった時点でやりきったような気持ちになり、成長意欲をなくしてしまうのです。 とはいえ、人間には「何となく気分が乗らない」という日もあるため、たまの停滞感なら大きな心配はありません。しかし、長く続く停滞感には要注意。このような状態は「キャリア・プラトー」と呼ばれ、キャリアの迷いに発展する可能性があります。 求められる責任と収入が見合っていない 40代は、責任の大きい仕事やマネジメントを任されることも増え、仕事の幅が広がりやすいです。 しかし、求められる責任のわりに収入が少ないと、不満からキャリアの悩みを抱くでしょう。 特に40代に突入すると、毎月の給料から介護保険料が引かれるため、場合によっては30代の頃よりも手取り額が減ります。子どもの進学資金や住宅ローンの返済など何かと出費が多い世代ですし、老後資金の準備を本格的に考える人も増えるため、金銭的な問題は軽視できません。 そもそも収入は、生活していく上で欠かせないだけでなく、仕事のモチベーションにも大きく影響するもの。 「ずっと昇給がない」「昇給してもごくわずか」 このような状態が長く続けば、働く意欲を失くしたり、今とは異なるキャリアを検討したりするのも当然といえます。 今の会社で働き続けることに不安がある 今の職場で働き続けることに何かしらの不安があり、そこからキャリアの悩みが起きる場合もあります。今の会社に不安を抱いたら、「自分の努力で不安を払拭できる可能性」を考えてみてください。 たとえば「業績が悪く、将来性がない」「体力勝負なため、今の働き方を続けられるか不安」といった場合は、自分の努力だけではどうにもできない可能性が高いため、思い切って転職するのも一つの手です。 しかし「自信がない」「プレッシャーが大きい」のような場合には、仕事への向き合い方や自分の心の持ちようで不安を解消できるかもしれません。 まずは不安の内容をじっくり見つめ、どうすれば不安解消になるのかを考えてみましょう。 子育て・介護との両立が難しい 40代は子育て世代の人が多いうえ、親の介護が始まる人もいます。子育て・介護と仕事を両立するのが難しく、キャリアの悩みに発展する場合も多いでしょう。 また、たとえ傍目には両立できているように見えても、仕事とライフイベントに自分の時間のほとんどを使ってしまい、心の奥ではむなしさを感じている場合もあると思います。 そうでなくても40代~50代は、「自分の人生はこのままでいいのだろうか」と葛藤するミドル・クライシスに陥りやすい時期だといわれています。慌ただしい日常を送れば送るほど自分の人生について考える時間が増え、キャリアに対する悩みや疑問が生まれるかもしれません。 40代がキャリア相談をしづらい理由 仕事や働き方に関して悩みを持つ40代は少なくありませんが、その悩みを他人に打ち明けられる人はごくわずか。ここでは、なぜ40代はキャリア相談できないのか、その理由を解説します。 先輩・上司が少ない キャリアの悩みを抱えた際、自分より経験豊富な先輩や上司に相談したいと考える人が大半です。しかし40代の先輩・上司となると、同じ40代もしくは少し年上の50代の人しかおらず、人数は限られます。 また、一応上司ではあるもののさほど年齢が離れていないことから「頼れる先輩」というよりも「仕事仲間」に近いような気がして、相談する気になれない場合も多いかもしれません。 忙しくて時間が取れない 40代は責任ある仕事を任されたり、家では家事に追われたりと、公私ともに忙しい人が多いです。そのため、キャリアの相談をしたくても時間が取れず、ついつい先延ばしにしてしまうことがあります。 しかし、キャリア相談を後回しにして悩みが長期化すると、心身にかかるストレス増加、仕事に対する意欲低下などが懸念されるので注意しましょう。 相談するのに抵抗がある 他人をよく気遣う人ほど、「相談したら迷惑だろう」「相手の時間を奪うのは申し訳ない」のように考え、相談することに抵抗を持つ傾向があります。40代は忙しく時間の大切さを理解している人が多いからこそ、他人に時間を使ってもらうことにも躊躇してしまうのです。 他にも、責任感が強い人の場合だと「自分のキャリアの問題くらい一人で解決しないと」と思いつめ、相談しないケースが見られます。 人からどう見られるのかが気になる 40代は、今まである程度長く社会人を続けてきたという自負から、プライドが高い人も少なくありません。 プライドを持つのは悪いことではありませんが、高すぎるプライドを持つと他人からどう見られるかを過剰に気にしてしまいます。 キャリアについて悩んでいても「こんな相談をしたらレベルが低いと思われるのでは」のように考え、誰にも話せない状況が続きやすいです。 悩みを言語化できない 悩みの原因は一つでないことも多く、相手に伝わるようにわかりやすく言語化するのは簡単ではありません。誰かに相談したい気持ちはあるもののどう伝えればいいのかわからず、相談できないという40代も多いでしょう。 そんなときは、頭の中にあるモヤモヤや大事にしている考えを紙に書き出し、一つずつ整理していくと言語化しやすくなります。悩みを相談するためだけでなく、自分の気持ちの整理にもなるので、ぜひ実践してみてください。 うまくキャリア相談できない40代の対処法 キャリアの悩みを抱えた際、他人に相談するだけで気持ちが軽くなったり現状把握しやすくなったりします。それでもなかなか相談できないという人は、以下の方法で悩みを打ち明けやすい状況を作ってみてください。 日頃から雑談・小さな質問をする 雑談したり小さな質問をしたりすることは、相談しやすいベース作りに役立ちます。雑談や質問内容は仕事に関することでも、仕事以外の些細なことでも問題ありません。 たとえば、普段ほとんど話さない人にいきなりキャリア相談を持ち掛けても、相手は驚くでしょう。適切な関係性が築けていないと、相談を拒否される可能性もあります。 日頃から会話や質問をして、周囲と良い関係作りをしておくのが大切です。 これまでのキャリアを振り返る 仕事の悩みを相談する前に、今までのキャリアを振り返り、自分の強みや弱み、適性や価値観を把握しておくのも重要です。これは「キャリアの棚卸」と呼ばれ、自分の能力や成果を可視化させて自己分析を深めます。 「何ができるのか」や「何がしたいのか」が明確になれば、誰かに相談する前に自力でキャリアの悩みから抜け出せるかもしれません。 これまでのキャリアを書き出して時系列に整理し、そこから自分の強みや働く目的を抽出してみてください。 キャリアの捉え方を広げる 今の職場で経験を積むことだけがキャリアではありません。ビジネスシーンで使われることが多い「キャリア」という言葉ですが、本来の意味は「個人の経歴」を意味します。 仕事だけでなく生き方全てを含めてキャリアといえるため、キャリアという言葉の捉え方を変えて視野を広げることも、仕事の悩みを相談できない40代に有効です。 「自分の人生において大切なことは何か」を軸に、働き方や生き方を見つめ直してみましょう。 具体的なキャリアビジョンを持つ 働き方や生き方の指標がある程度定まったら、それをもとにキャリアビジョンを立てます。自力で悩みを解決するにせよ、誰かに相談するにせよ「最終的にどうなりたいのか」は明確にしておかなくてはいけません。 ライフスタイルやプライベートも踏まえながら、どのように働きたいのか、どれくらいの収入がほしいのか、それらを実現するためにはどうすればいいと思うかなどを具体的に考えてみましょう。 相談前には内容をまとめておく ぶっつけ本番で相談すれば、話しているうちに考えが散らかり、悩みがうまく相手に伝わらない可能性があります。よって、相談前には内容をしっかりまとめておくことが欠かせません。 どんなことに悩んでいるのか、なぜ悩んでしまうのか、これからどうなりたいのか。 以上3つのポイントを前もって把握しておけば、相談内容を相手に曲解されるリスクは大幅に下がります。 40代がキャリア相談するのにおすすめの相手 「キャリアの相談をしたいけど、誰に話せばいいのか…」と悩んでしまう40代も多いです。ここでは、おすすめのキャリア相談相手を紹介するので、ぜひ参考にしてください。 身近な人 家族や友人、恋人といった身近な人は、最も心置きなくキャリア相談できる相手です。相手もあなたの人間性やライフスタイルをよく理解しているので、一般論ではなくあなたに合わせたアドバイスをしてくれる可能性があります。 年上の意見を聞いてみたいなら親や祖父母に、価値観の近い同世代の意見が欲しいなら配偶者や恋人、友人、兄弟などにキャリア相談するといいでしょう。 ただし、キャリアの相談はシリアスな内容になることが多く、身近な人だからこそ心配をかけたくなくて相談しにくいと感じるケースもあります。そんなときは、この後に紹介する相談相手を検討してみてください。 同じ職場の人 同じ職場の人は、仕事内容や労働環境をわかっているからこそ、共感を得やすい相談相手です。上司に相談した場合はすぐに適切な対処を取ってくれる可能性もあり、悩みの早期解決につながるかもしれません。 また、既に退職している「元・同じ職場の人」にキャリア相談を持ち掛けるのも効果的。元・同じ職場の人は、あなたの社内事情も理解しながら、異なる会社で培った多角的な視点を持っています。 キャリアコンサルタント キャリアコンサルタントは、仕事に関するどんな悩みでも聞いてくれる理想の相談相手です。話を聞いてくれるだけでなく、悩みの整理、キャリアの棚卸なども一緒に行ってくれるので、自分一人では気づけない課題や適性が見つかることもあります。 また、プロ視点の忖度ないアドバイスがもらえるので、理想のキャリア形成に向けた最短ルートがわかるでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボなら、オンライン面談で全国どこからでもキャリアコンサルティングが受けられ、忙しい40代にもおすすめです。 キャリアの悩みを持つ40代は積極的に相談を! 人生の後半戦に差しかかる40代は、自分の働き方や生き方を見直す人が多く、キャリアの悩みどきだといわれています。40代は「悩みがあるけど人に話しづらい」「誰に相談すればいいのかわからない」という人も少なくありませんが、そんなときはぜひキャリアコンサルタントに相談してみてください。 悩みは一人で抱え続けると大きなストレスにつながるため、できるだけ早い段階で誰かに相談するのがベスト。 キャリアコンサルティングを受ければ、人に話せたという安心感だけでなくアドバイスも得られ、心の負担が軽くなるはずです。

悩む40代のキャリア選択肢とは?今後のビジョンの立て方
既に十分な社会人経験がありながらも、まだまだ働き続けることが見込まれる40代は、キャリアに悩む人が増えやすい年代です。 「自分の人生やキャリアはこれでいいのだろうか」「どんなキャリアが自分にとって一番良いのか」 このように、キャリアに関する悩みを抱えている40代は男女問わず大勢います。 本記事では、40代におけるキャリアの選択肢や、悩み解決につながるキャリアビジョンの立て方を解説。40代以降も生き生きと働くために、自分のキャリアについてじっくり考えてみましょう。 キャリアに悩む40代が多い理由 なぜ40代がキャリアに悩みやすいのか、まずは理由から分析していきましょう。 40代は人生の折り返し地点 厚生労働省の「簡易生命表(令和5年)」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.14歳です。男女合わせた平均寿命は84.11歳であり、平均寿命をベースに考えると40代はちょうど人生の折り返し地点といえます。 そのため、折り返しを迎えたことを機に自分のこれまでの人生を振り返り、今後の人生について改めて考える40代が少なくありません。 また、40代は十分な知識・経験がありながらも、まだまだ昇進・転職に成功する可能性が高く、一方で定年退職後のセカンドキャリアも見据えだす時期。キャリアに関する選択肢が多いからこそ漠然と焦りや葛藤を抱き、今の会社で定年まで勤め続けていいのかという悩みを生みやすいです。 公私ともに変化が多い 40代は子育て中の人が多い上、親の介護がスタートする人もいます。このようなプライベートの変化が、キャリアの悩みのきっかけになるケースは多いです。 また、40代は仕事面にもさまざまな変化が。時代の変化に伴い、これまでとは異なるやり方で仕事を進めるよう指示されたり、今まで以上にマネジメント業務が増えたりして戸惑うこともあるでしょう。 40代は出世の話も現実味を帯びてきますが、思うように出世できない、もしくは希望しない昇進を持ち出されて悩んでしまう人も少なくありません。 周囲を取り巻く状況に変化が多いため、いつもと同じように仕事をしていてもなかなか普段通りには進まず、次第にキャリアの悩みへと発展します。 働く上で大切なことが見つかりやすい キャリアアップ、収入、プライベートの時間など、働く上で最も重要視することは人によって違います。20代30代のときは自分にとっての最重要ポイントが定まっておらず、無我夢中で仕事をした人も、経験を積んで40代になれば少しずつ大切にしたいものが見えてくるでしょう。 40代はさまざまなライフイベントが起きやすい年代でもあるため、ライフイベントの発生を契機に大切にしたいことが変化する場合も多いです。 しかしその際、自分が大切にしたいことを実現しにくい会社で働いていると、理想と現実のギャップからキャリアの悩みにつながってしまいます。 悩む40代におけるキャリア選択肢 キャリアの悩みの発端は、現状への不安や不満からスタートすることが多いです。よって、悩みを解消するためには、不安・不満を払拭できるキャリアプランを考えなくてはいけません。 ここからは、40代におけるキャリアプランの選択肢をいくつか紹介します。ぜひ自分の理想に近いキャリアプランを探してみてください。 今の会社でキャリアアップを目指す 社内で管理職への昇進を目指すのは、40代における王道のキャリアプランといえるでしょう。 昇進はこれまでの仕事ぶりが認められた証拠でもあるので、仕事のモチベーションアップになります。また、昇進すれば手当の支給や昇給にも期待でき、収入が原因でキャリアに悩んでいる人の解決策にもなり得るはずです。 管理職になればこれまで以上に業務の規模や責任が大きくなり大変なことも多いですが、だからこそ仕事のやりがいも増えます。 スキルを高めて専門職として活躍する 40代には、スキルを高めて専門職として活躍するというキャリアもあります。 ただし、専門職には一定の経験が求められることが大半のため、今から新しいスキルを身につけるよりかは、今持っているスキルをさらに磨いたほうがいいでしょう。 豊富な経験と専門性を持った人材は需要が高いので、今の会社で働き続けるキャリア以外に、同業他社に転職するというキャリアも実現しやすくなります。 高いスキルはキャリアの可能性を広げるため「現状を変えたいけど、具体的にどんなキャリアを歩みたいのかはまだ決められない」という人は、ひとまずスキル向上に励んでみるのもありです。 ワークライフバランスを重視する これまでよりも仕事のウエイトを減らし、ワークライフバランス重視のキャリアを選択する40代も多いです。 特に現代は、社会全体でワークライフバランスを尊重する傾向が強まっており、新しい働き方が次々登場しています。自分に合った働き方を実現しやすい社会のため、人生の折り返し地点で一度仕事とプライベートのバランスを見直す40代は少なくありません。 しかし、ワークライフバランス重視のキャリアには、今よりも年収が下がるリスクもあります。キャリアチェンジを望む場合は、理想を実現させた際の収入についても考え、現実的に生活できるかをシミュレーションしましょう。 転職・独立する 完全未経験の業種に40代からチャレンジするのは簡単ではありませんが、経験やノウハウがある業界であれば40代はまだまだ転職市場で価値が高いです。したがって、転職するというキャリアもあります。 また、経験を積んだ40代は仕事の知識だけでなく人脈も持っていることが多いので、それらを活かして独立起業するキャリアを選ぶ人も。 独立すれば、プライベート優先で働く、複数の取引先を掛け持ちして収入を増やすなど、自分の裁量で仕事を進められ理想のキャリアを実現できるでしょう。 とはいえ、転職や独立は40代のキャリア選択肢の中でも特に大きな変化をもたらし、当然リスクも高いです。転職・独立のキャリアを描く際は事前に入念な準備を行い、できるだけリスクを軽減してください。 周囲と比較せず堅実に働く 何か大きな変化をもたらすことだけが、40代のキャリアではありません。今の働き方が自分に合っているのなら、コツコツと継続して堅実に働き続けるのも40代におすすめのキャリアの一つです。 変化に乏しいため他のキャリアプランと比較すると地味な印象かもしれませんが、一つのことを長く継続できるのは立派なスキル。キャリアは一人ひとり異なって当然であり、人と比較するとマイナス思考や悩みにつながりやすいので、他人と自分のキャリアを比較する必要はありません。 しかし、ただ毎日会社に行って同じ仕事をするだけだと、マンネリ化しやすかったり社内評価が下がったりする可能性があるので要注意。コツコツ働く中でも作業効率や事業の成長を意識し、工夫を凝らすことが大切です。 40代で悩んだらキャリアビジョンを考えよう キャリアビジョンとは、仕事や人生を総合的に考えて「将来こうなりたい」と抱く理想像のこと。 理想像があれば自分のキャリアやアイデンティティにも迷いにくくなるので、悩んでいる40代はキャリアビジョンを明確に持つのがおすすめです。ここからは、キャリアビジョンの重要性を解説します。 本当の自分に気づける キャリアビジョンを描くには、自分の過去や今持っている価値観を振り返り、さらには今後どうしていきたいのかまでハッキリさせなくてはいけません。 何度も自己分析をする必要があるため、自分でも気づいていなかった長所や短所、譲れない価値観、仕事の進め方などを知るきっかけになるでしょう。また、これまで以上に自己理解が深まるので、自分に合った働き方やキャリア、今後伸ばしていくべきスキルが見つかることも。 「自分にはこんな特徴があったんだ!」という気づきから、これまでなら興味を持たなかったものに対しても意欲的になり、視野が広がる可能性があります。 人生プランを準備できる 40代は、退職後の人生を見据えてセカンドキャリアの準備を始めるのに適した時期でもあります。しかし実際には「まだ先のこと」と捉えてのんびり構えたり、忙しい日常に追われてなかなか考える余裕がなかったりする40代が大半でしょう。 そんなとき、人生トータルの理想を立てるキャリアビジョンを考えれば、自然と退職後のことにも意識が向き、無理なく人生プランを立てられます。 キャリアビジョンは3年後、5年後のような近い将来から想像を膨らませるため未来をイメージしやすく、50代60代になってから「こんなはずじゃなかった!」と後悔しにくくなるのです。 何をすればいいのかがわかる キャリアに悩む40代の中には、「何だか毎日モヤモヤするけど、どうすればいいのかわからない」という人も多いのではないでしょうか。もしかすると、どうすればいいのかわからない原因は、最終的なゴールが定まっていないからかもしれません。 キャリアビジョンで理想像が明確になれば、そこから逆算して今何をすればいいのかが見えてきます。また、たとえ途中で心が折れそうになったとしても、目標が明確なので踏ん張りが効き、最後まで頑張り抜く力になるはずです。 生きがい・働きがいになる 40代50代はふいに「自分の仕事や人生はこれでいいのだろうか」と考えて悲しくなることがあり、このような現象をミッドライフクライシスと呼びます。 ですが、キャリアビジョンを立てて自分のやるべきことが明確であれば、自分の選択・行動にも自信が持て、ミッドライフクライシスに陥りにくくなるでしょう。 「自分はこれでいいんだ」と自信を持つことは、生きがいや働きがいの向上にもつながるので、人生のモチベーションアップにも期待できます。 40代がキャリアビジョンを立てる方法 経験や価値観を洗い出し、そこから自己分析を経ることで、徐々にキャリアビジョンが明確になっていきます。ここからは、具体的なキャリアビジョンの立て方を紹介しましょう。 過去の経験から強みを把握 まずは、学歴や職歴、取得資格、スキル、転機となった出来事などを丁寧に洗い出します。そこから自分の強み・弱み、特徴などを把握しましょう。 自分一人ではなかなかうまくいかない場合は、自分のことをよく知る同僚や上司、家族などに質問してみるのもおすすめです。 第三者の意見を聞くことで新たな気づきが得られ、より自己理解が深まりやすくなります。 価値観を明確にする 洗い出した経験をもとに、大切にしていることや譲れないもの、やりがいを感じる瞬間などを考え、自分の価値観を明確にしていきます。 価値観が明確になると「自分に適したキャリア」も見えやすくなり、今抱えている悩みを解消できるかもしれません。 なお、価値観はキャリアに関することだけでなく、人生全般やプライベートも含んだ内容にするのがポイントです。 年数を区切ってやりたいことを計画する 把握した内容を踏まえながら、40代以降の自分がやりたいことやなりたい姿を考えていきます。 漠然と将来像を考えるのではなく、1年後、3年後、5年後のように細かく区切って、プライベートも含めたビジョンを膨らませるのが効果的です。 ただし、キャリアビジョンは夢とは異なり現実的でなくてはいけないため、実現させるのが難しい計画は立てないようにしましょう。 ビジョン達成には何が必要かを考える 将来像のビジョンが固まったら、ビジョンを達成するために自分が何をするべきかを考えます。 たとえば、ゆくゆく昇進するキャリアビジョンを描いているのであれば、今から業務遂行能力に加えてマネジメントスキルなどをさらに高めていく必要があるでしょう。また、ワークライフバランス重視のキャリアビジョンの場合は、働き方の見直しが必要ですよね。 ビジョンの達成プロセスを具体的に考え実行していくことで、悩みから抜け出し理想のキャリアに向かって進んでいけるはずです。 40代でキャリアに悩んだらコンサルティングを受けても◎ 「キャリアの悩み」というと、20代30代が抱くものという印象があるかもしれませんが、現実は違います。40代は公私だけでなく気持ちの面でもさまざまな変化が生じやすく、キャリアの悩みがより深刻化しやすいです。 そんなときはキャリアビジョンを立てるのがおすすめですが、プロの意見を聞けるキャリアコンサルティングを受けてみるのも効果的。キャリアコンサルティングでは悩みの原因解明はもちろん、キャリアの棚卸しやキャリアビジョンに関するアドバイスもしてもらえます。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、全国どこからでも電話でキャリアコンサルティングが受けられるので、忙しい40代はぜひ活用してみてくださいね!

子持ち主婦の再就職・成功する主婦はここが違います
「社会復帰をしたいから。」 「子どもの養育費が必要だから。」 「やりがいを感じたいから。」 様々な理由から、出産・専業主婦時代を経て再就職をしたいと考える女性は数多くいます。しかし出産後数年の離職期間(ブランク)を経ての再就職活動は、そう簡単なものではありません。 それでも、希望の再就職を実現できる人は何が違うのでしょうか。再就職に成功する主婦はこんなところが違うのです。 669