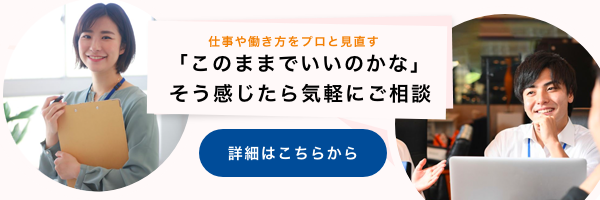就活の面接・「最後に質問ありますか?」で実は評価を下げる質問とは
就職活動の面接では、終盤に「最後に何か質問はありますか?」と聞かれることがよくあります。
これには、応募意欲や質問力、興味関心度を確認する意味もあり、的確な質問ができれば大きなアピール要素になります。一方で、質問内容によっては「マニュアル通りだな。」「あまり考えていないな。」とマイナス評価になってしまうこともあります。
面接にプラスになるようにと、「最後の質問」を考えておく学生は多いですが、実はその質問がかえってマイナスになってしまっている学生も少なくありません。
今、あなたの準備している質問は、評価を下げる残念な質問になってしまっていませんか?そうならないためにも、「評価を下げる質問の例」を確認しておきましょう。
1:「今後の事業戦略について教えてください。」
企業の事業戦略や経営戦略に関する質問は、一見、応募企業への意欲をアピールするいい質問のようにみえます。
「今後、次の柱にしたいと考えている事業について教えてください。」
「今、直面されている事業課題について、差し支えなければ教えてください。」
「今後シェアを拡大していくための戦略がありましたら、ぜひ教えてください。」
などの質問は賢そうにも見えますし、どんな企業にも使えるので「最後の質問」の例として用意している方も多いのではないでしょうか。もちろん真剣にこの回答の内容で、企業を判断したいと考えている人もいるでしょう。
その通りなのですが、実はこれを聞いて評価がプラスになるためには、「極めて重要な条件」があります。
多くの学生が見落としがちなので、ぜひ確認しておきましょう。このように事業戦略や経営戦略について聞いてプラスに評価され人は、それまでの面接で「戦略的・論理的思考力がある」と認められた人だけなのです。
「戦略的・論理的思考力がある」と認められるのは、自分のやりたいことと企業の事業が一致していることをわかりやすく語り、それに納得性が高く、かつ、その内容が極めて具体的で実現性が高いというケースです。
つまり、「事業戦略を聞けば、その意味を理解し活用できる」と面接官が認めるような、「極めてレベルの高い学生」がして初めて、この質問は絶大な威力を発揮します。
そうではない限り、この質問をしても面接官は、「事業戦略なんて聞いてどうするの?その意味がわかるの?」「就職活動のマニュアルをそのまま実行したな。」という印象ぐらいしか持ちません。いずれにしても、「ぜひ採用したい。」と思わないことだけは確かです。
そもそも、本気で事業戦略や経営戦略に興味がない限り、「とりあえず聞いてみた」感は確実に面接官に伝わります。気を付けましょう。
2:「どのような方が活躍されていますか?」
企業で活躍する人、評価される人はどんな人か?を確認する質問全般にも注意が必要です。
「おすすめの質問例」として推奨されていることもありますが、やはり「それを聞いてどうするの?」と思われかねないのも現実です。
なぜなら、配属先や業務によって必要とされる能力や評価されるポイントは異なるため、実際に企業で活躍している人、評価される人のタイプは様々だからです。だから、一言で「こんな人」と言い切れるものではありません。
一方で、一般的に活躍する人、評価される人は業種や職種に関係なく「どこの企業にも共通する一定の要素」があります。
だから聞かれても、「一概にこんな人とは答えられない。」、または「そんなの一般的に皆同じ。」というのが本音なのです。
これを聞いてあなたが知りたいことは何でしょうか。その企業の風土ですか?それとも評価される能力ですか?それを知ってどうしたいのですか?
この質問で知りたい内容をはっきりさせて、違う角度からより具体的に聞きましょう。
例えばもしその企業で「活躍している人をロールモデルにしたい」「仕事の具体的なイメージを知りたい」という思いがあれば、
「去年入社した人で、一番活躍されている方はどんな方ですか?どんな仕事をされていますか?」
とより具体的な質問のほうが、有益な情報が得られますし、面接官にも好印象を与えるはずです。
3:「どのようなスキルを身につけておくと仕事に役立ちますか?」
これも、「前向きな姿勢を表す質問として評価される。」と言われがちな質問です。この手の質問としては、「入社までに取得しておくとよい資格などありますか?」というものもあるでしょう。
悪くはないのですが、実は面接のタイミングで聞いても、特に評価でプラスされることもなければ、この質問で有益な情報を得る可能性も少ないのです。
なぜなら多くの場合、「入社までに身につけておけば仕事に役に立つようなスキル」はほとんどないからです。本当に入社までに身につけてほしいスキルがあれば、企業は内定者研修を用意します。
せっかくの質問の機会を、この質問で使ってしまうのは少しもったいないと理解しておきましょう。
4:「研修やスキルアップにはどんな機会がありますか?」
研修やスキルアップに関する質問も、「前向きな質問例」として紹介されていますが、実はこれも微妙な質問です。
この質問は「学ぶ意欲が高い」と解釈される一方で、「教えてもらうこと期待する、『待ち』の姿勢の学生」と解釈される可能性もあるからです。
企業の理想の人材を本音で言えば、自ら進んで仕事や仕事以外の機会を活かして、自主的に成長してくれるような人材です。
研修制度などを確認したいのであれば、「自分は入社後も仕事を通じて成長していきたいと考えていますが、研修など社員の成長をフォローする制度はありますか?」など、あくまで「自主的な姿勢」をアピールするようにしましょう。
5:「○○部署に配属されることは可能ですか?」
「配属部署」に関する質問には、職種別採用を行っている一部の企業を除き答えにくいのが本音です。
多くの日本企業では、新入社員の配属先は決まっていないか、あるいは「新入社員はまずはこの部署」とある特定の配属先に決まっているかどちらかです。
さらに配属は、本人の適性や志向性だけでなく、配属先の職務の適性、現場のニーズに合わせて決まります。あなたの適性を測りかねていることもあるでしょうし、希望の部署で求められる適性と、あなたの適性が実は異なっていることもあります。
そのため、企業は面接の段階で配属に関して聞かれてもほとんどの場合で明言しかねるのです。
だからあまりにも特定の配属先への思いやこだわりを示してしまうと、「入社してもその部署に配属されるとは限らないし、配属されなかったと辞められても困る。」と判断をされて不採用…ということになりかねません。
やりたいこと、キャリアプランを明確に語るのは大いにプラスですが、配属先にこだわってしまうのは、一般的には控えたほうがよいでしょう。
背伸びした質問をする必要はない
「じゃあどんなことを聞けばいいのだろう?」と思ったら、立ち止まって考えてみましょう。
あなたは面接の質問を考える時に、就職関連サイトや就職関連本に書いてある質問例を参考にしたり、真似したりしていませんか。もちろんそれ自体は決して悪いことではありません。しかし、質問を選ぶその判断基準が実は間違っているかもしれないのです。
「この質問をしたら、面接官受けがいいと書いてあった。」「この質問は、何となく賢そう(前向きそう)にみえるかも。」という「他人の評価」を意識して、質問内容を考えて(選んで)しまっていませんか。
実はそうやって選んだ質問内容は、あなたの興味関心や個性・適性と関係の薄いものになってしまいます。
これはきっと本人の本心からの興味関心ではない。何だか表面的。面接官は確実にそれを見抜きます。
質問内容は確かに評価対象にはなりますが、だからといって他人の評価を気にして背伸びをする必要は全くありません。本当に興味があって、あなたが知りたいと思うことを聞きましょう。
もちろん、就職関連サイトやマニュアルから選んでもかまいません。その代わりに、「これは本当に聞いてみたい。」と自分が心から思えるものを選んでください。本当に聞きたいことを聞く時には、真剣さや意欲、表情などが全く違ってきます。その「真剣さ」が何よりも大切なのです。
そして、共感できる質問を見つけたら、その質問で自分は何が知りたいのか?をよく考えてみましょう。「本当に知りたいこと」がわかれば、それを聞きだすためにもっと適切な「質問」も浮かんでくるかもしれませんよ。

「仕事が辛い」は甘えじゃない!悩みの原因と解決方法
仕事をしていれば誰でも一度は「辛い」「もう働きたくない」と思ったことがあるのではないでしょうか。同時に「こんな感情は甘えだ」と感じて、自分を責めてしまう人も多いかもしれません。 しかし仕事が辛いという感情は甘えではなく、悩みを抱えている心のサイン。サインに気づいたら仕事が辛いと感じる原因を探り、悩み解決に向けて行動することが大切です。 この記事では、仕事が辛いと感じる主な原因や辛い状況から抜け出すための対処法、悩んでいるときにやってはいけないNG行動を解説します。 仕事が辛いという悩みは甘えじゃない 仕事が辛いと感じると「こんな感情を抱く自分は考えが甘いのではないか」と不安になり、さらに落ち込む人もいるでしょう。しかし日々仕事をこなすなかで体調や気持ちに波が生じるのは当然であり、働いていれば時には「辛い」「苦しい」「しんどい」といったネガティブな感情を抱くこともあります。 また、辛いと感じる物事や感じる度合いには個人差があり「他の人が辛くないから自分も辛くない」とは限りません。 仕事が辛いという気持ちは働く人の多くが抱く感情であり、さらに物事をどう感じるかは人それぞれなので「自分は甘いんだ」「精神的に未熟なんだ」と思う必要はないのです。 辛いと感じるのは甘えだと捉えると、自分を責めたり心のSOSサインを見逃したりして、悩みがより大きくなることもあります。仕事が辛いと悩んだときは、甘えだと自分に追い打ちをかけるのではなく、どうすれば辛くなくなるかを考えることが大切です。 仕事が辛いと悩むのはどんなとき? 仕事が辛いのは甘えではないとわかったところで、辛いと感じる原因を探っていきましょう。原因がわかれば効果的なアプローチ方法も見つかりやすくなり、悩み解決に近づけるはずです。 ここからは、仕事が辛いと悩む原因になりやすい、5つの瞬間を紹介します。 職場の人間関係が悪いとき 職場の人とはほとんど毎日顔を合わせ、どちらかが異動・退職しない限りは関係が切れません。だからこそ、一緒に働く人と良い人間関係が築けないと、仕事そのものまで辛く感じることがあります。 パワハラ・セクハラ・いじめはもちろん、小さな嫌がらせや悪口などが横行している職場では、働き続けることを辛いと感じるでしょう。他にも、指示がコロコロ変わる上司、仕事をサボってばかりの同僚のような「トラブルメーカー」と一緒に働く場合も、小さなストレスが積み重なって大きな悩みへと発展しやすいです。 なお、職場の人間関係が悪いとチームワークがうまく機能しないため、仕事の効率も下がってしまう傾向にあります。 仕事ができないとき 大きな失敗をしてしまう、同じミスを繰り返す、成果が出ない…このように、「自分は人より仕事ができない」と感じたときも仕事が辛いと感じて悩んでしまうでしょう。 とはいえ、失敗したときや成果が出ない期間も経験値は蓄積されており、経験から学びを得ればいずれ立派なスキルになります。 しかし、やはり仕事では結果を出すことも求められるため、思うように仕事ができないと労働そのものを「辛い」「しんどい」と感じやすいです。また、仕事がスムーズに進まないと周囲に迷惑をかけてしまうこともあり、そこから自信をなくして悩みにつながる場合も。 「もう失敗できない」「今度こそちゃんとしないと」と自分で自分にプレッシャーをかけてしまうことも多く、その重圧で仕事を辛いと感じるケースもあります。 業務内容ややり方に問題があるとき 一人でこなすのが難しい大量の業務を任せられる、タイトすぎるスケジュールを組まれる、現実的ではないノルマを課せられるなど、業務内容・やり方に問題があるときも仕事を辛いと感じます。 また、やることが多いと脳がキャパオーバーを起こして、判断能力も鈍りがち。本来であればしないようなミスをしてしまったり、「仕事をうまく遂行できないのは自分の能力不足だ」と事実は異なるのに自分を責めたりして、負のループに陥るケースも少なくありません。 業務内容ややり方に問題があると長時間労働も起こりやすく、心だけでなく体の疲労にもつながることから深刻な悩みに発展しやすいです。 仕事にやりがいを感じないとき 仕事にやりがいを感じないと、「自分は何のために働いているんだろう」という漠然とした疑問を抱きやすくなります。労働に意義を見出せないため、仕事を辛いと感じることが増え、「会社に行きたくない」「働きたくない」という悩みへとつながっていくでしょう。 しかし仕事にやりがいを感じないときは、社風が合わない、思っていた仕事と違った、適性がないなど、別の部分に根本的原因が隠れていることも少なくありません。 そのため、仕事にやりがいがなく辛いと思ったときは、なぜやりがいを感じられないのか、なぜ辛いと感じるのかなど、自分の心とじっくり向き合ってみることが大切です。 会社から評価されていないと感じたとき 自分なりに頑張っているつもりでも、会社からあまり評価されていないと感じれば、働くモチベーションを失って仕事を辛いと感じやすくなります。 特に、年功序列で評価する企業で働くと、成果を出しても勤務歴を重ねなければ評価されず悩みに発展するでしょう。職場を選ぶ際は企業の評価制度にも目を向け、自分の考え方と合致する企業を選ばなくてはいけません。 ただし、どれだけ頑張ったとしても会社から求められることをしなくては、努力は評価されないので要注意。会社から正当に評価されず辛いときは、頑張りの方向性がずれていないかを一度立ち止まって考えてみることも重要です。 仕事が辛い…悩みの解決方法 ここでは、仕事が辛いと悩んだときに実践してほしい、具体的な対処法を解説します。解決方法の選択肢は複数あるため、悩みの原因や状況に応じて自分に合う方法を選んでください。 上司や周囲の人を頼る 悩みを誰かに打ち明けると、気持ちが軽くなり解決のヒントが見つかることがあります。上司や周囲の人を頼りにして、まずは話を聞いてもらいましょう。 思っていることを口に出すだけで感情が整理されますし、他者の視点を得ることで新たな気づきが得られる場合も多いです。また、職場内の人に相談した場合は、その後の仕事をサポートしてもらえる可能性もあります。 信頼できる人であれば職場外の人でも問題ないので、一人きりで悩みを抱えないことが大切です。 専門部署や窓口に相談する パワハラやセクハラ、いじめがある、労働基準法に反した就業規則があるといった場合は、人事部やコンプライアンス担当部門、公的な相談窓口などに相談しましょう。一人で立ち向かうよりも、専門知識を持っていたり仲介役を担ってくれたりする第三者に間に入ってもらったほうが、早く問題解決に辿り着けます。 ただし、職場の実情を知らない第三者に状況を正しく理解してもらうには、証拠や具体的な事例を提示しなくてはいけません。「いつ、どこで、どんな状況だったか」を明確に伝えられるように準備してから相談してください。 プライベートを充実させる 中には、仕事が辛いという悩みが大きすぎて、仕事終わりや休日などの勤務時間外までつい仕事のことを考えてしまうという人もいるのではないでしょうか。 しかし、プライベートまで仕事のことを考えていては心が休まらず、さらに辛い感情が膨らみやすくなります。仕事が辛いと悩んでいるときこそ、趣味を満喫したり家族・友人と楽しい時間を過ごしたりして、プライベートを充実させることが大切です。 仕事で辛いと感じることがあっても、仕事終わりや休日に思いきり気分転換できれば、大きな悩みに発展しにくくなります。また、プライベートの予定が詰まっていると「予定を楽しみに仕事を頑張ろう!」と思えるため、仕事のモチベーションも維持しやすいです。 小さい目標を設定して達成感を得る 仕事が辛いと悩んでいるときは、自分に自信をなくして自己肯定感も下がりがちです。そのため、自分にできることに目を向けて、小さな達成感から自信を取り戻すことも重要となります。 特に、仕事ができないと悩んでいるときややりがいを見失っているときは、小さな目標を立ててちょっとした達成感や楽しさを得るのが効果的。たとえばいつもやってる仕事でも、「いつもより1分でも早く終わらせよう」「いつもよりもきれいに仕上げよう」などと目標設定し、目標が達成できたら自分を褒めてあげましょう。 こうすることで、失いかけていた自信も復活し、モチベーションが向上しやすくなります。また、小さな努力を継続していれば大きな結果がついてくることもあり、好循環が生まれやすいです。 キャリアコンサルティングを受ける 辛いときは周囲の人や専門部署に相談するのがいいとお伝えしましたが、身近な人にはなかなか相談しづらかったり、窓口に行って問題が大きくなるのを避けたかったりする場合もあるでしょう。 そんなときは、キャリアコンサルティングを受けるという選択肢もあります。 「キャリアコンサルティングだと、キャリアの相談しかできないのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。キャリア・コンサルティング・ラボでは、キャリアのことはもちろん、辛いと感じていること、誰にも話せないモヤモヤなど、仕事にまつわるあらゆる悩みを相談できます。専門知識を持ったキャリアコンサルタントのアドバイスは的確で、悩みの早期解決につながるはずです。 転職活動をしてみる 自分と合わない会社で働いている場合、どんな対処法を試しても辛さが解消されないことがあります。「自分なりに工夫してみたけど、仕事の辛さがなくならない」という場合は、思い切って転職を検討するのもありでしょう。 どんな企業があるのか少し調べてみるだけでも、自分が勤める会社との違いを知れて視野が広がります。 ただし、職場を離れるのも一つの手ではあるものの、今の仕事が辛いからと勢いで転職するのは避けてください。仕事が辛いと思うことは誰しもにあり「辛いから転職!」を当たり前にすると辞め癖がついてしまう可能性があります。 仕事が辛いと悩んだときのNG行動 仕事が辛いという悩みが大きくなると、冷静さを欠いてつい取ってはいけない言動に出てしまうことがあります。ここからは、注意してほしいNG行動をチェックしていきましょう。 悩みを一人で抱える 今は専門の公的窓口やキャリアコンサルタントなど、相談相手の選択肢も広がっています。仕事が辛いという悩みは一人で抱えるのではなく、誰かに相談しましょう。一人きりで思い悩むと、ネガティブな感情がどんどん大きくなって、心身ともに疲弊するリスクが高くなります。 また、一人で考えているとどうしても視野が狭くなることから考え方も極端になり「辞める」「辞めない」の二択しかないと勘違いして突発的な行動に出てしまう場合も。 誰かに話を聞いてもらうだけでも心の負担は軽くなりやすいので、辛い気持ちを一人で抱えないでくださいね。 無断欠勤 仕事が辛いと悩んでいると、「会社に行きたくない」と思うこともあるでしょう。 しかし、どうしても行きたくないからと、会社に連絡を入れず休んでしまうのはNG!無断欠勤すると次の日から会社に行きにくくなり、そのまま辞めざるを得なくなる場合が多いです。また、何とか次の日に復帰できたとしても、職場や取引先からの信用を落としてしまいます。 仕事が辛すぎて会社に行くのが難しいなら、せめて会社に休むと連絡を入れましょう。 なお、行きたくないと思う頻度が高いなら、長期の有給休暇を取ってリフレッシュする、転職を検討するなどしてみてもいいかもしれません。 他人と自分を比較する 「同僚は楽しく働いているのに自分は辛い」「あの人はできるのに自分はできない」「同年代の人よりも自分のほうが給料が低い」 このように、他人と自分を比べても良いことは一つもありません。 それどころか、誰かと自分を比べることでさらなる自信喪失やモチベーション低下につながり、仕事の辛さが倍増しやすいです。 悩みを抱えると「他の人はどうなんだろう?」と、つい他人のことが気になるかもしれません。しかし、悩みから抜け出すためには自分の価値観を明確に持ち、人と比較しないことがカギとなります。 仕事が辛いと感じる原因を探って、悩みから抜け出そう 働いていれば仕事が辛いと感じる日もあり、それは甘えではありません。しかし辛いと感じる日が何日も続くなら、それは「解決するべき悩み」を抱えている証拠といえます。 仕事が辛いと感じる原因を丁寧に深掘りし、ベストな解決策を探してみましょう。今の自分にできることに精一杯取り組めば、しんどい現状から必ず抜け出せるはずです。

女性が抱えやすい働き方の悩みとは?仕事選びで後悔しないポイント
女性の社会進出が進んだ現代では、バリバリ仕事を頑張る女性や、結婚・出産後に仕事復帰する女性が増えました。 しかし、働く女性が増加したことにより「女性の働き方」に関する悩みも急増。 「自分に合う働き方がわからない」「育児と両立できる働き方ってあるの?」など、現在進行形で働き方に悩んでいる女性も多いのではないでしょうか。 この記事では、女性が抱えやすい働き方の悩みや、働き方選びで後悔しないコツを紹介します。 女性が働き方に悩む原因 どんなことが原因で、女性は働き方に悩むのでしょうか?まずは、女性の働き方において悩みの種になりやすい要素を理解しましょう。 人間関係 職場の人間関係に悩むのは男性も同じですが、女性のほうが人間関係の悩みに深刻になりやすいです。女性は男性よりも協調性を重要視する傾向があり、一緒に働く人と良い関係が築けないとひどく落ち込んだり悩んだりします。 しかし今は、テレワークやフレックスタイム制、個人事業主など、人間関係と距離を取りながら働くことも不可能ではありません。 人間関係に悩んだら、それをきっかけに働き方を見直して、今とは異なる働き方にシフトするのもありでしょう。 キャリア 女性には結婚や出産、介護など、なかなか予測が難しいライフイベントがたくさんあります。そのため自分のキャリアプランを明確に描けず、働き方に悩んでしまう女性が多いです。 また、男性に比べると収入が低くなりやすい、昇進のチャンスが少ないなど、日本の労働環境にはまだまだ働く女性に不利な部分があります。 着実にキャリア形成していきたいと思っても、安定した収入やキャリアアップが見えにくいことから「今の働き方を続けて本当に大丈夫なのか」と不安を感じ、そこから働き方の悩みにつながるのです。 ワークライフバランス 「家事育児は女性の役割」という考え方は、薄れつつある風潮にはなっていますが、現実にはまだ残っており、女性が家庭や育児と仕事を両立させるのは簡単なことではありません。家事育児のためにやむなく正社員のキャリアを諦めたり、仕事をセーブしたりするケースも珍しくなく、ワークライフバランスは女性が働き方に悩む大きな原因となっています。 また、一見うまくワークライフバランスが取れているように見えても、本人は「仕事も家庭も中途半端になっているのでは」とジレンマを抱えているケースも多いです。 働き方の種類 かつては「正社員」または「アルバイト・パート」くらいしか働き方の種類がありませんでしたが、今はさまざまな働き方や制度が生まれ、選択肢が一気に増えました。一人ひとりのライフスタイルや考え方に合わせた働き方が叶いやすくなり、「働きたいのに働けない」という女性の減少にもつながっています。 しかし一方で、選択肢が増えたからこそ「自分にはどんな働き方が合うのか」と悩んでしまう女性も増えました。各働き方の特徴を理解するだけでも時間がかかり、悩みが長期化しやすいのも懸念点といえます。 女性に人気の働き方とは? 女性と一口にいっても、仕事に求めるものや生活スタイルに応じて、合う働き方は異なります。 ここからは、女性から支持の高い働き方をご紹介。さまざまな働き方を知ることで「こんな選択肢もありかも」と、視野が広がるはずです。 正社員として働く 正社員は、しっかり稼ぎたい女性やキャリアアップを目指す女性、安定志向の女性に人気の働き方です。裁量の大きい仕事を任されやすいのでプレッシャーを感じることもあるかもしれませんが、そのぶんやりがいや達成感も大きくなります。 他の働き方に比べて時間の融通が利きにくいのがネックですが、今は「女性が長く働ける環境」に力を入れる企業が増加傾向にあります。従業員のライフイベントに理解のある企業で働けば、家事や育児と正社員の仕事を両立できるはずです。 多様な制度を利用して働く 働く女性にとってマイナス要素となりやすいのが「時間」と「場所」です。時間・場所に縛りがあると私生活と仕事を両立しにくく、キャリアを諦めざるを得ない場合もあります。 しかし働き方の多様化により、今は時短勤務やフレックスタイム制、テレワークといった制度・取り組みを導入する企業が多いです。 このような制度を利用すれば、育児や介護といったライフイベントと仕事を両立しやすくなり、ワークライフバランスが保てるでしょう。 非正規雇用で働く パートタイム・派遣社員・契約社員といった非正規雇用は、家庭を優先したい女性から特に支持されている働き方です。非正規雇用は働く日や時間の融通が利きやすく、プライベートを最優先にしながら働けます。 また、ダブルワークでしっかり稼ぐ、空いた日に1日だけ超短期で働くなど、自分の希望に合わせて柔軟に働き方を変えられる点も魅力です。 「未経験OK」「年齢制限なし」という条件での募集も多く、仕事にブランクがある主婦でも挑戦しやすいでしょう。 個人事業主として働く 自分のスキルや経験を活かして、個人事業主という働き方を選ぶ女性も増えてきました。 案件の獲得から税金の支払いまで全て自分一人で行わなくてはいけませんが、仕事量を自分で調節できるのが個人事業主の強み。労働時間や収入をコントロールしやすく、ライフイベントに合わせて働き方を大きく変えられるので、無理なく長期的に働けるでしょう。 また、働く場所も問わないので、自宅で育児や介護をしながら仕事をすることも可能です。 女性が働き方を選ぶうえで重視したい基準 女性が働き方を考える際、いくつか「重視してほしい基準」があります。自分に合った働き方を見つける際にも役立つので、以下の点に注目してみましょう。 やりがい 条件面を考慮することは大切ですが、「希望条件を満たしているから」という理由だけで働き方を選ぶと、途中でモチベーションが尽きてしまう可能性が高いです。選択した働き方を長く続けるためには、「やりがい」を見出すことが欠かせません。 やりがいがあれば、私生活と仕事の両立が大変でも気持ちが折れにくく、仕事が長続きしやすくなります。 やりがいは「やっていて楽しいと思えるか」「興味・関心のある分野か」「ある程度自分のアイデアを活かして働けるか」などに注目すると、見極めやすくなるはずです。 プライベートやライフイベント 仕事だけが人生ではないため、家族や友達、趣味といったプライベートの時間をきちんと確保できるかも、働き方を選ぶうえで重視しないといけません。働き方を選ぶ際は、企業の考え方や福利厚生から、従業員のプライベートを大切にしてくれるかを判断しましょう。 また、従業員のライフイベントに理解がある企業かという点も要チェックです。企業に理解があれば大きなライフイベントに直面しても、無理なく働き続けられる取り組みや工夫をしてもらえる可能性があります。 育休産休の取得率、女性従業員の平均年齢などを確認し、安定的に働けるかを考えてみましょう。 賃金や評価 男女平等が当たり前になったとはいえ、昇給や昇進において、意識レベルで男女格差が残っている企業があることも残念ながら事実です。「男女格差はあるものだから」「女性だから仕方ない」と自ら言い聞かせることで、自分に合わない働き方を選択してしまう危険性もゼロではありません。 近年は、成果に応じて性別関係なく正当に評価する企業が増えつつあります。また、男女ともにワークライフバランスが保てるよう職場環境を整備している企業も多いです。 働き方を選ぶ際は、企業の賃金や評価制度にも注目して「女性が働きやすい環境か」を判断してください。 選択肢の豊富さ ライフスタイルや考え方は年々変化するもので、今選択した働き方が将来的にもずっと合うとは限りません。特に女性は、結婚・出産でライフスタイルが大きく変わりやすく「10年後の自分に合う働き方」を予想することすら困難です。 そのため「働き方の選択肢が豊富」という点も、働き方を選ぶ際にぜひ意識したいポイント。 テレワークや時短勤務、週休3日制といった制度・取り組みを自分で自由に選択できれば、状況に合わせた働き方が可能となり、長期的なキャリア形成ができるでしょう。 女性の働き方選びで後悔しないコツ 女性が働き方を選ぶ際に重視すべきポイントをお伝えしましたが、ここからは自分に合う働き方を選ぶ具体的な方法を紹介します。後悔しない働き方をするために、以下のことを実践してみてください。 勇気を出して行動する 「今とは違う働き方がしたい!」と思いつつも不安や面倒くささに負けて、今の働き方を続けてしまう女性は少なくありません。 しかし、合わない働き方を続ければ仕事のモチベーションが下がりやすいうえ、そのまま年齢を重ねて働き方の選択肢が狭まってしまう恐れがあります。ゆくゆく後悔したくないなら、今の働き方に悩みや疑問を持った時点で、勇気を出して行動しましょう。 行動するといっても、いきなり転職のような大きなアクションを起こすのではありません。どんな働き方がしたいか条件を考えたり、働き方や企業の情報を集めたりすることも立派な行動の一つです。 小さなアクションを積み重ねることで大きな決断もしやすくなり、働き方を変えることへの不安も和らぎます。 悩み・キャリアプランを明確にする これまでの働き方を振り返り、「自分が負担に感じやすいこと」「悩みの種になりやすいもの」を明確にしましょう。嫌だ、辛いと感じるものを把握しておかなくては、また同じような働き方を選択してしまう可能性があるためです。 なお、悩みが把握できたら理想のキャリアプランについても考えてみてください。 今抱えている悩みから解放されることや、理想の働き方をすることはあくまで通過点であり、「理想の働き方ができたらどうなりたいか」を明確にするのが最終的なゴールです。 キャリアプランがはっきり描ければ、そこから逆算して「今やるべきこと」も見えてきます。 情報収集は徹底的に 家事育児をしている女性でも働きやすいよう、今はさまざまな働き方が登場しています。後悔しないためには、事前に一つ一つの働き方をよく調べることが大切です。 たとえば、最初はAという働き方が合っていると思っても、調べるうちにBの働き方のほうが理想に近いと発見するケースは少なくありません。 あらゆる可能性を探ることにもつながるため、情報収集は徹底的に行いましょう。 条件に優先順位をつける 自分に合った働き方を考えると、同時に「自分の理想を実現するための条件」も見えてきます。 条件は、働き方や企業を選ぶ際の基準となるため、明確にしておいて損はないでしょう。しかし、自分の理想が全て叶う好条件の企業はなかなか現れません。 大量の条件を挙げたり、過剰に条件にこだわったりすれば、適合する働き方がゼロになり悩みから抜け出しにくくなるため注意してください。 条件にこだわりすぎないようにするコツは、優先順位をつけることです。「絶対に譲れない」「あると嬉しい」「なくてもいい」と3つくらい指標を決めておけば、働き方に迷ったときも軸がブレにくくなります。 キャリアコンサルティングを受ける ここまで働き方を選ぶ具体的な方法を紹介してきました。しかし中には「一人で考えてもよくわからない」「忙しくてうまく情報収集できない」という女性もいるでしょう。 このような女性は、キャリアコンサルティングを受けるのがおすすめです。 プロのキャリアコンサルタントに相談すれば、抱えているモヤモヤを吐き出せて悩みが明確になるだけでなく、経験やデータに基づいた正確な情報を提供してもらえます。 具体的かつ大きな悩みを抱えている女性はもちろん、漠然と働き方に悩む女性にとっても、問題解決のヒントが見つかるはずです。 多様化する女性の働き方、自分の理想を見つけよう 人間関係やキャリア、ワークライフバランスなど、働く女性の悩みは尽きません。現状に悩みや違和感を持ったら、今とは違う働き方にも目を向けてみてください。 女性の働き方は時代と共に大きく変わり、今はさまざまな選択肢の中から自分の価値観に合うものを自由に選べるようになりました。 じっくり悩みと向き合い、理想の働き方について考えれば、自分に合うキャリアが見つかり悩みから抜け出せるはずです。

仕事の悩みがある人必見!プロに相談できるサービス【無料あり】
人間関係や仕事内容、お金のこと、将来について…。仕事をしていると、このようなあらゆる悩みに直面します。そんなとき、あなたは誰かに相談しているでしょうか? 「心配をかけると悪いから」「誰に相談していいかわからないから」という理由で、仕事の悩みを誰にも相談できないという人は少なくありません。 しかし、仕事の悩みを一人で抱えることには、多くのリスクがあります。 この記事では、仕事の悩み相談におすすめの相手や、相談に乗ってくれるプロのサービスを解説。適切な相手に相談してアドバイスが得られれば、悩み解決の糸口がきっと見つかるはずです。 悩む原因は?よくある仕事の相談内容 誰かに相談することを踏まえて、まずは自分の悩みの原因を整理しておきましょう。仕事の悩み相談でよくある原因を紹介するので、自分に当てはまる項目はないかチェックしてみてください。 人間関係がうまくいかない 仕事は「どんな仕事をするか」も大切ですが、「誰と一緒に働くか」も大切ですよね。職場の人全員と友人のように親しくなる必要はないものの、お互い相手に配慮し気持ちよく働けるよう工夫しなければ、悩む原因となります。 また、職場の人間関係がうまく構築できないと、頼るべきシーンで頼れず一人で業務を抱えすぎてしまったり、確認や相談ができずに失敗したりすることにもつながるでしょう。 人間関係の悩みは、パワハラやいじめなど、攻撃性が高く早急に対処したほうがいい場合も少なくありません。誰にも相談せず悩みを一人で抱えると、相手からの攻撃がどんどんエスカレートする恐れがあります。 給与が低い 「長く勤めても給与が上がらない」「昇進したのに手当が出なかった」 相談窓口には、このようなお金にまつわる悩みも多数寄せられています。給与は生活に直接的な影響を与える重要な要素だからこそ、悩みも深刻になりやすいです。最初のうちは「仕事を頑張ればいつか」と前向きな気持ちを維持できるかもしれませんが、給与が上がらない期間が長引けば希望も打ち砕かれ、大きな悩みになるでしょう。 また、思うように給与が上がらないということは「正当に評価してもらえていない」と感じる原因にもなり、仕事のモチベーション低下を招く可能性があります。 労働環境が悪い 休日出勤や残業が多い、パワハラ・セクハラが横行している、トップダウン方式が過剰で上司が意見を聞いてくれないといった労働環境の悪さも、「ずっとこの職場で働き続けるべきか」という悩みを生むでしょう。 ブラック企業は淘汰されつつありますが、グレーな企業運営で労働環境を改善しようとしない企業もまだまだ現存しています。また、労働環境の悪さに耐えて働き続けると、心身に不調をきたして新たな悩みにもつながりやすいです。 労働環境の悩みは、しかるべき機関・窓口に相談することで指導してもらえるケースもあります。「職場の人も我慢しているから」「これくらい堪えないと」と思わず、勇気を出して相談することが大切です。 やる気が出ない、やりがいがない 仕事はほとんど毎日繰り返し行うものなので、常にやる気全開!というわけにはいきません。長い社会人生活の中では、「今日は何だかやる気が出ない」と感じる日だってあるでしょう。 しかし、やる気が出ない状態が長く続くと、日々に虚しさを感じるようになったり仕事でのミスが増えたりして、深刻な悩みになることがあります。特に、ある程度仕事で経験を積んだ30代以降に多い悩みで、やる気が出ないからこそどんな仕事をしていてもやりがいを感じられず、毎日が無味乾燥に思えてしまうのです。 やる気が出ない、やりがいを感じないという悩みは、同じ会社の人には相談しづらく、一人でぐるぐると考えて「自分の気合いが足りないんだ」と自分で自分を責めてしまいがち。 ですが、悩みの根底にはモチベーション低下を引き起こした別の原因があることも珍しくないので、多角的に考えることが求められます。 会社や自分の将来が不安 会社や自分の将来についての悩みは、30~50代の働く人に多いです。30代以降は結婚・子育て・親の介護などライフイベントが起こりやすいため、未来のことを考えて不安になったり、一度立ち止まってキャリアを見つめ直したりする人が増えるのでしょう。 「自分が定年を迎えるまで、会社が存続しているか心配」「今のままで自分が思い描くキャリアプランは実現できるのか」 このように考え、キャリアチェンジすべきか否かで悩む人が少なくありません。 また、未来について考えるのは悪いことではないものの誰にも正確には予想できないため、明確な答えが出しにくく悩みが長期化する傾向にあります。 仕事の悩みを相談しないと起こること 仕事の悩みはなかなか相談しにくく、つい一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。 しかし、仕事の悩みを相談しないことには、主に3つのリスクが伴います。相談しないままだとどのようなことが起こりやすくなるのか、把握しておきましょう。 悩みが長期化する 自分一人だけで悩みを抱えると、どうしても視野が狭くなりがちです。そうすると何度も同じことを考えて悩む時間が延びてしまい、結果的に解決するまでに時間がかかります。 また、悩みが長期化すると判断能力が落ちやすくなるので、よく考えずに決断や行動して後悔することも。 しんどい時間の短縮、後悔しない選択をするためにも、悩みはできるだけ初期段階で誰かに相談するのがおすすめです。 ストレスが心身に影響を与える 悩んでいる間はずっとモヤモヤした気持ちを抱えて、ストレスを感じている状態が続きます。誰にも気持ちを吐き出せないとストレスはさらに膨らみ、心身に悪影響を与える危険性があるため注意しましょう。 数日休めば回復するような軽度のものならまだしも、取り返しのつかないような病気を招くこともあるため、ストレスは侮れません。特に仕事の悩みは暮らしや人生を大きく左右するため深刻になりやすく、ストレスも大きいです。 仕事のミスが増える 誰にも相談せず一人で悩んでいると、意識が悩みに引っ張られやすく集中力が下がり、仕事のミスが増える傾向にあります。明らかにミスが増えたりトラブルが重なったりすれば、自信喪失や自己嫌悪も起こりやすくなり、新たな悩みを抱える可能性もゼロではありません。 このように、仕事の悩みを誰にも相談しないことには悪循環を生むリスクがあるため、できるだけ第三者に相談して早期解決を目指しましょう。 仕事の悩みを相談すべき相手 仕事の悩みはシリアスな話題だからこそ、相談相手をよく選ぶ必要があります。ここからは、仕事の悩みを相談するのにおすすめの相手を解説していきましょう。 家族や友人 信頼できる家族や友人には本音を話しやすく、共感してもらうことで心の支えにもなります。元からあなたのことを知っている相手だからこそ、言葉にできない思いも汲み取ってもらえるかもしれません。 また、既に信頼関係が完成している間柄なので、忖度なくズバッとアドバイスしてくれる可能性が高いところも頼りになるでしょう。 「職場のことを何も知らない家族や友人には相談しにくい」と思う人もいるかもしれませんが、職場に全く関係がない第三者の意見を聞くことで客観的視点が得られる場合も多いです。 職場の人 職場の相談窓口や上司、同僚などに仕事の悩みを相談するのもありでしょう。同じ労働環境で働いているからこそ、職場の人はあなたの状況や悩みを理解してくれやすいです。 ただし相談する相手を間違えると、真剣に向き合ってもらえなかったり思わぬ噂を立てられたりして、余計に悩みが増える可能性があります。 職場の人に相談する場合は相手を見極めて、本当に信頼できるかをよく考えてください。 SNS ネットやSNSで相談すれば、多くの人からの意見を一斉に集めることができます。「身近な人に相談すると心配をかけそう」という人でも、お互いに顔が見えないネットでなら相談しやすいと感じるのではないでしょうか。 しかし、ネットやSNSを使って仕事の悩みを相談する際は、プライバシーに十分注意しなくてはいけません。この他、正確性に欠ける情報を提供する人がいる可能性もあるため、全てのアドバイスを鵜呑みにするのは厳禁です。 相談窓口やサービス 公的な相談窓口や転職エージェント、キャリアコンサルタントといった仕事の悩みのプロも、頼りになる相談相手です。専門知識を持つ相手ならアドバイスも的確で、悩みの早期解決に期待できるでしょう。 また、カウンセラーやコンサルタントには守秘義務があるので、人に言いにくいことや知られたくないことも気兼ねなく相談できます。 仕事の悩みを相談できる窓口やサービス ここからは、仕事の悩みをプロに相談できる窓口やサービスを紹介します。無料で相談できるサービスもあるので、ぜひ活用してみてくださいね。 総合労働相談コーナー 総合労働相談コーナーは、全国の労働基準監督署内に設置されている相談専用窓口です。予約不要かつ無料で個別相談に乗ってもらえ、出向くのが一般的ではあるものの電話でも相談できます。 労働基準関係法令に関する問題解決に向けた窓口であり、労働条件に悩む人におすすめ。 パワハラやいじめといった人間関係の悩みはもちろん、不当な賃金の引き下げや解雇、長時間労働など、働く上で起こる幅広い悩みを相談可能です。 また、こちらが適切に訴えかけても会社側が何もしてくれない場合は、指導・あっせんを行うケースもあります。 働く人の「こころの耳電話相談」 働く人の「こころの耳電話相談」は、専門のカウンセラーに電話で相談できるサービスです。「働く人の~」とついていますが、働く人の家族や人事労務担当者からの相談にも対応してもらえます。また、話すのが苦手な人や電話する時間がない人のため、メールやLINEでも相談可能です。 相談できる内容は主にメンタルの不調やストレス、過重労働による健康障害についてで、仕事のプレッシャーや人間関係に悩む人に適しているといえるでしょう。 キャリア形成・リスキリング支援センター キャリア形成・リスキリング支援センターは、厚生労働省が運営する、無料のキャリア形成支援施設です。各都道府県に拠点を構え、キャリアやスキルアップに関する悩み相談に乗ってもらえます。 スキルアップ目的の職業訓練を支援してもらえるケースもあり、キャリアの悩みを抱える人や、ライフワークバランスについてアドバイスを得たい人におすすめです。 ただし、キャリアコンサルティングを受けるには公式サイトから事前予約に申し込み、日程調整する必要があります。いきなり施設を訪れても相談には乗ってもらえないため注意しましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボ キャリア・コンサルティング・ラボは、働き方や人間関係、職場環境、転職などについて相談できる、コンサルティングサービスです。 仕事に関するあらゆる悩みに対応しているため「悩みが複数ある」「どこに相談すればいいかわからない」という人にもおすすめ。また、相談者と一緒に悩みの原因を探し解決を目指すことを目的としているので「モヤモヤした思いや漠然とした不安がある」という人でも相談しやすいでしょう。 全国どこからでもオンラインで相談できるので、自分の都合に合わせやすい点も魅力といえます。 就職だれでも相談 就職だれでも相談は、就職・転職活動にまつわる悩みを相談できるサービスです。専門のアドバイザーが電話、LINE、オンラインにて、仕事の選び方や履歴書の書き方、面接対策などを行ってくれます。 また、キャリア相談にも対応しているので、働き方に関する悩みや疑問がある人にもおすすめ。 匿名で利用できるのもポイントで、自分のプライバシーを守りつつ相談したいと考えている人にぴったりです。 仕事の悩みは誰かに相談して、早期解決を目指そう 仕事の悩みからいち早く抜け出して自分らしく働くためには、誰かに相談することが大切です。 悩みは相談を遅らせれば遅らせるほど深刻になりやすいので、早い段階で打ち明けるのがベスト。 誰に話していいのかわからないときや、身近な人に言いにくいとき、専門的なアドバイスが欲しいときは、プロに相談するという手もあります。 あなたの悩みに耳を傾け、気持ちに寄り添ってくれる人は必ずいるので、一人で悩みを抱えずに勇気を出して相談してみましょう。

合う働き方がわからない…を解決する方法は?NG行動も解説
現代は、一人ひとりの価値観を尊重する多様性社会。社会の変化に伴って働き方も多様化しており、以前よりも柔軟なワークスタイルで働けるようになりました。 しかし、自分の意思で自由に働き方が選べるようになったからこそ「どんな働き方を選べばいいの?」「自分に合う働き方がわからない」という悩みに直面している人も多いのではないでしょうか。 本記事では、働き方がわからない人に向けて原因や解決方法を解説します。併せて、働き方がわからないときにやってはいけないNG行動も紹介するので、ぜひ参考にしてください。 働き方がわからない瞬間は多くの人にある 新しい働き方がたくさん登場している現代において、「自分に合った働き方はこれ!」と自信を持っている人のほうが少数派です。 自分に合った働き方を選択したつもりでも、時間がたてば状況や考え方が変わり、働き方がわからなくなることがあります。また、働き方には明確な正解がないからこそ、定期的に「本当にこれでいいのか?」と迷う瞬間があるのです。 そのため、働き方がわからないからといって、焦ったり自分を情けなく思ったりする必要はありません。 働き方がわからないときは、自分とゆっくり向き合い視野を広げるタイミングです。自己分析や情報収集を繰り返し、わからないことを一つずつクリアしていけば、きっと自分に合う働き方が見つかります。 働き方がわからないと感じる原因 漠然と「働き方がわからない」と思っている人も多いのではないでしょうか。ですが、働き方がわからない状況から抜け出すには、原因を探ることが欠かせません。ここからは、働き方がわからないと感じる主な原因を解説します。 自分の強みがわからないから 自分の強みを活かせるか、は働く上で重要なポイントです。 強みを活かして働いている実感がある人は、仕事に対して疑問を抱きにくいので、自分が選んだ働き方にも自信が持てます。反対に、自分の強みがわからないと、今の仕事が本当に自分に合っているのかがわからなくて、働き方にも迷いやすいです。 強みがわからない人は、何でもそれなりにこなせる「器用貧乏」タイプの傾向が見られます。 オールマイティな才能を持っているため社内では頼りにされますが、あらゆる作業を難なくこなせるからこそ、どこが自分の長所なのかわからなくなるのです。 強みを見失ったことが原因で働き方がわからない場合は、やっていて楽しいと思えることや人から褒められたことに注目し、才能をより伸ばせるように工夫してみましょう。 失敗を恐れすぎているから 「働き方を変えて失敗したらどうしよう」という強い不安や恐怖も、働き方がわからなくなる原因の一つです。新しい働き方に挑戦してみたい!と思っても、強すぎる不安や恐怖があると、せっかく生まれたチャレンジ精神にストップをかけてしまうことがあります。 その結果、働き方を変えたい気持ちはあるものの何も行動できず、ぐるぐると働き方について考えてしまってわからなくなるのです。 失敗を恐れる気持ちはあって当然ですし、失敗しないようにと慎重になることは間違いではありません。しかし、慎重になりすぎると「この働き方にはデメリットがありそう」「あの働き方はブラックかも」など発想がネガティブになり、理想の働き方が見つかりにくくなるので注意しましょう。 現状の不満や悩みに意識が向いているから 働き方がわからない状況から抜け出すには、自分の理想の働き方を見つける必要があります。しかし現状抱えている不満や悩みに意識が向きすぎている人は、「とにかく今の働き方を変えたい!」という気持ちが先行してしまって、なかなか理想の働き方を見つけられません。 理想の働き方がわからないと「どんな行動を取ればいいの?早く現状を変えたいのに!」と焦る原因にもなり、時にはNG行動に出てしまうことも…。 今の不満や悩みをきっかけに働き方を見直す人は少なくありませんが、新しい働き方を考える際は意識を切り替える必要があります。「こんな働き方は嫌だ」という視点から新しい働き方を考えることもできるので、嫌だと思うだけで終わらせず、そこから「どうすれば嫌じゃなくなるか」を考えてみましょう。 働き方に関する知識が不足しているから テレワーク、時短勤務、フレックスタイム制度など、現代にはさまざまな働き方があります。中には「名前は聞いたことがあるけどよく知らない働き方」もあるのではないでしょうか。働き方がわからないと悩むのは、このような多様な働き方について知識が不足していることが原因かもしれません。 知識量が少なければ、働き方の実態を具体的に把握できず、自分の希望に合っているのかもわからないのは当然です。 どんな働き方が自分に合うのかわからないときこそ、意識して情報収集を行いましょう。 情報は、自ら意識的に取りに行かなければ逃してしまうことが多々あります。仕事に追われている人や気持ちに余裕がない人ほど、視野が狭くなり新しい情報をキャッチしにくくなるので、意識して情報収集の機会を作ってください。 仕事に対する理想が高すぎるから 理想の働き方を考える際、誰もが働く条件の希望を考えるでしょう。しかし、企業規模や勤務地、給与、休みなど条件にこだわりすぎると働ける企業がなくなり、働き方がわからなくなる原因にもなり得ます。 また、最初は働き方を変えたいという動機だったのに、条件面を重視するあまり働き方については二の次になってしまい、結果的に理想とは異なる働き方をすることになるケースも少なくありません。 新しい働き方に対して理想を持つことは大切ですが、高すぎる理想は高望みになってしまいます。 高望みが過ぎると「自分が求める働き方なんて存在しない。どんな働き方をすればいいかわからない」とさらなる悩みにもつながりやすいので、スキルやこれまでのキャリアを考慮した現実味のある理想を掲げてください。 「働き方がわからない」を解決する方法 自分自身をよく分析しつつ情報収集することで、働き方の悩みから抜け出しやすくなります。ここからは、働き方がわからないと悩んだときに試してほしい5つの解決方法を紹介するので、ぜひ実践してみてください。 これまでの出来事から自分を知る まずは、自己分析から始めましょう。働き方にはさまざまな種類があり、自分の本質を深く理解して自分基準で働き方を選ばなくてはいけないためです。 過去の出来事を整理して客観視すると、そこから自分の長所や適性が見えてきます。たとえば、過去を振り返って以下の質問に答えてみてください。 楽しかった仕事は? 褒められた仕事は? やりがいや達成感を感じた仕事は? 今までで働きやすかった職場環境は? やっていて「嫌だ」「大変だ」と思った仕事は? 自分の特徴が把握できたら、それをヒントに強みを活かせる仕事や自分に合いそうな働き方を考えてみましょう。 働き方や企業の情報を集める 知識を増やさなくては、働き方についてわからないままですよね。今とは異なる働き方、業界、企業の知識を増やす努力をしましょう。ネットで情報収集したり、身近な人に話を聞いたりするだけでも、思わぬ知識を得られることがあります。 また、さまざまな企業が一堂に会して説明会を実施する転職イベントは、一度にたくさんの働き方が知れるチャンス。転職する意思がそれほど高くない場合でも、一度参加してみるのもいいかもしれません。 広く情報収集を続ければ次第に「合いそうな働き方」「合わなさそうな働き方」の輪郭がハッキリしてきて、働き方がわからない状況から抜け出せるはずです。 続けていけそうな働き方を考える しかし、ピンとくる働き方なんてそう簡単に見つかるものではありません。時には、自己分析したり情報収集したりしても、自分に合う働き方がわからないときがあるでしょう。そんなときは、「無理なく続けられそうか」という視点で働き方を考えるのがおすすめ。長く続けられそうと思える働き方は、自分にとってデメリットが少なく適性がある可能性が高いです。 ただし「一生続けられそうか」と長期的すぎる見方をすると、壮大なテーマにプレッシャーを感じて適切な判断ができないことがあります。 将来のキャリアビジョンを描く際は、重荷にならない程度の近未来でイメージするのがポイントです。 転職以外の選択肢にも目を向ける 今とは違う働き方がしたいと考えたとき、真っ先に思い浮かぶのは転職ではないでしょうか。確かに、勤める会社を変えれば必然的に働き方も変わります。しかし、働き方を変える方法は転職だけではありません。 働き方改革の進展により、リモートワークや時短勤務といった制度の導入、副業禁止規定の撤廃などを行う企業が増えてきました。このような制度を利用したり副業を始めてみたりすれば、今の会社で働き続けながら今とは違う働き方をすることも不可能ではありません。 転職しないと絶対に変えられない働き方を希望する場合は転職するのも一つの手ですが、働き方を変えることと転職をイコールで考えるのは安直です。 働き方を考える際は転職だけに重きを置くのではなく、現職に残る選択肢も持っておいてください。 他人の意見を参考にする 働き方がわからないときは、自分一人で答えを出そうとするのではなく、他人の意見を参考にするのも有効な解決策です。 自分一人だとどうしても思考が固くなりやすいですし、得られる情報量も限られます。また、考えていることや悩みを人に聞いてもらうだけでも、気持ちの整理ができるでしょう。 身近な人には話しづらいときや、専門的なアドバイスが欲しいときは、キャリアコンサルティングを受けてみるのもおすすめ。キャリアコンサルティングは、仕事や働き方に関する悩みに寄り添い、ベストな答えを一緒に探してくれるのが魅力です。 第三者の視点を取り入れることで自分の視野も広がり、一人では気づけない強みや適性が見つかることもあります。 働き方がわからない人のNG行動 ここからは、働き方がわからないときに取りがちなNG行動を紹介します。NG行動を取るとさらに悩みが深刻になったり、周囲の人に迷惑をかけてしまったりする可能性があるので注意しましょう。 感情のまま仕事を辞める 働き方がわからないと「一度労働から離れて、ゆっくり考えたい」と思うかもしれません。しかしその感情に任せて、転職先を決めずに退職してしまうのはNG。 大きなストレスを抱えている場合や心身に不調が出ている場合などは別ですが、突然の退職は安定収入が絶たれるリスクの大きい行為です。また、日頃から深く考えて行動する癖をつけなければ、転職失敗も起こりやすくなります。 仕事を辞めるのは、自分に合う働き方がわかってからでも遅くないはずです。わからないことをゆっくり考えたいなら、有給休暇を取って時間を確保するという方法もあるので、突発的に退職しないようにしましょう。 目の前の仕事を疎かにする 「自分に合う働き方がわからない…」と悩むと注意力が散漫になり、仕事のミスが増えることがあります。また、働き方がわからないという問題から派生して「そもそも何で働いているんだっけ」という虚無感に襲われ、一気に仕事に対するモチベーションを失ってしまうことも。 しかし、目の前の仕事を疎かにすれば一緒に働く人に迷惑をかけてしまいますし、あなたの評価が下がってさらなるモチベーションダウンになります。 仕事に一生懸命取り組むと、意外な面白さや自分の適性が見つかることもあるので、勤務中は気持ちを切り替えて働きましょう。 安易な資格取得に励む いくら考えても自分に合う働き方がわからないと、資格取得を目指す人もいます。資格取得に向けて勉強している間は働き方について悩まなくていい上、いつか資格が役に立ちそうだからというのが主な理由です。 しかし、資格取得は悪いことではないものの「何となく役立ちそうだから」という安易な理由では取得しないほうが賢明でしょう。安易な資格取得は一種の現実逃避であり、資格を取ってもわからない働き方がわかるようにはなりません。 また、資格を取ると「この資格を活かせる働き方をしなきゃ…」という考えに捉われて、選択肢が狭まってしまうリスクもあります。 自分に合う働き方がわからなくても焦らないことが大切 「自分に合う働き方がわからない」と悩む人は多いです。また、かつては自分に合う働き方ができていても、長く働くうちに違和感が出てきて働き方に悩むこともあります。 合う働き方がわからないときは、焦らず自分の心と向き合うことが重要です。 なぜ今の働き方に違和感があるのか、どんな働き方なら自分に合いそうかなど丁寧に本音を探り、そこから理想の働き方を考えてみましょう。

働き方や仕事の相談をするのが苦手…原因&克服方法を解説
選択肢が豊富で明確な正解がないからこそ、働き方の悩みは大きくなりがち。仕事をしていると、働き方に対して悩みや不安を抱き「誰かに相談したい」と思うこともありますよね。 しかしそんなとき、つい「相手の迷惑になるのでは」「どうせ何も変わらない」と考えて、悩みを相談できない人もいるのではないでしょうか。 本記事では、働き方や仕事の相談をするのが苦手な人に向けて、原因、克服方法、うまく相談するコツを解説します。 働き方の悩みを相談できない原因 なぜ、働き方や仕事の悩みを人に相談できないのでしょうか?まずは「相談できない」「相談するのが苦手」という人が抱えやすい原因を解説します。 人に気を使いすぎる性格 優しくて、人に気を使いすぎてしまう性格の人ほど、相談できずに一人で悩みを抱えやすいです。このような人は悩みがあっても「相談すると心配をかけるのでは」と遠慮したり「今は忙しそうだから相談しないでおこう」と相手に配慮したりします。 自分よりも相手を尊重し、他人に迷惑をかけたくないという気持ちが強いため、悩みや迷い、トラブルに直面しても一人で乗り切ろうとするのでしょう。 しかし、気配り上手で自立心が強いからこそ「自分で何とかしないと」と自分で自分にプレッシャーをかけてしまい、一度悩むとそこからなかなか脱出できません。 プライドが高い プライドが高い人は「人からどう見られるのか」を強く意識して、本当の自分以上に自分を良く見せようとすることがあります。 このような人にとって、相談して悩んでいる姿を人に見せることは自分の弱さを人に見せることと同じであり、プライドが邪魔をして人に相談できないのです。 また、プライドが高い人は自分のプライドを傷つけられることを極端に怖がり、臆病な一面があります。「話を聞いてほしいと言って断られたらどうしよう」「相談に共感してもらえなかったらどうしよう」と考えてしまい、相談する勇気を持てません。 思考が閉鎖的 働き方について悩んだとき、誰にも会いたくない気分になったり、人から放っておかれたいと強く思ったりする人は、閉鎖的な思考の持ち主かもしれません。 考え方が閉鎖的な人は、悩めば悩むほど自分の殻に閉じこもり、人に相談しようという発想すら抱かない傾向があります。また、自分とは異なる考え方や別角度からの見方を受け入れられず、自分の考えに固執して頑なになってしまうのも、閉鎖的な思考を持つ人の特徴です。 しかし、思考が閉鎖的だと客観的視点が得られず極端な考え方に陥りやすいため、悩みがさらに長期化するリスクがあります。 過去の相談経験にトラウマがある 相談は、持ちかける相手やタイミングを間違えるとちゃんと話を聞いてもらえなかったり、見当違いなお説教をされたりすることがあります。 そして、このような相談失敗の経験がトラウマになって、働き方や仕事について相談できなくなってしまう人も多いです。 「人に相談する」という行為は決して簡単ではなく、勇気が必要なもの。せっかく勇気を出して相談したのに誠実に向き合ってもらえないと「相談には何の効果もない」「相談しても無駄」だと感じて、相談することの大切さを見失ってしまうでしょう。 働き方の悩みを相談する効果 働き方や仕事の相談をするのが苦手な人は「相談しても意味がない」という考えを持っていることが多いです。 しかし、悩みを誰かに相談することには、さまざまな良い効果があります。ここからは、働き方の悩みを人に相談する効果・メリットを紹介しましょう。 気持ちが軽くなる 悩んでいる期間は、不安や不満、迷いが心に負荷をかけ、ストレスになっています。そんなとき、相談を通じて自分の胸の内を誰かに話すと、心の中にあるモヤモヤを排出できるのでストレス軽減になり気持ちが軽くなるでしょう。 また、相談すると相手から「わかるよ」「それはつらいね」など、共感が得られることもあります。他人に共感してもらえると「自分は一人ではないんだ」と思えて孤独感が和らぐので、自然と気持ちが前向きになるはずです。 気持ちが軽くなって前向きになれば考え方もポジティブになり、悩みや迷いからも抜け出しやすくなります。 客観的視点が得られる 一人で悩んでいるとどんどん頭が混乱してきて、問題を事実以上に大きく捉えてしまうことがあります。 しかし、誰かに相談するとなれば「現状に起きていること」や「自分の希望」を誇張なしに言語化する必要があり、問題を客観的に捉えられるでしょう。 さらに、物事を順序だててわかりやすく説明しようとすることで、悩みの原因や自分の気持ちを整理できるのも相談による効果です。 客観的に悩みや問題を捉えられれば解決方法も見つけやすく、悩みの長期化防止にもつながります。 アドバイスが得られる 人に相談すると、自分とは違った視点や知識、経験を持つ人からのアドバイスがもらえます。 時には「そのアドバイスは、自分の考えとは合わないかも」と思うこともあるかもしれません。しかし、合う・合わないの判断材料にはなっていることから、自分の意見と異なるアドバイスにも価値はあるのです。 働き方に関する悩みは根深いことも多く、多くの人から意見を聞いて多角的に物事を判断したほうが、後悔しない答えに辿り着ける可能性が高まります。相談によってアドバイスが得られれば、自分が持つ知識・情報の枠を広げられるはずです。 「働き方・仕事の相談が苦手」を克服する方法 相談したり人を頼ったりするのが苦手な人は、いざ誰かに悩みを相談しようと思っても「どうやって相談すればいいのかわからない」という新たな悩みにぶつかることがあります。 ここでは、苦手を解消するための克服法を解説するので、ぜひ実践してみてください。 情報を整理する 相談しているうちに自分でも何を言っているのかわからなくなり、相手にうまく悩みが伝わらなかった…という経験をしたことがある人は多いはず。このような事態を避けるため、相談はいきなりするのではなく、前もって情報を整理してから行うのがおすすめです。 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」の3つの観点で情報を整理しておけば、悩みや自分の希望を言語化しやすくなります。 頭で考えるだけだとうまく整理できないときは、一度紙に書き出してから必要な情報だけをピックアップしてみてください。 具体的なエピソードを振り返る 「何があったのか」「どんなことに困っているのか」「何を求めているのか」という相談の要点がまとまったら、話の肉付けに必要な過去の事例も振り返りましょう。 相談は、具体的なエピソードを盛り込んだほうが伝わりやすく、共感や適切なアドバイスが得られます。そのため、悩んでから起きた事象や悩む前と悩んだ後の心境の変化などを、相談前にしっかり振り返り把握することが大切です。 ただし「あれもこれも」とエピソードを詰め込みすぎると、聞き手に冗長な印象を与えるので要注意。起きたこと全てを話すのではなく、自分にとって大きな出来事や重要なエピソードだけを簡潔にまとめてください。 相談を後回しにしない 働き方や仕事の相談が苦手な人は「うまく話せないかも」「相談したい相手が忙しそうだから」などの理由で、相談するのをためらったり後回しにしたりすることがよくあります。 しかし「また今度でいいや」と考える癖がつくと、何かと理由をつけてまた今度、またまた今度…と後回しを繰り返して、結局いつまで経っても相談できません。 「報告・連絡・相談は早めに」とはあらゆる場面で言われていますが、それは働き方に関する相談でも同じです。悩みを長期間一人で抱えることには苦痛が伴い、さまざまなリスクがあるので、相談を後回しにするのはやめましょう。 不利なことも隠さず話す 相談時は本音で話すのが鉄則なので「こんな本音を話すと、相手から悪く思われるのではないか」と不安になることがあるかもしれません。 しかし、たとえ自分にとって不利なことであっても、相談の場では隠さず話したほうがいいです。全ての情報を正しく伝えなければ、相手からのアドバイスも的外れなものになってしまいます。何より、わざわざ時間を使って心を砕いてくれた相談相手を騙すような行為は、単純に失礼ではないでしょうか。 隠していたことがバレて情報を後出しすると、その後で気まずくなる可能性もあります。相談に乗ってもらう際の最低限のマナーとして、正直な態度を貫きましょう。 キャリアコンサルタントを頼っても◎ 働き方の悩みを相談する相手は、家族や友人、上司、同僚など、信頼できる人であれば誰でも構いません。ですが、中には「身近な人には相談しにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人もいるのではないでしょうか。 働き方や仕事にまつわる話は、キャリアコンサルタントに相談するという方法もあります。 キャリアコンサルタントは、じっくり話を聞いて最適な答えを一緒に考えてくれる、働き方・仕事の悩みに関するスペシャリスト。相談者が抱える悩みや問題を丁寧に深掘りしてアドバイスを授けてくれるので、口下手でちゃんと話せるか心配な人でも安心です。 相談相手が見つからないときや、プロの助言で効率的に問題解決したいときは、ぜひキャリアコンサルタントを頼ってみてください。 働き方について上手に相談するコツ よりわかりやすく相談するためには、いくつか押さえたいポイントがあります。働き方について上手に相談するコツを掴んで、相談力をより高めてください。 「上手に伝えなくちゃ」と思わない 相談する際、聞き手のためにわかりやすく伝える工夫をすることは大切です。 しかし、絶対に上手に伝えないといけないわけではありません。伝え方にこだわりすぎると「まだうまく話せないから相談しないほうがいい」と考えて、相談を先延ばしにしやすくなるので注意しましょう。他にも「上手に話さないと」と強く思う気持ちがプレッシャーになり、余計に話せなくなってしまうというケースも。 事前に情報やエピソードをまとめていれば、大きく本筋からずれた内容が伝わる可能性は低いですし、多少わかりにくい部分はコミュニケーションを通して補完できます。「上手に伝えなくちゃ」と身構えるのではなく、リラックスして本音で話すことが大切です。 相談するときは事前にオファーを出す 聞き手の都合によっては、今すぐ相談に乗れないこともあります。そのため相談する際は「今度、相談に乗ってくれませんか?」と、前もって相談したい相手にオファーを出しておきましょう。 事前に約束を取り付けておけば、急に相談を持ち掛けて相手を驚かせる心配がありませんし、相手の時間に余裕があるタイミングで話を聞いてもらえるはずです。 相談して話を聞いてもらうということは、相手の時間を自分のために使ってもらうということでもあります。だからこそ相手の都合に配慮して、できるだけ負担にならないよう予定を合わせてください。 遠慮せず質問する 相談とはコミュニケーションの一種であり、こちらが一方的に悩みを話したり、相談された人が一方的にアドバイスしたりするものではありません。「聞く」「話す」をバランスよく繰り返し、その対話の中で悩み解決の糸口を見つけるのが、相談の正しい形と言えます。 よって、相手の話にわからない点や誤解がある場合は、臆することなく質問・訂正をしましょう。 もちろん聞き方や伝え方に配慮は必要ですが、遠慮は必要ありません。事実を伝えてお互いの認識のずれをなくし、そこから解決策や着地点を考えたほうが、働き方の悩みから早く抜け出せるはずです。 悩みやすい働き方。相談する大切さを知ろう 現代の働き方は多様化しており、種類や選択肢が増えたからこそ、迷ったり悩んだりする人も増えました。働き方の悩みは深刻化しやすく、一人で長期間抱えると心身に悪影響を及ぼす恐れもあります。悩んだときは「自分の力で何とかしよう」と考えるのではなく、その悩みを誰かに相談してみましょう。 最終的な答えを見つけるのは自分自身ですが、話を聞いてもらうだけでも心は軽くなりますし、新たな視点が得られれば一人で悩むよりも早く答えに辿り着ける可能性が高いです。 相談スキルは人生のあらゆるシーンで役立つので、まずは相談する大切さを知って、ぜひ一歩踏み出してみてください!
あわせて読みたい!

「自分のしたい仕事がわからない」からの抜け出し方
自分のしたい仕事が何なのか? 普段はそれを突き詰めて考える機会はなかなかありませんが、しかし、就職活動中や今の仕事がどうして合わず転職を考えているときには、「自分は何がしたいのか?」という問題に正面から向き合わなければならなくなります。 それでも、 とはいえ、あの仕事もこの仕事も興味がある。 もしくは、あの仕事もこの仕事も興味がない。 という自分のしたい仕事がわからず、答えがみつからない人も少なくありません。 「自分がしたい仕事は一体何なのか?」そんな袋小路に入ってしまったら、一旦肩の力を抜いてこう考えてみませんか? 781

就職活動でどこにも受かる気がしない時に気づいてほしい3つのこと
就職活動が始まって、会社説明会とか面接とか行ってみたけれど、一次面接もなかなか通過しないし、なんだかどこにも受かる気がしない…。 3月から一気にスタートして、次々に直面する現実に、思わず気が滅入ってしまっていませんか。 学生時代のコミュニケーションや、インターンシップとはまた違う、面接でのコミュニケーションに慣れず、「これで面接に受かるんだろうか・・・」と不安に感じてしまう気持ち、よくわかります。 さらに、空前の売り手市場と言われるなか、どんどん選考が進み、早くも内々定をもらう友人知人がいれば、焦りも生まれてしまいますよね。 就職活動でどこにも受かりそうな気がしなくて、ずっしり落ち込んでしまいそうになったら、面接のこんな一面をぜひ知ってください。 778

就職内定先が合わない!今から辞退したいときの考え方
入社が現実的になってきたからこそ、「やはり内定先が合わないかも…」という思いが拭えなくなってしまうことは、よくあります。 「今さら…」ではなくて、「辞退するなら今」という思いがどこかにあるからこそ、「内定先が合わない」という気持ちは大きくなってしまうものです。 辞退すべきかどうするか、迷ってしまったらこう考えてみませんか。 768