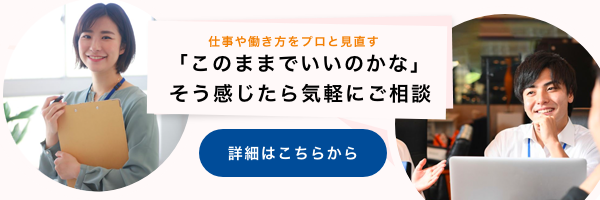キャリアがなんとなく不安!転職を考えている方へ
「私のキャリアって、このままでいいのかな…」
「なんとなく不安…」
「周りに転職している人が多いから、私も考えようかな…」
漠然としたキャリアの悩みを持っている方は、たくさんいます。今日は、キャリアに対してもやもや、漠然とした不安を抱えているあなたへ、転職を考えているあなたへ、お送りします。
このコラムを読んだ後には、その不安への解決策、考え方をわかっていただけると思います!
キャリアを不安に思っている人は多い

大前提として、キャリアに不安を感じている人は、とても多いです。
インターネット検索で、「キャリア」を打つと、上位に「不安」「転職」と予測変換が表示されます。このことから、多くの方が、キャリアに対してもやもやを感じていることがわかります。
キャリアに対する不安の例
では、具体的に、どういう不安を抱えているのでしょうか?今回は、例として、7つご紹介します。
年収が不安

「給与がどんどん減っていき、この先のお金の面が心配…」
「いつ会社がつぶれるかわからないし、終身雇用も崩壊したのでいつクビになるかもわからない…」
「どんどん物価が値上がりして、毎日の暮らしで精いっぱい…」
お金に関する不安は、切っても切り離せません。
やりがいがなくて不安
「今の仕事が全然楽しくないので、これがこのままずっと続くと思うと、不安」
「他になりたいことがあるのに、こんな仕事のままでいいのかな…」
仕事内容にやりがいを感じていない人は、不安に思う傾向があります。
働き方が不安
「今の仕事が激務で、深夜まで残業があるので、体力的に続けられないかも…」
「毎日出社だけれど、子どももいるし、リモートワークで働きたい…」
そんな働き方に関する不安です。
業界や仕事に将来性を感じない
「今の業界が、どんどん傾いて減収しているので、とても不安を感じる」
「今の仕事を続けていても、将来役に立つかわからなくて、将来性を感じることができない…」
今はAIなど技術の進化も早く、変化のスピードが速い時代。将来が不安になってしまう企業や業界もあるでしょう。
今の仕事に必要なスキルや知識が不足している
「今の仕事はやりがいを持っているけれど、スキルや知識が不足していて、しんどい…」
「周りが自分より専門性があるので、なんとなく疎外感を感じている…」
求められるレベルと自分自身の現状に不釣り合いを感じているケースです。
職場の環境
「人間関係がうまくいっていなくて、つらい…」
「職場の安全面で不安があるので、転職を考えている…」
人間関係や職場の安全面などで、不安を抱えている場合もあります。
語学力が足りていない

「上司が外国人になり、コミュニケーションがうまく取れず悩んでいる…」
「ミーティングが英語ばかりになってしまい、疲弊している」
今や多くの企業がグローバルを視野に進出しているので、英語力などがないとしんどいと感じる部署があります。
などなど、あなたにも心当たりがある不安がありましたか?例外はあると思いますが、多くの人の悩みは上記のいずれか、もしくは複数に当てはまるのではないかと思います。
キャリアの不安に対して、実行していること

では、その不安・悩みに対して、なにか実行していることはありますか?ここでは、一般的に実行している人が多い対策を挙げていきます。
資格取得を目指す
「資格を取得して、専門性と市場価値をあげて、年収アップを図っている」
「今の職場を離れて、別の会社に行きたいので、資格勉強をしている」
業務に必要とされる資格に興味を持っている人、実際に行動を起こしている人は多くいます。前向きに資格の勉強をすると、どんどん市場価値も上がりますね。
自己分析をする
「自分にどんな仕事が向いていて、何が得意なのか、改めて自己分析をしている」
「キャリアへの価値観の棚卸しなどを実践している」
などなど、自分のことをより理解すると、今後の仕事選びにも活きていきます。
キャリアコンサルタントに相談する
「国家資格をもつ、キャリアコンサルタントの方に相談している」
「キャリアコンサルタントに定期的にコーチングのように話を聞いてもらっている」
プロの専門家に相談すると、悩みもすんなり解決することがあります。
転職活動をする
「自分をもっと評価してもらえるような会社を探して、転職活動をしている」
「テレワークという働き方を実現するために、転職活動中」
転職はリスクはありますが、自分の望む条件を叶えやすい方法です。
転職がうまくいく人の特徴

転職という選択肢をとった方の中でも、転職がうまくいく人と、うまくいかない人がいると思います。
その違いは何なのでしょうか?3つご紹介します。
転職の軸をしっかり考えている
転職がうまくいく人は、転職の軸をしっかり考えています。具体的には、
・年収は今いくらくらいもらっていて、次は○○万円以上ほしい
・職種は○○か○○が良い
・業界は○○の分野か、○○の分野
・働き方は、残業○○時間以下は譲れない
・勤務はテレワークが良い
などなど、自分なりの軸をもって、転職活動に挑んでいます。
もし、自分なりの軸をもって転職をしていないと、エージェントの言葉をうのみにしてしまったり、望まない業界に入ってしまったりするなど、ミスマッチが起こりやすくなります。
「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないためにも、転職の軸を決めることが大切です。
中長期的なキャリアビジョンを持つ
転職がうまくいく人は、中長期的なキャリアビジョンを持っていることが多いです。
中長期的なキャリアビジョンとは、「5年後こうなっていたい」「10年後はこういう働き方をしていたい」などの、少し先の未来を思い描いて、計画を立てることです。
「5年後、10年後なんて、わかりっこないよ!」という方もいらっしゃると思いますが、ビジョンを持つことで、人間の脳はそのビジョンを目指して無意識的に動くこともあります。
漠然としたイメージでもいいので、中長期的なキャリアビジョンは持つようにしましょう。
自己分析をする
では、転職の軸を決めたり、中長期的なビジョンを持ったりするためには、どんなことをするとよいでしょうか?
それは、自分のことを知る、つまり自己分析です。
あなたは、自己分析をしたことがありますか?就職活動を経験した方なら、ほとんどの方に経験があると思います。
ただ、就職活動以来、たいして自己分析をしていないな…という方も多いのではないでしょうか?今日は、自己分析の方法もご紹介します。
自己分析の方法

自己分析をするための手法には様々なものがありますが、代表的な5つをご紹介します!
SWOT分析
SWOT分析は、以下の4つの要素から構成されています。
①Strengths(強み):自分が持っている優れた能力や資質、経験、人脈など
②Weaknesses(弱み):自分に不足している能力や資質、経験、人脈など
③Opportunities(機会):自分にとって、活躍できる可能性があるもの。
④Threats(脅威):自分とって、活躍しにくい要因となるもの。
SWOT分析は、自己分析だけではなく、企業やチームなどの分析にも応用されることがあります。
自分自身を客観的に見つめ直して、キャリアの方向性を見出す上で非常に役立つ手法と言えます。
MBTI診断
Myers-Briggs Type Indicatorの略称で、人格の傾向を16種類に分類して、自分自身のタイプを特定する手法です。
ちなみに、MBTIとは、以下の4つの要素から成り立っています。
①Extraversion(外向性)- Introversion(内向性)
②Sensing(感覚的)- Intuition(直感的)
③Thinking(思考型)- Feeling(感情型)
④Judging(判断型)- Perceiving(知覚型)
自分がどのタイプか、無料で診断できるサイトもありますので、気になる方はぜひ試してみてください!
ジョハリの窓
自分の意識している部分と、意識していない部分に分けて、情報を整理して、自己理解を深めるための手法です。
①開放の窓…自分も知っているし、相手も知っている部分
②秘密の窓…自分は知っているけれど、相手は知らない部分
③盲点の窓…自分は知らないけれど、相手は知っている部分
④未知の窓…自分も知らないし、相手も知らない部分
上記の4つに分けて分析します。
開放の窓をどんどん広げていくと、コミュニケーションが取りやすく良いとされています。
ライフラインチャート
自分自身の今までの経験を年代別に分けて、それぞれの時期で経験したことや感じたことを整理し、自己理解を深める方法です。
イベントごとに感情やモチベーション、幸福度の状態などを掘り下げていきます。
「あの時引っ越しをして、幸福度が上がったな~。なぜなら…」
「あの職場は○○の部分で自分に合わずに、モチベーションが下がったな…。具体的には…」
など、今までの経験をじっくり、具体的に、棚卸しをすることで、自分の人生の価値観や傾向などを把握することができます。
見つけた価値観は、今後も自分の価値観として動く可能性が高いので、その価値観に合った方向性を考えていきましょう。
周りに自分の長所・短所を聞いてみる
家族や友人、職場の人など、周りに自分について質問するのも、自己分析に役立つ手法です。
「私ってどんな強みがあると思う?」
「どんなところが課題かな?」
など、問いかけてみることによって、ジョハリの窓でいうと「他人が知っていて、自分が知らない」盲点の窓に気づくことが出来るチャンスがあるかもしれません。
周りの人々は、自分が思っている以上に、自分のことを観察してくれているものです。
転職以外の選択肢もある

ここまで、転職がうまくいく人の特徴や、自己分析について解説してきました。ただ、キャリアに不安がある場合は、転職以外の選択肢もあります。
どのようなものがあるのでしょうか?一緒に見ていきましょう。
今の会社で異動できるか、探ってみる
わざわざ転職をしなくても、あなたの望む状態を叶えられる場合があります。「異動で、問題を解決できるかも…?」と感じた方は、以下の方法も参考に、考えてみてください。
①会社内の情報を収集する
異動についての情報は、会社内のどこかに存在しています。まずは、上司や人事部の担当者、同僚などに異動に関する情報を聞いてみると良いでしょう。また、社内のポータルサイトや社内報などからも、情報を収集できます。
②自分でアプローチをする
自分から上司や人事部に異動の希望を伝えることも重要です。自分がどのような異動を希望しているかを明確に伝え、それに合った異動先がある場合は、チャンスをつかむことができます。
副業をする
また、転職の他に、「副業をする」という選択肢もあります。副業のメリットは下記をご参考ください。
①収入源を多様化できる
副業を持つことで、収入源を多様化することができます。本業だけでなく、副業の収入も得られるため、収入面でのリスクを分散することができます。
②新しいスキルや知識を身に着けられる
副業は、本業とは異なる分野で働くことができるため、新しいスキルや知識を習得することができます。これにより、自己成長やキャリアアップにつながることがあります。また、これが転職のアピールポイントになることも多いです。
副業は転職とは異なる形でキャリアアップや自己成長につながる可能性があります。ただし、副業を行う場合は、本業に支障が出ないように十分注意することが大切です。
フリーランスになる
また、フリーランスになるという選択肢もあります。
フリーランスになることで、自分自身のスキルや経験を最大限に活かし、自由な働き方をすることができます。
ただし、フリーランスになることは、自己管理やビジネススキルが必要になるため、自己研鑽やリスクマネジメント能力の向上が必要となってきます。
さいごに

キャリアが不安で転職を考えているということは、言い換えると新しい挑戦や成長を求めているということです。
転職は、自分自身を成長させ、自分の人生を変える機会でもあります。
まずは、自分自身が本当にやりたいことや、どのようなキャリアを目指したいのかを明確にすることが大切です。
転職にはリスクが伴いますが、自分自身のスキルや経験を客観的に見つめ直し、不足しているスキルや知識を習得することで、成功確率を高めることができます。
転職は一つの選択肢にすぎません。焦って何者かになろうとするのではなく、「本当は自分は何を達成したいのか?どうなりたいのか?」を、じっくり自分と向き合って考えていきましょう。

キャリアと子育ての両立は難しい?実現させるポイントと疲れたときの対処法
子育てしながら働く女性は増加傾向にありますが、キャリアと子育ての両立は簡単ではありません。 「子育て」と一括りにいっても、その中には「家事」と「育児」が含まれます。ワーママは「仕事」「家事」「育児」の3つを掛け持ちしているような状態ゆえに、さまざまな悩みに直面しやすいです。 この記事では、キャリアと子育ての両立を目指す人に向けて、実現させるためのポイントや、疲れたり悩んだりしたときの対処法を解説します。 キャリアと子育ての両立が難しい理由 キャリアと子育ての両立を難しく感じる理由は、個人の環境によって異なります。難しいと感じる代表的な要因を解説するので、まずは自分にとって何が障壁となっているのかを把握しましょう。 家事育児の負担が大きい 考え方は少しずつ変化しつつあるものの、日本では家事や育児の多くを女性が担う傾向が依然として強く見られます。フルタイム勤務を終えた後も、子どもの迎えや夕食づくり、洗濯、掃除などやることがたくさんあり、大きな負担を感じるケースは少なくありません。 また、子どもは急に機嫌が悪くなったり体調を崩したりすることも日常茶飯事。効率的にスケジュールを組んだとしても、予定通りに進むことはほとんどなく、大人側は自分の時間や睡眠時間の確保に苦労します。 職場や上司の理解がない 子どもがいると、独身時代のようには働けません。仕事が終わっても家事育児があるので残業をするのは難しいですし、子どもの体調不良を理由に急な欠勤も多くなります。 そんなとき、上司から嫌な顔をされたり、職場の人から心ない言葉をかけられたりして、傷つく経験をした人も多いです。 重要な仕事を任せてもらえなくなるケースもあり、会社に居心地の悪さを感じて、キャリアと子育てを両立する難しさを実感することもあるでしょう。 成果を出す難易度が高くなる 子育て中だとしても、仕事をしている限り成果を求められます。しかし、子育て中はどうしても仕事に割ける時間や集中力が限られるため、仕事だけに全力投球できた子なし時代と比べると、成果を出す難易度は高くなりがちです。 定時で帰ったり欠勤したりすることによって「大事な情報を自分だけ知らない」という状況も起こりやすく、思うように成果を出せないことに焦りや不安を感じるかもしれません。 成果に満足できない状態が続くと「キャリアと子育ては両立できないかも」と弱気になりやすいので、精神的にも疲弊してしまいます。 家族の協力が得られない キャリアと子育てを両立するためには、働きながら子育てする難しさをパートナーや親族に理解してもらい、協力を得る必要があります。パートナーが家事や子育てに協力的ではない、親に気軽にサポートを頼めないなどの条件が重なれば、あなた一人に負担が集中して悩むのは当然でしょう。 特にパートナーには、一緒に子育てをする責任があります。共働きであるにもかかわらず、パートナーが家事や子育てに非協力的だと、不満や悲しみから夫婦仲が悪化する可能性も高いです。 常に時間に追われて休めない 仕事をしながらの子育ては、分刻みのタスクの連続です。 保育園の登園時間に間に合ったら、今度は自分の出勤時間を意識、仕事中は定時で帰れるよう時間管理を徹底して、終業後はまたお迎え時間に間に合うよう急ぐ…。さらには帰宅してからも、子どもの食事や就寝が遅くならないよう常に時間に追われ、一日のタスクが終了する頃にはへとへとという人も多いでしょう。 子育てはいつまでも続くものではなく、このような慌ただしい日々もいつかは終わりを迎えます。とはいえ、子どもに手がかからなくなるまでにはある程度長い年月がかかるため、終わりの見えにくい日々に疲れを感じやすいです。 キャリアと子育てを両立するためのポイント キャリアと子育てを両立するためには、いくつかカギとなる考え方や行動があります。7つのポイントをお伝えするので、ぜひ実践してみてください。 完璧主義をやめる 限られた時間の中で、仕事・家事・育児の全てを完璧にこなすのは不可能です。そもそも、家事や育児には正解がなく、やろうと思えばどれだけでもタスクを増やせてしまいます。 全てにおいて完璧を目指すと、やるべきことが増えて負担が大きくなる上、タスクを完遂できなかったときには精神的にもダメージを受けるでしょう。 「完璧」や「100点」を目指すのではなく、最初から無理のない範囲で仕事と家事を両立することを意識するのが大切です。 優先順位をつけてから物事に取り組む あれもこれもと一度にたくさんのことに手を付けると、うっかりミスが増える、全部が中途半端になるなどの状況に陥りやすくなります。 物事を効率的に進めるためには、タスクに優先順位をつけ、一つ一つを確実にこなしていきましょう。 また、子育て中は優先順位をもとに予定を組んでも、突発的なトラブルにより予定通りにいかないこともしょっちゅうです。そのため、必要に応じて優先順位を入れ替える柔軟性も身につけてください。 家庭内の役割分担を明確にする 家事育児の役割を片方だけが担うのは負担が大きく、不公平感から不満が募るのも無理ありません。家庭内不和を回避するためにも、パートナーや家族と相談して、あらかじめ家庭内の役割分担を決めておきましょう。 なお、子どもの成長や仕事の状況の変化によって、担える役割が変わる場合もあります。そのため役割分担に関する会話は一度して終わりではなく、定期的に認識のすり合わせを行い、家族みんなが納得のいく生活を送れるよう配慮してください。 「頼り上手」を目指す 他人に頼るのが苦手な人ほど、全てを自分一人で抱え込んでしんどくなりがち。キャリアと子育てを両立させるためには、周囲の人や家族に頼るスキルも身につけなくてはいけません。 自分の苦手なことやできないことを、恥ずかしがらずに伝えるだけでも、助けてもらえる可能性はぐんと上がります。 他にも、頼むタイミングを見極める、頼むときの言葉選びに気をつける、助けられた際にはしっかりお礼を言うなども、頼み上手になるために意識すべきポイントです。 罪悪感を持たない 子育てをしながら仕事をすると、急な早退・欠勤によって一緒に働く人に負担を強いてしまう場合があり、罪悪感を抱きやすいです。また、仕事をしながら子育てをすることで、十分な育児時間が取れていないように感じられ、子どもにまで罪悪感を持つケースも。 しかし、罪悪感は自信喪失やストレスの増加などを招き、どんどん心の余裕を奪っていきます。 うまくできなかったことを反省するのも大切ですが、できたことや頑張ったという事実にも目を向け、罪悪感を長引かせないようにしてください。 子どもと過ごす時間を決めておく 慌ただしい日常の中では、なかなか子どもとゆっくり過ごす時間が取れません。「空いた時間で子どもに話しかけよう」と思っていると、バタバタしてちゃんと話す間もなく一日が終わってしまうなんてこともしょっちゅうです。 しかし親だけでなく子どもにとっても、親子で過ごす時間はかけがえなく大切なもの。そのため、前もって一日の予定の中に「子どもと過ごす時間」を組み込んでおいたほうがいいでしょう。 親子間で毎日コミュニケーションが取れていれば信頼関係が構築され、子どもに対する罪悪感も生まれにくいです。 支援サービスや会社の制度を活用する 地域の支援サービスや会社の制度をうまく活用するのもおすすめです。 たとえば、どうしても子どもの面倒を見るのが難しい場合は、市区町村または委託された団体が運営する子育てサポート組織「ファミリーサポート」を利用するのも一つの手といえます。他にも、リモートワークや時短勤務が可能な会社なら、このような制度を利用するのも有効です。 サービスや制度を活用することで、キャリアと子育てを両立する際に生じる負担を小さくできる可能性があります。 サービスや制度は知らない間に新設されている場合も多いので、まずは、自分が住む地域や働く会社にどのようなサポート体制があるのかを調べてみましょう。 キャリアと子育ての両立に疲れたときの対処法 キャリアと子育てを両立すると、どちらにも手を抜けず「疲れた」「しんどい」と感じることもあります。ここでは、そんなときに試してほしい対処法について解説します。 同じ境遇のワーママと話す しんどさや悩みを一番理解してくれる相手は、やはり同じ辛さを経験したワーママです。ワーママと話すと「わかる!」「大変だよね!」とお互いに共感し合えるので、孤独感が和らぎ気持ちが明るくなるでしょう。 また、相手が先輩ワーママである場合は、経験をもとにした「キャリアと子育てを両立させるコツ」をアドバイスしてもらえるかもしれません。 さまざまなワーママの意見や体験談に触れると視野が広がり、自分に合った困難の乗り切り方が見つかりやすくなります。 家族会議を開く 家族にやってもらいたいことや、今抱えている悩みを相談する場として、カジュアルな家族会議を定期的に開くのもおすすめです。 親やパートナーに相談して協力が得られれば、キャリアと子育てを両立する負担を小さくできます。 もちろん、家族にも各々事情や都合があり、相談してもすぐには解決しないかもしれません。しかし、あなたの悩みや負担を家族が把握することで、気にかけてもらえたりサポートしてもらえたりする機会はぐんと増えるでしょう。 自分の時間を作る あまりにも自分の時間がなさすぎると、心に余裕がなくなって疲労を感じやすくなります。キャリアと子育ての両立に疲れたときは、思い切って自分一人の時間を作り、リフレッシュするのも効果的です。 パートナーや家族に頼めるなら子どもを見てもらえばいいですし、難しいなら一日くらい家事をサボってもいいでしょう。 仕事はともかく、家事育児はやってもあまり人から褒められにくいので、自分で自分を労ってモチベーションアップを図ってください。 働き方を見直す 今と異なる働き方をすれば、キャリアと子育てを両立する負担が減り、家事育児にゆとりが生まれる可能性があります。特に現代は、柔軟な働き方を推奨する傾向が強まっているため、今の会社でキャリアを維持したまま働き方だけ変更できるケースも多いです。 時短勤務や在宅勤務、フレックスタイムなどを導入する企業も増えているので、このような働き方ができないか検討してみましょう。もしも会社の制度が整っていなくても、相談してみると承諾してもらえることがあります。 キャリアと子育てを両立しやすい会社への転職を検討する 業務内容によっては、どうしても働き方を変えられないこともあるでしょう。また、社風として子育てへの理解がない、職場と家が遠いなど、働き方以外の理由で両立するのが難しい場合もあります。 今の会社ではキャリアと子育てを両立できないと感じたら、育児しながらでも働きやすい会社へ転職するのも選択肢の一つ。 転職先を探す際は、子育てサポート企業の証である「くるみんマーク」を取得している会社を選ぶと、子どもとの時間も大切にしながら自分らしく働ける可能性が高いです。 両立に悩んだら、キャリアのプロに相談するのもおすすめ キャリアと子育ての両立に悩みはつきもの。特に働き方の見直しや転職を検討している人は、それらを実行することで積み上げたキャリアがなくなるのではと不安になっている人もいるでしょう。 「身近な人には相談しにくい」「的確なアドバイスが欲しい」という場合には、キャリアコンサルティングを受けるのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、相談者の価値観を整理しながら、正しい情報や的確なアドバイスを提供してもらえます。キャリアのプロに相談すれば自分自身の不安や疑問を解消でき、自分の状況や自分が大切にしたい価値観を整理しながら、キャリアと子育てを両立するための活路が見つかるはずです。 工夫を積み重ねて、上手にキャリアと子育てを両立しよう 共働きの世帯割合は全体の約7割に達していますが、共働きが浸透してもキャリアと子育ての両立は未だに難しく、子育てしながら働く女性の毎日はハードになりがちです。 キャリアと子育てを両立するためには、家族に協力してもらいながら小さな工夫を積み重ね、必要であれば働き方や職場の見直しも行いましょう。 難しいのは事実ですが、キャリアと子育てを両立するのは不可能ではありません。悩んだときは経験・実績共に豊富なキャリアコンサルタントを頼りつつ、キャリアと子どもの両方を大切にする方法を探していきましょう。

仕事の人間関係がストレス!割り切るポイントと解消法
「人間関係の悩み」は、仕事のストレスになりやすい要素の一つ。 「職場の人間関係にうまく馴染めない」「社内に苦手な人がいて折り合いが悪い」 ビジネスパーソンなら誰でも一度は、このような人間関係のストレスを感じた経験があるのではないでしょうか。 本記事では、仕事の人間関係にストレスを抱えている人に向けて、気持ちを割り切るポイントやモヤモヤしたときの解消法などを解説します。 人間関係は仕事のストレスに直結しやすい 令和5年に厚生労働省が実施した「労働安全衛生調査」にて、「職場にストレスと感じる事柄がある」と回答した人は82.7%もいました。その中で「対人関係がストレス」と答えた人の割合は29.6%となっており、働く多くの人にとって人間関係が仕事のストレスになっているのがうかがえます。 また、対人関係にストレスを感じると答えた人の男女比は男性が26.3%、女性が33.7%であり、男性よりも女性のほうが仕事の人間関係にストレスを感じやすいようです。 同年実施の「雇用動向調査」においても、「職場の人間関係が好ましくなかった」という転職理由は上位にランクインしていて、人間関係のストレスでキャリアチェンジする人も少なくない事実が浮き彫りとなっています。 仕事の人間関係にストレスを感じるのはなぜ? なぜ、仕事の人間関係はストレスになりやすいのでしょうか。ここでは、考えられる理由を解説します。 職場はコミュニケーション不足が起きやすいから 大前提として職場は仕事をする場所。そのため、各々が自分の仕事に没頭するあまりコミュニケーション不足が起きやすく、第一印象や先入観でお互いを理解した気になりやすいです。 しかしそうすると、自分がイメージしていたものとは異なる言動を相手が取った際に不信感や違和感が生まれ、悪い印象を持つきっかけに。 お互いをきちんと理解できていないため意思の疎通もうまくいきにくく、意見が割れたり対立が起きたりしてストレスを感じることがあります。 自分の意見が言えないから 家族や友達と話すときとは異なり、あらゆる人に配慮する必要がある仕事中は、思っていることをストレートに言えない場面も少なくありません。 そのため、自分の意見を言えないまま望まない方向に業務が進んで、ストレスを感じるケースがあります。 また、自分の意見が言いにくい環境は、わからないことがあっても質問できなかったり、相手にやめてほしいことを伝えられなかったりする状況を招くリスクも。仕事に支障が出る、いつまでも不快な思いをし続けるなどして、人間関係に強いストレスを感じる可能性があります。 苦手な人とも関わらなくてはいけないから プライベートでは、付き合う人を自由に選定して苦手な人を避けられます。しかし仕事においては、自分の意思で付き合う人を選べないため、苦手な人とも必要に応じて関わらなくてはいけません。職場にはさまざまな価値観・タイプの人がいるので、中には「合わない」「苦手」と感じる人もいるでしょう。 しかしそう感じる相手であっても、うまくコミュニケーションや連携を取る必要があるため、仕事の人間関係はプライベートの人間関係よりもストレスが生じやすいです。 仕事はお互いの人間性が出やすいから 職場は、意外と人間性が出る場所です。トラブル発生時の行動や誰もが嫌がるような仕事への向き合い方、困っている人がいたときの対応などから、普段は隠されている本当の性格が見えることがあります。 また、毎日顔を合わせて長時間一緒に働くことで、気分屋な一面や効率の悪さが露見する場合もあるでしょう。 仕事の人間関係がストレスになりやすいのは、そもそも職場が「お互いの嫌な部分が目につきやすい場所」であるのも一因だと考えられます。 ハラスメントがあるから パワハラやいじめがある職場で、過度な叱責や不当な扱いを体験することは、深刻なストレスにつながるでしょう。自分自身がハラスメントの被害者になった場合はもちろんですが、直接的な被害はなくても近くで見ているだけで精神的負担は相当なものです。 ハラスメントが横行する職場では、誰を信じていいのかもわからなくなりやすいので、孤立感が強まります。 職場の人とのちょっとした交流にも緊張してホッとできる瞬間が少ないため、ストレスがどんどん蓄積しやすいです。 仕事の人間関係にストレスを抱えやすい人の特徴 仕事の人間関係にストレスを抱えやすい人には、よく見られる特徴がいくつかあります。代表的な3つを紹介するので、自分に当てはまっていないかチェックしてみてください。 人とのコミュニケーションが苦手 コミュニケーションに苦手意識がある人は、自ら積極的に人と交流しようとしないため、相手の人柄をよく理解しないまま勝手なイメージを固定化しやすいです。思っていることがあってもそれを伝えられず、自分の意見や感情を内に溜め込んでストレスを抱えてしまいます。 また、たとえ長く働いても人と交流を持たなければ信頼関係は育たないので、仕事中に緊張や不安が生じやすく、それもストレスになるでしょう。 真面目で厳格な性格 いい加減なことを嫌う真面目な性格は長所でもありますが、自らの几帳面さを他人にも求める傾向が強いので、他人の予想外の言動にイライラを募らせやすいです。 「一般的に考えてこうあるべき」のように一般論や自分の考えに固執しがちで融通が利きにくいため、時に相手やその場の空気に合わせなくてはいけない仕事の人間関係にストレスを感じるでしょう。 仕事が理想通りに進まないと厳しい態度で周囲に接することもあり、自ら人間関係を悪くしてストレスを抱えるかもしれません。 共感力が高すぎる 共感力が高い人は、他人との境界線があいまいになりがち。相手の身に起きた出来事や感情を自分のことのように捉え、良い影響も悪い影響もダイレクトに受けて人間関係に疲れを感じやすいです。 また、共感力が高い人は他人に寄り添う能力があるからこそ「相手は困っているだろう」「助けてほしいと思っているだろう」と察して要望全てに応えようとします。 自分のことを後回しにしてでも他人を優先させる傾向が強いので、仕事の人間関係で不満やストレスを溜めやすいです。 ストレスをなくすには仕事の人間関係を割り切るのがカギ 上手に気持ちを割り切れると、仕事の人間関係におけるストレスはぐんと減ります。ここからは、仕事の人間関係を割り切るための5つのポイントをお伝えしましょう。 仕事とプライベートは別だと考える まずは気持ちを整理して、仕事とプライベートにしっかり線引きをしましょう。仕事とプライベートを別物として割り切ることで、こだわりや感情にとらわれにくくなります。 「職場で最もやるべきことは仕事であり、友達作りではない」と思えれば、他人の目や評価を気にする回数も減るでしょう。 「相手から嫌われたらどうしよう」という恐怖も和らぎやすいので、今より自己主張できたり嫌なことをきちんと断れたりして、人間関係のストレスが減る可能性が高いです。 他人に期待しすぎない 他人に対し「〇〇の仕事を手伝ってもらいたい」「短所を直してもらいたい」のように思うのは、過度な期待です。 そして、他人に対して期待しすぎてはいけません。過度な期待は、叶わなかったときの絶望感も大きく、さらにストレスを強めてしまいます。 期待をするべき相手は、他人ではなく自分です。他人に何かしてもらおう、変わってもらおうとするのではなく、自分が成長や変化するにはどうすればいいかを考えましょう。 事実だけに目を向ける 人間は、誰しも良い面・悪い面の両方を持っています。他人の嫌な部分を一度見ただけで「嫌な人」と決めつけてしまうと、職場中が嫌いな人だらけになり、余計に人間関係のストレスが増えるでしょう。 そのため、他人の嫌な面に触れても「相手にはこんな悪いところもあるんだ」と事実だけを受け止め、自身の感情と深く結び付けないように意識するのがコツ。 「嫌い」「苦手」「合わない」など、ネガティブな感情を発生させないように工夫すれば、自然と人間関係のストレスは軽減します。 人間関係は「広く浅く」を意識 仕事の人間関係を割り切るなら、特定の人とだけ深く関わったり、他人との交流を断ち切って孤立したりするのではなく、広く浅い関係を構築するのがおすすめです。 広い人間関係を築いておけば、仕事上のトラブルに見舞われた際にも周囲に助けを求めやすくなります。 また、あえて深く交流しないことで、お互いに自分のペースを乱さずに済み、適度な距離感を維持できるでしょう。 人間関係に完璧を求めない さまざまな人がいる職場では、全員と良好な人間関係を築くのは不可能だと理解して、完璧を求めないようにするのも大切です。 全員と良好な関係を結べるのが理想ではあるものの、人間には相性があるのでどうしても難しい場合もあります。また、無理に全員から好かれようとすれば自分を抑制する場面が増え、ストレスは強くなるでしょう。 苦手だと思う気持ちや折り合いが悪い現状もありのまま認め、時には現状維持でも良しとする柔軟性が必要です。 仕事の人間関係のストレスを解消する方法 どれだけ割り切っていても、仕事の人間関係にストレスを感じることもあるでしょう。ここではそんなときに試してほしい、ストレス解消法を紹介します。 ストレスを感じたときは状況と感情を客観視する 誰かにイラっとしたときや、モヤモヤした感情が溜まっているときは、一度今の状態と自分の感情を客観視してみてください。 「何にストレスを感じ、そのとき自分はどんな気持ちになったのか」「今なおストレスはあるのか」「今後ストレスが改善される可能性はあるか」といったように、ストレスを感じた瞬間から現在までを時系列で考えます。 状況と感情を丁寧に分析すると気持ちが落ち着き、「よくよく考えてみたら、意外と大したことじゃないかも」と思えて、ストレスが消えていくケースも少なくありません。 苦手な人とは必要に応じて距離を取る 苦手な人と一緒にいるだけでストレスを感じるときは、仕事に支障をきたさない程度にうまく距離を取るのも大切です。 人間関係のストレスは、苦手な人と接触する機会が減れば自然と低減します。 露骨に相手を避けたり、業務上必要な連絡まで怠ったりするのはNGですが、苦手な人との私的な交流機会が減るだけで仕事の人間関係はやりやすくなるでしょう。 一日の中に気分転換やリラックスできる時間を設ける 気分転換やリラックスできる時間を一日の中のどこかに設け、こまめにストレス発散できるルーティンを作りましょう。ストレスは蓄積させればさせるほど解消が難しくなるので、できるだけその日のうちにリフレッシュしたほうがいいです。 また、時には長期休暇を取り、日常的な気分転換だけでは発散できなかったストレスを思いきり開放させるのも大切です。 身近な人に相談する 友だちや職場の上司、家族などに、仕事の人間関係について相談してみるのも有効なストレス解消法といえます。 信頼できる人に自分の本心を打ち明けることで、気持ちが軽くなったり客観的視点を得るきっかけになったりする可能性が高いです。その後話題が変わったとしても、楽しく盛り上がればいい気分転換になるでしょう。 大きなストレスを抱えると一人でふさぎ込みがちになりますが、不安や孤独感を解消させるためにも、できるだけ積極的に他人と交流してください。 キャリアコンサルティングを受けてみる 「何をやっても仕事のストレスが大きくてつらい」「仕事の人間関係がストレスすぎて、転職を考えている」 このような場合は、キャリアコンサルティングを受けてみるのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、キャリアに関する悩みはもちろん、人間関係の悩みにも丁寧にアドバイスしてもらえます。 プロ目線の具体的なアドバイスを参考にすれば、ストレスの原因に的確にアプローチしやすく、悩み解決の突破口が開けるはずです。 上手に人間関係を構築して、仕事のストレスを低減させよう 多くの人と協力しながら進めなくてはいけない仕事では、人間関係のストレスが必ず発生します。 しかし、自らの考え方や行動を変えて上手に人間関係を構築できれば、仕事のストレスは大幅に減少するはずです。 無理にストレスに強くなろうとするのではなく、ストレスが発生しにくい環境を自分で整えて、気持ちよく働けるように工夫しましょう。キャリア・コンサルティング・ラボでは、そのお手伝いをするための相談を受け付けているので、ぜひ気軽に利用してみてくださいね!

仕事のストレス限界サイン7選!症状が出たときの対処法
仕事にはさまざまなストレスがありますが、ストレスを限界まで溜めると心や体、行動などに変化が現れ、放置すると深刻な病気に発展するリスクも! 今回は、仕事のストレスが限界に達しているときに現れる症状や、つらい現状を変えるための対処法を解説します。 仕事のストレスに悩まされている人は、この記事を参考に適切に対処し、気持ちよく働ける日々を取り戻しましょう。 仕事のストレスとは?原因と影響 仕事のストレスとは、外部からの刺激(ストレッサー)によって心身に生じる反応のことです。 何にどれだけ心身が反応するかは人それぞれ異なるため、ストレスを限界だと感じる基準も一人ひとり異なります。 「この程度の仕事のストレスで限界を感じるなんて甘えかな」「他の人は限界を迎えてなさそうだから、自分も頑張らないと」 このように考えて自分を責めたり無理をしたりする人も少なくありませんが、ストレス耐性は人によって違うため、過度な我慢は禁物。仕事のストレスを限界突破させないためには「つらい」という気持ちを素直に受け止め、その都度適切に対処するのが大切です。 仕事のストレスが限界に達する原因 仕事のストレスはほとんどが「精神的刺激」が原因で発生します。精神的刺激になる主な要素は以下の通りです。 職場の人間関係に悩んでいる 仕事の量や納期が適切ではない 評価や給与に不満がある プレッシャーが大きすぎる 適性に合わない仕事をしている このような要因があると不安や不満、緊張が生まれやすく、心理的負担がストレスとなります。 ただし、労働環境が暑すぎる・寒すぎる、騒音が激しいといった「物理的刺激」も仕事のストレスになり得るので、まずは自分が何にストレスを感じているかを考えてみましょう。 仕事のストレスがもたらす影響 ストレスは、一気に大きな影響をもたらすのではなく、じわじわと心身に影響を及ぼすのが特徴です。 そのため、仕事でストレスを感じても、ほとんどの場合最初は軽い疲労感を感じる程度でしょう。しかし、そのまま対処せずにいると次第にストレスは蓄積し、集中力の低下や体調不良、メンタルの疾患などを引き起こす可能性があります。 場合によっては、就労を続けるのが困難なほど甚大な影響をもたらす恐れがあり、小さなストレスも軽視できません。 仕事のストレスが限界なときに現れるサイン・症状 ここでは、仕事のストレスが限界なときに現れる代表的なサインを紹介します。心の限界に早く気付くためにも、自分に以下のような症状が出ていないかチェックしてみてください。 関心や集中力の低下 初期のストレス限界サインとして、物事への興味や集中力の低下が挙げられます。 ストレスが心の大半を占めると、常に悩みや不安にとらわれて、好きだった趣味や息抜きに行っていた行動にも関心が湧きにくくなるのです。また、仕事に対する興味も失いやすく、集中力低下によってミスが増えるという悪循環に陥るケースもあります。 人との交流に対しても関心を持てなくなる傾向なので、人間関係を希薄にして孤立感を深めてしまうかもしれません。 頭痛や肩こり 仕事でストレスを感じると、つい全身に力が入ってしまうという人は多いのではないでしょうか。また、不安や緊張を感じると気が張り詰めて動きがぎこちなくなり、長時間同じ姿勢を取って血行不良になりやすいです。 そして、このような状態は筋肉の緊張や神経伝達物質の乱れを招き、頭痛・肩こり・めまいなどを引き起こす可能性を高めます。 風邪気味や疲れだと勘違いして放置してしまう人も多いですが、ストレスによる身体症状は市販薬や通常の治療では治りにくいのが特徴です。 食欲不振または過食 食欲の変化は、わかりやすいストレスの限界サインといえます。 仕事のストレスが限界に達すると、胃腸の動きが鈍くなりやすいです。気分の落ち込みによって食事を楽しもうという気も起きにくくなるので、空腹感を感じずに食欲不振に陥るケースがあるでしょう。 一方、限界まで溜めたストレスによって過食に走る人もいます。特に、もともと食べてストレス解消していた人は、大きなストレスを抱えれば抱えるほど食べてしまう傾向です。 胃痛や消化不良 仕事のストレスが限界に近づくと、胃の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすくなります。胃酸が過剰分泌されやすくなるため胃粘膜が刺激され、胃の痛みや不快感、胸やけ、吐き気などの症状が出る場合があるでしょう。 胃酸過多により食べ物が正常に消化されにくくなり、便秘や下痢といった消化不良を起こすリスクも上がります。放置して慢性化すると胃潰瘍や十二指腸潰瘍になる恐れもあり、注意が必要です。 なおこれらの症状は、上記で取り上げた食欲不振や過食によって引き起こされるケースもあります。 睡眠障害 「なかなか眠れない」もしくは「眠りすぎてしまう」など、仕事のストレスは毎日の睡眠にも影響します。 仕事のストレスが限界だと、帰宅後や休日も仕事のことが頭から離れにくくなり、リラックスできずに寝つきが悪くなりやすいです。また、仕事のストレスによって自律神経が乱れると、睡眠の質が低下して過眠症状が現れる場合もあります。 いずれの場合も良質な睡眠はとれておらず、睡眠不足や疲労感が蓄積して、体調不良を招くリスクが高いです。 感情をコントロールできない 些細なことでイライラしてしまう、突然怒りがこみあげてくる、急に涙が止まらなくなるのように、仕事でストレスを感じると感情のコントロールが難しくなることがあります。 精神的負担が大きすぎて心がいっぱいいっぱいになっている証拠であり、まさにストレスの限界が近いサインといえるでしょう。 誰かが言った他愛もない冗談に激怒してしまったり、イライラしている自分を見せないようにと人付き合いを避けたりしやすくなるので、職場の人間関係がギクシャクしてさらにストレスを抱えてしまう場合もあります。 気分が沈んだ状態が続く 365日気分が上向きという人はいませんが、憂鬱な気分や落ち込んだ気持ちが続く場合、ストレスによって心が限界を迎えていると判断できるでしょう。 このようなうつ状態に陥ると不安や自己批判の感情が強まり、全ての物事に対して無気力になります。何をするにも億劫で、仕事に行くのはもちろん、普段通りの日常生活を送ることさえ難しいと感じる人も少なくありません。 うつ状態が続く場合は、うつ病を発症している可能性があるため、早めに専門の病院やクリニックを受診して適切な治療を受けてください。 限界まで仕事のストレスを溜めてしまう人の特徴 限界まで仕事のストレスを溜めてしまう人には、いくつか共通する特徴があります。ここからは、ストレスを感じやすい人・溜めやすい人の特徴を見ていきましょう。 責任感が強く頑張りすぎてしまう人 責任感が強い人は、全てを一人で抱え込んで無理をするところがあります。完璧主義の傾向も強いので、常に高い水準の成果を求めて仕事を頑張りすぎてしまい、ストレスを溜めやすいです。 責任感の強さから人の頼みごとに「NO」と言えないタイプで、頼まれるとつい何でも引き受けてストレスを限界突破させてしまうことも。 また、目標達成意欲が高いからこそ、達成できないと自分を過剰に責めてしまい、それがストレスになるケースも少なくありません。 周囲に気を遣いすぎる人 気配り上手は長所でもあるものの、度が過ぎる人は仕事中も常に周囲を気遣って他人を優先させてしまいます。他人の顔色に合わせて言動を変えたり、周囲の空気を読んで自分の意見を飲み込んだりするため、気疲れによって限界までストレスを溜めやすいです。 「自分の思いや考えを伝えると相手に嫌われるのでは」という可能性を考えて不安に駆られやすいのも特徴で、ストレスが慢性化する可能性があります。 せっかちな人 せっかちな人は、常に何かしていないと気が済まない性格で、仕事の生産性も高いです。 しかし、周囲にも自分と同等の行動量や生産性を求めやすく、一緒に働く人に対してイライラしてストレスを溜めてしまうことがあります。 また、せっかちな人は心に落ち着きがないので、物事を深く考えずに発言しがち。悪気はないものの、厳しい言葉で他人を急かしてプレッシャーを与えてしまい、職場の人間関係悪化によってストレスを感じる場合もあるでしょう。 正義感が強すぎる人 正義感が強すぎる人は真面目で、決められたルールを重んじます。ルールや規律に沿って仕事を進めるのは間違いではありませんが、ルールを絶対視しすぎると融通が利きません。 イレギュラーな事態により、業務範囲外の仕事をお願いされたり、やむを得ずルールから外れた行動を取る他人を見たりするとイライラが止まらず、ストレスが限界に達しやすいです。 「常にルールを守る自分は正しい」と思い込むので他人の意見を受け入れられず、職場の人間関係がうまくいきにくいのもストレスの原因になるでしょう。 自己評価が低い人 自己評価が低い人は「自分は人より劣っている」と常に自分自身を否定的に捉えるので、自分で自分にストレスをかけがちです。 「自分なんて」という気持ちが常にあるため、仕事で理不尽な目に遭っても自己犠牲的に我慢しやすく、限界までストレスを溜めてしまいます。 現状から抜け出したいと思っても、自分に自信がないため失敗を恐れて行動できず、ストレスや悩みを一人で抱えやすいです。 仕事のストレスが限界なときの対処法 ここからは、仕事のストレスが限界に達してしまったときの対処法を解説します。今日からすぐに取り組めるものもあるので、ぜひ実践してみてください。 現状を認めて休む 仕事のストレスを限界まで溜めてしまう人は、自分が疲れていることやストレスを感じていることをなかなか素直に認められません。しかし、現状を認めず無理に頑張れば状況は悪化する一方なので、まずは「自分はストレスを感じている」と事実を受け止めましょう。 その上で、しっかりと休息を取るのが大切です。休暇を取得すればストレスの原因である仕事から離れられ、疲れた心が徐々に回復する可能性があります。 SNSやネットから離れる ストレスが限界に近ければ近いほど、ネガティブな情報に敏感になり、影響を受けやすくなります。 「有益なストレス対処法が知りたい」「自分と同じような境遇の人を見つけて孤独感を和らげたい」 このような思いからついSNSやネットを開きがちですが、過度な情報にさらされると疲労やストレスは大きくなりやすいので、時には思い切ってスマートフォンやパソコンから離れましょう。 必要のない情報を遮断する時間は、自分自身とだけ向き合えて気持ちを前向きにしやすいです。 人と話す 信頼できる人とじっくり話すのも、仕事のストレスが限界なときに有効な対処法です。とりとめのない話を楽しむだけでも気持ちが明るくなりますし、愚痴や悩みを聞いてもらえばストレスが軽減する可能性があります。 また、家族や友達に話しにくい内容は、キャリアコンサルティングで打ち明けるのも良いでしょう。キャリアコンサルティングでは、キャリアに関する相談はもちろん、職場のストレスや仕事全般の悩み相談にも乗ってもらえます。 現状に対してプロ目線のアドバイスが受けられるので、できるだけ早くストレスを対処したい人におすすめです。 心身の不調は専門家に相談する 限界に達したストレスによって心身に不調が出ているなら、それは専門の医師に相談する目安です。 頭痛や下痢、肩こりなど身体症状が出ているときは、まず内科や消化器内科、整形外科など専門の診療科を受診します。専門の診療科で病気の可能性を調べてもらった後、ストレスが原因の可能性が高いと診断された場合は、心療内科やメンタルクリニックを受診すると良いでしょう。 異動・転職する ストレスが限界に達して心身が悲鳴を上げている状態に陥ってまで、続けないといけない仕事はありません。さまざまな対処法を試してもストレスが大きいままという場合は、異動や転職によって働く環境を変えるのも一つの方法です。 なお、今すぐストレスを解消したいという思いで突発的に退職する人もいますが、このような行為は後の転職活動にも悪影響を及ぼす可能性が高いのでNG。事前に準備や相談をした上で適切な手順を踏み、円満に事を進めてください。 仕事のストレスは限界がくる前に対処するのが大切 仕事をしている以上ストレスとは切っても切れない関係が続きますが、ストレスを限界まで溜めると心身にさまざまな悪影響が出ます。大切なのは、小さなストレスサインも見逃さず、自分の気持ちを尊重してこまめにケアをすることです。 また、人に話しにくい悩みがあったりストレスの解決策がなかなか見つからなかったりするときは、キャリアコンサルティングを受けてみましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボなら、オンラインで気軽に相談できるので「仕事のストレスが限界かも」と感じている人は一度利用してみてください。

職場のストレス対処法は?仕事中でもすぐできる発散方法を紹介
職場にストレスはつきものだからこそ、社会人は「上手なストレス対処法」を身に付ける必要があります。 今回は、職場での気疲れやイライラが蓄積している人に試してもらいたい、ストレスの対処法を解説! 職場でできる簡単なものから大きなストレス解消になるものまで、合計10個のストレス対処法を紹介するので、ぜひ自分に合う方法を見つけてください。 職場でストレスを感じたときに真っ先にやるべきこと ストレスは「解消」できるものと「発散」させたほうがいいもの、大きく2タイプあります。「解消」は根本的問題を解決してストレスを元からなくすこと、「発散」は溜まったストレスを開放したり気分転換を図ったりすることです。 全てのストレスを解消できるのが理想ではあるものの、職場のあらゆる問題を全て解決するのは難しく、受けたストレスは発散させたほうがいい場合もあります。発散でしか対処できないストレスを無理に解消しようとすれば、うまくいかずさらにストレスを抱えてしまう可能性も! そのため、職場でストレスを感じたら、まずは「解消」と「発散」どちらの方法で対処すべきかを考えてみましょう。ストレスの原因を特定し、解決が見込める問題かどうかを考えると、どちらを選ぶべきかがわかりやすいです。 職場でできる!手軽なストレス対処法 ここでは、仕事中や職場ですぐにできる手軽なストレス対処法を紹介します。ストレスを溜めないためにも、小さなストレスを感じた時点でこまめに行ってみてください。 深呼吸・ストレッチをする 仕事中にストレスを感じたら、その場でゆっくり深呼吸をしてみましょう。深呼吸をすると副交感神経が刺激され、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールの分泌を抑えてくれるといわれています。 また、座ったまま行える簡単なストレッチを仕事中にするだけでも、身体がほぐれて呼吸が深まるので不安やストレス緩和に効果的です。 場所を移動する 同じ場所で長く作業していると、だんだんストレスが溜まってくる…という人も多いでしょう。そんなときは、少し歩いたり仕事をする場所を変えたりするのがおすすめ。 トイレや休憩室に行く、オフィスではなくカフェで仕事をするなどするだけで、気分が入れ替わりストレス軽減になる場合も少なくありません。 なお、リモートワークができる会社ならリモートワークを選択するのもありです。 休憩する 仕事の合間にしっかり息抜きするのも、良いストレス対処法といえるでしょう。具体的には、間食としてコーヒーや甘いものを摂取する、同僚と雑談をする、昼寝をするなどが挙げられます。 ストレスを感じて心がモヤモヤすると休憩時間まで暗い気持ちになりがちです。しかし、意識的にオンオフをつけると気持ちの切り替えにもなり、ストレスが溜まりにくくなります。 職場のストレスが溜まったときの対処法 手軽な方法だけでは対処できない、手ごわいストレスも存在します。ここからは、職場のストレスが蓄積して心が疲れてしまったときの対処法を解説します。 まずは休む! 十分な休息が取れていないと、それだけでストレスは増加してしまいます。リラックスできる時間と睡眠時間をたっぷり確保し、心身ともに休息を取りましょう。 帰宅後や休日を利用してしっかり休める場合は問題ありませんが、物足りなさを感じる場合は有給休暇などを利用して長期で休むのもありです。 また、普段から規則正しい生活や健康的な食事を意識して、生活習慣から心身を労わるのも忘れないでください。休養によって心身の疲れが取れると思考もクリアになり、ストレスに強いメンタルを育むことにもつながります。 適度に体を動かす ストレスを感じると呼吸は浅くなり、身体が緊張する傾向にあります。これらを解消させて心身にリラックスをもたらすのが、運動です。 運動といっても、激しく体を動かす必要はありません。運動によってしんどい思いをするとさらにストレスを感じてしまうので、ウォーキングやジョギング、ストレッチ、ヨガなど、無理なくできる軽めの運動をできるだけ継続しましょう。 なお、運動中は日光を浴びると、幸せホルモンことセロトニンやエンドルフィンがより多く分泌されてストレス軽減効果が高まります。 ストレスを紙に書き出す 「職場のストレスで心がモヤモヤする」という場合は、感情を紙に書き出してみてください。 自分の気持ちを書き出すと、ストレスの原因や職場の状況、自分の考え方の癖などを深く理解でき、気持ちの整理がつきやすくなります。 その後、思いきり感情をぶつけて書いた紙をびりびりに破いたり、シュレッダーにかけたりするのも一つの対処法です。自分の気持ちそのものである紙を物理的に破壊することで、怒りや不満といったストレスの元になる感情が静まり、気持ちをリセットできる場合があります。 プライベートを楽しむ 職場のことを完全に忘れて自分の時間を楽しむのも、非常に効果の高いストレス対処法の一つ。例としては、趣味に没頭する、外出して新鮮さを得る、おいしいものを食べるなどが挙げられます。 この他、映画やドラマを見て思いきり笑ったり泣いたりするのも、感情を放出できるのでストレス発散になるでしょう。 プライベートをしっかり楽しめると「自分には職場とは別に楽しい居場所がある」とも思えます。良い意味で職場への依存度が下がるので、割り切った考え方ができてストレス耐性も高まりやすいです。 周囲の人と話をする 友人・家族と雑談をして盛り上がったり、嫌だったことやストレスに感じていることの話を聞いてもらったりするのも有効な対処法です。職場とは全く関係のない話題であっても、楽しく盛り上がっていると気分転換になりストレスが軽減します。 また、職場の悩みなどを打ち明けると、自分の気持ちを整理できる他、第三者視点からのアドバイスが得られ考え方が広がるでしょう。 丁寧な対話には、それだけで安心感や充足感をもたらす効果があります。誰かとじっくり話をすると「話を聞いてもらえた」「優しくしてもらえた」と感じられ、気持ちが落ち着きやすいです。 専門家に相談する ストレスを根本から解消したいものの対処法がわからない場合や、周囲にアドバイスを求めてみてもなかなかピンとこないときは、専門家を頼りましょう。 職場のストレスを相談できる専門家の中でも特におすすめなのは、キャリアコンサルタントです。 キャリアコンサルタントは職場の幅広い悩みに対応し、相談者の価値観や考え方を尊重した上でアドバイスを授けてくれます。職場のストレスの悩みから派生してキャリアや転職の悩みが生じた際も、そのまま相談できるので心強いです。 ただし、ストレスによって心身に不調が出ている場合は、先に専門の医療機関で医師に相談してください。 異動や転職を視野に入れる あらゆる対処法を試してもストレスを取り除けず、心身や日常生活に悪影響が出ている場合は、自分に合わない職場で働いている可能性も考えられます。 今の職場を離れることを検討し、異動や転職を視野に入れてもいいかもしれません。ただし、異動や転職がキャリアに与える影響は大きく、今後の人生がガラリと変わる可能性もゼロではないので、慎重な判断が必要です。 異動や転職についてもキャリアコンサルティングで相談できるので、迷ったときは利用してみましょう。 職場のストレス耐性を高める5つの習慣 今あるストレスに対処するのも大切ですが、耐性を高めてストレスを受けにくい人になる努力をするのも大切です。ここでは、ストレス耐性を高めるために実践してほしい、5つの習慣を解説します。 小さいストレスにすぐ対処する ストレス耐性が高い人とは、言い換えれば「ストレスを感じてもすぐに解消・発散できる人」です。 一切ストレスがない職場はほとんど存在しませんが、たとえストレスがあってもすぐになくすことができれば負担は最小限で済みます。 ストレスを早期に解消・発散するためには、小さなストレスを軽視しないことが大切です。ストレスは蓄積させればさせるほど対処が難しくなるので、程度が軽くても見て見ぬ振りせず、できるだけその日のうちに自分を癒す対処を行いましょう。 周囲を頼る 職場でストレスを感じやすい人は、周囲に頼るのが苦手という特徴を持っている場合が多いです。うまく周囲に頼れないため、仕事を抱えすぎたり悩みを誰にも相談できなかったりして、よりストレスを大きくしてしまう傾向があります。 しかし、職場は一緒に働く人と協力して仕事を進める場なので、負担が大きいときやしんどいときは周囲の人を積極的に頼るべきといえるでしょう。 まずは「周囲に頼っていいんだ」という意識を持ち、小さな頼み事から始めてみてください。この他、普段から信頼関係を築き、頼りやすい関係性を作っておくのも忘れてはいけません。 物事を前向きに受け止める 何事も、できるだけ前向きに捉える習慣を身に付けましょう。物事をネガティブに受け止めると、心配や不安、怒りといった感情が生まれやすくなりストレスにつながります。 できていないことよりもできていることに目を向ける、意識してポジティブな言葉を使うようにするなどするだけでも、徐々に思考が前向きになるはずです。 また、ネガティブな捉え方をしてしまったときも自分を責めず、ポジティブに捉えられないか別の視点から考え直してみてください。 仕事に優先順位をつける 仕事に時間がかかりすぎてしまったり、自分の仕事ぶりに納得できなかったりするのがストレスという人は、仕事に優先順位をつけるのをマイルール化してみてください。 タスクをメモに書き出し、緊急性の高さやタスク完遂までにかかる時間を考えます。それらから考えられる優先順位の高いタスクから順番に着手していけば、今より効率的に作業できストレスそのものを解消させられるかもしれません。 自分をしっかり持つ 周囲に合わせすぎてしまう人は、職場でも他人を優先して自分の考えを抑えがちなので、気疲れによってストレスを感じやすいです。 そのため「必ずしも他人に合わせなくていい」と自分で自分を許し、自分はどうしたいのかという部分を大切にする考え方を身に付けてください。また、コミュニケーション力を磨き、自分の意見を正確に相手に伝えられるよう努力するのも重要です。 自分をしっかり持つと、人の意見や言動に左右されにくくなり、ストレス予防につながります。 職場でストレスを感じてもやってはいけない対処法 ストレス対処法の中には、良かれと思ってやるとマイナスな効果につながる「NG対処法」もあります。以下のようなNG対処法は選択しないようにしましょう。 食べすぎ・深酒 おいしいものを食べたりお酒を飲んだりしてリフレッシュするのは効果的なストレス対処法ですが、それは「適量」の場合です。 食べすぎ・飲みすぎは身体にかかる負担が大きく、肥満やメタボリックシンドローム、その他疾患などを引き起こしやすくなります。 「ストレスを感じたら食べる」と脳がインプットしてしまうと、食欲をコントロールするのも難しくなるので、早めに飲み食いの代わりになるストレス対処法を見つけてください。 過剰なギャンブル・ショッピング ギャンブルやショッピングは、行っている間一時的に脳内が活性化しドーパミンという快楽物質が大量放出されるため、依存症を招くリスクが高いです。 もちろん節度を持って行う分には問題ありませんが、ストレスを受けるたびにギャンブルやショッピングをしていると依存症になりやすいので注意しましょう。 また、既に依存症に陥っている疑いがある場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。 悪口 誰かに話を聞いてもらうのもストレス対処法の一つですが、話す内容が悪口である場合、さらにストレスが増加するリスクがあるので要注意。 悪口を言うと脳内では、快楽物質・ドーパミンとともにストレス物質・コルチゾールも分泌されます。悪口は、一時的には楽しくても実は心身に負荷をかける行為なので、結果的に心身の不調を招きやすいです。 対処法を知って、職場のストレスをコントロールしよう 職場のストレスは、程度の小さい段階であれば軽めの方法で対処でき、その後深刻な悩みへと発展しません。 そのため、前もって自分に合った対処法を見つけておくのが大切。一人では対処が難しい場合は、キャリアコンサルタントをはじめとする専門家を頼ってください。 生じたストレスを適切に対処できれば、メンタルはもちろん仕事のパフォーマンスも安定します。この記事を参考に自分に合った対処法を把握し、職場のストレスと上手に付き合っていきましょう。

もう仕事行きたくない!職場のストレスの原因と乗り切り方
職場には大なり小なりストレスがあるもの。ですが、あまりにもストレスが大きすぎると心は疲弊し、限界を超えないためのSOSサインとして「もう仕事に行きたくない」と思います。 今回は、職場が嫌になる原因やストレスを抱えたときのNG行動、仕事に行きたくない気持ちの対処法などを解説します。 毎日「行きたくない」と思いながら職場に向かうのは辛いので、この記事を参考に一日でも早い問題解決を目指してください。 ストレスにより「職場に行きたくない」と思う人は多い 厚生労働省が実施した「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)」で、「現在の仕事・職場環境にストレスがある」と回答した人は全体の82.2%にも達しています。 この結果から「毎日職場に行くのが楽しみ!」という人のほうが少数派であり、社会人の多くが「職場がストレス」「職場に行きたくない」と感じた経験があると推察できるでしょう。 真面目な人ほど「職場に行きたくない」という感情を否定して、辛い気持ちを無視したりネガティブな自分を責めたりしやすいです。しかし、大切なのは目の前の気持ちに向き合うことであり、そこから「どうすれば職場に行きたくないほどのストレスを軽減できるか」に考えをシフトするのがベスト。 働いていれば前向きな気持ちで出社できる日もあれば、出社するのが辛くて仕方がないという日もあって当然なので、まずは自分の気持ちに正直になるのが問題解決のスタートラインです。 「職場に行きたくない」につながるストレスの原因は? 職場に行きたくない気持ちを解消させるには、ストレスの原因を把握する必要があります。ここでは、出社が嫌になりやすいよくある職場のストレスを解説するので、自分に当てはまっていないか確認してみてください。 職場の人間関係がうまくいかない 職場のストレス要因としてよく挙げられるのが、人間関係の問題です。職場はさまざまな人が集う場所なので、自分とは異なる価値観・考え方を持つ人も少なくありません。 個性を認め合って協力し合える関係を構築できれば良いですが、考え方の違いから対立する関係になってしまうと仕事の連携がうまく取れず、働く上で大きなストレスとなります。 特に、直属の上司やプロジェクトを一緒に進行する同僚、教育を任された後輩のような距離が近い人とトラブルになると、接する機会が多い分ストレスも強くなり、職場に行きたくない気持ちが膨らむでしょう。 仕事量が多すぎる 仕事量が多すぎると、常に時間に追われながら仕事をするので気が休まりません。 残業や休日出勤などが常態化するケースも多く、自分の時間をゆっくり持つのが困難で疲れが取れにくいためストレスが溜まります。 また、一人当たりの仕事量が多い職場では、あなただけではなく他の人も業務量の多さにストレスを抱えているはずです。誰にも余裕がない状態で仕事が進んでいくので職場はピリピリとした雰囲気になりやすく、そこから人間関係の悪化や会社そのものへの不満といった別のストレスが生まれる場合もあります。 仕事の質や内容に問題がある 自分のやりたい仕事ではなかったり、自分には適性がない仕事を多く任せられたりした場合も、職場にストレスを感じやすいです。 また、入社時は希望通りの仕事内容だったとしても、昇進や異動により役割が変わり、仕事内容に不満を持つケースも。 自分の仕事に納得や満足ができないと、働いていてもやりがいを得られません。「どうして自分に合った仕事をさせてくれないのか」と上司や会社に対する不信感も募りやすいので、働くモチベーションが下がって職場に行きたくないと感じてしまいます。 大きなプレッシャーや責任を抱えている プレッシャーや責任は、重要なポジションや責任の重い仕事を任されたときはもちろん、自分の物事の受け止め方によっても発生します。 たとえば、過去の失敗を引きずってうまく気持ちを切り替えられない人は「もう絶対に失敗できない」と自分で自分を追い詰めて過剰なプレッシャーを感じるでしょう。他にも、責任感が強すぎると「何が何でも一人でやらないと」のように考えて、膨大な量の仕事を抱え込みがちです。 しかし、人が一人で抱えきれるプレッシャーや責任は、いくら個人差があるといえども限度があります。プレッシャーや責任が限度を超えるとストレスも限界突破して「もう職場に行きたくない!」という気持ちになりやすいです。 職場環境や待遇に不満がある 安全性への配慮が欠けている、評価システムが不明確といった職場環境の問題や、賃金が低い、福利厚生が整っていないのような会社の待遇も、ストレスに大きく関与します。 職場環境や待遇が悪いと、会社への不信感は増すばかりです。特に、問題意識が薄く、環境・待遇の悪さを放置して改善に期待ができない会社で働いている場合、不安感から強いストレスを感じるでしょう。 「このまま今の会社にいて良いのか」と悩んだり「会社に貢献してもメリットがない」と働く意欲が下がったりするので、職場に行きたくないと感じるのも無理はありません。 入社直後や休み明け直後 入社直後は、慣れないことばかりで毎日が緊張の連続。「ちゃんとやっていけるだろうか」という不安も感じやすい時期なので、このような緊張・不安感がストレスとなり、職場に行きたくないと感じる人が少なくありません。 また、休み明け直後も、楽しかった休日といつも通り働く日常のギャップについていけず、ストレスを感じることがあります。 入社直後や休み明け直後に感じるストレスは一過性である場合も多いので、しばらく様子を見て職場に行きたくない気持ちが緩和していくようなら心配はいらないでしょう。しかし、中には本当に強いストレスを感じて限界が近い場合もあるので、数日経っても気持ちに一切変化がない場合は対処を考えてください。 ストレス過多で職場に行きたくなくても避けるべきNG行動 ストレスによって職場に行きたくないと、つい突発的かつ突飛な行動を取りがち。しかし、以下のような行動は後悔につながりやすいので避けましょう。 無断欠勤・突発的に退職する 無断欠勤および突発的な退職は、職場に行きたくないときに最もやってはいけない行動の一つ。 無断欠勤すると、次の出社がしづらくなってしまいます。たとえ何とか出社して仕事を再開したとしても、周囲からの信頼が下がるので働きにくさを感じやすいです。 また、職場に行きたくない気持ちが最高潮に達すると、「最も簡単な出社しない方法」として突発的に退職してしまう人がいますが、これもキャリアプランが崩れて後悔する可能性が高いのでおすすめしません。 欠勤や退職も選択肢の一つであるものの、それにはルールに則ったり熟考したりする必要があることを心に留めておきましょう。 自分を責める 自分を責めるには、大きく分けて2つのパターンがあります。 1つ目は「職場に行きたくないと思うなんてダメだ」と自分の考え方を責めるパターン。そして2つ目は、行きたくないと思いつつ出社して「不満があるのに現状を変える行動をしない自分はダメだ」と自分の行動を責めるパターンです。 しかしどちらにせよ、働いていれば職場に行きたくないと感じる日もあるものなので、自分を責める必要はありません。自分を責めるとマイナス思考になりストレスがより増幅するので、過剰な自責・自己嫌悪は控えましょう。 ストレスを一人で抱え込んで解決を諦める ストレスを抱える社会人は多いとお伝えしましたが、それは「ストレスはあって当然なものだから、あなたもストレスを我慢しろ」という意味ではありません。百害あって一利なしのストレスは、完全になくすのは難しくても少しでも軽減できるよう、誰もが工夫しなくてはいけないものです。 そのため「職場はどうせ良くならない」「社会人は皆こうだから」と解決を諦めたり、ストレスを一人で抱え込んだりするのはNG。 蓄積したストレスは心身に悪影響を及ぼす可能性もゼロではないため、後で紹介する職場に行きたくないときの対処法を実践して問題解決を図りましょう。 間違ったストレス解消法を取る 職場に行きたくないストレスを発散させるため、さまざまなストレス解消法を試してみるのは良いアイデアといえます。しかし選択するストレス解消法を間違えると、一時的にはストレス発散になったとしても、長期的に見ればストレスを悪化させる場合があるので要注意。 間違ったストレス解消法には「ストレス発散にはなるが代償がある」という特徴があります。たとえば、やけ食いや過剰な飲酒・喫煙は身体に負担がかかりますし、ギャンブルや買い物による散財も経済的負担が発生するでしょう。 このような、後々さらなるストレスにつながる恐れがある間違った方法は、選択しないようにしてください。 ストレスで職場に行きたくないときの乗り越え方 ここでは、職場に行きたくない気持ちの乗り越え方を紹介します。実践しやすそうなものや効果が見込めるものから取り組み、現状打開を目指しましょう。 思い切って仕事を休む 精神的に疲弊している場合、無理に出勤せず職場を休むのが正解です。特に、ストレスで体調を崩している人や集中力が低下している人は、出勤してもいつも通りのパフォーマンスを発揮できない可能性が高いので休んだほうがいいでしょう。 ただし、何も言わずに休むと無断欠勤になってしまうので、きちんと連絡はしてくださいね。 また、有給休暇を使って長期休暇を取り、リフレッシュするのもおすすめです。 ストレスの原因を特定して対策を考える 感受性が強い人ほど「辛い」「しんどい」「職場に行きたくない」という感情が先行しやすく、ストレスの原因に気づきにくいです。 しかし辛い現状から抜け出すには、原因を特定して対策を考えなくてはいけません。 ストレスには必ず原因があるので、原因探しの方法として「なぜ職場に行きたくないのか」「どんなときに辛いと感じるのか」考え、思いつくことを紙に書きだしてみましょう。自分の感情を可視化するとストレスの原因を把握しやすくなり、そこから取るべき対策を考えられます。 小さな成果を褒める 職場に行きたくないときに自分を責めてしまう人は、小さな成果に注目して意識的に自分で自分を褒めてみてください。 たとえば、行きたくないと思いつつも出社した場合は、それだけで自分を「えらい!」と褒めていいです。他にも仕事で成長を実感したときは、たとえ成果に直結していなくても「すごい!」「頑張った!」と自分を讃えていいでしょう。 自責の念が強い人は、真面目で責任感も強い傾向にあるので、少し大げさくらいに自分で自分を褒めて、自己肯定感を下げないようにするのが大切です。 誰かに相談する 一人きりでストレスを抱えると、ネガティブな感情がどんどん蓄積して解消する難易度も上がります。誰かに話を聞いてもらうだけでもストレス解消に効果的なので、職場に行きたくない気持ちは人と共有しましょう。 友だちや家族、職場の人などに相談するのもありですが、より効率的な問題解決を望むならキャリアコンサルティングを受けるのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、現状の課題やストレスの原因を洗い出し、あなたに合った解決策を一緒に考えてくれます。好きな場所から都合のいいタイミングでキャリアコンサルティングを受けられるオンラインサービスも登場しているので、ぜひ利用してみてください。 休職や異動、転職を考える 上記の方法を試してもストレスを解消できないときや、職場に行きたくない気持ちが和らがないときは、職場と距離を取るのが効果的。代表的な方法としては、休職や異動の希望を申し出る、転職するなどが挙げられます。 ただし、これらの方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、今後のキャリアに与える影響も大きいため、よく考えた上で決断してください。 また、「休職・異動・転職、どれを選ぶべき?」「転職したいけど、自分に合う仕事がわからない」といった悩みにも、上記で紹介したキャリアコンサルティングが役立ちます。 職場に行きたくない気持ちと向き合い、ストレス軽減を目指そう 行きたくないと思うほどに職場のストレスが大きい場合、ストレスの原因を見つけ、対策を取ることが求められます。 ただし強すぎるストレスを受けると人は考えがまとまりにくくなり、ネガティブ思考になりやすいので、一人で問題解決しようとせず信頼できる人を頼りましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボなら、職場に行きたくないという悩みも真摯に受け止め、ストレスの根本的原因を探りつつ解決策をアドバイスしてくれます。自分の気持ちと向き合う場として、ぜひ気軽に相談してみてください!
あわせて読みたい!

仕事の人間関係がストレス!割り切るポイントと解消法
「人間関係の悩み」は、仕事のストレスになりやすい要素の一つ。 「職場の人間関係にうまく馴染めない」「社内に苦手な人がいて折り合いが悪い」 ビジネスパーソンなら誰でも一度は、このような人間関係のストレスを感じた経験があるのではないでしょうか。 本記事では、仕事の人間関係にストレスを抱えている人に向けて、気持ちを割り切るポイントやモヤモヤしたときの解消法などを解説します。 人間関係は仕事のストレスに直結しやすい 令和5年に厚生労働省が実施した「労働安全衛生調査」にて、「職場にストレスと感じる事柄がある」と回答した人は82.7%もいました。その中で「対人関係がストレス」と答えた人の割合は29.6%となっており、働く多くの人にとって人間関係が仕事のストレスになっているのがうかがえます。 また、対人関係にストレスを感じると答えた人の男女比は男性が26.3%、女性が33.7%であり、男性よりも女性のほうが仕事の人間関係にストレスを感じやすいようです。 同年実施の「雇用動向調査」においても、「職場の人間関係が好ましくなかった」という転職理由は上位にランクインしていて、人間関係のストレスでキャリアチェンジする人も少なくない事実が浮き彫りとなっています。 仕事の人間関係にストレスを感じるのはなぜ? なぜ、仕事の人間関係はストレスになりやすいのでしょうか。ここでは、考えられる理由を解説します。 職場はコミュニケーション不足が起きやすいから 大前提として職場は仕事をする場所。そのため、各々が自分の仕事に没頭するあまりコミュニケーション不足が起きやすく、第一印象や先入観でお互いを理解した気になりやすいです。 しかしそうすると、自分がイメージしていたものとは異なる言動を相手が取った際に不信感や違和感が生まれ、悪い印象を持つきっかけに。 お互いをきちんと理解できていないため意思の疎通もうまくいきにくく、意見が割れたり対立が起きたりしてストレスを感じることがあります。 自分の意見が言えないから 家族や友達と話すときとは異なり、あらゆる人に配慮する必要がある仕事中は、思っていることをストレートに言えない場面も少なくありません。 そのため、自分の意見を言えないまま望まない方向に業務が進んで、ストレスを感じるケースがあります。 また、自分の意見が言いにくい環境は、わからないことがあっても質問できなかったり、相手にやめてほしいことを伝えられなかったりする状況を招くリスクも。仕事に支障が出る、いつまでも不快な思いをし続けるなどして、人間関係に強いストレスを感じる可能性があります。 苦手な人とも関わらなくてはいけないから プライベートでは、付き合う人を自由に選定して苦手な人を避けられます。しかし仕事においては、自分の意思で付き合う人を選べないため、苦手な人とも必要に応じて関わらなくてはいけません。職場にはさまざまな価値観・タイプの人がいるので、中には「合わない」「苦手」と感じる人もいるでしょう。 しかしそう感じる相手であっても、うまくコミュニケーションや連携を取る必要があるため、仕事の人間関係はプライベートの人間関係よりもストレスが生じやすいです。 仕事はお互いの人間性が出やすいから 職場は、意外と人間性が出る場所です。トラブル発生時の行動や誰もが嫌がるような仕事への向き合い方、困っている人がいたときの対応などから、普段は隠されている本当の性格が見えることがあります。 また、毎日顔を合わせて長時間一緒に働くことで、気分屋な一面や効率の悪さが露見する場合もあるでしょう。 仕事の人間関係がストレスになりやすいのは、そもそも職場が「お互いの嫌な部分が目につきやすい場所」であるのも一因だと考えられます。 ハラスメントがあるから パワハラやいじめがある職場で、過度な叱責や不当な扱いを体験することは、深刻なストレスにつながるでしょう。自分自身がハラスメントの被害者になった場合はもちろんですが、直接的な被害はなくても近くで見ているだけで精神的負担は相当なものです。 ハラスメントが横行する職場では、誰を信じていいのかもわからなくなりやすいので、孤立感が強まります。 職場の人とのちょっとした交流にも緊張してホッとできる瞬間が少ないため、ストレスがどんどん蓄積しやすいです。 仕事の人間関係にストレスを抱えやすい人の特徴 仕事の人間関係にストレスを抱えやすい人には、よく見られる特徴がいくつかあります。代表的な3つを紹介するので、自分に当てはまっていないかチェックしてみてください。 人とのコミュニケーションが苦手 コミュニケーションに苦手意識がある人は、自ら積極的に人と交流しようとしないため、相手の人柄をよく理解しないまま勝手なイメージを固定化しやすいです。思っていることがあってもそれを伝えられず、自分の意見や感情を内に溜め込んでストレスを抱えてしまいます。 また、たとえ長く働いても人と交流を持たなければ信頼関係は育たないので、仕事中に緊張や不安が生じやすく、それもストレスになるでしょう。 真面目で厳格な性格 いい加減なことを嫌う真面目な性格は長所でもありますが、自らの几帳面さを他人にも求める傾向が強いので、他人の予想外の言動にイライラを募らせやすいです。 「一般的に考えてこうあるべき」のように一般論や自分の考えに固執しがちで融通が利きにくいため、時に相手やその場の空気に合わせなくてはいけない仕事の人間関係にストレスを感じるでしょう。 仕事が理想通りに進まないと厳しい態度で周囲に接することもあり、自ら人間関係を悪くしてストレスを抱えるかもしれません。 共感力が高すぎる 共感力が高い人は、他人との境界線があいまいになりがち。相手の身に起きた出来事や感情を自分のことのように捉え、良い影響も悪い影響もダイレクトに受けて人間関係に疲れを感じやすいです。 また、共感力が高い人は他人に寄り添う能力があるからこそ「相手は困っているだろう」「助けてほしいと思っているだろう」と察して要望全てに応えようとします。 自分のことを後回しにしてでも他人を優先させる傾向が強いので、仕事の人間関係で不満やストレスを溜めやすいです。 ストレスをなくすには仕事の人間関係を割り切るのがカギ 上手に気持ちを割り切れると、仕事の人間関係におけるストレスはぐんと減ります。ここからは、仕事の人間関係を割り切るための5つのポイントをお伝えしましょう。 仕事とプライベートは別だと考える まずは気持ちを整理して、仕事とプライベートにしっかり線引きをしましょう。仕事とプライベートを別物として割り切ることで、こだわりや感情にとらわれにくくなります。 「職場で最もやるべきことは仕事であり、友達作りではない」と思えれば、他人の目や評価を気にする回数も減るでしょう。 「相手から嫌われたらどうしよう」という恐怖も和らぎやすいので、今より自己主張できたり嫌なことをきちんと断れたりして、人間関係のストレスが減る可能性が高いです。 他人に期待しすぎない 他人に対し「〇〇の仕事を手伝ってもらいたい」「短所を直してもらいたい」のように思うのは、過度な期待です。 そして、他人に対して期待しすぎてはいけません。過度な期待は、叶わなかったときの絶望感も大きく、さらにストレスを強めてしまいます。 期待をするべき相手は、他人ではなく自分です。他人に何かしてもらおう、変わってもらおうとするのではなく、自分が成長や変化するにはどうすればいいかを考えましょう。 事実だけに目を向ける 人間は、誰しも良い面・悪い面の両方を持っています。他人の嫌な部分を一度見ただけで「嫌な人」と決めつけてしまうと、職場中が嫌いな人だらけになり、余計に人間関係のストレスが増えるでしょう。 そのため、他人の嫌な面に触れても「相手にはこんな悪いところもあるんだ」と事実だけを受け止め、自身の感情と深く結び付けないように意識するのがコツ。 「嫌い」「苦手」「合わない」など、ネガティブな感情を発生させないように工夫すれば、自然と人間関係のストレスは軽減します。 人間関係は「広く浅く」を意識 仕事の人間関係を割り切るなら、特定の人とだけ深く関わったり、他人との交流を断ち切って孤立したりするのではなく、広く浅い関係を構築するのがおすすめです。 広い人間関係を築いておけば、仕事上のトラブルに見舞われた際にも周囲に助けを求めやすくなります。 また、あえて深く交流しないことで、お互いに自分のペースを乱さずに済み、適度な距離感を維持できるでしょう。 人間関係に完璧を求めない さまざまな人がいる職場では、全員と良好な人間関係を築くのは不可能だと理解して、完璧を求めないようにするのも大切です。 全員と良好な関係を結べるのが理想ではあるものの、人間には相性があるのでどうしても難しい場合もあります。また、無理に全員から好かれようとすれば自分を抑制する場面が増え、ストレスは強くなるでしょう。 苦手だと思う気持ちや折り合いが悪い現状もありのまま認め、時には現状維持でも良しとする柔軟性が必要です。 仕事の人間関係のストレスを解消する方法 どれだけ割り切っていても、仕事の人間関係にストレスを感じることもあるでしょう。ここではそんなときに試してほしい、ストレス解消法を紹介します。 ストレスを感じたときは状況と感情を客観視する 誰かにイラっとしたときや、モヤモヤした感情が溜まっているときは、一度今の状態と自分の感情を客観視してみてください。 「何にストレスを感じ、そのとき自分はどんな気持ちになったのか」「今なおストレスはあるのか」「今後ストレスが改善される可能性はあるか」といったように、ストレスを感じた瞬間から現在までを時系列で考えます。 状況と感情を丁寧に分析すると気持ちが落ち着き、「よくよく考えてみたら、意外と大したことじゃないかも」と思えて、ストレスが消えていくケースも少なくありません。 苦手な人とは必要に応じて距離を取る 苦手な人と一緒にいるだけでストレスを感じるときは、仕事に支障をきたさない程度にうまく距離を取るのも大切です。 人間関係のストレスは、苦手な人と接触する機会が減れば自然と低減します。 露骨に相手を避けたり、業務上必要な連絡まで怠ったりするのはNGですが、苦手な人との私的な交流機会が減るだけで仕事の人間関係はやりやすくなるでしょう。 一日の中に気分転換やリラックスできる時間を設ける 気分転換やリラックスできる時間を一日の中のどこかに設け、こまめにストレス発散できるルーティンを作りましょう。ストレスは蓄積させればさせるほど解消が難しくなるので、できるだけその日のうちにリフレッシュしたほうがいいです。 また、時には長期休暇を取り、日常的な気分転換だけでは発散できなかったストレスを思いきり開放させるのも大切です。 身近な人に相談する 友だちや職場の上司、家族などに、仕事の人間関係について相談してみるのも有効なストレス解消法といえます。 信頼できる人に自分の本心を打ち明けることで、気持ちが軽くなったり客観的視点を得るきっかけになったりする可能性が高いです。その後話題が変わったとしても、楽しく盛り上がればいい気分転換になるでしょう。 大きなストレスを抱えると一人でふさぎ込みがちになりますが、不安や孤独感を解消させるためにも、できるだけ積極的に他人と交流してください。 キャリアコンサルティングを受けてみる 「何をやっても仕事のストレスが大きくてつらい」「仕事の人間関係がストレスすぎて、転職を考えている」 このような場合は、キャリアコンサルティングを受けてみるのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、キャリアに関する悩みはもちろん、人間関係の悩みにも丁寧にアドバイスしてもらえます。 プロ目線の具体的なアドバイスを参考にすれば、ストレスの原因に的確にアプローチしやすく、悩み解決の突破口が開けるはずです。 上手に人間関係を構築して、仕事のストレスを低減させよう 多くの人と協力しながら進めなくてはいけない仕事では、人間関係のストレスが必ず発生します。 しかし、自らの考え方や行動を変えて上手に人間関係を構築できれば、仕事のストレスは大幅に減少するはずです。 無理にストレスに強くなろうとするのではなく、ストレスが発生しにくい環境を自分で整えて、気持ちよく働けるように工夫しましょう。キャリア・コンサルティング・ラボでは、そのお手伝いをするための相談を受け付けているので、ぜひ気軽に利用してみてくださいね!

仕事のストレス限界サイン7選!症状が出たときの対処法
仕事にはさまざまなストレスがありますが、ストレスを限界まで溜めると心や体、行動などに変化が現れ、放置すると深刻な病気に発展するリスクも! 今回は、仕事のストレスが限界に達しているときに現れる症状や、つらい現状を変えるための対処法を解説します。 仕事のストレスに悩まされている人は、この記事を参考に適切に対処し、気持ちよく働ける日々を取り戻しましょう。 仕事のストレスとは?原因と影響 仕事のストレスとは、外部からの刺激(ストレッサー)によって心身に生じる反応のことです。 何にどれだけ心身が反応するかは人それぞれ異なるため、ストレスを限界だと感じる基準も一人ひとり異なります。 「この程度の仕事のストレスで限界を感じるなんて甘えかな」「他の人は限界を迎えてなさそうだから、自分も頑張らないと」 このように考えて自分を責めたり無理をしたりする人も少なくありませんが、ストレス耐性は人によって違うため、過度な我慢は禁物。仕事のストレスを限界突破させないためには「つらい」という気持ちを素直に受け止め、その都度適切に対処するのが大切です。 仕事のストレスが限界に達する原因 仕事のストレスはほとんどが「精神的刺激」が原因で発生します。精神的刺激になる主な要素は以下の通りです。 職場の人間関係に悩んでいる 仕事の量や納期が適切ではない 評価や給与に不満がある プレッシャーが大きすぎる 適性に合わない仕事をしている このような要因があると不安や不満、緊張が生まれやすく、心理的負担がストレスとなります。 ただし、労働環境が暑すぎる・寒すぎる、騒音が激しいといった「物理的刺激」も仕事のストレスになり得るので、まずは自分が何にストレスを感じているかを考えてみましょう。 仕事のストレスがもたらす影響 ストレスは、一気に大きな影響をもたらすのではなく、じわじわと心身に影響を及ぼすのが特徴です。 そのため、仕事でストレスを感じても、ほとんどの場合最初は軽い疲労感を感じる程度でしょう。しかし、そのまま対処せずにいると次第にストレスは蓄積し、集中力の低下や体調不良、メンタルの疾患などを引き起こす可能性があります。 場合によっては、就労を続けるのが困難なほど甚大な影響をもたらす恐れがあり、小さなストレスも軽視できません。 仕事のストレスが限界なときに現れるサイン・症状 ここでは、仕事のストレスが限界なときに現れる代表的なサインを紹介します。心の限界に早く気付くためにも、自分に以下のような症状が出ていないかチェックしてみてください。 関心や集中力の低下 初期のストレス限界サインとして、物事への興味や集中力の低下が挙げられます。 ストレスが心の大半を占めると、常に悩みや不安にとらわれて、好きだった趣味や息抜きに行っていた行動にも関心が湧きにくくなるのです。また、仕事に対する興味も失いやすく、集中力低下によってミスが増えるという悪循環に陥るケースもあります。 人との交流に対しても関心を持てなくなる傾向なので、人間関係を希薄にして孤立感を深めてしまうかもしれません。 頭痛や肩こり 仕事でストレスを感じると、つい全身に力が入ってしまうという人は多いのではないでしょうか。また、不安や緊張を感じると気が張り詰めて動きがぎこちなくなり、長時間同じ姿勢を取って血行不良になりやすいです。 そして、このような状態は筋肉の緊張や神経伝達物質の乱れを招き、頭痛・肩こり・めまいなどを引き起こす可能性を高めます。 風邪気味や疲れだと勘違いして放置してしまう人も多いですが、ストレスによる身体症状は市販薬や通常の治療では治りにくいのが特徴です。 食欲不振または過食 食欲の変化は、わかりやすいストレスの限界サインといえます。 仕事のストレスが限界に達すると、胃腸の動きが鈍くなりやすいです。気分の落ち込みによって食事を楽しもうという気も起きにくくなるので、空腹感を感じずに食欲不振に陥るケースがあるでしょう。 一方、限界まで溜めたストレスによって過食に走る人もいます。特に、もともと食べてストレス解消していた人は、大きなストレスを抱えれば抱えるほど食べてしまう傾向です。 胃痛や消化不良 仕事のストレスが限界に近づくと、胃の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすくなります。胃酸が過剰分泌されやすくなるため胃粘膜が刺激され、胃の痛みや不快感、胸やけ、吐き気などの症状が出る場合があるでしょう。 胃酸過多により食べ物が正常に消化されにくくなり、便秘や下痢といった消化不良を起こすリスクも上がります。放置して慢性化すると胃潰瘍や十二指腸潰瘍になる恐れもあり、注意が必要です。 なおこれらの症状は、上記で取り上げた食欲不振や過食によって引き起こされるケースもあります。 睡眠障害 「なかなか眠れない」もしくは「眠りすぎてしまう」など、仕事のストレスは毎日の睡眠にも影響します。 仕事のストレスが限界だと、帰宅後や休日も仕事のことが頭から離れにくくなり、リラックスできずに寝つきが悪くなりやすいです。また、仕事のストレスによって自律神経が乱れると、睡眠の質が低下して過眠症状が現れる場合もあります。 いずれの場合も良質な睡眠はとれておらず、睡眠不足や疲労感が蓄積して、体調不良を招くリスクが高いです。 感情をコントロールできない 些細なことでイライラしてしまう、突然怒りがこみあげてくる、急に涙が止まらなくなるのように、仕事でストレスを感じると感情のコントロールが難しくなることがあります。 精神的負担が大きすぎて心がいっぱいいっぱいになっている証拠であり、まさにストレスの限界が近いサインといえるでしょう。 誰かが言った他愛もない冗談に激怒してしまったり、イライラしている自分を見せないようにと人付き合いを避けたりしやすくなるので、職場の人間関係がギクシャクしてさらにストレスを抱えてしまう場合もあります。 気分が沈んだ状態が続く 365日気分が上向きという人はいませんが、憂鬱な気分や落ち込んだ気持ちが続く場合、ストレスによって心が限界を迎えていると判断できるでしょう。 このようなうつ状態に陥ると不安や自己批判の感情が強まり、全ての物事に対して無気力になります。何をするにも億劫で、仕事に行くのはもちろん、普段通りの日常生活を送ることさえ難しいと感じる人も少なくありません。 うつ状態が続く場合は、うつ病を発症している可能性があるため、早めに専門の病院やクリニックを受診して適切な治療を受けてください。 限界まで仕事のストレスを溜めてしまう人の特徴 限界まで仕事のストレスを溜めてしまう人には、いくつか共通する特徴があります。ここからは、ストレスを感じやすい人・溜めやすい人の特徴を見ていきましょう。 責任感が強く頑張りすぎてしまう人 責任感が強い人は、全てを一人で抱え込んで無理をするところがあります。完璧主義の傾向も強いので、常に高い水準の成果を求めて仕事を頑張りすぎてしまい、ストレスを溜めやすいです。 責任感の強さから人の頼みごとに「NO」と言えないタイプで、頼まれるとつい何でも引き受けてストレスを限界突破させてしまうことも。 また、目標達成意欲が高いからこそ、達成できないと自分を過剰に責めてしまい、それがストレスになるケースも少なくありません。 周囲に気を遣いすぎる人 気配り上手は長所でもあるものの、度が過ぎる人は仕事中も常に周囲を気遣って他人を優先させてしまいます。他人の顔色に合わせて言動を変えたり、周囲の空気を読んで自分の意見を飲み込んだりするため、気疲れによって限界までストレスを溜めやすいです。 「自分の思いや考えを伝えると相手に嫌われるのでは」という可能性を考えて不安に駆られやすいのも特徴で、ストレスが慢性化する可能性があります。 せっかちな人 せっかちな人は、常に何かしていないと気が済まない性格で、仕事の生産性も高いです。 しかし、周囲にも自分と同等の行動量や生産性を求めやすく、一緒に働く人に対してイライラしてストレスを溜めてしまうことがあります。 また、せっかちな人は心に落ち着きがないので、物事を深く考えずに発言しがち。悪気はないものの、厳しい言葉で他人を急かしてプレッシャーを与えてしまい、職場の人間関係悪化によってストレスを感じる場合もあるでしょう。 正義感が強すぎる人 正義感が強すぎる人は真面目で、決められたルールを重んじます。ルールや規律に沿って仕事を進めるのは間違いではありませんが、ルールを絶対視しすぎると融通が利きません。 イレギュラーな事態により、業務範囲外の仕事をお願いされたり、やむを得ずルールから外れた行動を取る他人を見たりするとイライラが止まらず、ストレスが限界に達しやすいです。 「常にルールを守る自分は正しい」と思い込むので他人の意見を受け入れられず、職場の人間関係がうまくいきにくいのもストレスの原因になるでしょう。 自己評価が低い人 自己評価が低い人は「自分は人より劣っている」と常に自分自身を否定的に捉えるので、自分で自分にストレスをかけがちです。 「自分なんて」という気持ちが常にあるため、仕事で理不尽な目に遭っても自己犠牲的に我慢しやすく、限界までストレスを溜めてしまいます。 現状から抜け出したいと思っても、自分に自信がないため失敗を恐れて行動できず、ストレスや悩みを一人で抱えやすいです。 仕事のストレスが限界なときの対処法 ここからは、仕事のストレスが限界に達してしまったときの対処法を解説します。今日からすぐに取り組めるものもあるので、ぜひ実践してみてください。 現状を認めて休む 仕事のストレスを限界まで溜めてしまう人は、自分が疲れていることやストレスを感じていることをなかなか素直に認められません。しかし、現状を認めず無理に頑張れば状況は悪化する一方なので、まずは「自分はストレスを感じている」と事実を受け止めましょう。 その上で、しっかりと休息を取るのが大切です。休暇を取得すればストレスの原因である仕事から離れられ、疲れた心が徐々に回復する可能性があります。 SNSやネットから離れる ストレスが限界に近ければ近いほど、ネガティブな情報に敏感になり、影響を受けやすくなります。 「有益なストレス対処法が知りたい」「自分と同じような境遇の人を見つけて孤独感を和らげたい」 このような思いからついSNSやネットを開きがちですが、過度な情報にさらされると疲労やストレスは大きくなりやすいので、時には思い切ってスマートフォンやパソコンから離れましょう。 必要のない情報を遮断する時間は、自分自身とだけ向き合えて気持ちを前向きにしやすいです。 人と話す 信頼できる人とじっくり話すのも、仕事のストレスが限界なときに有効な対処法です。とりとめのない話を楽しむだけでも気持ちが明るくなりますし、愚痴や悩みを聞いてもらえばストレスが軽減する可能性があります。 また、家族や友達に話しにくい内容は、キャリアコンサルティングで打ち明けるのも良いでしょう。キャリアコンサルティングでは、キャリアに関する相談はもちろん、職場のストレスや仕事全般の悩み相談にも乗ってもらえます。 現状に対してプロ目線のアドバイスが受けられるので、できるだけ早くストレスを対処したい人におすすめです。 心身の不調は専門家に相談する 限界に達したストレスによって心身に不調が出ているなら、それは専門の医師に相談する目安です。 頭痛や下痢、肩こりなど身体症状が出ているときは、まず内科や消化器内科、整形外科など専門の診療科を受診します。専門の診療科で病気の可能性を調べてもらった後、ストレスが原因の可能性が高いと診断された場合は、心療内科やメンタルクリニックを受診すると良いでしょう。 異動・転職する ストレスが限界に達して心身が悲鳴を上げている状態に陥ってまで、続けないといけない仕事はありません。さまざまな対処法を試してもストレスが大きいままという場合は、異動や転職によって働く環境を変えるのも一つの方法です。 なお、今すぐストレスを解消したいという思いで突発的に退職する人もいますが、このような行為は後の転職活動にも悪影響を及ぼす可能性が高いのでNG。事前に準備や相談をした上で適切な手順を踏み、円満に事を進めてください。 仕事のストレスは限界がくる前に対処するのが大切 仕事をしている以上ストレスとは切っても切れない関係が続きますが、ストレスを限界まで溜めると心身にさまざまな悪影響が出ます。大切なのは、小さなストレスサインも見逃さず、自分の気持ちを尊重してこまめにケアをすることです。 また、人に話しにくい悩みがあったりストレスの解決策がなかなか見つからなかったりするときは、キャリアコンサルティングを受けてみましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボなら、オンラインで気軽に相談できるので「仕事のストレスが限界かも」と感じている人は一度利用してみてください。

職場のストレス対処法は?仕事中でもすぐできる発散方法を紹介
職場にストレスはつきものだからこそ、社会人は「上手なストレス対処法」を身に付ける必要があります。 今回は、職場での気疲れやイライラが蓄積している人に試してもらいたい、ストレスの対処法を解説! 職場でできる簡単なものから大きなストレス解消になるものまで、合計10個のストレス対処法を紹介するので、ぜひ自分に合う方法を見つけてください。 職場でストレスを感じたときに真っ先にやるべきこと ストレスは「解消」できるものと「発散」させたほうがいいもの、大きく2タイプあります。「解消」は根本的問題を解決してストレスを元からなくすこと、「発散」は溜まったストレスを開放したり気分転換を図ったりすることです。 全てのストレスを解消できるのが理想ではあるものの、職場のあらゆる問題を全て解決するのは難しく、受けたストレスは発散させたほうがいい場合もあります。発散でしか対処できないストレスを無理に解消しようとすれば、うまくいかずさらにストレスを抱えてしまう可能性も! そのため、職場でストレスを感じたら、まずは「解消」と「発散」どちらの方法で対処すべきかを考えてみましょう。ストレスの原因を特定し、解決が見込める問題かどうかを考えると、どちらを選ぶべきかがわかりやすいです。 職場でできる!手軽なストレス対処法 ここでは、仕事中や職場ですぐにできる手軽なストレス対処法を紹介します。ストレスを溜めないためにも、小さなストレスを感じた時点でこまめに行ってみてください。 深呼吸・ストレッチをする 仕事中にストレスを感じたら、その場でゆっくり深呼吸をしてみましょう。深呼吸をすると副交感神経が刺激され、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールの分泌を抑えてくれるといわれています。 また、座ったまま行える簡単なストレッチを仕事中にするだけでも、身体がほぐれて呼吸が深まるので不安やストレス緩和に効果的です。 場所を移動する 同じ場所で長く作業していると、だんだんストレスが溜まってくる…という人も多いでしょう。そんなときは、少し歩いたり仕事をする場所を変えたりするのがおすすめ。 トイレや休憩室に行く、オフィスではなくカフェで仕事をするなどするだけで、気分が入れ替わりストレス軽減になる場合も少なくありません。 なお、リモートワークができる会社ならリモートワークを選択するのもありです。 休憩する 仕事の合間にしっかり息抜きするのも、良いストレス対処法といえるでしょう。具体的には、間食としてコーヒーや甘いものを摂取する、同僚と雑談をする、昼寝をするなどが挙げられます。 ストレスを感じて心がモヤモヤすると休憩時間まで暗い気持ちになりがちです。しかし、意識的にオンオフをつけると気持ちの切り替えにもなり、ストレスが溜まりにくくなります。 職場のストレスが溜まったときの対処法 手軽な方法だけでは対処できない、手ごわいストレスも存在します。ここからは、職場のストレスが蓄積して心が疲れてしまったときの対処法を解説します。 まずは休む! 十分な休息が取れていないと、それだけでストレスは増加してしまいます。リラックスできる時間と睡眠時間をたっぷり確保し、心身ともに休息を取りましょう。 帰宅後や休日を利用してしっかり休める場合は問題ありませんが、物足りなさを感じる場合は有給休暇などを利用して長期で休むのもありです。 また、普段から規則正しい生活や健康的な食事を意識して、生活習慣から心身を労わるのも忘れないでください。休養によって心身の疲れが取れると思考もクリアになり、ストレスに強いメンタルを育むことにもつながります。 適度に体を動かす ストレスを感じると呼吸は浅くなり、身体が緊張する傾向にあります。これらを解消させて心身にリラックスをもたらすのが、運動です。 運動といっても、激しく体を動かす必要はありません。運動によってしんどい思いをするとさらにストレスを感じてしまうので、ウォーキングやジョギング、ストレッチ、ヨガなど、無理なくできる軽めの運動をできるだけ継続しましょう。 なお、運動中は日光を浴びると、幸せホルモンことセロトニンやエンドルフィンがより多く分泌されてストレス軽減効果が高まります。 ストレスを紙に書き出す 「職場のストレスで心がモヤモヤする」という場合は、感情を紙に書き出してみてください。 自分の気持ちを書き出すと、ストレスの原因や職場の状況、自分の考え方の癖などを深く理解でき、気持ちの整理がつきやすくなります。 その後、思いきり感情をぶつけて書いた紙をびりびりに破いたり、シュレッダーにかけたりするのも一つの対処法です。自分の気持ちそのものである紙を物理的に破壊することで、怒りや不満といったストレスの元になる感情が静まり、気持ちをリセットできる場合があります。 プライベートを楽しむ 職場のことを完全に忘れて自分の時間を楽しむのも、非常に効果の高いストレス対処法の一つ。例としては、趣味に没頭する、外出して新鮮さを得る、おいしいものを食べるなどが挙げられます。 この他、映画やドラマを見て思いきり笑ったり泣いたりするのも、感情を放出できるのでストレス発散になるでしょう。 プライベートをしっかり楽しめると「自分には職場とは別に楽しい居場所がある」とも思えます。良い意味で職場への依存度が下がるので、割り切った考え方ができてストレス耐性も高まりやすいです。 周囲の人と話をする 友人・家族と雑談をして盛り上がったり、嫌だったことやストレスに感じていることの話を聞いてもらったりするのも有効な対処法です。職場とは全く関係のない話題であっても、楽しく盛り上がっていると気分転換になりストレスが軽減します。 また、職場の悩みなどを打ち明けると、自分の気持ちを整理できる他、第三者視点からのアドバイスが得られ考え方が広がるでしょう。 丁寧な対話には、それだけで安心感や充足感をもたらす効果があります。誰かとじっくり話をすると「話を聞いてもらえた」「優しくしてもらえた」と感じられ、気持ちが落ち着きやすいです。 専門家に相談する ストレスを根本から解消したいものの対処法がわからない場合や、周囲にアドバイスを求めてみてもなかなかピンとこないときは、専門家を頼りましょう。 職場のストレスを相談できる専門家の中でも特におすすめなのは、キャリアコンサルタントです。 キャリアコンサルタントは職場の幅広い悩みに対応し、相談者の価値観や考え方を尊重した上でアドバイスを授けてくれます。職場のストレスの悩みから派生してキャリアや転職の悩みが生じた際も、そのまま相談できるので心強いです。 ただし、ストレスによって心身に不調が出ている場合は、先に専門の医療機関で医師に相談してください。 異動や転職を視野に入れる あらゆる対処法を試してもストレスを取り除けず、心身や日常生活に悪影響が出ている場合は、自分に合わない職場で働いている可能性も考えられます。 今の職場を離れることを検討し、異動や転職を視野に入れてもいいかもしれません。ただし、異動や転職がキャリアに与える影響は大きく、今後の人生がガラリと変わる可能性もゼロではないので、慎重な判断が必要です。 異動や転職についてもキャリアコンサルティングで相談できるので、迷ったときは利用してみましょう。 職場のストレス耐性を高める5つの習慣 今あるストレスに対処するのも大切ですが、耐性を高めてストレスを受けにくい人になる努力をするのも大切です。ここでは、ストレス耐性を高めるために実践してほしい、5つの習慣を解説します。 小さいストレスにすぐ対処する ストレス耐性が高い人とは、言い換えれば「ストレスを感じてもすぐに解消・発散できる人」です。 一切ストレスがない職場はほとんど存在しませんが、たとえストレスがあってもすぐになくすことができれば負担は最小限で済みます。 ストレスを早期に解消・発散するためには、小さなストレスを軽視しないことが大切です。ストレスは蓄積させればさせるほど対処が難しくなるので、程度が軽くても見て見ぬ振りせず、できるだけその日のうちに自分を癒す対処を行いましょう。 周囲を頼る 職場でストレスを感じやすい人は、周囲に頼るのが苦手という特徴を持っている場合が多いです。うまく周囲に頼れないため、仕事を抱えすぎたり悩みを誰にも相談できなかったりして、よりストレスを大きくしてしまう傾向があります。 しかし、職場は一緒に働く人と協力して仕事を進める場なので、負担が大きいときやしんどいときは周囲の人を積極的に頼るべきといえるでしょう。 まずは「周囲に頼っていいんだ」という意識を持ち、小さな頼み事から始めてみてください。この他、普段から信頼関係を築き、頼りやすい関係性を作っておくのも忘れてはいけません。 物事を前向きに受け止める 何事も、できるだけ前向きに捉える習慣を身に付けましょう。物事をネガティブに受け止めると、心配や不安、怒りといった感情が生まれやすくなりストレスにつながります。 できていないことよりもできていることに目を向ける、意識してポジティブな言葉を使うようにするなどするだけでも、徐々に思考が前向きになるはずです。 また、ネガティブな捉え方をしてしまったときも自分を責めず、ポジティブに捉えられないか別の視点から考え直してみてください。 仕事に優先順位をつける 仕事に時間がかかりすぎてしまったり、自分の仕事ぶりに納得できなかったりするのがストレスという人は、仕事に優先順位をつけるのをマイルール化してみてください。 タスクをメモに書き出し、緊急性の高さやタスク完遂までにかかる時間を考えます。それらから考えられる優先順位の高いタスクから順番に着手していけば、今より効率的に作業できストレスそのものを解消させられるかもしれません。 自分をしっかり持つ 周囲に合わせすぎてしまう人は、職場でも他人を優先して自分の考えを抑えがちなので、気疲れによってストレスを感じやすいです。 そのため「必ずしも他人に合わせなくていい」と自分で自分を許し、自分はどうしたいのかという部分を大切にする考え方を身に付けてください。また、コミュニケーション力を磨き、自分の意見を正確に相手に伝えられるよう努力するのも重要です。 自分をしっかり持つと、人の意見や言動に左右されにくくなり、ストレス予防につながります。 職場でストレスを感じてもやってはいけない対処法 ストレス対処法の中には、良かれと思ってやるとマイナスな効果につながる「NG対処法」もあります。以下のようなNG対処法は選択しないようにしましょう。 食べすぎ・深酒 おいしいものを食べたりお酒を飲んだりしてリフレッシュするのは効果的なストレス対処法ですが、それは「適量」の場合です。 食べすぎ・飲みすぎは身体にかかる負担が大きく、肥満やメタボリックシンドローム、その他疾患などを引き起こしやすくなります。 「ストレスを感じたら食べる」と脳がインプットしてしまうと、食欲をコントロールするのも難しくなるので、早めに飲み食いの代わりになるストレス対処法を見つけてください。 過剰なギャンブル・ショッピング ギャンブルやショッピングは、行っている間一時的に脳内が活性化しドーパミンという快楽物質が大量放出されるため、依存症を招くリスクが高いです。 もちろん節度を持って行う分には問題ありませんが、ストレスを受けるたびにギャンブルやショッピングをしていると依存症になりやすいので注意しましょう。 また、既に依存症に陥っている疑いがある場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。 悪口 誰かに話を聞いてもらうのもストレス対処法の一つですが、話す内容が悪口である場合、さらにストレスが増加するリスクがあるので要注意。 悪口を言うと脳内では、快楽物質・ドーパミンとともにストレス物質・コルチゾールも分泌されます。悪口は、一時的には楽しくても実は心身に負荷をかける行為なので、結果的に心身の不調を招きやすいです。 対処法を知って、職場のストレスをコントロールしよう 職場のストレスは、程度の小さい段階であれば軽めの方法で対処でき、その後深刻な悩みへと発展しません。 そのため、前もって自分に合った対処法を見つけておくのが大切。一人では対処が難しい場合は、キャリアコンサルタントをはじめとする専門家を頼ってください。 生じたストレスを適切に対処できれば、メンタルはもちろん仕事のパフォーマンスも安定します。この記事を参考に自分に合った対処法を把握し、職場のストレスと上手に付き合っていきましょう。