
仕事にやりがいも成長もいらない?「仕事のやりがい」問題が気になったら…
仕事にやりがいや成長はつきもの、あって当然と思われる風潮ってありますよね。 1日8時間以上もの時間を費やし、人生の大半を占めるのだから、やりがいを感じられる仕事についたほうがいいという考え方です。さらに、「仕事を通じて成長したい」というのは、就職活動や転職活動で企業に好印象を与える決まり文句でもあり、「仕事で成長とかしなくていいし」と口にしようものなら、「やる気のない奴」の烙印を押されてしまう可能性は高いでしょう。 でも、仕事にやりがいや成長を他人から求められるのって疲れてしまうし、何だか違和感がある…そう感じたことはありませんか。 そんな「仕事のやりがい」や「仕事での成長」問題のモヤモヤに、向き合ってみましょう。 仕事のやりがいや成長とは? さて、「仕事のやりがい」や「仕事を通じて成長する」という言葉を聞いたとき、その「やりがい」や「成長」にはどんなイメージを持ちますか。 「仕事のやりがい」ときくと、なんとなく目覚ましく活躍している状態や質の高い提案をして、プレゼンでどんどん企画を通すようなイメージをしてしまったり、「仕事での成長」と言われれば、どんどんスキルアップ、レベルアップしてできないことができるようになり、出せる成果が大きくなるという姿を描いてしまったりしませんか。 自分の仕事が、社内外で高く評価されていたり、「この仕事は自分しかできない」と思えるような成果を出し、周囲からも認められていたり、という具合です。自分ではそうは思っていなくても、「上司から求められるのは、そんな感じだ」という方も多いかと思います。 しかし、大辞林を調べてみると、「やりがい」とは「物事をするにあたっての心の張り合い」と説明されています。この言葉の意味通りに「やりがい=心の張り合い」と考えると、仕事のやりがいも、人それぞれでいろんな「心の張り合い」があっていいのです。 「成長」についても同様です。「成長」も、その意味を調べてみると、「1.人や動植物が育って大きくなること。おとなになること」「2. 物事の規模が大きくなること」とあります。物事の規模でなく、「人」にフォーカスすれば、つまり「おとなになること」です。人としての成熟は、決して仕事の業績だけで測れるものではありません。仕事で成果を上げるとか、仕事の質が高くなる、早くなる、〇〇ができるようになるなどは、もちろん素晴らしいことですが、決してそれだけではないのです。 なぜ、仕事にやりがいや成長が必要だといわれるのか しかし、会社で期待される「やりがい」の答えも、何かハイレベルな仕事の成果や質に関するものであることが多いのではないでしょうか。そして、会社で上司から「成長しろ」といわれるときの「成長」はこんな意味ではありませんよね。 なぜそれが求められるのかといえば、企業は、経済成長を続けることが前提の資本主義のなかで企業活動を行っているので、成長をし続けるためには組織で働く人も、「業績をあげ続けること」「より高い成果、より大きな成果を出せる人材になること」「できないことができるようになること」が必要だからです。 だから組織では、成長意欲が高い人が採用され、評価されるようになっています。でもそれはあくまで、「会社としての言い分」。それに共感し、応えようと思うことも、「自分はそうではないな」と思うことも、どちらでもよく、決めるのは自分次第です。 仕事のやりがいや成長は自分自身で決めるもの 本来の意味を考えれば、「やりがい」は心の張り合いですから、自分自身の心にちょっとした張り合いが生まれればどんなことでも「やりがい」です。たとえば、 ・目の前のお客様に、「ありがとう」と喜んでもらえた。・誰かの役に立っていると実感できた。・一生懸命仕事をして、今日も社食のお昼がおいしく食べられた。・気の合う同僚と、和気あいあいと働けている。・尊敬できる上司と一緒に仕事ができている。・オフィス環境が良くて、毎日快適に働けている。 などのこうした日々のちょっとした「心の張り合い」だって、十分仕事の「やりがい」なのです。 「成長」だって同様です。仕事を通じて、どんどん何かができるようになり、出せる成果が大きくなり、質が良くなることだけが成長ではありません。 ・人との距離の取り方がうまくなった(適度に距離を取るということも含めて)。・自分の心を穏やかに保てるようになった。・嫌なことがあっても気にしなくなった。・立ち直りが早くなった。・要領よくやることを覚えた。・嫌なことをスルーし、ストレスをためないスキルがついた。 このように、自分が心地よく生きるための人としての「成長」も、仕事を通して得られる成長です。 いかがでしょう?このように考えると、身の回りにも「やりがい」や「成長」が見えてきませんか。 「やりがい」も「成長」もどちらも自分自身の内面の問題ですから、何をやりがいとし、何を成長とするかは本来、自分自身で決めるものです。そして自分自身の問題だからこそ、他人にとやかく言われる筋合いは本来ありません。 自分のやりたい仕事をやって、充実した成果を出していて、しかもそれが評価されていて、満足な報酬を得ている。そしてどんどん重要な仕事を任されるようになり、キャリアアップしている。 このような状態に「やりがい」や「成長」を感じる人もいますが、「やりがい」も「成長」もそれだけではないのです。ですからこうした「やりがい」や「成長」のイメージに縛られてしまっていると、日々の仕事に溢れているちょっとした心の張り合いや人としての成長を見落としてしまいます。 上司から求められる「成長」ばかりが、必要な成長ではない。そう考えると、少し気持ちも楽になるのではないでしょうか。 仕事にやりがいはいらなくたっていい もちろん、別の考え方もあります。「そもそも、仕事にやりがいはいらない」というものです。 確かに1日8時間かそれ以上の時間を仕事に費やしますが、人生で大切なのはもちろん仕事だけではありません。仕事だけが成長感や充実感、達成感を感じる場ではありません。いくら人生のうちの長い時間を費やすからといって、「仕事」にやりがいを感じなければいけない理由は何もないのです。 仕事を「仕事以外の場所にある、自分の心の張り合いを支える収入の糧として、割り切って取り組むもの」として捉えると、楽になることはたくさんあります。 たとえば以前、ある国民的男性アイドルグループの大ファンで、「毎年開催される全国ツアーを、各地に観に行くのが生きがい」という女性にお会いしました。 彼女は、そのために「コンサートツアーに参加しやすい仕事」という軸で仕事を選び、実際に毎年全国各地で開催されるコンサートに行ける今のライフスタイルを実現し、自分のやりたいことができる仕事にとても満足していました。 「仕事はもちろん、一生懸命やります。でも私にとって仕事は、生活費とコンサートに行ける費用が稼げればいいものなので」と自分の人生の価値基準が明確な彼女は、「仕事にやりがいが必要なのか?」という問題に悩むことはありません。 彼女は「自分の趣味(推し)のため」でしたが、これが「他にやりたいことのため」「子どものため」「家族と過ごす時間のため」など、何でもいいでしょう。 自分の人生にとって大切な「心の張り合い」は仕事以外の場にあり、仕事はそのための生活の糧としてあるだけ。別に、仕事で成長感や達成感、充実感なんてなくていい。それも、とても素敵な考え方なのです。 「仕事のやりがいと成長」問題には、人それぞれの答えがある 仕事にやりがいはいるのか、いらないのか。仕事で成長したほうがいいのか、いらないのか。その問いには万人共通の正解はなく、人それぞれに答えがあります。 仕事にやりがいを感じたい人もいれば、そんなものは仕事にいらないという人もいます。仕事を通じて成長し、自己実現したい人もいれば、そんなものは必要ないという人もいます。 大事なのは、どちらもその人にとって「正解」なので、他人が否定したり、とやかく言ったりする問題ではないということです。 他人の答えは、自分の価値観や判断軸を考える上での参考にはなりますが、自分にも同じように当てはまるわけではありません。同じように、自分の価値観が他人にも同じように当てはまるわけでもありません。 ただ、いずれにしても「やりがい」や「成長」を考える上でとても大切なことが2つあります。 「やりがい」は他人と比べると見失いがちになる それは、「やりがい」は他人と比べると見失いがちになってしまうということです。「やりがい=自分の心の張り合い」であり、人それぞれに答えがあるからこそ、他人の状況と比べていると、いつまでたっても「やりがい」は見つからず、感じにくくなってしまう可能性があります。 たとえば、自分は年収450万で仕事も楽しいし、成長も感じているのに、年収600万円の友人と比べてしまい、収入の差をネガティブに受け止めてしまうと、今まで感じていた楽しさや成長に疑問を感じてしまうかもしれません。 SNSで友人が仕事の充実した生活を発信しているのをみて、「それに比べて、自分は…」と思ってしまうかもしれません。 目の前のお客様には「ありがとう」と言ってもらえて、嬉しいとは思うのに、社内でもっと営業の業績を上げている同僚と比べてモヤモヤしてしまったり…ということはありませんか。 他人との比較を判断基準にしてしまうと、必要以上に「足りない」と感じてしまったり、あるいは、どんな状況にも必ず「上には上」がいますから、どこかで満たされなくなったりしてしまいます。 「他人と比べない」というのは、簡単にみえてなかなか難しいですが、ぜひ自分の心にまっすぐに向き合ってみましょう。 「成長」は「現状維持」のなかにもある 成長を前提とした資本主義の中で活動する企業では、成長意欲が高い人が採用され、評価されますが、そうした企業の期待に応え続けられる人、応え続けることにやりがいを感じる人ばかりではないですし、そのような人ばかりでも組織は成り立ちません。 Twitterでこのような投稿が話題になったことがあります。 https://twitter.com/rexcoaster/status/1420572222905753600 まさにこの通りで、「10を10として維持する」という、表面的な仕事としては「成長」ではなく「現状維持」をきちんとしていく多くの人がいてこそ、組織は成り立ちます。組織にとっては、どちらも大切なのです。 「10を10として維持する」ことのなかにある「やりがい」や「人としての心の成長」は、たとえ組織としてそれを評価する軸がなかったとしても、尊いものです。その大切さにも、目を向けていきましょう。 自分の内発的動機付けや外発的動機付けを考えると自分にとっての「やりがい」や「成長」がみえてくる 前述のように、企業は組織として成長を前提としている資本主義のなかで活動をしているからこそ、その構成要員である社員にも成長を求めます。 しかし、「やりがい」や「成長」は企業が求めるものがすべてではありません。 業績をあげ続けることや、より大きな成果を上げることが、「自分が好きなことをやっていたら、結果的に業績があがったり、大きな成果を上げていた」というのであれば理想なのですが、「周囲の期待に応えたいから」「周囲の評価を得たいから」という外発的動機付けによるものであれば、どこかで無理をし過ぎて苦しくなる時がやってくるかもしれません。 では自分にとっての「やりがい」や「成長」はどこにあるのか。それは何なのか。それは、自分の内発的動機付けや外発的動機付けを整理すると見えてきます。 「仕事に成長はいらない。でもなんか現状にはモヤモヤする」もし、そんな思いがよぎったら、自分の動機付けを整理し、働くことや仕事に対する考え方を整理してみませんか。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、このような「働くことや仕事に対する考え方を整理し、自分にとって大切にしたいことを実現する働き方や仕事を探す」ためのサポートも行っています。一人で整理することが面倒になったら、ぜひプロのサポートも活用してみてくださいね。

仕事で怒られてばかりで辞めたい時に今を見直す3つのポイント
仕事で怒られてばかりの毎日が続くと、本当に気が滅入ってしまいますよね。自分はこの仕事に向いていないんじゃないか、自分には価値がないのではないか、辞めた方がいいのではないかと自己評価もどんどん下がって、思考回路が負のスパイラルに突入してしまっているのではないでしょうか。 でも実はこんなときこそ、今の自分や仕事、職場を見直す、とてもいいチャンスなのです。 仕事で怒られてばかりで辞めたいほど辛い時、今をどのように客観的に捉えて、今後につなげていけばよいのか、キャリアコンサルタントの視点からご紹介します。 1. 怒られてしまう理由を考える まずは、なぜこんなに怒られてばかりなのか、怒られてしまう理由を冷静に、客観的に考えてみましょう。怒られてしまうのは、自分に何か至らないところがあるか、環境に何か問題があるか、あるいは上司に何か問題があるかいずれかにあります。 状況を客観的に捉え、自分が至らないところがないか落ち着いて振り返るのは、なかなか難しいことではありますが、これができると状況改善の道も見えてきます。 この振り返りは誰かに共有するものではありませんので、素直に認めたからといって何かに影響があるわけではありません。自分ができていなかったところは素直に認める気持ちを持って、以下のような行動に心当たりがないか、振り返ってみましょう。 仕事が覚えられず、同じミスを繰り返してしまう 仕事で同じミスを繰り返してしまってはいませんか。初めてのミスなら仕方ないと思っている上司も、何度も同じミスを繰り返していると「なぜ、何度も同じミスを繰り返すのか?」「ミスをしないように対策はしていないのか?」と感情的にイラっとしてしまうかもしれません。 ただ、もし「仕事が覚えられず、同じミスを繰り返してしまう」ことが怒られる原因ならば、状況は比較的改善しやすいと言えます。「仕事が覚えられない」のであれば、すべての手順や確認事項を細かくマニュアルやチェックシートにし、業務を行うときはそのマニュアルやチェックシートに沿って進めれば、同じミスが防げるようになるからです。 このようなケースでは、頭で「覚えている」「できている」と思ってしまっていることが要因です。覚えていると思っている業務でも、ミスが続くようなら必ずマニュアルやチェックシートを作りましょう。そのマニュアルやチェックシートに「漏れ」があるとそれがミスの原因になってしまうので、上司に確認してもらうとよいでしょう。 それによって同じミスが防げるようになるのはもちろん、「次にミスを起こさない」ために対策をしているあなたの姿勢に、上司の評価も変わってくるはずです。 報連相ができていない 仕事で怒られる理由は、ミスだけでなく、上司が必要としている「報連相(報告・連絡・相談)」が足りていないことが原因であることもあります。 「あいつは何をやっているのか、報告がないからちっともわからない」「相談もなく、勝手に判断して業務を進めてしまう」「連絡がいつも何か足りない」 と、業務に関するコミュニケーションについて日頃から上司が不満を感じていると、何かうまくいかなかったときや成果が芳しくなかったときに、その不満が爆発する形で「怒る」という感情になってしまうのです。 「報連相はしている」「コミュニケーションは取っている」 と思っていても、自分が「これで十分だろう」と思うコミュニケーションの量やタイミングと、相手が必要としているコミュニケーションの量やタイミングには、ギャップがあることが多々あります。 今までの上司との会話で「こういうときは、ちゃんと確認して」等の指摘をされたことはありませんか?もし心当たりがあれば、実は「報連相」、つまりコミュニケーションが足りていない可能性があります。 「報連相」で適切なコミュニケーションをとることは、上司のためでだけではなく、自分の状況を理解してもらい、自分の仕事を進めやすくする、自分の状況をよくすることにもとても効果的です。 たとえば、営業で顧客との関係がうまくいっていなかったとしましょう。しかしあなたは「自分でなんとかできる」「相談するほどでもない」と思い、上司に相談しなかったとします。 これで結局うまくいかずクレームになってしまったとき、それまでのプロセスで何も相談していなかったら、上司は「何でこうなるまで相談しなかったんだ」という反応になる可能性が高くなります。 しかし、もし上司に「こういう状況でうまくいっていない」と事前に相談していたら、上司からのアドバイスがあってクレームを防げたかもしれませんし、結果的にクレームになったとしても、上司はプロセスを理解しているので、対応が全く変わってくるでしょう。 このように適切な「報連相」は、上司からの評価を上げるだけでなく、自分の仕事の質を高め、自分にとってもプラスになります。 「怒られてばかり」な今は、自分の「報連相」を見直すチャンスかもしれません。仕事ができ、周囲から評価されている人は、必ず適切な「報連相」ができています。「報連相」のタイミングややり方については、ビジネス書やネットにもノウハウが紹介されていますので、ぜひこの機会に改めて学んでみましょう。 自分のミスや失敗を認めない、受け入れられない ミスや失敗をしたとき、あなたはそれを素直に受け入れ、反省していますか。他人や環境のせいにしてはいませんか。ミスや失敗の理由を説明するつもりが、言い訳のようになってしまってはいませんか。 人間なので、ある程度のミスや失敗は仕方がないものです。おそらくどんな上司でも、それはある程度理解しているでしょう。それでも部下のミスに対して怒ってしまうのは、そのミスが会社や業績に大きな損害を与えるか、何度いっても改善できない同じミスが繰り返されているか、ミスをしたあなたの態度がよくないか、あるいは上司に何か問題があるかどれかです。 「自分の態度に、まずいところがあったのかもしれない」と自分を謙虚に客観視することは、とても難しいのですが、それができるようになると大きく成長できます。 もし心当たりがあれば、ミスや失敗をしたときに謙虚になって自分の態度を改めてみましょう。周囲の態度もきっと変わってくるはずです。 業務のスピードが遅い、業務の質が低い 仕事で怒られる原因は、ミスや失敗だけとは限りません。上司や周囲が期待している、あるいは通常あるべきスピードよりも遅かったり、提案や企画、資料などのクォリティが求められているレベルよりも低いときに怒られることもあります。 しかしこの場合も、適切な「報連相」である程度状況は改善できます。たとえば業務のスピードが遅いならば、業務が遅くなってしまう理由やその改善方法を上司に「相談」することで改善するかもしれません。相談することで、もっと効率のよいやり方がみつかることもあるでしょうし、実は必要のない業務も含まれていたということもありますし、「遅い」のではなくて「必然的に時間がかかってしまう業務」だと理解してもらえることもあります。 業務の質が低いのであれば、「どんなものが求められているのか?」「そのためにどうすればいいのか?」を上司に「相談」し、求められるものを確認することで仕事の質を高めることができます。 また、「報連相」をすることで上司があなたを理解できれば、求める仕事のレベルの期待値調整もできるでしょう。 「まだできないの?」「こんなこともできないの?」と怒られてしまうときには、勇気を出して「なぜ時間がかかってしまっているのか」を相談してみるといいかもしれません。 ルールや時間、締切を守らない また、怒られてしまう原因として考えられるのは、社内のルールや締切、時間を守らないというものです。ついつい「まあ、いっか」「これぐらい大丈夫だろう」と自分を甘やかしてしまうことはありませんか。 この場合はルールや時間、締切を守れば状況は改善するので、解決策はとてもシンプルです。もし守れない特別な状況があるならば、それをきちんと上司に相談しましょう。締切を守れないときにも、守れない理由や状況を、それがわかった時点でなるべく早めに相談しておけば、締切を伸ばしたり、他の業務を調整したりなど、上司も対応することができます。 ルールや時間、締切を守るのは、どんな会社にいっても仕事をする上での基本中の基本なので、ここでしっかりと身につけておきましょう。 社風としてミスや失敗を許さない さて、ここから先は「仕事で怒られる」理由があなたではなく、周囲や上司にあるケースをご紹介します。まずは周囲にあるケースです。 「ミスや失敗、質の低い仕事などをどのように受け止めるか」という考え方や対応は、その会社の社風にも大きく影響されます。会社や業界などによっては、ミスや失敗、質の低い仕事が絶対に許されない職場もあれば、比較的寛容でそれらを前向きにとらえていく職場もあります。 自分だけが怒られているのではなく、職場の雰囲気として「厳しい」のであれば、怒られないように仕事の質を高める努力をするか、その社風に慣れていくか、職場を変えるか、になります。 「社風」は転職すれば確実に変わる要素の1つです。職場全体が厳しく自分に合わないのであれば、自分はこの先もこうした社風のなかで仕事をしていきたいのか、真剣に考えてみてはいかがでしょうか。 上司の機嫌が悪い 身もふたもない話ですが、単に上司が機嫌が悪かったために、八つ当たりされて怒られるということもあります。上司自身が何かトラブルやストレスを抱えて、いつもイライラしている状態であれば、そのせいで「怒られてばかり」になってしまうこともあるでしょう。 上司を客観的に観察し、もしこれに当てはまるのであれば、他人の感情を変えることはできないので、「上司の機嫌が悪いから、仕方ない」「私が悪いのではない」と諦めるしかありません。 ただ、あまりにも上司の機嫌が不安定な状況が続く場合や、改善が見込めない場合には、異動希望を出すことや転職することを考えたほうがいいかもしれません。 上司の性質に問題がある 機嫌の問題なら、比較的一時的な問題ですみますが、上司の性質に問題があることもあります。そうなると性質はそうそう変わらないので、ちょっとやっかいです。 このような性質には、たとえば・細かい性質で、部下の業務をいちいちチェックして求めるレベルにしないと気が済まない。・自分が思うように進められないと気が済まない。・完璧主義で求めるレベルが高すぎるし、部下の仕事がそれに達しないと許せない。・怒ることが部下を成長させるマネジメントだと思っている。・あなたを怒ることでストレス発散している。 等が考えられます。他にも、モラハラやパワハラのようなケースもあるでしょう。 その性質の問題度が「こういう人だから仕方がない」と割り切れる程度であれば、割り切ってやり過ごすという対処法もありますが、あなたへの攻撃性があまりにも高い場合には心身の健康を害する前に、社内で異動希望をだすか、転職活動を始めたほうがよいでしょう。 本当は上司は怒っていないのに「怒られている」と受け止めている 最後に、上司は怒っているつもりはなく、ただ「改善してほしい」「仕事を通じて成長してほしい」と思って軽く注意したり、厳しく指摘したりしたことを、あなたが「怒られた」と受け止めてしまっている可能性があることも理解しておきましょう。 ただし、これに当てはまるかどうかを自分で判断するのは、今すでに「自分は怒られてばかりいる」と受け止めてしまっている感情がある以上、「上司はそんなつもりではないのだろう」とその可能性を考えるのはなかなか難しいものです。 しかし、受け止め方を変えることができれば、今後「怒られてばかりいる」と辛くなることを減らすことができます。 もし可能であれば、信頼できる友人や知人、あるいはカウンセラーやキャリアコンサルタントに「こういう状況で、こんな風に言われたのだが…」と話し、第三者としての視点を聞いてみてはいかがでしょうか。「それって、怒られたわけではないのではないか」「上司はこういうつもりだったのではないか」等、自分にはなかった視点に気づくかもしれません。 2.上司の立場になって考えてみる 前述のように「怒られてばかり」と思うと、自分のことで頭がいっぱいになってしまいますが、この状況を上司の立場になって考えてみると、また違う視点で捉えることができます。 あなたが上司だったとして、今のあなたと同じような部下がいたらどのように対応するでしょうか。 ・「もっと仕事を通して成長してほしい」と思って厳しめに注意してしまう。・「何度言っても同じミスをする」ことについイライラしてしまう。・自分の仕事やプライベートでストレスがあってつい仕事がうまくいかない部下にあたってしまう。 などの状況にほんの少し理解ができませんか。上司とはいえ人間で、常に情緒が安定し、完璧なマネジメントができる人ばかりではありません。 「この人はなぜ怒っているのか?」と相手の立場に思いを寄せると、相手の気持ちが理解できたり、それによって自分の気持ちも落ち着いたり、改善点や対応策が見えてきたりすることもあります。 自分を怒ってばかりの相手のことを考えるのは、嫌な気持ちになるかもしれませんが、上司の立場になって状況を想像してみると、それをきっかけに今のこともより客観的に落ち着いて受け止められるようになるかもしれません。 3. 怒られて嫌になった時の対処法を知っておく 最後に、怒られてばかりで辛い状況を変えるための対処法もご紹介しましょう。怒れられてばかりでどうしていいかわからないと辛いですが、自分に合った対処法がわかれば、行動を起こし、「今」を変えていくことができます。 何も行動を起こさなければ、状況は変わりません。怒られる内容や、今の気持ちに合わせて、自分に合うものを試してみませんか。 身近な誰かに話す もし友人や知人、家族などで話を聞いてくれる人がいるならば、今の状況を聞いてもらいましょう。「愚痴をこぼす」というとネガティブに聞こえるかもしれませんが、愚痴をこぼすことでストレスを発散できますし、自分の気持ちの整理もできます。 話をしているうちに落ち着いて、「自分もこうすればよかったのかも」と気づきがあるかもしれません。 成長する機会だと捉えて、業務や仕事の進め方を改善する パワハラ体質やモラハラ体質だったり、感情的すぎたりと、上司の体質に何らかの問題があるケースを除けば、「怒られる理由」の一因は多かれ少なかれ自分にあります。でも理由が自分にあるのは、決して悪いことではありません。それを改善すれば、自分の仕事の質を高め、成長することができるからです。 もし自分に原因があるならば、たとえ転職して「働く場所」を変えても、その行動を改善しないかぎり、転職先でも「怒られる」可能性は大いにあります。 怒られる理由を冷静に振り返り、自分に改善できることを試してみることで、「今」を成長の機会にすることができるでしょう。 異動や転職に向けてアクションする 「怒られる理由」を客観的に考えてみたときに、モラハラやパワハラなど上司に問題があり、その被害が大きいケースや、精神的にすでに追い詰められてしまっているようなケースでは、「場を変える」ことが一番の対処法になります。 社内に異動希望を申請する制度があれば活用し、もしそのような制度がなければ人事部に相談するなどして、異動できる可能性を探ってみましょう。 もし社内での異動が難しい状況であれば、転職活動を始めましょう。「上司に怒られたくらいで」と気が引ける思いもあるかもしれませんが、「怒られてばかり」の原因が上司にあるならば、ストレスで心身の健康に影響が出てしまったり、怒られてばかりで自己評価が低くなりすぎたりしてしまう前にその場を離れることを決断することも大切です。 「上司との人間関係」は、本音の転職理由で常に上位にランクインしており、多くの人が上司とうまくいかないことをきっかけに転職活動を始めています。自分の行動を改善することも大事ですが、自分の行動を変えただけでは変わらない状況については、見切りをつける勇気を持ちましょう。 キャリアコンサルタントに相談する ここまでに、一般的な「怒られる理由」や、怒られてばかりの時の対処法を紹介してきましたが、自分がどれに当てはまるのか、なかなか客観的に状況を捉えたり、気持ちを整理することが難しいこともあるかと思います。 また、誰かに話を聞いてほしいけれど、適切な人が思い浮かばないという方もいらっしゃるでしょう。 そんな時はぜひ、私たちキャリアコンサルタントにご相談ください。キャリアコンサルタントは、現状を客観的に把握し、これからの仕事への向き合い方や考え方を整理するサポートをするプロフェッショナルです。お話を丁寧にお伺いしながら、「怒られてばかり」になってしまう可能性を客観的にアドバイスし、今の仕事や会社に対する気持ちを整理しながら、現状改善するのがよいのか、転職するのがよいのか、あなたが納得感を持って選択できるよう、サポートしていきます。 いずれにしても、「怒られてばかり」の状況は、精神的にも仕事の進め方としてもあまりよい状態ではありません。この状況を少しでも早く改善できるように、行動を起こしてみましょう。

仕事を辞めたいほど人間関係が辛い状況を改善する6つの方法
仕事を辞める本音の退職理由で上位を占めるのが、「人間関係」です。実際に辞める方も多いのですから、辞める手前で職場の人間関係に多かれ少なかれ悩むことは、誰でも一度は経験するといっても過言ではないでしょう。 人間関係の悩みがなんとかやり過ごせるうちはいいのですが、本当に仕事を辞めたくなるほど辛くなってしまったときにはどうすればいいのか。このまま仕事を辞めてもいいのか。ここでは、キャリアコンサルタントの視点から、そんな状況を改善するためのおすすめの方法についてご紹介します。 人間関係が辛い!よくある4つのケース 人間関係が辛い状況を改善するには、まずは自分の状況を客観的に捉える視点を持つことが大切です。そうすることで、「辛い」「もう嫌だ」という感情から少し距離を置くことができ、「今どんな状況なのか?」「なぜ嫌だと思ってしまうのか?」「改善する方法はないのか?」と冷静に考えられるようになるからです。 その第一歩として、今辛いと思っている人間関係は、どのような状況なのか、客観的に整理してみましょう。 1.上司と合わない 職場の人間関係のストレスで最も多いのが、直属の上司との人間関係です。2019年に「月刊 人事のミカタ」(株式会社エン・ジャパン)が行った調査によると、「上司と合わない」は本音の転職理由の第2位となっています。一言に「上司と合わない」と言っても、いろんなケースがあり、 ・部下に対して業務の指示が適切ではない。指導をしない。・仕事に対するスタンスや考え方が合わない・マイクロマネジメントで指示や監視が細かすぎる。・部下ばかりに仕事をさせておいて、自分は仕事をしない。・やる気がない。・部下を褒めない。評価しない。・気分屋でその日、その時によって判断や行動が異なるので振り回される。・生理的に合わない(言動に腹が立つ)。・やたらと厳しい。 などの状況が考えられます。完璧な上司はそうそういませんが、自分にとって「これはちょっと許せない」と思うような言動が上司にあると、「この上司とは合わない」という感情はどんどん育ってしまいます。もしかしたら、あなたが合わないと思っている上司の言動を、気にしない他の同僚は、その上司とうまくやれているということもあるでしょう。 この場合、上司のどんな言動について「合わない」「許せない」と思うかによって対処法は異なってきますが、それを考えるためにも上司の何が合わないのか?を分析してみましょう。 冷静に考えてみると「どうしてもいや」「ホント、合わない」と思う点は1つか2つと少なく、ただそれに対する拒絶反応が非常に大きくなってしまっているということもあるかもしれません。「どうしてもいや」と思うことが1つか2つならば、対処法も見つかりやすくなりますので、ぜひ客観的に整理してみましょう。 2.上司がパワハラ、モラハラ、セクハラをする ただ単に合わないのではなく、上司がパワハラ、モラハラ、セクハラを行う、もしくはそれに近いことを行うというケースもあります。「上司と合わない」ケースとの違いは、その言動にハラスメント(嫌がらせ、いじめ)の要素があるかどうかです。 「上司と合わない」ケースは、自分の考え方を変えたり、行動を変えたりすることで、状況が改善する可能性もありますが、パワハラ、モラハラ、セクハラの場合は自分の言動を変えることで状況が改善することは極めて難しいといえます。 上司本人がハラスメントを行っている自覚がないことも多いので、もしこの状況に当てはまるのではないかと思ったときには、人事部に相談しましょう。社内の人事部に相談するのが気が引ける場合には、公の無料相談窓口を利用してみてください。 【ハラスメントに関する無料相談窓口】・労働基準監督署の総合労働相談コーナー労働基準監督署にあり、パワハラのほか嫌がらせ、いじめ、解雇、雇い止めなど様々な労働問題を相談できます。電話でも相談できます。 ・労働相談センター全国労働組合総連合が運営する相談窓口で、パワハラをはじめとする労働者への不当な要求や嫌がらせ行為の悩みを相談できます。 ・みんなの人権110番法務省が運営する窓口で、パワハラや差別、虐待など様々な人権問題を相談できます。 3.職場の同僚と合わない ・仕事にガツガツしている人ばかり。・ノリが合わない。・仕事にやる気がない など、上司ではなく、職場の同僚と合わないこともあるでしょう。職場で友達を作る必要は全くないとはいえ、毎日顔を合わせる職場に気が合う人がいなければ、仕事のモチベーションに影響するのも無理はありません。 実際に前述の「月刊 人事のミカタ」のアンケート調査でも、「職場の人間関係が合わない」は、「上司と合わない」と並んで本音の転職理由の2位にランクインしています。 特定の誰かと合わないのであれば、その人が異動するのを待つ、もしくは自分が異動希望を出すなどの対処法が考えられますが、「職場の雰囲気(社風)が全体的に合わない」となると、転職を考えたほうがよいかもしれません。 4.部下や後輩と合わない 自分が指導する相手である、部下や後輩と合わないというのも気が重い問題です。この場合、部下の仕事に問題がある場合には、自分はそれをマネジメントしていかなければならないというのもストレスになるでしょう。 まずはその部下の何が合わないのか、それがなぜ嫌なのか感情を整理し、仕事だと割り切って付き合う方法を模索してみてはいかがでしょうか。 人間関係が辛い状況を改善する6つの方法 今の人間関係がどのような状況なのか、整理できるころには、状況を客観的に捉えられるようになっていると思います。その冷静で客観的な視点で、この状況を改善するにはどうすればいいのかを考えてみましょう。 ここでは一般的に、職場の辛い人間関係を改善する6つの方法をご紹介します。今のあなたの状況や心境から、試してみたいと思う方法があったらぜひ試してみてください。 1.考え方、見方を変えてみる アドラー心理学を紹介し、世界累計485万部の大ベストセラーとなった「嫌われる勇気」(岸見一郎著 ダイヤモンド社)では、「全ての悩みは対人関係の悩みである」といっています。そして、その上で認知論を紹介し、 人は主観的な意味付けの世界で生きている、つまりその人特有のメガネで世の中を眺めており、全て個人の解釈が介在しているので、あなたのかけているメガネ=解釈の癖は、自分で今すぐに変えられる と説いています。 このように、目の前にある人間関係の悩みやストレスも自分の考え方や見方を変えれば、状況は異なってきます。自分が「いつもこうだ」「絶対そうだ」と思いこんでいるものほど、「本当にそうなのか?」と一度視点を変えて冷静になってみると、違うこともよくあります。 人間関係が辛くなったら、この状況は本当に自分が思い込んでいるような状況なのだろうか?と自分の見方を変えてみると違うものが見えてくる可能性もあります。「どうやって変えたらいいのか、わからない」という場合は、「嫌われる勇気」を読んでみるのもおすすめです。 https://www.amazon.co.jp/%E5%AB%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%8B%87%E6%B0%97-%E5%B2%B8%E8%A6%8B-%E4%B8%80%E9%83%8E-ebook/dp/B00H7RACY8 2.自分の言動を振り返り、行動を改めてみる 心理学でいう「鏡の法則」をご存じでしょうか。「相手の態度や反応は、自分の態度や気持ちを映し出したものである」というもので、人間関係で最も重要なのはこの「鏡の法則」といわれています。 ハラスメントなど、相手の性質に一方的に問題があることもありますが、多くの場合、人間関係は多かれ少なかれ、双方に何かしらの原因があることがほとんどです。今辛い人間関係は、自分にも何かしらの原因があり、自分の言動を振り返り、行動を改めてみることで、仕事を辞めたいほど辛い人間関係も、改善する可能性が大いにあります。 今、人間関係が辛いと感じる相手に対し、あなたはいつも誠実に接していたでしょうか。相手の業務上の要求に、きちんと応えていたでしょうか。人間関係が辛いと感じる相手が上司であるならば、適切な報連相ができていたでしょうか。気持ちよい挨拶はできていたでしょうか。相手にとってあなたは「感じのいい人」であったでしょうか。 もし自分の行動に少しでも改善できることがあると気づいたならば、ぜひ今日からでも、できることからでも、行動を改めてみましょう。他人の行動を変えることは難しいですが、自分の行動は意識次第で今からでも変えることができます。人間関係では、自分の行動が変われば「鏡の法則」に従って相手の行動も徐々に変わっていくことがほとんどです。 会社員として働く以上、職場の人間関係の問題はどこに転職してもずっとついて回ります。どうしてもうまくいかないときはその場を離れることも大事ですが、人間関係がうまくいかないと感じる度に転職するわけにはいきません。ここで人間関係を改善できる能力を身につけておくと、この後ずっと役に立ちます。今を自分の成長の機会と捉えて、自分を客観的に見つめ、行動を変えてみましょう。 3.身近な人に相談してみる 人間関係のストレスを聞いてくれる友人や先輩、同僚、家族がいるならば、身近な人に相談するのも有効な方法です。 ストレスは、話を聞いてもらうだけでもすっきりするものですし、話を聞いてもらっているうちに自分の状況や気持ちを客観的に捉えられるようになることもあります。また、話を聞いてくれた相手から、「考え方や見方を変える」ような一言があるかもしれません。 人間関係のストレスは、一人で抱え込まず、上手に発散していくことが大切です。身近な方をぜひ頼ってください。 4.キャリアコンサルタントなどプロに相談する もし身近で話せる人がいない場合には、キャリアコンサルタントなどプロに相談するという選択肢もぜひ知っておいてください。 キャリアコンサルタントは、キャリアプランを立てるためだけではなく、仕事や職場に関する悩みの解消にも活用することができます。現状を改善するために、状況や気持ちを整理して、どうすればよいかを考えるサポートをしていますので、「どうしていいか、自分だけではよくわからない」という方はぜひお気軽にご相談ください。 5.人事部に異動希望を出してみる 上司や同僚との人間関係に問題があっても、会社や待遇には特に不満がない場合には、社内で異動の可能性を探ってみましょう。 異動希望を申告する制度があればぜひ活用し、ない場合には人事部に相談してみてください。 パワハラなど、傍からも明らかに問題があるとわかるような場合には、人間関係を理由に異動を希望しても大丈夫ですが、そうでない場合には人間関係を理由にしてしまうと、異動希望はなかなか叶いません。 異動希望を出す場合には、「今の部署以外のどこか」ではなく、「社内のこの部署で、こういう経験を積んでキャリアを広げたい。なぜなら~と考えていて、今までの××の経験も活かせるから」など、具体的で前向きなキャリアプランを伝えれば、希望も実現しやすくなります。 異動希望を実現させるためにも、異動先でのキャリアプランについてしっかりと準備をしておきましょう。もしキャリアプランが思い付かない場合には、ぜひキャリアコンサルティングサービスを活用してください。今の状況をお伺いしながら、社内でのキャリアの可能性について、選択肢を整理するサポートをいたします。 6.転職を考える ここまで退職せずに、社内に残って状況を改善する方法を紹介してきました。しかし、人間関係が原因で辞める人が多いのですから、「転職する」というのも人間関係が辛い状況を改善する有効な方法です。 会社員として仕事をする以上、職場の人間関係の問題は、一生ついてまわりますから、次の転職先で人間関係に恵まれるという保証はありませんし、人間関係に問題がある度に転職するわけにもいきませんが、少なくとも目の前の状況は変えることができます。 上司を選ぶことはできませんが、中途採用の面接では直属の上司となる予定の配属先部署の管理職が面接官になることもよくあるので、面接の場で「この会社や次の上司は、合うか合わないか」を肌感覚で判断することもできるでしょう。 「合わない」と思った人間関係を、うまく処理する能力を身につけることが重要なのと同じくらい、限界になってすっかり消耗してしまい、ストレスで心身の不調をきたす前に、その場から離れる勇気を持つことも、また重要です。 「どうにも無理だ」と思ったときには、ぜひ転職活動を始めましょう。 ただ、中途採用の面接では、転職理由に「人間関係が理由で」ということ正直に伝えてしまうのは得策ではありません。状況を知らない相手からみたら、「この人にも何かコミュニケーション上の問題があるのではないか」「転職しても、人間関係がうまくいかなくなったら、また辞めてしまうのではないか」と思われてしまうからです。 異動希望を出す場合と同様に、転職活動でも前向きなキャリアプランを元にした転職理由をまとめるようにしましょう。 自分に合う人ばかりの夢のような職場は、そうそう出会えるものではありません。職場の人間関係に100%満足している方は、よほど運がいいか、今の自分の状況を「満足」と捉えるモノの見方ができているのかどちらかでしょう。職場の人間関係に対するちょっとしたストレスは、誰でも多かれ少なかれ持っているものです。 しかしそれが「仕事を辞めたい」と思うほど辛くなってしまったならば、心身の健康に支障をきたしてしまう前に、その心のSOSをきちんと受け止め、現状を変えるためのアクションをぜひ勇気をもって起こしてください。

楽しくない仕事を辞めたい…辞めるか現状維持か迷ったら
「仕事が楽しくない…」というと、「仕事は楽しくなくて当たり前」なんて返しをされることもあるかもしれませんが、仕事はつまらないよりは面白いに越したことはありません。 ただ、仕事が楽しくなくても気にならない生き方があったり、状況は変わらなくても考え方を変えたり…と辞める前にもできることはいろいろあります。辞めることはいつでもできます。仕事が楽しくない状況をなんとかしたいと思ったら、こう考えてみませんか。 仕事が楽しくない理由を分析する 「仕事が楽しくない」と一言にいっても、「楽しくない」理由はいろいろあります。仕事が楽しくない現状を改善するには、自分がなぜ仕事を楽しくないと思っているのか、気持ちを整理することが大切です。楽しくない理由がわかれば、対処法も見えてくるからです。 「仕事が楽しくない」と感じるには、一般的に以下のような原因が考えられます。今の自分はどれに当てはまるのか、自分の気持ちを客観的に見つめてみましょう。 1. 人間関係がストレスになっている 仕事が楽しくない、つまらないと感じる理由の1つが人間関係です。なかでも、大きく影響するのが、仕事の指示を出し、自分の仕事の評価者でもある上司との人間関係でしょう。 「上司との人間関係が良好で何の問題もない」「上司は尊敬できる相手」と思えるのは、よほど運が良い方で、多くの会社員は多かれ少なかれ上司には何らかのストレスを抱えています。パワハラやモラハラとまではいかなくても、上司に対してストレスを感じてしまう要素はいくらでもあるからです。 たとえば、上司が次のようなタイプだったら、一緒に働く部下はちょっと大変ではないでしょうか。 ・自分のことしか考えていない。・「自分の意見や経験が絶対」というタイプで部下の意見を全く聞かない。・部下を理解・評価しようとしない。・部下の業績を自分のものにしてしまう。・部下をえこひいきする。・経営層にばかりいい顔をして、部下への態度が横柄。・マイクロマネジメントで細かく関与してくる。・部下にあまり関心がない。・仕事が全然できない。あるいは仕事をしない。 上司とはいえ人間ですから、多少の欠点は誰でもあるものですが、それでも許容範囲を超えてしまうと仕事へのモチベーションに大きくしてしまうでしょう。 2. 職場に「いいな」と思える人がいない 「人間関係がストレス」というほど、トラブルはないけれど、尊敬できる上司や先輩もいない。一緒に仕事をしていて刺激し合ったり、気が合うような同僚もいない。 そんな「可もなく不可もなく」の状況は、トラブルを抱えている状況と比べれば恵まれてはいますが、どこか物足りなさを感じてしまうのも無理はありません。 すぐに退職を決意するほど切羽詰まっていないからこそ、何か物足りない、不完全燃焼のような状況がズルズルと続いてしまう可能性もあります。 3. 仕事が簡単・単調すぎて成長を感じない 仕事が簡単すぎる、毎日同じことの繰り返しで変化がなく、単調で刺激がないという方もいらっしゃるでしょう。 「同じ給与なら、簡単で単調な方が楽でいい」という考え方もありますが、仕事に変化や成長を求めるタイプの方がこのような仕事についてしまうと、物足りなくなってしまうのも無理はありません。 4. 仕事にやりがいを感じられない 事業は、誰かがその商品やサービスに対価を支払うことで成り立っています。対価を支払うということはそれだけ必要とされていることであり、仕事はそうした事業に関連して発生しているので、あなたの仕事は必ずどこかで誰かに必要とされ、役に立っているはずです。 しかし、「誰のための仕事なのか?」という相手が見えにくかったり、無駄な業務が多かったり、成果がなかなか感じられなかったり、上司の納得できない指示に仕方なく従わなければならない仕事だったりすると、「この仕事は何のために、誰のためにやっているのだろう?」とやりがいを感じられなくなってしまいます。 仕事の意義や価値を見失ってしまうと、仕事もつまらないと感じてしまうようになってしまうでしょう。 5. 仕事内容が合わない 仕事内容が、自分の適性に合っていない方もなかにはいらっしゃるでしょう。 たとえば、人と話すことが好きなのに、事務作業ばかりで誰とも会話することがなく1日が終わってしまったり、数字が苦手なのにデータ集計の業務が多かったり、人と話すのが苦手なのに営業職だったり…。あるいは、自分の適性が何かはわからないけれど、「なんとなく今の仕事内容はどこかつまらない」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。 自分が「好きなこと」と「できること」と、会社が「あなたに任せたいこと」が、できる限り一致していると仕事は楽しくなりますが、その重なりが小さくなればなるほど、仕事に楽しさを見出すのは難しくなってしまうでしょう。 6. 評価や報酬が見合わない 「仕事が楽しくない」という感情のなかには、「こんなに頑張っているのに、評価や報酬が満足できないから、面白くない」という種類の感情もあります。 その原因としては、 ・上司が部下のことをちゃんと見ていなかった。・上司(会社)が評価するポイントと、あなたが力を入れていたポイントが異なっていた。・上司がえこひいきするタイプで不当に低い評価をされてしまっている。 などが考えられます。 報酬が見合わないのは、上司による査定評価が影響する賞与が低いのが納得できない場合と、そもそも会社の報酬体系全体の年収が低い場合と2つのパターンがあります。前者は自分か上司かどちらかが異動すれば、解決できる可能性がありますが、後者は会社全体の問題なので、転職しない限り改善するのは難しいといえます。 辞めるか現状維持か?仕事が楽しくないときの対処法 さて、今自分が「仕事が楽しくない」と思っているのは何が理由なのか、なんとなく見えてきましたでしょうか。 仕事が楽しくない理由がわかったら、これから紹介する改善する対処法に目を通し、「やってみようかな」と思えるものがあったら、ぜひ試してみてください。試してみるときには、「試しにやってみようかな」くらいの軽い気持ちでトライし、自分には合わなそうだったり、無理そうだったりしたら、すぐにやめて他の方法を試してみましょう。 楽しくない仕事は辞めたくなるでしょうし、「仕事が面白くないなら、辞めればいい」という誘惑もあると思います。 しかし、仕事を辞めて「この仕事なら楽しいはず」と思って転職した仕事が、入社してみたら実は楽しくなかった、ということは十分にあります。また、転職して最初はよかったけど、いつの間にかまた「仕事が楽しくない」状況に直面することも考えられます。 仕事はつまらないよりも楽しいに越したことはありませんが、この先何十年も働き続ける人生で、環境要因に恵まれ続けて「楽しい仕事を続けられる」ことはまずありえません。だからこそ、ここで ・どんな仕事や環境でも、楽しさを見いだせる力・仕事が楽しくなくても特に気にならない力・自分の環境を「仕事が楽しい状況」にできる力のいずれか1つを身につけておくと、この後の人生で非常に役に立ちます。辞めるのはいつでもできます。まずは現状維持をしながら、自分が今ここで身につけられるのはどの「力」か、模索してみるのはいかがでしょうか。 1. 自分の考え方や捉え方を変えてみる 自分の考え方や捉え方を変えることができると、「どんな仕事や環境でも楽しさを見いだせる力」が身についてきます。 たとえば、嫌な上司も「むかつく」ではなく、「上司もいろいろあるんだな」と思えれば見方も変わります。仕事ができない上司も「なんでこんなに仕事ができないのに、自分よりも給与をもらっているんだ」と思うと、不条理を感じずにはいられませんが、「そんな人にムカついていても、何の特にもならない」と自分の関心の外にその上司を追いやることができれば、心が乱されることも少なくなります。 大ベストセラーになった「嫌われる勇気」(岸見一郎著 ダイヤモンド社)でも、 人は主観的な意味付けの世界で生きている。つまりその人特有のメガネで世の中を眺めており、全て個人の解釈が介在しているから、あなたのかけているメガネ=解釈は、自分で今すぐに変えられる。 と紹介されています。自分の解釈、つまり考え方や捉え方を変えるだけでも、状況を変えることはできるのです。 ただ、今まで自分の一部であった考え方や捉え方を変えるには、何かの「きっかけ」が必要なこともあります。そのためにも誰かと話してみたり、本を読んでみたり、何か新しい情報に触れるきっかけをつくっていくとよいでしょう。 2. 同僚や先輩に相談する もし、相談できる同僚や先輩がいれば、楽しくない今の状況について話をしてみるのもおすすめです。 「誰かに話す」ことで自分の気持ちを整理できますし、声に出して話すことで「ああ、自分はこう考えていたんだ」と気づくこともあります。ただ話を聞いてもらうだけでも考えや気持ちがすっきりするでしょう。 また、もしかしたら同僚や先輩のアドバイスや視点が、今の状況に対する考え方や捉え方を変える「きっかけ」になるかもしれません。あるいは、あなたが知らない社内の情報を教えてくれて、それが状況そのものを改善する突破口になる可能性もあります。 時には思い切って周囲の人に頼ってみましょう。 3. プライベートで楽しめることを始める 仕事は楽しいに越したことはないですが、仕事に「楽しさ」を求めない生き方もあります。「仕事は生活費を得る手段」と割り切って、プライベートを充実させていくと、仕事が楽しくないことも気にならなくなります。つまり、「仕事が楽しくなくても特に気にならない力」が身に付くのです。 趣味の時間を充実させたり、初めてみたかった習い事を始めたり、ジムやヨガ、ジョギングやウォーキングなど運動を始めたり、料理に凝ったりするのもいいでしょう。 プライベートの時間を充実させることで、自分の世界も広がりますし、仕事以外で気の合う友人を見つけたり、将来退職してからも続けられるような趣味や仕事につながったりと、得るものは意外に多くあります。 もし今、仕事や職場が楽しくなくても、待遇には不満がなく、特にこれといってやりたいことや目指したいキャリアも思い付かないのであれば、現状維持のまま仕事以外で楽しいものを見つけるというのは、現実的に考えて最もリスクが少なく、得られるものが多いおすすめの方法です。 4. 副業やプロボノ活動をしてみる 最近は副業OKの会社も増えています。もし今の会社が副業OKならば、仕事以外の時間で副業を始めるのもよいでしょう。 「副業に生かせるようなスキルや資格もないし…」という方は、趣味や自分の興味のある分野でブログを書いて広告収入を得ることを目指したり、あるいはNGOやNPOでボランティアやプロボノ活動をしてみるのもおすすめです。 副業にしてもプロボノにしても、本業以外のこうした活動をすることで、自分の世界が広がります。「会社の仕事」だけがメインの生活をしていると、それがつまらないのが気になってしまいますが、他に自分が何か打ち込むフィールドがあれば、自分の世界は「会社の仕事」だけではなくなります。 他に興味関心があり、自分が活躍できるフィールドがあれば、「会社の仕事」がつまらないのは大きな問題ではなくなってくるはずです。 5. 配置換えや担当替えを上司に相談する もし、上司との人間関係には問題なく、かつ上司が部下思いであれば、部署内での配置換えや担当替えを相談し、現状を改善できないか試みるという方法もあります。これが「自分の環境を『仕事が楽しい状況』にできる力」です。 ただこれが実現するには、 ・上司の物分かりがよく、部下のキャリア形成を真剣に考えている。・配置換えや担当替えが適切な対応である、前向きな理由を訴える。(つまらないからとかではなく、「自分はこちらの方が得意」「こういうことにチャレンジしてみたい」などあくまで前向きな理由で相談することが重要です)・配置や担当を替える余地がある。 という3つの条件が満たされている必要があるので、難易度は高いのですが、ものは試し。一度相談しておくと、今は配置や担当替えの余地がなくても、そのような機会ができたときに考慮してもらえる可能性につながりますので、相談できそうな上司であれば、試してみてはいかがでしょうか。 6. 異動希望を出す もし社内に異動希望を申請する制度があるならば、異動願いを出す。そうした行動を起こすのも「自分の環境を『仕事が楽しい状況』にできる力」です。 異動希望を申請する制度がないならば、人事や異動希望先の部署の課長や部長に直接訴えるという手段もあります。 かなりの勇気も必要だと思いますが、「なぜその部署に異動したいのか?」「自分はその部署で、今までの経験を活かしてどんな貢献ができるのか?」を前向きに、具体的に訴えることができれば、異動の実現可能性は高くなるでしょう。 7. 転職活動をする 最後の対処法が「転職活動をする」です。他の対処法を試してみたけど、なんとなく状況は変わらないと思ったら、実際に転職活動を始めてみましょう。本当に転職するかどうかは、活動を始める時点では決めていなくても構いません。 実際に転職サイトに登録し、転職エージェントに相談して、具体的な求人を探し、面接に行き…と転職活動をしていると、他社の情報と比較して、今の環境や自社を客観的に捉えることができます。 その時に「やっぱり今の環境は無理だな」と思えれば、そのまま転職活動を続けて転職すればいいですし、「改めてみると、実は悪くないかも」と思えれば現状維持でもまた新たな気持ちで仕事に向かうことができます。 転職活動も視野を広げる機会の1つです。実際に転職するかどうかはさておいても、ここで転職活動をして視野を広げることは決して無駄にはならないでしょう。 答えが見つからない時はキャリアコンサルタントに相談を 「仕事が楽しくない」という状況を変えるには、その状況に対する自分の考え方や捉え方を変えるか、環境そのものを変えるかどちらかです。しかし、自分がどうしたいのか、自分の気持ちがわからない、あるいは相談できるような同僚や先輩、上司がいないということもあるでしょう。 そんな答えが見つからない時には、ぜひキャリアコンサルタントを活用してみませんか。お話を丁寧にお伺いしながら、「本当は何がネックになっているのか?」「自分にとってはどうするのがいいのか?」を見つけるサポートをさせていただきます。

仕事を辞めたい!ストレス限界なのに、辞める決心がつかない方へ
どんな職場でも、どんな仕事でも、多少のストレスはあるものですが、ストレスが溜まっていくと次第に仕事を辞めたいという考えが大きくなっていきます。しかし本当に辞めたいし、ストレスも限界なのに、いざ辞めて転職するとなるとなかなか踏ん切りがつかない、辞める決心がつかないという方も多いのではないでしょうか。 仕事を辞めたい。でも「辞める」という決断がなかなかできない。そんなストレスフルな状況のときにはどうすればいいのか、キャリアコンサルタントの視点からまとめました。 見逃していませんか?ストレス限界のサイン ストレスが限界になると、心身ともに今までとは違う様々なサインが現れます。特に、次のような症状がある場合、うつの初期症状の可能性もありますので、転職よりもまずは休息を取り、心身の健康を回復することが先決となります。 ☑よく眠れない(なかなか寝付けない、早朝に目が覚めてしまう)☑食欲不振になる、または過食になる☑アルコールの量が増えた☑体重が大幅に増えた、または減った☑頭痛や吐き気がする☑疲れがとれない☑何をするにもやる気がおきない☑最近感情の起伏がなくなったと思う これらのうち、当てはまる項目が少ない場合、多くの項目に当てはまっても「どちらかと言えばそう思う」と症状が軽い場合は、まずは心身の健康を整えるためにストレス解消のために適度な運動を生活に取り入れたり、食生活を見直したりしてみましょう。キャリアのことを考えるのは、それからでも遅くはありません。 厚生労働省が発表した「健康づくりのための身体活動基準2013」では、身体活動や運動が生活習慣病の罹患率や死亡率を低下させるとともに、気分転換やストレス解消につながり、メンタルヘルスの改善にも効果があるとしています。 軽い運動でも、ストレスを解消させるホルモンのセロトニンやエンドルフィンが分泌されますので、ウォーキングやストレッチなど手軽に始められそうなものから始めてみてはいかがでしょうか。 当てはまる項目が多い場合、もしくは当てはまる項目が少なくてもその症状がひどい場合には、有給休暇をとって休むことから考えてみましょう。また、症状が気になる場合は、心療内科などを受診することも検討しましょう。 有給休暇では回復しないような場合、もしくは有給休暇が取りにくくこのままでは休息をとることが難しい場合には、会社を辞めてゆっくり休み、リフレッシュすることも選択肢として考えてみてください。 辞めたいほど溜まってしまったストレスの原因は? ストレスは溜まっているけれども、まだ心身に影響が出るほどではないという方は、心身に影響が出る前に今の状況を改善することが望ましいといえます。 そのためにも今の状況を客観的に見直し「仕事を辞めたい」と思うほどに溜まってしまったストレスの原因はどこにあったのか、考えてみましょう。ストレスの原因によっては、転職をした方がいいケースもありますし、転職がベストな選択ではないケースもあります。どちらに当てはまるのか、確認してみましょう。 仕事の量が多く、残業が多い 繁忙期だけ忙しいのではなく、常に仕事の量が多く、慢性的に残業している…そのような状況が続くと、心身ともに疲れもストレスも溜まってしまいます。 問題が「仕事の量の多さ」だけであり、仕事内容や職場の人間関係などにはそれほど問題がないのであれば、思い切って上司に仕事の量が多いことを伝え、業務量を調整できないか、あるいは職場の人員を増やしてもらえないか確認してみましょう。 あなたが仕事の量に対してストレスを抱えていることを、上司が認識していないこともよくあります。状況が改善されないと、仕事を長く続けることは難しいと思っていることも伝えれば、真剣に受け止めてくれるはずです。たとえすぐにではなかったとしても、事態を改善する方向に向かっていくでしょう。 もしそのように訴えても真剣に受け止めず、対策を取らないような上司や職場、あるいはそもそもそのような訴えもできないような職場ならば、心身の健康を壊す前に転職したほうがよいかもしれません。 また、仕事の量が多いだけでなく他にも問題があったり、恒常的に仕事の量が多いことを問題視しないような社風(定時に仕事を終えることをよしとしないような社風)だったりする場合は、このまま会社に残っても状況が良くなる可能性は低いと言えます。この場合もやはり、早めに転職を真剣に考えたほうがよいでしょう。 給与が低い 給与に対する不満があっても、仕事内容や職場の人間関係に大きな不満がなければ、「まあ、なんとかなるし…」と最初は受け止めることができるでしょう。 しかしいつまでも低いままだと、将来への備えに対する不安も生まれてきます。また、異動などで仕事内容や職場が変わり、仕事内容や職場の人間関係への不満を持つような環境に変わると、「このストレスにこの給与じゃ、やってられない」と思うようになることもあるかもしれません。 給与が低いことに対してずっと不満だったのか、それとも社内での環境が変わって給与に対する考え方も変わったのか、いずれにしても、給与体系は組織として決まっているので個人で働きかけて改善できるようなものではありません。 厚生労働省の調査によると、転職して年収が上がった人は全体の4割だそうです。転職で確実に年収アップするとはいえませんが、年収アップを実現するのはそう難しくありません。給与への不満がストレスの原因ならば、給与に不満を転職の可能性が広がりやすい20代、30代前半のうちに転職したほうがよいでしょう。 職場の人間関係がうまくいっていない 一般的に、ストレスの原因の第一位が人間関係によるものだといわれています。少し前の調査になりますが、総合人材サービスのマンパワーグループ株式会社が2016年に行った勤務先で感じるストレスについて行った調査では、職場でのストレスを感じている原因の第一位が、男女ともに「上司との人間関係」でした。 「同僚との人間関係」や「部下との人間関係」という回答も多く、職場の人間関係がストレスに大きく影響していることがわかります。 しかし、人間関係は自分が変わることで今の職場の人間関係を改善できる可能性も高く、また転職したとしてもその転職先での人間関係が今よりもよくなるとは限りません。さらに、人間関係はどのような職場でも避けられないことから、ある程度の対処法を身につけていくことも必要です。 もちろんストレスで耐えきれない時には、心身の健康を損ねる前に退職し、転職したほうがいいのですが、その前にできることがないかもう一度考えてみてはいかがでしょうか。 こちらのコラムでは、特に上司のとの人間関係がストレスで辞めたいと思う時の対処法をご紹介しています。よろしければぜひご覧ください。 https://career-lab.biz/column/yametai_201226/ 仕事がうまくいかない、評価されない 仕事がうまくいかない、または自分ではがんばっているのに評価されないのも職場でのストレスの原因となります。仕事がうまくいかないといっても、その原因は状況によって異なり、 ・仕事が合わない。・そもそも仕事が「無茶ぶり」で、前提条件に無理がある。・仕事に必要な情報を周囲が伝えていない。・関係者と必要なコミュニケーションが取れていない。・やり方が間違っている。・ミスが多い。・経験が不足している。 などが考えられます。このうち、「仕事が合わない」のであれば、適性のある業務に異動希望をだすか、転職することを考えたほうがよいかもしれません。 また、仕事の無茶ぶりが常態化していたり、仕事に必要な情報を上司や周囲が伝えない・教えないような環境であり、それを改善するのは難しいようであれば、これも転職を考えたほうが賢明でしょう。 しかし、それ以外の原因であれば今の職場でまだできることがあり、それを試して身につけることが、自分のスキルを磨くことにも繋がります。 「仕事がうまくいかない」からといって転職しても、転職先での仕事がうまくいくとは限りません。むしろ、同じような仕事内容への転職であっても、新しい会社のルールや仕事の進め方を1から覚えることから始まりますので、環境に慣れて成果を出せるようになるまで少し時間も必要です。 なぜ今の仕事がうまくいかないのか、どうすれば状況を改善できるのか、考えがまとまらない場合はぜひ、キャリア・コンサルティング・ラボにご相談ください。キャリアコンサルタントが、現状を整理し、改善策を自分で見つけるためのサポートをさせていただきます。 会社を辞めたいのに迷ってしまう原因は? さて、ストレスの原因別に転職を考えたほうがいいのか、今の職場で状況を改善することを模索したほうがいいのかをご紹介させていただきましたが、転職を検討したほうがいいケースであったり、本当に辞めたいと思っていても、いざ辞めるとなると躊躇してしまう方も多いのではないでしょうか。 仕事は辞めたいけれど、転職にも踏み切れない…そんなときはその「辞めたいのに迷ってしまう原因」を整理してみましょう。 次にやりたいことがわからない 転職活動では、面接で必ず「志望動機」を聞かれます。何がやりたくてこの求人に応募したのか、自分の「やりたいこと」を前向きに語らなけれ[ばなりません。 それは転職活動では避けては通れない道だからこそ、「次にやりたいことがわからない」(面接でどう答えていいかわからない)という理由から、転職に踏み切れない方も多くいらっしゃいます。「自分は本当は何がやりたいのか?」という問いに答えを見つけるのは、実はとても難しいのです。 「やりたいこと」は自分で興味を持てること、これをやってみたいと思う情報に出会わないとなかなか見つからないものなので、その情報を探すためにもまずは転職情報サイトに登録し、自分のキャリアや希望条件に合う具体的な求人を検索してみてはいかがでしょうか。1つ1つの求人やその企業情報を見ながら、興味を持てる求人があればその内容を調べ、それを自分の「やりたいこと」としてまとめてみましょう。 また、転職が前提であれば転職エージェントに登録して相談してみることで、「これをやってみたい」と思える求人に出会える可能性もあります。 さらに、「やりたいこと」ではなく「こういう環境で働きたい」という働く環境を優先して求人検索を行い、その希望にマッチする求人に合う志望動機を後付けで考えていくのもアリです。 「次にやりたいことがわからない」のは、今自分が持っている情報が足りないせいかもしれません。そんなときこそ、行動を起こして情報を取りにいってみましょう。 転職がうまくいくか不安 これといって特別なスキルや業績があるわけではないから、転職がうまくいくか不安という方も多くいらっしゃいます。しかし転職に成功しているのは、優秀な人や業績を上げている人だけではありません。企業も、「優秀な人」ではなく普通に仕事をちゃんと真面目にやってくれる人を求めていることも、とても多いのです。 また、転職先でうまくやれるかどうかという不安もあるかと思いますが、これは事前の情報収集をきちんと行い、転職先を選ぶことでそのリスクを少なくすることはできます。 それでもなかなか不安は消えないかと思いますが、そんな時は転職エージェントをうまく活用しましょう。転職エージェントでは今の経験でどんな選択肢があるか、そしてその企業はどんな企業か、情報を提供してくれます。上手に活用すれば、ネットでは検索しきれない情報収集を効率的に行うことできるでしょう。 ただ、転職エージェントによっては「あなたの気持ちや希望に合う企業」ではなく、「あなたが転職できる企業」を勧めるケースもありますので、その点は賢く距離をとってエージェントと付き合うことが大切です。 ストレスはあるが、手放しがたいものもある 転職への迷いの原因が、転職に対する不安ではなく、「そうはいっても、今の環境を手放すのは惜しい」という方もいらっしゃいます。 ・ストレスは多いけれど、給与や福利厚生などの待遇はよい。・人間関係はよくないが、仕事内容は希望通りでやりがいがある。・仕事内容には不満があるが、職場の人間関係もよく、待遇にも不満はない。・転職はしたいが、求人を検索してみると今の条件よりもよいものが見つからない。 といった具合です。 このような場合は、「自分にとって仕事を続ける上で、本当に一番大事なものは何か?」を落ち着いて考えてみるとよいかもしれません。仕事や働く環境に対する自分の価値観を改めて整理してみることで、今「手放しがたい」と思っているものに対して、実は「それほど重要ではないかも」と執着する気持ちがなくなって転職に前向きになれたり、自分自身で納得して「やっぱり転職しないほうがいい」という結論にたどり着いたりできます。 キャリア・コンサルティング・ラボを活用して、その答えを見つけた方もいらっしゃいます。もし考えがうまくまとまらない場合は、ぜひキャリア・コンサルティング・ラボをご活用ください。 家族に反対される 家族に反対されて転職を踏みとどまる方は多くいらっしゃいます。なかには、転職先から内定がでた段階で家族に話し、猛反対されて泣く泣く内定を断るというケースも。 特に、今の会社が大企業であったり、報酬がよかったりする場合、家族も今ある環境を変えたくないという思いからこの傾向が強くなり、奥様から転職を反対されることを「嫁ブロック」という言葉さえあるほどです。 家族の性格を熟知しているからこそ、理解してもらうことの難しさもわかってしまい、それが転職を躊躇う理由になっているかもしれません。「家族に反対されるから、今の会社でがんばろう」と気持ちが切り替えられるならそれもいいのですが、「本当は辞めたいのに…」と辞めたい気持ちが強いならば、その状態でこの後何十年も今の会社で働くことは心身の健康にとってもあまりよいことではないでしょう。 家族に反対されるのはわかっているけれど、でもどうしても辞めたいならば、きちんとコミュニケーションをとっていくことで、家族の理解を得られる可能性はあります。 こちらのコラムでは、転職したい気持ちを理解してもらうためのコミュニケーションのポイントをまとめていますので、よかったら参考にしてみてください。 https://career-lab.biz/column/%e5%ab%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e2%81%89%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%81%ab%e5%8f%8d%e5%af%be%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a6%bb%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%90%91%e3%81%8d%e5%90%88%e3%81%84/ 辞めたいのになかなか踏ん切りがつかない、その状況は人によって様々な要因があるかと思いますが、「そもそも辞めたい原因は何なのか?」「踏み切れない理由は何なのか?」を冷静に整理することで、自分の本心が本当に求めているものが見えてきます。 ストレスにイライラしたり、モヤモヤしたりするときこそ、落ち着いてその根っこににある原因に目を向けてみましょう。

仕事ができない…将来への不安で落ち込むときの乗り切り方
仕事のミスや上司から叱られることが続いたとき、仕事がよくできる同僚や後輩と比べたときに、「仕事ができない…」「うまくいかない…」と気持ちがふさぎ込んでしまうことは誰にでもあります。しかしそれが何度か続くと、「この先、自分はやっていけるのだろうか」と将来への不安でいっぱいになってしまうことも。 落ち込んだ気持ちのままでは、あなたの良さや強みまで発揮されなくなってしまいます。仕事に対する不安は、このように考えて乗り切ってみませんか。 なぜ仕事ができないのか?その理由を考えてみる まずは、自分は仕事がなぜできないのか、あるいはできないと思ってしまうのか、その理由や今の状況を客観的に捉えてみましょう。その理由がわかれば、対処法や改善策も見えてきます。 以下に、一般的に仕事がうまくいかない原因とその対策法をご紹介します。自分の場合は何が当てはまるのか、考えてみましょう。 段取りを考えるのが苦手 仕事は段取り8割といわれています。仕事での「段取り」とは、仕事がうまく進むように手順や流れを事前に考えておくことで、どんな業務でも必要とされます。 「段取り」とは大まかにいえば ・業務の目的にそって、必要な業務を洗い出す・必要な納期までのスケジュールを立てる ことにつきます。 仕事に取り組む前に必要な業務を洗い出し、納期までのスケジュールを立て、「次に必要な業務は何か?」「業務の漏れや抜けはないか?」「この後の業務に必要な準備は何か?」をチェックし、それを上司に確認しながら進めれば、仕事はスムーズになります。 そのため、段取りが苦手だと、必要なことができていなかったり、業務の漏れや抜けがあったりして、「仕事ができない」という評価になってしまうのです。 この段取りが苦手な理由としては ・必要な業務がわからない・スケジュールが立てられない・必要な業務の抜けや漏れがある ということが多いように見受けられます。 しかし、このような場合はいずれも、上司や先輩社員に必要な業務やスケジュール、業務の抜けや漏れがないかを確認してもらう習慣をつけることで、段取りを考える力が磨かれていきます。 また定型業務などは、チェックリストを作成したり、マニュアル化したりすることでもカバーできるので、段取りを考えることに苦手意識がある場合はぜひ試してみてください。 同じミスを繰り返してしまう 得意な業務だけできればよいのですが、仕事ではそうもいきません。人によっては、「どうしても苦手な業務」も担当することになり、それで何度も同じようなミスを繰り返してしまうということもあります。 この場合は、ミスを繰り返してしまう業務について「なぜミスが発生してしまうのか」「どこでミスが発生してしまうのか」という視点から分析してみましょう。その結果から、 ・そもそもミスが発生しやすい複雑な業務フローであれば、業務フローそのものの見直す。・ミスが発生しやすいポイントをチェック項目にして、毎回チェックできるようにする。 などの対策をとっていきましょう。 何をすればいいのかわからず、指示待ちになってしまう 仕事では、必要な業務を自分で考えて進めていくことが求められます。会社や上司は、言われたことだけでなく、業務改善や新たなことを自分で考え、提案し、取り組んでほしいと期待しているでしょう。 しかし、そのようなことが得意な方ばかりではありません。次のような理由から、なかなか自分から動けない方もいらっしゃいます。 ・「どうするのがいいのか?」を考えるのが苦手。・優柔不断でどうしていいか、自分では決められない。・自分に自信がないので、意見を言えない。・知識不足で次に何をしていいかわからない。・上司や先輩など周囲に対して気を使ってしまい、質問ができない。・仕事にやりがいを感じていないので、「これをやったほうがいい」とか思い付かない。・仕事を増やしたくないから、余計なことをやりたくない。・自分の役割がよくわからない。・臨機応変に対応するのが得意ではない。 いずれにしても、もし「指示待ちな自分を変えたい」という思いがあるならば、自分の仕事のやり方や考え方、周りの状況を整理して、必要なアクションをとることで改善していくことができます。キャリア・コンサルティング・ラボでは、そのような仕事の質を改善するための相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。 また、なかにはそれが自分の性質なので、なかなか根本から変えることが難しいという方もいらっしゃるでしょう。指示通りにきちんとミスなく業務ができるならば、それもとても大事なスキルです。「言われたことはきちんとできる」ことに自信を持ち、できることを増やしていきましょう。 やる気がでない、モチベーションが低い 「やる気がない」「モチベーションが低い」には様々な原因があります。 ・仕事の成果がでない。・上司との人間関係が良くない。上司と合わない。・仕事が向いていない。・仕事の業務量が多く、休みが少ない。・同僚や職場の人とうまくいかない。・クライアントや外注先など、社外関係者とのコミュニケーションが難しい、トラブルが多い。 など、原因によって対処法が変わってきますので、やる気がでないときには、「なぜ自分はそんなにやる気がでないのか」を客観的に分析してみましょう。 やる気がでない仕事でも成果が出せる人は、そう多くありません。しかし、やる気が満タンにならなくても、少なくともマイナスな状態から抜け出せれば、状況は改善していきます。やる気が満タンで、モチベーションが高い状態ではなく、まずはマイナスではないニュートラルな状態を目指し、気持ちのあり方を整えていきましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、キャリアに関する全般の相談を承っていますので、このような「なんとなくやる気がでない」という現状を整理し、仕事に対してどのように向き合っていけばいいかを考えるサポートもしています。 もし、自分だけではなかなか考えがまとまらない場合には、ぜひプロのサポートを活用してみてください。 上司への報連相が苦手、報連相をあまりしない 会社という組織で働いている以上、今のあなたの仕事の評価をするのは、良くも悪くも会社であり上司です。そのため、適切なタイミングで上司に確認や報告をしなければ、仕事の成果が上司や会社が求めているものではないものになってしまいかねません。 「仕事では、報連相(報告・連絡・相談)が大切」といわれる理由はそこにあるのですが、仕事ができない方はこの「報連相」が苦手だったり、「自分が報連相をすればいいと思っているタイミング」と「上司が必要だと思っているタイミング」がズレていたりすることが多くあります。 もし、自分のアウトプットに対し、上司からの修正やネガティブなフィードバックが多い場合は、報連相が適切なタイミングで行われていない可能性が高いです。 上司と一度話し合い、プロセスのどの段階で何を確認するのが望ましいのか、仕事の成果をあげるために必要な報連相のタイミングについて確認してみてはいかがでしょうか。 他責傾向が強すぎる、または自責傾向が強すぎる どんな仕事でもうまくいかなかったり、誰でもミスをしてしまったりすることがあります。その時に、いつも他人や環境のせいにしてしまってはいませんか? または、どんなときも「自分が悪かった」「これは全て私のせい」と自分のせいにしてしまってはいませんか? 仕事がうまくいかないときには、「環境が悪かった」「上司の伝え方がよくなかった」など、自分ではどうにもならないケースと、自分が行動を改善することでうまくケースがあります。 他人や環境のせいにする他責傾向が強すぎると、「自分が行動を改善する必要があったケース」を見逃してしまい、仕事の質を高め、成長するチャンスを失ってしまいます。そして自分のせいにする自責傾向が強すぎると、「何でも私が悪い」と自己肯定感が低くなってしまい、これも仕事の質を高め、成長するチャンスを失うことになります。 仕事がうまくいかない、ミスが発生するときには、それぞれの原因があります。いつも他人や環境のせいにしたり、なんでも「自分が悪かった」と考えるのではなく、「これはなぜ発生してしまったのか?」と冷静に、客観的に状況を捉える視点を持つよう心がけましょう。 うまくいかない原因を適切に理解できるようになると、それが次に発生しないように改善をすることができます。それが「仕事ができない」状況を改善していくことにもつながるでしょう。 つい自分に甘くなってしまい、決めたことができない 中には、段取りを考えたり業務を整理したりすることはできるけれども、ついつい自分に甘くなってしまい、「決めたことがなかなかできない」「締切が守れない」という方もいらっしゃいます。 仕事の出来が悪かったり、ミスがあったりするわけではないけれど、「ついつい…」と自分に甘くなってしまうがゆえに、成果がでない、周囲に迷惑がかかっているタイプです。 「決めたことをきちんとやる」と、意識さえ変われば改善できるのがこのタイプなのですが、つい自分に甘くなってしまう意識を変えるというのはもしかしたら一番難しいかもしれません。 「仕事ができない」と思い込んでしまっている 自己肯定感が低かったり、思考がネガティブになりがちな傾向があったりすると、客観的にみれば仕事ができないわけでは決してないにも関わらず、「自分は仕事ができない」と思い込んでしまっていることもあります。 上司や周囲のちょっとした一言を、その言葉を発した本人が全く意図していない意味で受け止めてしまって落ち込んでしまったり、ものすごく優秀な同僚や後輩と比べて「仕事ができない」と思ってしまったり…といった具合です。 ただ、このケースに当てはまるのかどうなのか、自分では判断するのは極めて難しいです。もし上司が相談できるような相手ならば、「仕事ができない」と思う状況を共有し、どうしたら仕事がうまくいくか相談してみてはいかがでしょうか。あなたが思っているほど、仕事ができないわけではないならば、上司はそのようなフィードバックをするでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボでも、お話を丁寧にお伺いし、仕事がうまくいかない理由がこれまでに挙げた理由のどれに当てはまるのかを分析したうえで、現状を変えるためにそうすればいいのか、アクションプランを立てるサポートをしています。上司にこのような内容を相談するのが難しい場合には、ぜひ活用してみてください。 「仕事ができない不安」を解消する方法 仕事ができない…と思ってしまうと、この先自分はやっていけるのか、仕事や収入に対する不安が尽きなくなってしまうかもしれません。そのように将来に対し、恐怖や緊張、不安を感じて脳内からノルアドレナリンが分泌されると、意欲や集中力が低下するといわれています。 意欲や集中力が低下した状態で仕事に取り組んでも、成果を上げることは難しいですから、不安を感じることでますます「仕事ができない」状態に陥ってしまう、悪循環になってしまいます。 不安の原因である「仕事ができないと思う理由」がわかり、対処法がみえて、行動を起こすことができれば、自分も状況も変わっていきます。 そこで、ここまで紹介させていただいた「仕事ができないと思う理由別の対処法」の他に、どんな状況でも共通する「行動の起こし方」も紹介させていただきます。 苦手なこと、得意なことを整理する 誰にでも苦手なことがあり、得意なこと(好きなこと)があります。まずはそれを整理し、得意なこと(好きなこと、苦にならないこと)に磨きをかけていくようにしましょう。 例えば、「定型業務をミスなくこなすことならスムーズにできる」「接客は好き」など、自分のなかでなにか「これなら…」という業務はありませんか。もし1つでも「これなら…」というものがあれば、そのスキルを高めるにはどうすればいいのか、考えてみましょう。 この苦手なこと、得意なこと(好きなこと、苦にならないこと)は、「他人と比べて、人よりできるかどうか」ではなく、自分のなかで「他の業務より好きで、よくできるかどうか」で整理してください。 「自分には得意なことなんてない」と思う方は、他人と比べてしまっている方が多くいらっしゃいます。しかし、ここで大切なのは「他人よりもうまくできること、評価を得ること」ではなく、「自分はこれができる」「これなら得意」というものを1つでも持って、自分に自信をつけることです。 どんなに小さなことでも1つでも自信が持てることがあれば、それを1つ1つ増やしていくことで、できることが増え、仕事への自信がでて、それが他の業務にもいい影響をもたらしていきます。 この「自分の得意なことを見つけ、それを磨いていくにはどうしたらいいか」を考えることも「キャリアプラン」です。キャリア・コンサルティング・ラボではそれを見つけていくサポートもしていますので、自分の苦手なことはわかっても、得意なことが何かわからない方、得意なことを磨くために何をどうすればいいのかわからない方は、ぜひお気軽にご相談ください。 、 仕事に対する自分の考えを整理する 今は変化が激しく、先が見えにくい「VUCAな時代」といわれています。そのうえ、自分がどう生きたくて、何がしたいのか自分の行き先がわからないと、将来に対する不安はますます大きくなります。「この先、やっていけるのだろうか」という将来への不安は、このように自分自身、仕事に対しての考え方があまりはっきりしていないことにも一因があります。 自分はどんな生き方をしたいのか。そしてそのために、どんな仕事をして、どんな働き方をして、いくらぐらいの収入が必要なのか。自分の人生で大切にしたいものを軸にしながら、どんな生き方、働き方、仕事をしたいのか、考えを整理してみましょう。 こうした「どんな生き方、働き方、仕事をしたいのか」を考えることも、キャリアプランです。キャリアプランというと、「どうやってキャリアアップしていくか?」を考えるものとイメージされがちですが、キャリアプランは「どんな生き方、働き方、仕事をしたいか?」を考えるもの。自分らしく生き、働くのはどういう状態かを考えて、それを実現するための行動計画を立てるのもキャリアプランなのです。 本来の意味でのキャリアプランを考えることで、「将来の不安」は、「自分が目指したい生き方や働き方を実現するために、今何をしたらよいのか」という「行動計画」に変わっていきます。不安になった時こそ、しっかり立ち止まって、仕事に対する考えを整理してみましょう。 健康的な食事と適度な運動、睡眠をとる 最後に、仕事ができない…と気分が落ち込んでしまう時、将来に対する不安がいっぱいな時にとても大切なことを。 そんなときこそ、健康的な食生活を心がけ、適度な運動と睡眠を取ることにまずは意識を集中してみましょう。 いろんな不安で頭がいっぱいになると、「それどころではなくなってしまう」のが食事であり、運動であり、睡眠です。しかし、栄養不足、運動不足、睡眠不足はさらに精神的・肉体的な悪影響をもたらします。もしできるならば、将来が不安なときこそ、目の前の夕食をきちんとバランスよく食べることや、練る前に数分ストレッチをすることに意識を向けてみてください。 不安やストレスは脳で感じるものですが、脳は栄養でコントロールされているので、日々の食生活や栄養を改善することで不安やストレスも改善するといわれています。また、運動により脳の血流がよくなり、脳が活性化され、心に安らぎをもたらすセロトニンなどの神経伝達物質が脳内に増えることも分かっています。 将来が不安でふさぎ込んでしまうときこそ、生活を見直し、より気持ちが整った状態で仕事ができるようにしていくことも考えていきましょう。 不安が少しずつでも解消し、仕事に対してネガティブな気持ちがなくなっていけば、周囲の人とのコミュニケーションや仕事での成果が変わっていきます。まずは小さなことでも自分のなかでできることを1つずつ増やしていくことを目指して、仕事に向き合ってみましょう。

新卒入社した会社に後悔が止まらない時の対処法
新卒で入社しだけど、こんなはずじゃなかったと後悔している…。そう思う方は少なくないようです。2018年に株式会社レバレジーズが発表した、新卒で入社した就職先に関する意識調査によると、「入社を後悔している」と回答が59.8%でした。この調査ではなんと6割もの方が、入社を後悔していることが明らかになったのです。 インターンを経験してから就職する方も増えてはきましたが、多くの場合、新卒採用情報が公開されてから、入社の意思決定をするまでは数ヶ月しかありません。企業との接点も説明会と面接の数回だけという時間のなかで、企業のことを十分に知るのは難しいため、「思っていたのと違っていた」というのはわりとよくある話です。 また、企業が説明会や面接のときにはいいことばかり言っていたけれど、入社してみたら内情は違っている、という状況もあるでしょう。 もし今、「こんな会社、入社するんじゃなかった…」と後悔しているのなら、これからに向けて、こう考えてみませんか。 772

ミスが多いから仕事を辞めたい…逃げ出したくなった時の対処法
仕事でミスが重なり、落ち込んでしまうことは誰にでもあります。しかし、それが続いたり、多くなったりするうちに、周囲からの評価や視線が気になって、仕事のモチベーションも下がり、「仕事を辞めたい」と思うようになってしまうこともあるでしょう。 現状から逃げ出したい…そんな「今」を改善するための対処法を、キャリアコンサルタントの視点からお伝えしたいと思います。 仕事でミスが多い人によくある原因 仕事でミスが多いことを改善するには、「なぜミスが多くなってしまうのか」、その原因を自分で認識する必要があります。 ここに一般的に、「仕事でミスが多い人によくある原因」を7つリストアップしました。自分はどれに当てはまるのか、まずは現状を客観的に捉えてみましょう。 1. 仕事内容が理解できてない 今の業務についてまだ年数が浅い、経験が少ないことがミスの原因になっていることはよくあります。 社会人歴がまだ浅い方、異動してまだ業務経験が少ない方、転職して新しい会社のやり方になれていない方が該当します。 よく職場では「わからないことがあったら聞いて」と言われますが、仕事内容の全容や、「なぜこの仕事をするのか?」という業務の目的や背景がよくわからないので、 「何がわかっていないのか、わからない」「わかっていないことに、気づかない」 ために、ミスが発生してしまいます。わからないことを「わからない」と聞ければミスは減らせますが、多くの場合は「どこで質問すればよかったのかさえも、わからない」状況でしょう。 新しい業務や経験が少ない業務について誰もが多かれ少なかれ直面する問題ですが、一般的にはこの状況は業務経験が長くなれば、一般的には徐々に改善していきますので、それほど苦にしなくても大丈夫です。 もし業務経験は1年以上あるのに、仕事内容が理解できていないということであれば、なぜ理解ができていないのか、まずはその原因から真剣に考えたほうがよいでしょう。 2. 仕事に集中できる環境が整ってない 仕事に集中できないと、ミスは発生しやすくなりますが、「仕事でミスが発生しやすい、集中できない環境」があります。 ・書類が多くて机の上が乱雑している。・パソコンのファイルの整理がされていなくて、必要なファイルが見つけにくい。・会議が多くて集中して自分の業務に取り組む時間がとれない。 このような、集中力に悪影響がある状況に思い当たることはありませんか。その場合、集中できる環境が整えば、ミスが減る可能性があります。自分の環境を見直して整えてみましょう。 3. 会社や上司、先輩社員の教育体制に問題がある また、ミスが多い原因が会社や上司、先輩社員などにあることもあります。それが以下のようなケースです。 ・上司や先輩社員の指示が曖昧でわかりにくい。・そもそも業務に必要なことをきちんと教えていない。・わからないことを聞いても、「今忙しい」「見て覚えて」などで教えてくれない。・質問をしたときの対応が威圧的なので、質問がしにくい。・いつも忙しそうで質問したくても質問できない。・マニュアルやチェックリストがないので、ミスが発生しやすい体制になっている。 こうしたなかには、「質問したいけど、質問できない」ならば、上司とのコミュニケーションの取り方を工夫する、「マニュアルやチェックリストがない」ならば、自分で作成するなど対応できるものもあります。 しかし、ミスを他人のせいにすることは好ましくはないとはいえ、会社や上司、先輩社員など職場の教育体制に問題があると、なかなか個人で状況を改善をするのが難しくなります。 4. スケジュール管理やタスク管理ができていない スケジュール管理やタスク管理が苦手な場合、それがミスの原因になっていることもあります。 特に、業務が多い状況で、スケジュール管理とタスク管理がうまくできないと、マルチタスクで「言われたことからやる」「気が付いたことからやる」ような状態になってしまうことも多くなります。そうなると、1つの業務に集中できず、業務を体系的に捉える視点が薄れてしまうので、業務の漏れが発生し、ミスにつながりやすくなってしまいます。 5. 疑問点をそのままにしている 仕事の疑問点をそのままにしてしまうことも、ミスの原因になります。 「あれ?これでよかったんだっけ?よくわからないけど、今上司は忙しそうだし、これでいいや」「何でこうなっているんだろう?ちょっと気になるけど、このままでいいか」 など、なんとなく業務を流してしまっていることはありませんか? 仕事に関する疑問点をそのままにしておくと、仕事に対する理解がいつまでも深まりません。そうなると、表面的な業務理解で仕事を進めることになり、それがミスの原因になってしまうのです。 6. 仕事が合わない ミスが多い原因には、「仕事が合わない(適性がない)」という原因もあります。例えば、「数字を扱うのが苦手なのに、営業管理や経理関連の仕事をしている」「対人折衝が得意ではないのに、営業している」というケースです。 合わない仕事をするのは、なかなか気が進まず、モチベーションもあがらないのは致し方ないことです。しかし、ネガティブな気持ちで仕事に取り組むと、集中力も下がり、それが結果的にミスの原因となってしまいます。 この場合は、自分に合う仕事への転職を検討したほうがよいかもしれません。 7. 心配事がある、疲れている 仕事やプライベートで何か心配事があり、それで頭がいっぱいになっていたり、心身ともに疲れているときには、集中力は大きく下がりますので、ミスも発生しやすくなります。 仕事上で心配事があるときには、その原因を解消できるように動いてみましょう。その心配事を解消するために何をすればよいのかわからないときには、周囲に思い切って相談してみてください。 また、プライベートでの心配事があるときには、気になるものではありますが、業務時間中はその心配事を解消するためのアクションができるわけではありません。できる限り、目の前のことに集中するよう心がけましょう。 そして心身共に疲れているときには、休息が必要です。定時で帰ってゆっくり休むようにするだけではなく、状況によってはもう少し長い期間休む必要があることもありますので、自分の不調をおろそかにしないようにしてください。 仕事のミスを減らすための対処法 ミスが多い原因がどこにあるのか見当がついたら、ミスを減らすための対処法も見えてきます。「仕事を辞めたい」と思うくらい、現状が嫌になってしまっているかもしれませんが、ミスが多いことが原因であるならば、「転職すること」はベストな解決策ではありません。 ミスを減らし、自分自身の仕事の質が高められるように、以下の対処法を試してみましょう。 メモを取る まだ業務について経験が浅いがゆえに、ミスが多くなってしまう場合には、仕事内容を理解することがミスを減らすことにつながります。 「仕事内容への理解が足りていない」という認識がないこともあるかもしれませんが、業務経験が浅いうちでのミスの多さは、「作業手順をメモする」「業務のポイントをメモする」ことで減らすことができます。 最近は、メモもデジタル化し、「紙に書く」ことに馴染みがない方も多いかもしれませんが、ミスを減らすことが目的であれば、「メモ帳にメモを取る」ことをおすすめします。 手書きする間に自分なりにその内容を理解したり要約する作業が発生するため、手書きのほうが脳を刺激することは専門家からも指摘されており、アメリカのプリンストン大学とカリフォルニア大学ロサンゼルス校の共同研究では、「講義のときに手書きでノートをとる生徒は、パソコンでノートをとる生徒よりも記憶が定着しやすく成績もよい」ということが判明しています。 「仕事内容が理解できていない」ケースは、メモを取ることで理解が進み、状況の改善が期待できますので、ぜひ試してみてください。 気になったら先輩社員や上司に聞く 「わからないことがあったら、先輩社員や上司に確認を」ということは、よく言われていることではありますが、一方でよく聞くのも「仕事で『わからないこと』がわからない」という声です。 ミスを防ぐには、「あれ?これでよかったんだっけ?」と何かが気になった時点で確認することがとても重要です。業務で気になることがあったら、遠慮なく先輩社員や上司に確認するようにしましょう。 その際は、何度も同じことを確認しなくても済むように、しっかりメモを取ることも忘れないようにしてください。 先輩社員や上司が忙しくしていると、声をかけにくいと感じてしまう方も少なくないようですが、確認せずに業務を進めてミスをするよりも、確認をしてミスなく業務を遂行するほうが周囲にとっても望ましいことなので、遠慮なく確認しましょう。 ただ、細々と何度も確認をするのは、その都度仕事が中断してしまいお互いに非効率的なので、確認事項が多くなりそうなときにはまとめて確認するようにするのがおすすめです。 ミスをしやすい業務のマニュアルやチェックリストをつくる 「仕事内容が理解できていない」「マニュアルやチェックリストがない」ときには、ミスをしやすい業務のマニュアルやチェックリストを作成するのも効果的な方法です。 自分で作成し、それを先輩社員や上司にチェックしてもらい、「そのマニュアルやチェックリストを確認して業務を行えば、ミスは発生しない」ものをつくりましょう。 そのマニュアルやチェックリストを作るプロセスでも、業務理解を深めることができるので、一石二鳥です。 マニュアルやチェックリストをみなくても、ミスなく業務ができるようになるまではそれを活用することで、ミスもなくなり、自分自身のスキルアップにも繋がるはずです。 集中力の高い午前中を活用する 今まで、1日の時間のなんとなく過ごしてはいませんか。ミスが多い状況が続いたら、ぜひ時間の使い方から見直してみましょう。 よく言われるように、午前中はドーパミンやアドレナリンなどの神経伝達物質が多く分泌されるので、集中力が向上します。 大事な仕事や、集中力が必要な仕事、そしてミスが多くなってしまうような業務は、午前中に取り組むようにスケジュール管理・タスク管理を行いましょう。 休息をとる 心身ともに疲労がたまり、それがミスの原因になっている場合には、何よりもまず休息を取ることが大切です。バランスのよい食事、適度な運動、適切な睡眠を取るようにしましょう。 「業務が多くて最近疲れが抜けない」という一時的に疲労が溜まっている方も、「なんとなくいつもだるい」という慢性疲労の方も、食事を変えることで疲れがとれやすくなります。たんぱく質、ビタミンB1、ビタミンD、カルシウム、アスパラギン酸、亜鉛を含む食材を取るように心がけてみてください。気軽に摂取できるものでは、豆腐や納豆などの大豆製品、もやし、肉、玄米などがおすすめです。 またストレッチやヨガなど、家の中でできる簡単な運動でも、疲労回復には効果が期待できます。きちんと食べて、軽く体を動かし、しっかり睡眠をとる生活を心がけると、疲労も回復でき、集中力も高まってきます。 食事管理や適度な運動が難しい場合には、瞑想を試してみましょう。瞑想は、どこでも簡単にでき、5分行うだけでも脳の疲れをとり集中力を高める効果があります。瞑想のやり方については関連書籍も多く、ネットでも多くの情報を検索できますので、興味がある方は調べてみてください。 疲れがたまると集中力が減少するだけでなく、思考もネガティブになりがちで、それが心配事につながることもあります。「疲れているな」「最近、気持ちに余裕がないな」と感じたら、無理せずしっかり休みましょう。 「ミスが多い」で転職を検討したほうがいいケース 一方、なかには転職を検討したほうがいいケースもあります。ミスを環境や他人のせいにすることは好ましいことではありませんが、「これはどうしようもない」というケースです。 以下のような状況に当てはまる場合には、転職も視野にいれたほうがよいかもしれません。 教育体制が整っていない 会社や職場の社風として、「そもそも業務に必要なことをきちんと教えない」「人を育てるという意識や余裕がない」という環境もあります。 そのような職場でミスを改善し、業務を身につけていくには、かなりの自立性が求められ、それは人によって向き不向きがあります。ミスが多いだけが原因ではなく、「この会社ではやっていけない」と感じたら、転職を考えたほうがよいでしょう。 仕事が合わない 思うような成果が出せなかったり、先輩社員や上司に叱られてばかりだったり、そもそもやりがいも成長も感じられなかったり…と、「この仕事は、自分に向いていない」と思う原因はいくつか考えられます。 「思うような成果がだせない」「周囲に叱られることが多い」ということならば、ミスを減らす対処法を実践し、少しずつ結果がではじめることで、状況は改善していくでしょう。しかし、「そもそもやりがいも成長も感じられない」ということであれば、自分の適性に合い、前向きに取り組める環境へ転職することを検討してもよいかもしれません。 但し、転職の際には「では、どのような仕事が自分に向いているのか?」「自分はどんな仕事がやりたいのか?」というキャリアプランをしっかり考える必要があります。ここでこのキャリアプランをきちんと考えておかなければ、転職先でもまた「仕事が合わない」と思ってしまいかねません。 「仕事が合わない」は自分にとってもよい状況ではありません。それを今回で終わりにするためにも、転職はキャリアについてきちんと考えてからにしましょう。 「ミスが多いから」で仕事を辞めてしまうリスク 転職したほうがいいケースもありますが、「ミスが多いし、もう仕事辞めたい」という思いから転職するリスクもあります。多くの方が見落としがちな、2つのリスクについてもぜひ知っておいてください。 転職先でミスがなくなるとは限らない 当たり前のことではありますが、転職したからといって、ミスがなくなるわけではありません。 「ミスが多い」という自分の仕事の癖は、限られたケースを除けば、環境を変えることで改善できるものではなく、自分自身で業務の質を高める努力をしていかなければ改善することはできません。ただ、その努力がしやすい環境としにくい環境があるだけで、根本的な解決は自分自身の意識とスキルアップにかかっています。 転職すれば、また新しい業務を覚え、新しい環境に適応していく必要もあります。新しいことをまた1から覚えるということは、覚えきるまでは今まで慣れた環境よりもミスが発生しやすいともいえます。 それでも、心機一転には一定の効果もあります。今度こそミスなく仕事ができるように、仕事の質を高めていこうという思いを忘れないようにしましょう。 「辞め癖」がついてしまうかもしれない 「仕事でミスが多いからやめる」「うまくいかないから辞める」「成果が出せないからやめる」 一度、「現状がうまくいかないから、辞めて他の場所を探す」ことを体験してしまうと、次に何かうまくいかないことがあったときに、「また辞めて別の場所を探せばいいや」と今の会社を辞めて転職することに抵抗がなくなりがちです。 それを1~2回繰り返して、「これだ!」と思うような仕事や会社に出会えればよいのですが、そうはならずに転職を繰り返してしまう方もいらっしゃいます。 20代のうちはそれでもまだ求人はあり、転職もできるので、何も問題は感じないでしょう。しかしそれが回数が重なったり、30代になってしまうと、状況は一転します。 「うまくいかないから、辞める」「気に入らないから辞める」といった、「辞め癖」がついてしまうと、「転職するたびに年収が下がる」「転職するたびに、勤務条件が悪くなる」といった事態にもなりかねません(実際に、そのような方にもお会いしてきました)。 「辞め癖」の末路についてはこちらのコラムで詳しく紹介していますので、ぜひそのリスクについても知っておいてください。 https://career-lab.biz/column/%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%AE%E8%BE%9E%E3%82%81%E7%99%96%E3%81%A8%E9%80%83%E3%81%92%E7%99%96%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%9C%AB%E8%B7%AF%E3%81%AB%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%EF%BC%9F/ キャリア・コンサルティング・ラボでは、キャリアプランに関することだけでなく、みなさまの仕事がよりよくなるような相談全般にも対応しております。 「ミスが多いのをどうしたらよいのか?」といった状況につきましても、現状を整理し、最適な対処法を見つけるサポートをしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

入社5年目、仕事を辞めたい!と壁にぶつかった時の対処法
入社5年目といえば、社内では中堅社員。成長企業やベンチャー企業に勤めている方でしたら、早い人ではマネージャーになる人も出てくるなど、現場のリーダー職として仕事を任されている年代です。 しかし、大卒入社では27歳前後になる入社5年目のこの時期は、30歳を目前に仕事でいろんな壁に直面する時期でもあります。様々な理由から辞めたいと思うようなこともあるでしょう。そんな時にはどうすればいいのか、キャリアコンサルタントの視点から対処法をまとめました。 入社5年目の時期によくある、「辞めたくなる理由」 入社5年目では、どんな理由から「仕事を辞めたい」と思うような壁に直面するのか、入社5年目によくある「辞めたくなる理由」をみてみましょう。 仕事に慣れてマンネリ化、モチベーションが保てない なかには入社3~4年目のタイミングで異動する方もいますが、新卒時の配属から異動もなく同じ仕事を続けている、あるいは部署を異動しても顧客が変わっただけで、基本的に業務は変わらない、など仕事に大きな変化がなく5年目を迎えている方も多いでしょう。 同じ仕事をずっと続けて5年経つと、マンネリを感じてしまうのも無理はありません。仕事には慣れて業務をこなせるようになっても、同じことの繰り返しでなかなかモチベーションが保てない。そんなときに、「新しいことにチャレンジしたい」「このまま終わりたくない」といった理由から「仕事を辞めたい」と感じてしまう方も少なくないようです。 同期や後輩が昇進 入社5年目は、「仕事のできる同期」が頭角を現すころでもあります。社内でも重要なプロジェクトや案件、顧客を任されていたり、早い人だと管理職になったりする人もでてきます。また、同期ではなく、できる後輩が自分よりも業績を上げることもあるでしょう。 「人は人、自分は自分」とは思っていても、組織で働いているとどうしても他人の評価と比べてしまうものです。「自分はこの会社ではやっていけないのではないか」「がんばっているけれど、結果が出せない」「評価されない」など様々な思いが複雑に絡み、この会社での自分の将来が見えなくなってしまうこともあるようです。 マネジメントを任されるようになる 反対に、社内で評価されているからこそマネジメントを任されるようになったことがきっかけで、「自分がやりたいのはマネジメントではない」と、会社を辞めたいと感じるようになる方もいらっしゃいます。 マネジメントを任され、チームの業績や後輩の指導もする立場になると、自分の業務ばかりに専念するわけにはいかなくなります。「自分の業務の専門性を高めたい」「後輩やチームのマネジメントにはあまり興味がない」というスペシャリスト志向の強い方は、望まないマネジメント業務を任されたことをきっかけに評価してくれている会社も辞めたくなってしまうようです。 30歳を前に自分の働き方を真剣に考える 「30代になると、専門性やマネジメント経験がないと転職は難しい」などの情報はどこでも目にします。だからこそ、20代後半のこのタイミングで「この先、自分がやりたいことを考えたらこの会社の今の仕事ではないのではないか」「今のうちに転職しておいたほうがいいのではないか」と、改めて自分自身に向き合う方も少なくありません。 残業や給与、休日など待遇に不満 ・残業が多い・給与が少ない・年間休日が少ない など、待遇への不満はどの年代でも「仕事を辞めたい理由」の上位にランクインしています。 特に入社5年目で27歳前後のこの時期は、友人知人からの結婚の知らせも相次ぐ時期です。新卒時からなんとなく感じていた待遇への不満も、将来を考えたときに、「このままの働き方では続けられない」「結婚もしたいし、もう少し年収を上げたい」と会社を辞めて環境を変えることを選択する方も多くいます。 周囲に転職して成功している人が出てくる 厚生労働省が発表している「新規学卒就職者の離職状況」によると、新卒大卒・者の3割以上が入社3年以内に離職しています。もちろん入社4年目で転職する人もいますので、入社5年目ともなると周囲で転職した友人知人の1人や2人は必ずいるようになります。 業界や業種を変えるキャリアチェンジの転職や、年収アップや待遇アップを実現する転職、中小・中堅企業から安定した大手企業や有名企業への転職も実現しやすい20代中盤の転職では、「転職してよかった」「正解だった」「年収が大幅にアップした」「やりたい仕事に就けた」という成功談を耳にすることも珍しくありません。また、ネットでもそのような転職体験談はいくらでもあります。 周囲で、あるいは同じ年代で「転職して、自分の望む仕事に就いた」「希望する環境や待遇を手に入れた」という話をきくと、「自分も考えたほうがいいのではないか」と思ってしまうことが「辞めたい」と考えるきっかけになることもあるでしょう。 仕事ができない、周囲からの評価が辛い 5年目だけど仕事が合わない、仕事ができないと感じている方もいらっしゃいます。新入社員や入社2~3年目までは、周囲からの評価も「まだ新入社員だし」「まだ若いから」と入社年次の浅いことが加味されますが、入社5年目となると、周囲からの評価もそうはいかなくなります。 「入社5年目だから、これくらいはできて当然ではないか」という見方をされることもあるでしょうし、また「入社5年目なのに、こんなこともできないのか」と心無い評価を受けることが辛くストレスになり、退職へと気持ちが向かってしまうのです。 会社を辞めずに乗り切る方法 「仕事を辞めたい」と思っても、多くの方は実際に会社を辞めるよりもまずは会社を辞めないで乗り切る方法を考えるのではないでしょうか。 転職は、働く会社も一緒に仕事をする人間関係も、仕事内容も、待遇も働き方も、ライフスタイルも、一気に変えることができる手段です。転職により今抱えている悩みをリセットし、再スタートを切ることができるでしょう。 しかし、自分を取り巻く環境が大きく変わってしまうからこそ、「転職」そのもののストレスも大きいものです。また、転職するとなると、職務経歴書や履歴書などの準備から始まる転職活動も、大きな負担となります。 さらに言えば、転職したとしても、転職ですべてが思い通りに変わるとは限りません。周囲には、もしかしたら何もかもが希望通りの運のよい転職を実現できた方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしも、自分も同じように「何もかも希望通りの転職」が実現できる保証もないのが現実です。 そこで、「仕事を辞めたい」と思ったときには、まずは以下のような「会社を辞めずに乗り切る方法」を検討してみることをおすすめします。 キャリアプランを考え直す 「仕事を辞めたい」と思ったときは、今の自分の環境や働き方、仕事内容やこれからのキャリアプランを考える、いい機会でもあります。これを機に、今後のキャリアプランを考えてみましょう。 「キャリアプラン」といっても、「そんなに先のことはわからない」「具体的にどのように考えていいのかわからない」という場合は、こちらにキャリアプランの考え方を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。 https://career-lab.biz/column/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/ 「自分ができることは何か?」「これから何をやりたいのか?」「どんな働き方をしたいのか?」「どんなライフスタイルを実現したいのか?」 などを考えていくと、仕事を辞めずに今の会社での仕事を見直すことが自分にとってよい選択ということも十分にありえます。「辞めたい」という気持ちも、キャリアプランを考えることで現状の捉え方が変わり、気持ちも変わっていくこともあります。 また、転職するにしても、キャリアプランを明確にしておいたほうが、面接での受け答えも変わり評価を得やすくなりますし、より自分のやりたいこと、実現したいライフスタイルに合った転職先を見つけることができるでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、キャリアプランを考え直し、キャリアプランを立てるサポートも行っています。キャリアプランをどのように整理していけばよいかわからない、またはキャリアの棚卸の仕方がよくわからないという方は、ぜひお気軽にご相談ください。 新しいスキルや知識を身につける 仕事にマンネリを感じていたり、評価に不満を感じていたりする場合には、今の会社に勤めながら積極的に新しいスキルや知識を身につけることを検討してみてはいかがでしょうか。 企業によっては、中堅社員がキャリアアップできるような研修制度や人材育成制度を用意しています。社内にそのような制度がない場合も、社外に多くのビジネススクールや研修、講座などがありますので、自分の磨きたいスキル、広げたい視野に合うものがないかぜひ探してみましょう。 仕事に対するマンネリ感、「将来が見えない」という不安、同期や後輩が評価され昇進していることへの焦りは、自分自身の視野を広げスキルを磨くことで、新たな自信が生まれて解消できることも少なくありません。 いつもの毎日に、「新しいことを学ぶ」という変化を加えることで、いつもの仕事に対する気持ちや考え方も変わってくるでしょう。 ボランティアやプロボノ活動をしてみる 仕事を辞めて転職することの一つのメリットは、新しい環境に身を置き、新しい知識や新しい人との出会いを得ることですが、今の仕事を続けながら新しい環境に触れ、視野を広げ、新しい人と出会う機会を得る手段の1つが、ボランティアやプロボノ活動です。 ボランティアというと地域の清掃活動や募金活動、災害復旧活動などのイメージが強い方もいらっしゃるかもしれませんが、今は様々なNPOや社会的企業が、様々なボランティアをオンラインで募集し、オンライン上だけで参加できるものも多くあります。 プロボノは、ボランティア活動のなかでも「職業上のスキルや専門知識を活かした活動」を指し、より自分の仕事のスキルや経験が活かせる活動です。プロボノも、多くのNPOやNGO、社会的企業がプロボノを募集しているサイトがあります。 今の仕事とは全く違う世界に、ボランティアやプロボノ活動を通じて触れることで今の仕事を捉える視点も変わり、今感じている「壁」を乗り越えるきっかけやヒントがみつかるかもしれません。 生活リズムを整え、休息をしっかりとる 仕事で「壁」を感じたり、ストレスを感じたりするときは、心身共に疲れがたまっている状態です。 キャリアプランも考える気がしない。新たな知識を学びに行くのも面倒。ボランティアやプロボノなんて、全く興味ないしもってのほか。そんな状況でしたら、もしかしたら、今一番必要なのは、休息をしっかりとることかもしれません。 もしそんな状況に当てはまるのならば、できる限り仕事を定時で切り上げ、好きなことをする自分の時間をゆっくり過ごし、ストレッチや筋トレなど家でできる簡単なものでもいいので適度に体を動かし、野菜などをしっかりとって、お風呂にゆっくり入り、睡眠をたっぷりとりましょう。 人間の脳は、疲れているときにはネガティブになりやすいといわれています。これからのことを考えたり決断したりするのは、まずはゆっくり疲れをとってからでも遅くはないでしょう。 転職して乗り切る方法 転職は準備も必要ですし、転職ですべてが解決するとは限りませんが、それでも「待遇に不満」など、「仕事を辞めたい」と思う理由によっては、転職をしなければ解決できないものもあります。またキャリアプランを考えた結果、やはり転職するのがベストという結論になることもあるでしょう。 たしかに転職ですべてが思い通りになるわけではないものの、入社5年目のこのタイミングは、他の年代に比べて比較的希望通りの転職がしやすい時期でもあります。転職を成功させるためにも、入社5年目の転職活動を取り巻く環境と、転職活動を成功させるためのポイントを確認しておきましょう。 入社5年目の転職活動を取り巻く環境 大卒入社の場合、入社5年目は27歳前後となります。社会人としてのビジネスマナーについては問題なく、実務経験を備えながらも、まだ20代で入社後の成長性、新しい企業に馴染む柔軟性が期待できるこの年代に対しては、企業の採用意欲も高いです。 厚生労働省が発表する「雇用動向調査結果」をみても、年代別の転職入職率は26-30歳を過ぎて30代になるとぐっと下がっていきます。 【年齢階級別転職入職率】 画像引用元:厚生労働省「2024年転職入職者の状況(1)年齢階級別転職入職率 令和5年1年間.」 転職を考えているならば、このタイミングを逃さずに、20代のうちに行動を起こしたほうが可能性は広がりやすいでしょう。 入社5年目の転職活動を成功させるには 入社3年目未満の転職であれば、企業も「第二新卒」として可能性を重視しますので、意欲の高さ、前向きさをアピールすることが重要です。 しかし入社5年目となると、企業はこれまでの実績も求めるようになります。そのため、転職活動では、今までの実績を企業にわかりやすくアピールすることが重要です。数字が出せる部分は可能な限り実績を数字で伝えるようにし、どんな強みや実績があるのかを職務経歴書にわかりやすく記載していきましょう。 また、入社5年目はこれまでの実績が求められる年代ではありますが、一方で20代後半は未経験職種にキャリアチェンジできる最後のチャンスでもあります。 未経験職種へのチャレンジは、企業がより成長性やポテンシャルを重視することから20代前半が成功しやすく、より即戦力として活躍することが求められる30代になると、未経験職種への転職は格段に難易度が上がり、チャンスも減ってしまいます。今までの仕事が合わず、他の仕事にチャレンジしたい方は、ぜひ万全の準備をして臨んでください。 その際も「職種としては未経験だが、今までの業務で身につけたこのスキルや経験が、このようにこれからの仕事に活かせると思う」など、今までの経験を生かした上での成長性や意欲のアピールが重要になります。未経験職種へのチャレンジを希望する場合には、転職エージェントやキャリアコンサルタントなどプロの力をうまく活用するようにしましょう。 入社5年目で仕事を辞めたくなるような「壁」を感じることは、よくあります。これを成長の機会とし、自分にとって良い選択ができるように、キャリアコンサルタントが必要な時にはぜひお気軽にお問合せください。

仕事を辞めたい40代が辞める前に絶対知っておきたいこと
新卒入社から20年近い年月が過ぎ、でも定年まではあと20年近くある、「折り返し地点」ともいえる40代。このタイミングで、「このままでいいのか?」「この後残りの人生どんな生き方・働き方をしたいのか?」と改めて真剣に、キャリアを見つめ直す方も多いのではないのでしょうか。 しかし、その先の老後や家族のことを考えると、その選択で失敗したくない、リスクを極力抑えたいと思うのもこの年代ならではの本音ではないかと思います。そこで今回は、40代からのキャリアの選択で後悔しないために、ぜひ知っておきたいことをキャリアコンサルタントの視点でまとめました。 1. 40代が仕事を辞めたいと思う理由 会社を辞めたい理由を大別すると、どの年代も共通して以下のような理由が一般的です。 【仕事を辞めたい理由】 ・新たなチャレンジをしたい(仕事がつまらない)・評価に納得がいかない(自分の業績が評価されない)・人間関係(特に上司)に問題がある・会社の業績や、この会社での自分の将来に不安がある・働き方を変えたい 20代や30代では、待遇(給与、残業時間)への不満も本音の転職理由の上位に入りますが、待遇に不満があれば40代になる前に転職して状況を変えていることがほとんどですので、40代になって「仕事を辞めたい」と思う理由には、待遇以外の要因が大きくなってくるようです。 また、「働き方を変えたい」という理由も40代になると 「30代まではがむしゃらに働き、残業が多い仕事も厭わなかったけれど、もう少し仕事をペースを落としてプライベートの時間も大切にしたい」「自分の専門分野で独立をしたい」など、仕事人生の後半戦で自分が望む働き方をするために、一歩踏み出す方も多くいらっしゃいます。 いずれにしても、20代のころとは異なり、今の仕事を辞めるリスクも十分に理解している40代。だからこそ、本当に辞めたいと思うときには、上記のいくつかの理由が重なっていることが多いようです。 2. 転職を決める前に確認しておきたいこと ではその「仕事を辞めたい」と思う気持ちを大切に、新たなチャレンジを選んだほうがいいのか。それとも今の会社で、状況を改善する可能性を探ったほうがいいのか。その選択は難しいものですが、この先に後悔しないためにも「仕事を辞めたい」と思ったときには、次のような視点からもう一度客観的に状況を見直してみましょう。 辞めたい理由は、退職しないと本当に解決できないのか? 20代や30代とは違い、経験がある40代だからこそ、「辞めたい」と思った今の時点ですでにあらゆる状況改善の可能性を探り、改善が見込めないと思うからこそ「辞めたい」と考えていらっしゃるのではないかとは思います。しかしもう一度だけ、「辞めたい理由は、会社を辞めないと本当に解決できないのか?」と考えてみませんか。 たとえば、「評価に納得がいかない」という理由の場合、転職して自分の業績を評価してくれる環境に変わることもありますが、それが実現しないこともありえます。 また、「仕事がつまらない、マンネリ化している」という理由も、次の仕事は外から見たら面白そうだったけれど、実際にやってみたらそうでもない可能性もありますし、数年経てばまた「マンネリ」を感じてしまう可能性もあります。 「働き方を変えたい」など、会社を辞めなければ解決できない理由もありますが、なかにはこのように、転職だけで解決するとは限らない、根本的な解決は他にあるかもしれないケースもあります。 キャリア・コンサルティング・ラボに相談される方のお話を伺うと、「辞めたい本当の理由」は表面的な「辞めたい理由」と別のところにあることも実は多いです。また、「その辞めたい本当の理由は、辞めなくても解決できる」と気づき、転職することを辞める方もいらっしゃいます。 「辞めたい本当の理由」は、自分で考えているだけでは気づかず、他人に話をするうちに自分の考えが整理されて、本当の気持ちに気づくこともよくあります。このように「誰かに話す」ことの効果は大きいので、友人で話せる方がいらっしゃったら、ぜひ一度話をしてみてはいかがでしょうか。 この決断で経済的な問題が発生しないか? 40代になると、経済面も重要な判断材料になります。扶養対象となるご家族がいらっしゃる場合は、家族への経済的影響も考慮する必要があるでしょう。 そのため、「仕事を辞める」という決断で経済的な問題が発生しないか、もし発生するならばそれが対応できる範囲かどうかについては、あらゆるリスクを考えて検証しておく必要があります。 その意味でも、転職をするとしても、収入が途絶える期間がないように在職中から転職活動を始め、退職は転職が決まってからにするのがおすすめです。 40代の転職でも、転職により年収アップを実現する方もいらっしゃいますが、現状維持も難しい方も多くいらっしゃいます。もし自分の希望を叶えるために年収が下がってしまうとしたら、いくらまでなら収入ダウンを許容できるのか、自分だけでなく家族のライフイベントも考慮しながら、中長期的な視野で検討しておきましょう。 家族の理解は得られるか? 結婚をしている方の場合、この年代で今の会社を辞めることは、家族にも大きく影響します。収入はもちろん、働き方が変われば、生活パターンへの影響もあるからです。また、それまで有名企業や大手企業に勤めていた場合は、パートナーも福利厚生を始め、様々な恩恵を受けています。会社を辞めて、その恩恵も失うことにもなれば、それに対する抵抗感もあるでしょう。 このように40代で結婚をしている方の場合、「会社を辞める」ことがもたらす家族への影響が大きいからこそ、辞めることに対し家族の理解が得られないケースがよくあります。内定をもらってからご家族に相談する方もいますが、その時点で大反対されて泣く泣く内定を断る…という方も少なくありません。 そのような事態を避けるためにも、様々なご家族の事情もあるかとは思いますが、辞めたいという気持ちが固まった時点でご家族に伝え、理解を得ておくことをおすすめします。 もし反対された場合、それに自分が納得できればよいのですが、自分の思いを我慢してしまうと、その影響はこれから先20年前後も続く仕事人生に影響してしまいます。それを考えれば、ここで自分の気持ちを我慢するのは良い選択とは言い難いでしょう。 実際にはご家族からの反対があったために、転職を諦める方も多いのが事実ですが、相手の気持ちも想像しながら、転職したいという思いに反対されないようにコミュニケーションをしていけばスムーズに進むこともあります。相手の気持ちを理解し、相手に転職への思いを理解してしまうコミュニケーションのポイントは、こちらのコラムで紹介しています。適切なコミュニケーションで、「辞めたい」気持ちへの家族の理解を早めに得ておきましょう。 https://career-lab.biz/column/%e5%ab%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e2%81%89%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%81%ab%e5%8f%8d%e5%af%be%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a6%bb%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%90%91%e3%81%8d%e5%90%88%e3%81%84/ 3.転職活動をする前に知っておきたいこと 転職を決める前にもう一度考え直した結果、やはり仕事を辞めたい理由が転職をしなければ解決できないものであるならば、転職活動はできるだけ早くスタートしましょう。厚生労働省が、平成19年に求人の募集・採用時に年齢制限を設けることや年齢を理由に採否を決めることを禁止したとはいえ、実際には年齢が上がるほど、転職の難易度は高くなってしまうからです。 転職活動を成功させるためにも、転職活動を始める前に40代の人材に対して企業からどのようなニーズがあるのかを確認しておきましょう。 40代の転職で企業から求められるもの 20代や30代は、その成長性を見込んだポテンシャル採用や、次期マネージャー候補としての採用を検討しますが、40代を採用したい場合には、専門性と経験を兼ね備えたマネージャーや管理職、経営幹部としての採用ニーズがほとんどです。ただし、慢性的な人手不足で、20代や30代だけでは必要な人材が採用できない業界・企業では、メンバークラスでも40代を採用するケースもあるでしょう。 いずれにしても、40代の転職で企業が求めるのものは即戦力です。それには、企画力や提案力、プレゼンテーション力、そしてリーダーシップやマネジメント力などを期待されます。すべてを兼ね備える必要はないですが、自分の強みは何なのかをより明確にし、それを必要としている企業を見極めていく必要があります。 また、40代の転職では新しい企業文化に対応できる柔軟性やコミュニケーション能力も求められます。40代を採用する場合、企業は「それまでの経験や知識から、新しい企業、社風に馴染めないのではないか」ということを懸念しますので、新たな環境への意欲や柔軟性が面接で伝わるようにすることも、転職成功のポイントになります。 40代の転職の現実 企業は40代の人材に即戦力を求めているので、高い専門性、実績などがあれば求人はあり、年収アップを実現される方もいらっしゃいます。 しかし、そうでない場合は20代、30代に比べると求人数は少なく、転職活動は長期化する傾向があります。それは、 ・年功序列型の賃金体系が残る企業では、職務能力やスキルなどが同じならば、より労働コストを押さえられること・採用後に自社で長く活躍してくれることを期待していること・新しい企業文化を受け入れる柔軟性を持っていそうなこと などの理由から、同じ職務能力やスキルならば、より若い人材を採用したいと考えるからです。 転職活動は限られた求人から選択することになるため、自分の希望条件にこだわり続けると転職活動が長期化してしまいます。人はどうしても「待っていたら、そのうち自分の希望に合う求人が出てくるのではないか」と期待してしまうのですが、その「自分に合う求人」が見つかる可能性は、20代や30代の頃に比べると格段に低く、出てこない可能性も極めて高いと認識しておきましょう。 また、退職後に転職活動が長期化してしまうと、何もしていない「ブランク期間」が長くなってしまいます。ブランク期間が長いと 「転職活動を計画性がない(=仕事能力にも問題がある)のではないか」「理想が高すぎるのではないか」「何か問題がある人だから、他の企業でも採用されなかったのではないか」 と懸念され、40代の転職活動では非常に不利になってしまいますのでので、よほどの事情がない限り、転職活動は仕事を続けながら行うことがおすすめです。 4.40代の転職活動を成功させるために 40代の転職を取り巻く環境は、厳しいものではありますが、転職を成功させている方はいらっしゃいます。これからいい転職をするために、そのような方が実践されている「40代の転職を成功させるために大切な3つのこと」をご紹介します。 経験を活かし、できることを明確にする 専門性や経験が求められる40代の転職では、自分の経験や専門性を、実績をベースにできるかぎり明確にすることが転職成功のカギとなります。 それがわかりやすく企業に伝われば伝わるほど、自分にとっても、自分の強みを活かすことができ、それを高く評価してくれる企業と出会いやすくなります。 20代や30代と異なり、経験が長い分だけ職務経歴書に記載することが多くなるので、転職活動では企業研究を入念に行い、自分の今までの経験を全部伝えようとするのではなく、「応募企業の強みや業界でのポジションなどを理解し、企業のニーズに沿った強み」をわかりやすくアピールする職務経歴書を作成するようにしましょう。 志望動機を具体的に、現実的に 40代の転職をスムーズに進めるためには、志望動機もより重要です。もちろん志望動機はどの年代でも重要なものですが、特に40代の志望動機では、 ・なぜその応募企業を選んだのか。・その企業で今までの経験をどのように活かし、何を実現したいのか。・今までの経験を活かし、会社に対し、どんな貢献ができるのか。 について、これまでの経験やスキルをもとにより具体的に、そして現実的に記載することが必要です。20代のころは「どの企業にも転用できるような志望動機」で書類選考を通過することができても、40代では通用しません。 1社1社、しっかり企業研究を行い、その企業に合わせ、「このような考えを持っているならば、うちで働くのが一番だし、活躍してくれそうだ」と企業が思うような、各社毎にオリジナルの志望動機をまとめましょう。 「転職で実現したいこと」の優先順位を明確にする 40代になると、自分の今までの経験、実績、報酬に対する自信から、転職条件へのこだわりも無意識のうちに強くなってしまいます。また、家庭などの事情から「これは譲れない」という条件もいつの間にか多くなりがちです。 全てを叶えることができれば理想的ですが、求人数が少ない40代の転職では、こだわりの条件が多ければ多いほど、転職実現度は低くなります。そのため、今の状況を変えたいのであれば、「これだけは譲れない条件」を1~2つ程度明確にし、それ以外は柔軟に検討する姿勢が極めて重要です。 たとえば、「年収だけは維持したい」という場合には、年収が維持できるならば、業界や企業規模、知名度、仕事内容などにはこだわらずに求人を探し、その会社、その求人の良いところを見つけるようにして、自分の選択肢を広げていきましょう。 応募する求人の仕事を具体的にイメージし、面接で確認する また、転職活動では「応募する求人の仕事内容を遂行している自分」をできる限り具体的にイメージし、面接で気になることを積極的に質問して確認しましょう。 このことには2つのメリットがあります。1つめは、きちんと仕事内容を確認しておくことで、業務への理解が深まり、入社後に「こんなはずではなかった」とギャップを感じるリスクを小さくできることです。40代の転職は、多くの方にとっておそらく最後の転職になります。ここでの失敗を避けるためにも、面接でイメージと現実のギャップを埋めておくことはとても重要です。 2つめは、その積極的な姿勢が企業から評価対象になることです。適切な質問は、前向きな意欲の表れとして好印象につながります。また、質問次第では、それが仕事能力の裏付けとなり、高評価にもつながるでしょう。 5.40代からのキャリアの選択にプロのアドバイスを このように40代からのキャリアの選択は、20代や30代のころの転職よりもより計画的に、より深く今後のキャリアを考える必要があります。 経験も積み重なり、20代や30代のころに比べれば考慮すべきことも増えるからこそ、どのように情報を整理し、情報の取捨選択をしていけばよいか、一人ではなかなか難しいこともあるでしょう。 40代からのキャリア選択にこそ、プロのキャリアコンサルタントのサポートは効果的です。プロの力をうまく活用しながら、もうあと20年、気持ちよく仕事ができる選択を見つけていきましょう。 その他参考記事:40代で仕事辞めたい、疲れたと感じる女性必見!今すぐできる対処法とおすすめの仕事5選(ママキャンMamCamp)

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動
新卒入社から20年近い年月が過ぎ、でも定年まではあと20年近くある、「折り返し地点」ともいえる40代。このタイミングで、「このままでいいのか?」「この後残りの人生どんな生き方・働き方をしたいのか?」と改めて真剣に、キャリアを見つめ直す方も多いのではないのでしょうか。 しかし、その先の老後や家族のことを考えると、その選択で失敗したくない、リスクを極力抑えたいと思うのもこの年代ならではの本音ではないかと思います。そこで今回は、40代からのキャリアの選択で後悔しないために、ぜひ知っておきたいことをキャリアコンサルタントの視点でまとめました。 1. 40代が仕事を辞めたいと思う理由 会社を辞めたい理由を大別すると、どの年代も共通して以下のような理由が一般的です。 【仕事を辞めたい理由】 ・新たなチャレンジをしたい(仕事がつまらない)・評価に納得がいかない(自分の業績が評価されない)・人間関係(特に上司)に問題がある・会社の業績や、この会社での自分の将来に不安がある・働き方を変えたい 20代や30代では、待遇(給与、残業時間)への不満も本音の転職理由の上位に入りますが、待遇に不満があれば40代になる前に転職して状況を変えていることがほとんどですので、40代になって「仕事を辞めたい」と思う理由には、待遇以外の要因が大きくなってくるようです。 また、「働き方を変えたい」という理由も40代になると 「30代まではがむしゃらに働き、残業が多い仕事も厭わなかったけれど、もう少し仕事をペースを落としてプライベートの時間も大切にしたい」「自分の専門分野で独立をしたい」など、仕事人生の後半戦で自分が望む働き方をするために、一歩踏み出す方も多くいらっしゃいます。 いずれにしても、20代のころとは異なり、今の仕事を辞めるリスクも十分に理解している40代。だからこそ、本当に辞めたいと思うときには、上記のいくつかの理由が重なっていることが多いようです。 2. 転職を決める前に確認しておきたいこと ではその「仕事を辞めたい」と思う気持ちを大切に、新たなチャレンジを選んだほうがいいのか。それとも今の会社で、状況を改善する可能性を探ったほうがいいのか。その選択は難しいものですが、この先に後悔しないためにも「仕事を辞めたい」と思ったときには、次のような視点からもう一度客観的に状況を見直してみましょう。 辞めたい理由は、退職しないと本当に解決できないのか? 20代や30代とは違い、経験がある40代だからこそ、「辞めたい」と思った今の時点ですでにあらゆる状況改善の可能性を探り、改善が見込めないと思うからこそ「辞めたい」と考えていらっしゃるのではないかとは思います。しかしもう一度だけ、「辞めたい理由は、会社を辞めないと本当に解決できないのか?」と考えてみませんか。 たとえば、「評価に納得がいかない」という理由の場合、転職して自分の業績を評価してくれる環境に変わることもありますが、それが実現しないこともありえます。 また、「仕事がつまらない、マンネリ化している」という理由も、次の仕事は外から見たら面白そうだったけれど、実際にやってみたらそうでもない可能性もありますし、数年経てばまた「マンネリ」を感じてしまう可能性もあります。 「働き方を変えたい」など、会社を辞めなければ解決できない理由もありますが、なかにはこのように、転職だけで解決するとは限らない、根本的な解決は他にあるかもしれないケースもあります。 キャリア・コンサルティング・ラボに相談される方のお話を伺うと、「辞めたい本当の理由」は表面的な「辞めたい理由」と別のところにあることも実は多いです。また、「その辞めたい本当の理由は、辞めなくても解決できる」と気づき、転職することを辞める方もいらっしゃいます。 「辞めたい本当の理由」は、自分で考えているだけでは気づかず、他人に話をするうちに自分の考えが整理されて、本当の気持ちに気づくこともよくあります。このように「誰かに話す」ことの効果は大きいので、友人で話せる方がいらっしゃったら、ぜひ一度話をしてみてはいかがでしょうか。 この決断で経済的な問題が発生しないか? 40代になると、経済面も重要な判断材料になります。扶養対象となるご家族がいらっしゃる場合は、家族への経済的影響も考慮する必要があるでしょう。 そのため、「仕事を辞める」という決断で経済的な問題が発生しないか、もし発生するならばそれが対応できる範囲かどうかについては、あらゆるリスクを考えて検証しておく必要があります。 その意味でも、転職をするとしても、収入が途絶える期間がないように在職中から転職活動を始め、退職は転職が決まってからにするのがおすすめです。 40代の転職でも、転職により年収アップを実現する方もいらっしゃいますが、現状維持も難しい方も多くいらっしゃいます。もし自分の希望を叶えるために年収が下がってしまうとしたら、いくらまでなら収入ダウンを許容できるのか、自分だけでなく家族のライフイベントも考慮しながら、中長期的な視野で検討しておきましょう。 家族の理解は得られるか? 結婚をしている方の場合、この年代で今の会社を辞めることは、家族にも大きく影響します。収入はもちろん、働き方が変われば、生活パターンへの影響もあるからです。また、それまで有名企業や大手企業に勤めていた場合は、パートナーも福利厚生を始め、様々な恩恵を受けています。会社を辞めて、その恩恵も失うことにもなれば、それに対する抵抗感もあるでしょう。 このように40代で結婚をしている方の場合、「会社を辞める」ことがもたらす家族への影響が大きいからこそ、辞めることに対し家族の理解が得られないケースがよくあります。内定をもらってからご家族に相談する方もいますが、その時点で大反対されて泣く泣く内定を断る…という方も少なくありません。 そのような事態を避けるためにも、様々なご家族の事情もあるかとは思いますが、辞めたいという気持ちが固まった時点でご家族に伝え、理解を得ておくことをおすすめします。 もし反対された場合、それに自分が納得できればよいのですが、自分の思いを我慢してしまうと、その影響はこれから先20年前後も続く仕事人生に影響してしまいます。それを考えれば、ここで自分の気持ちを我慢するのは良い選択とは言い難いでしょう。 実際にはご家族からの反対があったために、転職を諦める方も多いのが事実ですが、相手の気持ちも想像しながら、転職したいという思いに反対されないようにコミュニケーションをしていけばスムーズに進むこともあります。相手の気持ちを理解し、相手に転職への思いを理解してしまうコミュニケーションのポイントは、こちらのコラムで紹介しています。適切なコミュニケーションで、「辞めたい」気持ちへの家族の理解を早めに得ておきましょう。 https://career-lab.biz/column/%e5%ab%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e2%81%89%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%81%ab%e5%8f%8d%e5%af%be%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a6%bb%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%90%91%e3%81%8d%e5%90%88%e3%81%84/ 3.転職活動をする前に知っておきたいこと 転職を決める前にもう一度考え直した結果、やはり仕事を辞めたい理由が転職をしなければ解決できないものであるならば、転職活動はできるだけ早くスタートしましょう。厚生労働省が、平成19年に求人の募集・採用時に年齢制限を設けることや年齢を理由に採否を決めることを禁止したとはいえ、実際には年齢が上がるほど、転職の難易度は高くなってしまうからです。 転職活動を成功させるためにも、転職活動を始める前に40代の人材に対して企業からどのようなニーズがあるのかを確認しておきましょう。 40代の転職で企業から求められるもの 20代や30代は、その成長性を見込んだポテンシャル採用や、次期マネージャー候補としての採用を検討しますが、40代を採用したい場合には、専門性と経験を兼ね備えたマネージャーや管理職、経営幹部としての採用ニーズがほとんどです。ただし、慢性的な人手不足で、20代や30代だけでは必要な人材が採用できない業界・企業では、メンバークラスでも40代を採用するケースもあるでしょう。 いずれにしても、40代の転職で企業が求めるのものは即戦力です。それには、企画力や提案力、プレゼンテーション力、そしてリーダーシップやマネジメント力などを期待されます。すべてを兼ね備える必要はないですが、自分の強みは何なのかをより明確にし、それを必要としている企業を見極めていく必要があります。 また、40代の転職では新しい企業文化に対応できる柔軟性やコミュニケーション能力も求められます。40代を採用する場合、企業は「それまでの経験や知識から、新しい企業、社風に馴染めないのではないか」ということを懸念しますので、新たな環境への意欲や柔軟性が面接で伝わるようにすることも、転職成功のポイントになります。 40代の転職の現実 企業は40代の人材に即戦力を求めているので、高い専門性、実績などがあれば求人はあり、年収アップを実現される方もいらっしゃいます。 しかし、そうでない場合は20代、30代に比べると求人数は少なく、転職活動は長期化する傾向があります。それは、 ・年功序列型の賃金体系が残る企業では、職務能力やスキルなどが同じならば、より労働コストを押さえられること・採用後に自社で長く活躍してくれることを期待していること・新しい企業文化を受け入れる柔軟性を持っていそうなこと などの理由から、同じ職務能力やスキルならば、より若い人材を採用したいと考えるからです。 転職活動は限られた求人から選択することになるため、自分の希望条件にこだわり続けると転職活動が長期化してしまいます。人はどうしても「待っていたら、そのうち自分の希望に合う求人が出てくるのではないか」と期待してしまうのですが、その「自分に合う求人」が見つかる可能性は、20代や30代の頃に比べると格段に低く、出てこない可能性も極めて高いと認識しておきましょう。 また、退職後に転職活動が長期化してしまうと、何もしていない「ブランク期間」が長くなってしまいます。ブランク期間が長いと 「転職活動を計画性がない(=仕事能力にも問題がある)のではないか」「理想が高すぎるのではないか」「何か問題がある人だから、他の企業でも採用されなかったのではないか」 と懸念され、40代の転職活動では非常に不利になってしまいますのでので、よほどの事情がない限り、転職活動は仕事を続けながら行うことがおすすめです。 4.40代の転職活動を成功させるために 40代の転職を取り巻く環境は、厳しいものではありますが、転職を成功させている方はいらっしゃいます。これからいい転職をするために、そのような方が実践されている「40代の転職を成功させるために大切な3つのこと」をご紹介します。 経験を活かし、できることを明確にする 専門性や経験が求められる40代の転職では、自分の経験や専門性を、実績をベースにできるかぎり明確にすることが転職成功のカギとなります。 それがわかりやすく企業に伝われば伝わるほど、自分にとっても、自分の強みを活かすことができ、それを高く評価してくれる企業と出会いやすくなります。 20代や30代と異なり、経験が長い分だけ職務経歴書に記載することが多くなるので、転職活動では企業研究を入念に行い、自分の今までの経験を全部伝えようとするのではなく、「応募企業の強みや業界でのポジションなどを理解し、企業のニーズに沿った強み」をわかりやすくアピールする職務経歴書を作成するようにしましょう。 志望動機を具体的に、現実的に 40代の転職をスムーズに進めるためには、志望動機もより重要です。もちろん志望動機はどの年代でも重要なものですが、特に40代の志望動機では、 ・なぜその応募企業を選んだのか。・その企業で今までの経験をどのように活かし、何を実現したいのか。・今までの経験を活かし、会社に対し、どんな貢献ができるのか。 について、これまでの経験やスキルをもとにより具体的に、そして現実的に記載することが必要です。20代のころは「どの企業にも転用できるような志望動機」で書類選考を通過することができても、40代では通用しません。 1社1社、しっかり企業研究を行い、その企業に合わせ、「このような考えを持っているならば、うちで働くのが一番だし、活躍してくれそうだ」と企業が思うような、各社毎にオリジナルの志望動機をまとめましょう。 「転職で実現したいこと」の優先順位を明確にする 40代になると、自分の今までの経験、実績、報酬に対する自信から、転職条件へのこだわりも無意識のうちに強くなってしまいます。また、家庭などの事情から「これは譲れない」という条件もいつの間にか多くなりがちです。 全てを叶えることができれば理想的ですが、求人数が少ない40代の転職では、こだわりの条件が多ければ多いほど、転職実現度は低くなります。そのため、今の状況を変えたいのであれば、「これだけは譲れない条件」を1~2つ程度明確にし、それ以外は柔軟に検討する姿勢が極めて重要です。 たとえば、「年収だけは維持したい」という場合には、年収が維持できるならば、業界や企業規模、知名度、仕事内容などにはこだわらずに求人を探し、その会社、その求人の良いところを見つけるようにして、自分の選択肢を広げていきましょう。 応募する求人の仕事を具体的にイメージし、面接で確認する また、転職活動では「応募する求人の仕事内容を遂行している自分」をできる限り具体的にイメージし、面接で気になることを積極的に質問して確認しましょう。 このことには2つのメリットがあります。1つめは、きちんと仕事内容を確認しておくことで、業務への理解が深まり、入社後に「こんなはずではなかった」とギャップを感じるリスクを小さくできることです。40代の転職は、多くの方にとっておそらく最後の転職になります。ここでの失敗を避けるためにも、面接でイメージと現実のギャップを埋めておくことはとても重要です。 2つめは、その積極的な姿勢が企業から評価対象になることです。適切な質問は、前向きな意欲の表れとして好印象につながります。また、質問次第では、それが仕事能力の裏付けとなり、高評価にもつながるでしょう。 5.40代からのキャリアの選択にプロのアドバイスを このように40代からのキャリアの選択は、20代や30代のころの転職よりもより計画的に、より深く今後のキャリアを考える必要があります。 経験も積み重なり、20代や30代のころに比べれば考慮すべきことも増えるからこそ、どのように情報を整理し、情報の取捨選択をしていけばよいか、一人ではなかなか難しいこともあるでしょう。 40代からのキャリア選択にこそ、プロのキャリアコンサルタントのサポートは効果的です。プロの力をうまく活用しながら、もうあと20年、気持ちよく仕事ができる選択を見つけていきましょう。 その他参考記事:40代で仕事辞めたい、疲れたと感じる女性必見!今すぐできる対処法とおすすめの仕事5選(ママキャンMamCamp)

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法
新卒入社から20年近い年月が過ぎ、でも定年まではあと20年近くある、「折り返し地点」ともいえる40代。このタイミングで、「このままでいいのか?」「この後残りの人生どんな生き方・働き方をしたいのか?」と改めて真剣に、キャリアを見つめ直す方も多いのではないのでしょうか。 しかし、その先の老後や家族のことを考えると、その選択で失敗したくない、リスクを極力抑えたいと思うのもこの年代ならではの本音ではないかと思います。そこで今回は、40代からのキャリアの選択で後悔しないために、ぜひ知っておきたいことをキャリアコンサルタントの視点でまとめました。 1. 40代が仕事を辞めたいと思う理由 会社を辞めたい理由を大別すると、どの年代も共通して以下のような理由が一般的です。 【仕事を辞めたい理由】 ・新たなチャレンジをしたい(仕事がつまらない)・評価に納得がいかない(自分の業績が評価されない)・人間関係(特に上司)に問題がある・会社の業績や、この会社での自分の将来に不安がある・働き方を変えたい 20代や30代では、待遇(給与、残業時間)への不満も本音の転職理由の上位に入りますが、待遇に不満があれば40代になる前に転職して状況を変えていることがほとんどですので、40代になって「仕事を辞めたい」と思う理由には、待遇以外の要因が大きくなってくるようです。 また、「働き方を変えたい」という理由も40代になると 「30代まではがむしゃらに働き、残業が多い仕事も厭わなかったけれど、もう少し仕事をペースを落としてプライベートの時間も大切にしたい」「自分の専門分野で独立をしたい」など、仕事人生の後半戦で自分が望む働き方をするために、一歩踏み出す方も多くいらっしゃいます。 いずれにしても、20代のころとは異なり、今の仕事を辞めるリスクも十分に理解している40代。だからこそ、本当に辞めたいと思うときには、上記のいくつかの理由が重なっていることが多いようです。 2. 転職を決める前に確認しておきたいこと ではその「仕事を辞めたい」と思う気持ちを大切に、新たなチャレンジを選んだほうがいいのか。それとも今の会社で、状況を改善する可能性を探ったほうがいいのか。その選択は難しいものですが、この先に後悔しないためにも「仕事を辞めたい」と思ったときには、次のような視点からもう一度客観的に状況を見直してみましょう。 辞めたい理由は、退職しないと本当に解決できないのか? 20代や30代とは違い、経験がある40代だからこそ、「辞めたい」と思った今の時点ですでにあらゆる状況改善の可能性を探り、改善が見込めないと思うからこそ「辞めたい」と考えていらっしゃるのではないかとは思います。しかしもう一度だけ、「辞めたい理由は、会社を辞めないと本当に解決できないのか?」と考えてみませんか。 たとえば、「評価に納得がいかない」という理由の場合、転職して自分の業績を評価してくれる環境に変わることもありますが、それが実現しないこともありえます。 また、「仕事がつまらない、マンネリ化している」という理由も、次の仕事は外から見たら面白そうだったけれど、実際にやってみたらそうでもない可能性もありますし、数年経てばまた「マンネリ」を感じてしまう可能性もあります。 「働き方を変えたい」など、会社を辞めなければ解決できない理由もありますが、なかにはこのように、転職だけで解決するとは限らない、根本的な解決は他にあるかもしれないケースもあります。 キャリア・コンサルティング・ラボに相談される方のお話を伺うと、「辞めたい本当の理由」は表面的な「辞めたい理由」と別のところにあることも実は多いです。また、「その辞めたい本当の理由は、辞めなくても解決できる」と気づき、転職することを辞める方もいらっしゃいます。 「辞めたい本当の理由」は、自分で考えているだけでは気づかず、他人に話をするうちに自分の考えが整理されて、本当の気持ちに気づくこともよくあります。このように「誰かに話す」ことの効果は大きいので、友人で話せる方がいらっしゃったら、ぜひ一度話をしてみてはいかがでしょうか。 この決断で経済的な問題が発生しないか? 40代になると、経済面も重要な判断材料になります。扶養対象となるご家族がいらっしゃる場合は、家族への経済的影響も考慮する必要があるでしょう。 そのため、「仕事を辞める」という決断で経済的な問題が発生しないか、もし発生するならばそれが対応できる範囲かどうかについては、あらゆるリスクを考えて検証しておく必要があります。 その意味でも、転職をするとしても、収入が途絶える期間がないように在職中から転職活動を始め、退職は転職が決まってからにするのがおすすめです。 40代の転職でも、転職により年収アップを実現する方もいらっしゃいますが、現状維持も難しい方も多くいらっしゃいます。もし自分の希望を叶えるために年収が下がってしまうとしたら、いくらまでなら収入ダウンを許容できるのか、自分だけでなく家族のライフイベントも考慮しながら、中長期的な視野で検討しておきましょう。 家族の理解は得られるか? 結婚をしている方の場合、この年代で今の会社を辞めることは、家族にも大きく影響します。収入はもちろん、働き方が変われば、生活パターンへの影響もあるからです。また、それまで有名企業や大手企業に勤めていた場合は、パートナーも福利厚生を始め、様々な恩恵を受けています。会社を辞めて、その恩恵も失うことにもなれば、それに対する抵抗感もあるでしょう。 このように40代で結婚をしている方の場合、「会社を辞める」ことがもたらす家族への影響が大きいからこそ、辞めることに対し家族の理解が得られないケースがよくあります。内定をもらってからご家族に相談する方もいますが、その時点で大反対されて泣く泣く内定を断る…という方も少なくありません。 そのような事態を避けるためにも、様々なご家族の事情もあるかとは思いますが、辞めたいという気持ちが固まった時点でご家族に伝え、理解を得ておくことをおすすめします。 もし反対された場合、それに自分が納得できればよいのですが、自分の思いを我慢してしまうと、その影響はこれから先20年前後も続く仕事人生に影響してしまいます。それを考えれば、ここで自分の気持ちを我慢するのは良い選択とは言い難いでしょう。 実際にはご家族からの反対があったために、転職を諦める方も多いのが事実ですが、相手の気持ちも想像しながら、転職したいという思いに反対されないようにコミュニケーションをしていけばスムーズに進むこともあります。相手の気持ちを理解し、相手に転職への思いを理解してしまうコミュニケーションのポイントは、こちらのコラムで紹介しています。適切なコミュニケーションで、「辞めたい」気持ちへの家族の理解を早めに得ておきましょう。 https://career-lab.biz/column/%e5%ab%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e2%81%89%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%81%ab%e5%8f%8d%e5%af%be%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a6%bb%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%90%91%e3%81%8d%e5%90%88%e3%81%84/ 3.転職活動をする前に知っておきたいこと 転職を決める前にもう一度考え直した結果、やはり仕事を辞めたい理由が転職をしなければ解決できないものであるならば、転職活動はできるだけ早くスタートしましょう。厚生労働省が、平成19年に求人の募集・採用時に年齢制限を設けることや年齢を理由に採否を決めることを禁止したとはいえ、実際には年齢が上がるほど、転職の難易度は高くなってしまうからです。 転職活動を成功させるためにも、転職活動を始める前に40代の人材に対して企業からどのようなニーズがあるのかを確認しておきましょう。 40代の転職で企業から求められるもの 20代や30代は、その成長性を見込んだポテンシャル採用や、次期マネージャー候補としての採用を検討しますが、40代を採用したい場合には、専門性と経験を兼ね備えたマネージャーや管理職、経営幹部としての採用ニーズがほとんどです。ただし、慢性的な人手不足で、20代や30代だけでは必要な人材が採用できない業界・企業では、メンバークラスでも40代を採用するケースもあるでしょう。 いずれにしても、40代の転職で企業が求めるのものは即戦力です。それには、企画力や提案力、プレゼンテーション力、そしてリーダーシップやマネジメント力などを期待されます。すべてを兼ね備える必要はないですが、自分の強みは何なのかをより明確にし、それを必要としている企業を見極めていく必要があります。 また、40代の転職では新しい企業文化に対応できる柔軟性やコミュニケーション能力も求められます。40代を採用する場合、企業は「それまでの経験や知識から、新しい企業、社風に馴染めないのではないか」ということを懸念しますので、新たな環境への意欲や柔軟性が面接で伝わるようにすることも、転職成功のポイントになります。 40代の転職の現実 企業は40代の人材に即戦力を求めているので、高い専門性、実績などがあれば求人はあり、年収アップを実現される方もいらっしゃいます。 しかし、そうでない場合は20代、30代に比べると求人数は少なく、転職活動は長期化する傾向があります。それは、 ・年功序列型の賃金体系が残る企業では、職務能力やスキルなどが同じならば、より労働コストを押さえられること・採用後に自社で長く活躍してくれることを期待していること・新しい企業文化を受け入れる柔軟性を持っていそうなこと などの理由から、同じ職務能力やスキルならば、より若い人材を採用したいと考えるからです。 転職活動は限られた求人から選択することになるため、自分の希望条件にこだわり続けると転職活動が長期化してしまいます。人はどうしても「待っていたら、そのうち自分の希望に合う求人が出てくるのではないか」と期待してしまうのですが、その「自分に合う求人」が見つかる可能性は、20代や30代の頃に比べると格段に低く、出てこない可能性も極めて高いと認識しておきましょう。 また、退職後に転職活動が長期化してしまうと、何もしていない「ブランク期間」が長くなってしまいます。ブランク期間が長いと 「転職活動を計画性がない(=仕事能力にも問題がある)のではないか」「理想が高すぎるのではないか」「何か問題がある人だから、他の企業でも採用されなかったのではないか」 と懸念され、40代の転職活動では非常に不利になってしまいますのでので、よほどの事情がない限り、転職活動は仕事を続けながら行うことがおすすめです。 4.40代の転職活動を成功させるために 40代の転職を取り巻く環境は、厳しいものではありますが、転職を成功させている方はいらっしゃいます。これからいい転職をするために、そのような方が実践されている「40代の転職を成功させるために大切な3つのこと」をご紹介します。 経験を活かし、できることを明確にする 専門性や経験が求められる40代の転職では、自分の経験や専門性を、実績をベースにできるかぎり明確にすることが転職成功のカギとなります。 それがわかりやすく企業に伝われば伝わるほど、自分にとっても、自分の強みを活かすことができ、それを高く評価してくれる企業と出会いやすくなります。 20代や30代と異なり、経験が長い分だけ職務経歴書に記載することが多くなるので、転職活動では企業研究を入念に行い、自分の今までの経験を全部伝えようとするのではなく、「応募企業の強みや業界でのポジションなどを理解し、企業のニーズに沿った強み」をわかりやすくアピールする職務経歴書を作成するようにしましょう。 志望動機を具体的に、現実的に 40代の転職をスムーズに進めるためには、志望動機もより重要です。もちろん志望動機はどの年代でも重要なものですが、特に40代の志望動機では、 ・なぜその応募企業を選んだのか。・その企業で今までの経験をどのように活かし、何を実現したいのか。・今までの経験を活かし、会社に対し、どんな貢献ができるのか。 について、これまでの経験やスキルをもとにより具体的に、そして現実的に記載することが必要です。20代のころは「どの企業にも転用できるような志望動機」で書類選考を通過することができても、40代では通用しません。 1社1社、しっかり企業研究を行い、その企業に合わせ、「このような考えを持っているならば、うちで働くのが一番だし、活躍してくれそうだ」と企業が思うような、各社毎にオリジナルの志望動機をまとめましょう。 「転職で実現したいこと」の優先順位を明確にする 40代になると、自分の今までの経験、実績、報酬に対する自信から、転職条件へのこだわりも無意識のうちに強くなってしまいます。また、家庭などの事情から「これは譲れない」という条件もいつの間にか多くなりがちです。 全てを叶えることができれば理想的ですが、求人数が少ない40代の転職では、こだわりの条件が多ければ多いほど、転職実現度は低くなります。そのため、今の状況を変えたいのであれば、「これだけは譲れない条件」を1~2つ程度明確にし、それ以外は柔軟に検討する姿勢が極めて重要です。 たとえば、「年収だけは維持したい」という場合には、年収が維持できるならば、業界や企業規模、知名度、仕事内容などにはこだわらずに求人を探し、その会社、その求人の良いところを見つけるようにして、自分の選択肢を広げていきましょう。 応募する求人の仕事を具体的にイメージし、面接で確認する また、転職活動では「応募する求人の仕事内容を遂行している自分」をできる限り具体的にイメージし、面接で気になることを積極的に質問して確認しましょう。 このことには2つのメリットがあります。1つめは、きちんと仕事内容を確認しておくことで、業務への理解が深まり、入社後に「こんなはずではなかった」とギャップを感じるリスクを小さくできることです。40代の転職は、多くの方にとっておそらく最後の転職になります。ここでの失敗を避けるためにも、面接でイメージと現実のギャップを埋めておくことはとても重要です。 2つめは、その積極的な姿勢が企業から評価対象になることです。適切な質問は、前向きな意欲の表れとして好印象につながります。また、質問次第では、それが仕事能力の裏付けとなり、高評価にもつながるでしょう。 5.40代からのキャリアの選択にプロのアドバイスを このように40代からのキャリアの選択は、20代や30代のころの転職よりもより計画的に、より深く今後のキャリアを考える必要があります。 経験も積み重なり、20代や30代のころに比べれば考慮すべきことも増えるからこそ、どのように情報を整理し、情報の取捨選択をしていけばよいか、一人ではなかなか難しいこともあるでしょう。 40代からのキャリア選択にこそ、プロのキャリアコンサルタントのサポートは効果的です。プロの力をうまく活用しながら、もうあと20年、気持ちよく仕事ができる選択を見つけていきましょう。 その他参考記事:40代で仕事辞めたい、疲れたと感じる女性必見!今すぐできる対処法とおすすめの仕事5選(ママキャンMamCamp)
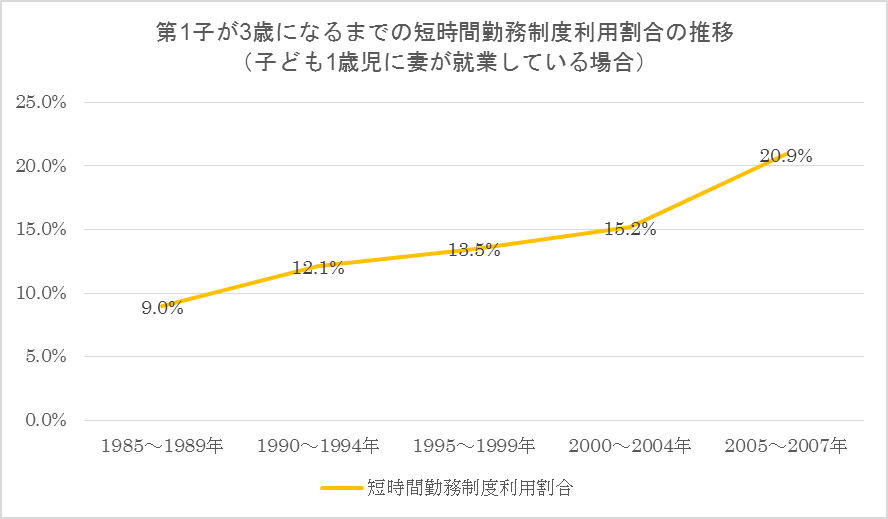
「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い
新卒入社から20年近い年月が過ぎ、でも定年まではあと20年近くある、「折り返し地点」ともいえる40代。このタイミングで、「このままでいいのか?」「この後残りの人生どんな生き方・働き方をしたいのか?」と改めて真剣に、キャリアを見つめ直す方も多いのではないのでしょうか。 しかし、その先の老後や家族のことを考えると、その選択で失敗したくない、リスクを極力抑えたいと思うのもこの年代ならではの本音ではないかと思います。そこで今回は、40代からのキャリアの選択で後悔しないために、ぜひ知っておきたいことをキャリアコンサルタントの視点でまとめました。 1. 40代が仕事を辞めたいと思う理由 会社を辞めたい理由を大別すると、どの年代も共通して以下のような理由が一般的です。 【仕事を辞めたい理由】 ・新たなチャレンジをしたい(仕事がつまらない)・評価に納得がいかない(自分の業績が評価されない)・人間関係(特に上司)に問題がある・会社の業績や、この会社での自分の将来に不安がある・働き方を変えたい 20代や30代では、待遇(給与、残業時間)への不満も本音の転職理由の上位に入りますが、待遇に不満があれば40代になる前に転職して状況を変えていることがほとんどですので、40代になって「仕事を辞めたい」と思う理由には、待遇以外の要因が大きくなってくるようです。 また、「働き方を変えたい」という理由も40代になると 「30代まではがむしゃらに働き、残業が多い仕事も厭わなかったけれど、もう少し仕事をペースを落としてプライベートの時間も大切にしたい」「自分の専門分野で独立をしたい」など、仕事人生の後半戦で自分が望む働き方をするために、一歩踏み出す方も多くいらっしゃいます。 いずれにしても、20代のころとは異なり、今の仕事を辞めるリスクも十分に理解している40代。だからこそ、本当に辞めたいと思うときには、上記のいくつかの理由が重なっていることが多いようです。 2. 転職を決める前に確認しておきたいこと ではその「仕事を辞めたい」と思う気持ちを大切に、新たなチャレンジを選んだほうがいいのか。それとも今の会社で、状況を改善する可能性を探ったほうがいいのか。その選択は難しいものですが、この先に後悔しないためにも「仕事を辞めたい」と思ったときには、次のような視点からもう一度客観的に状況を見直してみましょう。 辞めたい理由は、退職しないと本当に解決できないのか? 20代や30代とは違い、経験がある40代だからこそ、「辞めたい」と思った今の時点ですでにあらゆる状況改善の可能性を探り、改善が見込めないと思うからこそ「辞めたい」と考えていらっしゃるのではないかとは思います。しかしもう一度だけ、「辞めたい理由は、会社を辞めないと本当に解決できないのか?」と考えてみませんか。 たとえば、「評価に納得がいかない」という理由の場合、転職して自分の業績を評価してくれる環境に変わることもありますが、それが実現しないこともありえます。 また、「仕事がつまらない、マンネリ化している」という理由も、次の仕事は外から見たら面白そうだったけれど、実際にやってみたらそうでもない可能性もありますし、数年経てばまた「マンネリ」を感じてしまう可能性もあります。 「働き方を変えたい」など、会社を辞めなければ解決できない理由もありますが、なかにはこのように、転職だけで解決するとは限らない、根本的な解決は他にあるかもしれないケースもあります。 キャリア・コンサルティング・ラボに相談される方のお話を伺うと、「辞めたい本当の理由」は表面的な「辞めたい理由」と別のところにあることも実は多いです。また、「その辞めたい本当の理由は、辞めなくても解決できる」と気づき、転職することを辞める方もいらっしゃいます。 「辞めたい本当の理由」は、自分で考えているだけでは気づかず、他人に話をするうちに自分の考えが整理されて、本当の気持ちに気づくこともよくあります。このように「誰かに話す」ことの効果は大きいので、友人で話せる方がいらっしゃったら、ぜひ一度話をしてみてはいかがでしょうか。 この決断で経済的な問題が発生しないか? 40代になると、経済面も重要な判断材料になります。扶養対象となるご家族がいらっしゃる場合は、家族への経済的影響も考慮する必要があるでしょう。 そのため、「仕事を辞める」という決断で経済的な問題が発生しないか、もし発生するならばそれが対応できる範囲かどうかについては、あらゆるリスクを考えて検証しておく必要があります。 その意味でも、転職をするとしても、収入が途絶える期間がないように在職中から転職活動を始め、退職は転職が決まってからにするのがおすすめです。 40代の転職でも、転職により年収アップを実現する方もいらっしゃいますが、現状維持も難しい方も多くいらっしゃいます。もし自分の希望を叶えるために年収が下がってしまうとしたら、いくらまでなら収入ダウンを許容できるのか、自分だけでなく家族のライフイベントも考慮しながら、中長期的な視野で検討しておきましょう。 家族の理解は得られるか? 結婚をしている方の場合、この年代で今の会社を辞めることは、家族にも大きく影響します。収入はもちろん、働き方が変われば、生活パターンへの影響もあるからです。また、それまで有名企業や大手企業に勤めていた場合は、パートナーも福利厚生を始め、様々な恩恵を受けています。会社を辞めて、その恩恵も失うことにもなれば、それに対する抵抗感もあるでしょう。 このように40代で結婚をしている方の場合、「会社を辞める」ことがもたらす家族への影響が大きいからこそ、辞めることに対し家族の理解が得られないケースがよくあります。内定をもらってからご家族に相談する方もいますが、その時点で大反対されて泣く泣く内定を断る…という方も少なくありません。 そのような事態を避けるためにも、様々なご家族の事情もあるかとは思いますが、辞めたいという気持ちが固まった時点でご家族に伝え、理解を得ておくことをおすすめします。 もし反対された場合、それに自分が納得できればよいのですが、自分の思いを我慢してしまうと、その影響はこれから先20年前後も続く仕事人生に影響してしまいます。それを考えれば、ここで自分の気持ちを我慢するのは良い選択とは言い難いでしょう。 実際にはご家族からの反対があったために、転職を諦める方も多いのが事実ですが、相手の気持ちも想像しながら、転職したいという思いに反対されないようにコミュニケーションをしていけばスムーズに進むこともあります。相手の気持ちを理解し、相手に転職への思いを理解してしまうコミュニケーションのポイントは、こちらのコラムで紹介しています。適切なコミュニケーションで、「辞めたい」気持ちへの家族の理解を早めに得ておきましょう。 https://career-lab.biz/column/%e5%ab%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e2%81%89%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%81%ab%e5%8f%8d%e5%af%be%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a6%bb%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%90%91%e3%81%8d%e5%90%88%e3%81%84/ 3.転職活動をする前に知っておきたいこと 転職を決める前にもう一度考え直した結果、やはり仕事を辞めたい理由が転職をしなければ解決できないものであるならば、転職活動はできるだけ早くスタートしましょう。厚生労働省が、平成19年に求人の募集・採用時に年齢制限を設けることや年齢を理由に採否を決めることを禁止したとはいえ、実際には年齢が上がるほど、転職の難易度は高くなってしまうからです。 転職活動を成功させるためにも、転職活動を始める前に40代の人材に対して企業からどのようなニーズがあるのかを確認しておきましょう。 40代の転職で企業から求められるもの 20代や30代は、その成長性を見込んだポテンシャル採用や、次期マネージャー候補としての採用を検討しますが、40代を採用したい場合には、専門性と経験を兼ね備えたマネージャーや管理職、経営幹部としての採用ニーズがほとんどです。ただし、慢性的な人手不足で、20代や30代だけでは必要な人材が採用できない業界・企業では、メンバークラスでも40代を採用するケースもあるでしょう。 いずれにしても、40代の転職で企業が求めるのものは即戦力です。それには、企画力や提案力、プレゼンテーション力、そしてリーダーシップやマネジメント力などを期待されます。すべてを兼ね備える必要はないですが、自分の強みは何なのかをより明確にし、それを必要としている企業を見極めていく必要があります。 また、40代の転職では新しい企業文化に対応できる柔軟性やコミュニケーション能力も求められます。40代を採用する場合、企業は「それまでの経験や知識から、新しい企業、社風に馴染めないのではないか」ということを懸念しますので、新たな環境への意欲や柔軟性が面接で伝わるようにすることも、転職成功のポイントになります。 40代の転職の現実 企業は40代の人材に即戦力を求めているので、高い専門性、実績などがあれば求人はあり、年収アップを実現される方もいらっしゃいます。 しかし、そうでない場合は20代、30代に比べると求人数は少なく、転職活動は長期化する傾向があります。それは、 ・年功序列型の賃金体系が残る企業では、職務能力やスキルなどが同じならば、より労働コストを押さえられること・採用後に自社で長く活躍してくれることを期待していること・新しい企業文化を受け入れる柔軟性を持っていそうなこと などの理由から、同じ職務能力やスキルならば、より若い人材を採用したいと考えるからです。 転職活動は限られた求人から選択することになるため、自分の希望条件にこだわり続けると転職活動が長期化してしまいます。人はどうしても「待っていたら、そのうち自分の希望に合う求人が出てくるのではないか」と期待してしまうのですが、その「自分に合う求人」が見つかる可能性は、20代や30代の頃に比べると格段に低く、出てこない可能性も極めて高いと認識しておきましょう。 また、退職後に転職活動が長期化してしまうと、何もしていない「ブランク期間」が長くなってしまいます。ブランク期間が長いと 「転職活動を計画性がない(=仕事能力にも問題がある)のではないか」「理想が高すぎるのではないか」「何か問題がある人だから、他の企業でも採用されなかったのではないか」 と懸念され、40代の転職活動では非常に不利になってしまいますのでので、よほどの事情がない限り、転職活動は仕事を続けながら行うことがおすすめです。 4.40代の転職活動を成功させるために 40代の転職を取り巻く環境は、厳しいものではありますが、転職を成功させている方はいらっしゃいます。これからいい転職をするために、そのような方が実践されている「40代の転職を成功させるために大切な3つのこと」をご紹介します。 経験を活かし、できることを明確にする 専門性や経験が求められる40代の転職では、自分の経験や専門性を、実績をベースにできるかぎり明確にすることが転職成功のカギとなります。 それがわかりやすく企業に伝われば伝わるほど、自分にとっても、自分の強みを活かすことができ、それを高く評価してくれる企業と出会いやすくなります。 20代や30代と異なり、経験が長い分だけ職務経歴書に記載することが多くなるので、転職活動では企業研究を入念に行い、自分の今までの経験を全部伝えようとするのではなく、「応募企業の強みや業界でのポジションなどを理解し、企業のニーズに沿った強み」をわかりやすくアピールする職務経歴書を作成するようにしましょう。 志望動機を具体的に、現実的に 40代の転職をスムーズに進めるためには、志望動機もより重要です。もちろん志望動機はどの年代でも重要なものですが、特に40代の志望動機では、 ・なぜその応募企業を選んだのか。・その企業で今までの経験をどのように活かし、何を実現したいのか。・今までの経験を活かし、会社に対し、どんな貢献ができるのか。 について、これまでの経験やスキルをもとにより具体的に、そして現実的に記載することが必要です。20代のころは「どの企業にも転用できるような志望動機」で書類選考を通過することができても、40代では通用しません。 1社1社、しっかり企業研究を行い、その企業に合わせ、「このような考えを持っているならば、うちで働くのが一番だし、活躍してくれそうだ」と企業が思うような、各社毎にオリジナルの志望動機をまとめましょう。 「転職で実現したいこと」の優先順位を明確にする 40代になると、自分の今までの経験、実績、報酬に対する自信から、転職条件へのこだわりも無意識のうちに強くなってしまいます。また、家庭などの事情から「これは譲れない」という条件もいつの間にか多くなりがちです。 全てを叶えることができれば理想的ですが、求人数が少ない40代の転職では、こだわりの条件が多ければ多いほど、転職実現度は低くなります。そのため、今の状況を変えたいのであれば、「これだけは譲れない条件」を1~2つ程度明確にし、それ以外は柔軟に検討する姿勢が極めて重要です。 たとえば、「年収だけは維持したい」という場合には、年収が維持できるならば、業界や企業規模、知名度、仕事内容などにはこだわらずに求人を探し、その会社、その求人の良いところを見つけるようにして、自分の選択肢を広げていきましょう。 応募する求人の仕事を具体的にイメージし、面接で確認する また、転職活動では「応募する求人の仕事内容を遂行している自分」をできる限り具体的にイメージし、面接で気になることを積極的に質問して確認しましょう。 このことには2つのメリットがあります。1つめは、きちんと仕事内容を確認しておくことで、業務への理解が深まり、入社後に「こんなはずではなかった」とギャップを感じるリスクを小さくできることです。40代の転職は、多くの方にとっておそらく最後の転職になります。ここでの失敗を避けるためにも、面接でイメージと現実のギャップを埋めておくことはとても重要です。 2つめは、その積極的な姿勢が企業から評価対象になることです。適切な質問は、前向きな意欲の表れとして好印象につながります。また、質問次第では、それが仕事能力の裏付けとなり、高評価にもつながるでしょう。 5.40代からのキャリアの選択にプロのアドバイスを このように40代からのキャリアの選択は、20代や30代のころの転職よりもより計画的に、より深く今後のキャリアを考える必要があります。 経験も積み重なり、20代や30代のころに比べれば考慮すべきことも増えるからこそ、どのように情報を整理し、情報の取捨選択をしていけばよいか、一人ではなかなか難しいこともあるでしょう。 40代からのキャリア選択にこそ、プロのキャリアコンサルタントのサポートは効果的です。プロの力をうまく活用しながら、もうあと20年、気持ちよく仕事ができる選択を見つけていきましょう。 その他参考記事:40代で仕事辞めたい、疲れたと感じる女性必見!今すぐできる対処法とおすすめの仕事5選(ママキャンMamCamp)

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?
新卒入社から20年近い年月が過ぎ、でも定年まではあと20年近くある、「折り返し地点」ともいえる40代。このタイミングで、「このままでいいのか?」「この後残りの人生どんな生き方・働き方をしたいのか?」と改めて真剣に、キャリアを見つめ直す方も多いのではないのでしょうか。 しかし、その先の老後や家族のことを考えると、その選択で失敗したくない、リスクを極力抑えたいと思うのもこの年代ならではの本音ではないかと思います。そこで今回は、40代からのキャリアの選択で後悔しないために、ぜひ知っておきたいことをキャリアコンサルタントの視点でまとめました。 1. 40代が仕事を辞めたいと思う理由 会社を辞めたい理由を大別すると、どの年代も共通して以下のような理由が一般的です。 【仕事を辞めたい理由】 ・新たなチャレンジをしたい(仕事がつまらない)・評価に納得がいかない(自分の業績が評価されない)・人間関係(特に上司)に問題がある・会社の業績や、この会社での自分の将来に不安がある・働き方を変えたい 20代や30代では、待遇(給与、残業時間)への不満も本音の転職理由の上位に入りますが、待遇に不満があれば40代になる前に転職して状況を変えていることがほとんどですので、40代になって「仕事を辞めたい」と思う理由には、待遇以外の要因が大きくなってくるようです。 また、「働き方を変えたい」という理由も40代になると 「30代まではがむしゃらに働き、残業が多い仕事も厭わなかったけれど、もう少し仕事をペースを落としてプライベートの時間も大切にしたい」「自分の専門分野で独立をしたい」など、仕事人生の後半戦で自分が望む働き方をするために、一歩踏み出す方も多くいらっしゃいます。 いずれにしても、20代のころとは異なり、今の仕事を辞めるリスクも十分に理解している40代。だからこそ、本当に辞めたいと思うときには、上記のいくつかの理由が重なっていることが多いようです。 2. 転職を決める前に確認しておきたいこと ではその「仕事を辞めたい」と思う気持ちを大切に、新たなチャレンジを選んだほうがいいのか。それとも今の会社で、状況を改善する可能性を探ったほうがいいのか。その選択は難しいものですが、この先に後悔しないためにも「仕事を辞めたい」と思ったときには、次のような視点からもう一度客観的に状況を見直してみましょう。 辞めたい理由は、退職しないと本当に解決できないのか? 20代や30代とは違い、経験がある40代だからこそ、「辞めたい」と思った今の時点ですでにあらゆる状況改善の可能性を探り、改善が見込めないと思うからこそ「辞めたい」と考えていらっしゃるのではないかとは思います。しかしもう一度だけ、「辞めたい理由は、会社を辞めないと本当に解決できないのか?」と考えてみませんか。 たとえば、「評価に納得がいかない」という理由の場合、転職して自分の業績を評価してくれる環境に変わることもありますが、それが実現しないこともありえます。 また、「仕事がつまらない、マンネリ化している」という理由も、次の仕事は外から見たら面白そうだったけれど、実際にやってみたらそうでもない可能性もありますし、数年経てばまた「マンネリ」を感じてしまう可能性もあります。 「働き方を変えたい」など、会社を辞めなければ解決できない理由もありますが、なかにはこのように、転職だけで解決するとは限らない、根本的な解決は他にあるかもしれないケースもあります。 キャリア・コンサルティング・ラボに相談される方のお話を伺うと、「辞めたい本当の理由」は表面的な「辞めたい理由」と別のところにあることも実は多いです。また、「その辞めたい本当の理由は、辞めなくても解決できる」と気づき、転職することを辞める方もいらっしゃいます。 「辞めたい本当の理由」は、自分で考えているだけでは気づかず、他人に話をするうちに自分の考えが整理されて、本当の気持ちに気づくこともよくあります。このように「誰かに話す」ことの効果は大きいので、友人で話せる方がいらっしゃったら、ぜひ一度話をしてみてはいかがでしょうか。 この決断で経済的な問題が発生しないか? 40代になると、経済面も重要な判断材料になります。扶養対象となるご家族がいらっしゃる場合は、家族への経済的影響も考慮する必要があるでしょう。 そのため、「仕事を辞める」という決断で経済的な問題が発生しないか、もし発生するならばそれが対応できる範囲かどうかについては、あらゆるリスクを考えて検証しておく必要があります。 その意味でも、転職をするとしても、収入が途絶える期間がないように在職中から転職活動を始め、退職は転職が決まってからにするのがおすすめです。 40代の転職でも、転職により年収アップを実現する方もいらっしゃいますが、現状維持も難しい方も多くいらっしゃいます。もし自分の希望を叶えるために年収が下がってしまうとしたら、いくらまでなら収入ダウンを許容できるのか、自分だけでなく家族のライフイベントも考慮しながら、中長期的な視野で検討しておきましょう。 家族の理解は得られるか? 結婚をしている方の場合、この年代で今の会社を辞めることは、家族にも大きく影響します。収入はもちろん、働き方が変われば、生活パターンへの影響もあるからです。また、それまで有名企業や大手企業に勤めていた場合は、パートナーも福利厚生を始め、様々な恩恵を受けています。会社を辞めて、その恩恵も失うことにもなれば、それに対する抵抗感もあるでしょう。 このように40代で結婚をしている方の場合、「会社を辞める」ことがもたらす家族への影響が大きいからこそ、辞めることに対し家族の理解が得られないケースがよくあります。内定をもらってからご家族に相談する方もいますが、その時点で大反対されて泣く泣く内定を断る…という方も少なくありません。 そのような事態を避けるためにも、様々なご家族の事情もあるかとは思いますが、辞めたいという気持ちが固まった時点でご家族に伝え、理解を得ておくことをおすすめします。 もし反対された場合、それに自分が納得できればよいのですが、自分の思いを我慢してしまうと、その影響はこれから先20年前後も続く仕事人生に影響してしまいます。それを考えれば、ここで自分の気持ちを我慢するのは良い選択とは言い難いでしょう。 実際にはご家族からの反対があったために、転職を諦める方も多いのが事実ですが、相手の気持ちも想像しながら、転職したいという思いに反対されないようにコミュニケーションをしていけばスムーズに進むこともあります。相手の気持ちを理解し、相手に転職への思いを理解してしまうコミュニケーションのポイントは、こちらのコラムで紹介しています。適切なコミュニケーションで、「辞めたい」気持ちへの家族の理解を早めに得ておきましょう。 https://career-lab.biz/column/%e5%ab%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e2%81%89%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%81%ab%e5%8f%8d%e5%af%be%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a6%bb%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%90%91%e3%81%8d%e5%90%88%e3%81%84/ 3.転職活動をする前に知っておきたいこと 転職を決める前にもう一度考え直した結果、やはり仕事を辞めたい理由が転職をしなければ解決できないものであるならば、転職活動はできるだけ早くスタートしましょう。厚生労働省が、平成19年に求人の募集・採用時に年齢制限を設けることや年齢を理由に採否を決めることを禁止したとはいえ、実際には年齢が上がるほど、転職の難易度は高くなってしまうからです。 転職活動を成功させるためにも、転職活動を始める前に40代の人材に対して企業からどのようなニーズがあるのかを確認しておきましょう。 40代の転職で企業から求められるもの 20代や30代は、その成長性を見込んだポテンシャル採用や、次期マネージャー候補としての採用を検討しますが、40代を採用したい場合には、専門性と経験を兼ね備えたマネージャーや管理職、経営幹部としての採用ニーズがほとんどです。ただし、慢性的な人手不足で、20代や30代だけでは必要な人材が採用できない業界・企業では、メンバークラスでも40代を採用するケースもあるでしょう。 いずれにしても、40代の転職で企業が求めるのものは即戦力です。それには、企画力や提案力、プレゼンテーション力、そしてリーダーシップやマネジメント力などを期待されます。すべてを兼ね備える必要はないですが、自分の強みは何なのかをより明確にし、それを必要としている企業を見極めていく必要があります。 また、40代の転職では新しい企業文化に対応できる柔軟性やコミュニケーション能力も求められます。40代を採用する場合、企業は「それまでの経験や知識から、新しい企業、社風に馴染めないのではないか」ということを懸念しますので、新たな環境への意欲や柔軟性が面接で伝わるようにすることも、転職成功のポイントになります。 40代の転職の現実 企業は40代の人材に即戦力を求めているので、高い専門性、実績などがあれば求人はあり、年収アップを実現される方もいらっしゃいます。 しかし、そうでない場合は20代、30代に比べると求人数は少なく、転職活動は長期化する傾向があります。それは、 ・年功序列型の賃金体系が残る企業では、職務能力やスキルなどが同じならば、より労働コストを押さえられること・採用後に自社で長く活躍してくれることを期待していること・新しい企業文化を受け入れる柔軟性を持っていそうなこと などの理由から、同じ職務能力やスキルならば、より若い人材を採用したいと考えるからです。 転職活動は限られた求人から選択することになるため、自分の希望条件にこだわり続けると転職活動が長期化してしまいます。人はどうしても「待っていたら、そのうち自分の希望に合う求人が出てくるのではないか」と期待してしまうのですが、その「自分に合う求人」が見つかる可能性は、20代や30代の頃に比べると格段に低く、出てこない可能性も極めて高いと認識しておきましょう。 また、退職後に転職活動が長期化してしまうと、何もしていない「ブランク期間」が長くなってしまいます。ブランク期間が長いと 「転職活動を計画性がない(=仕事能力にも問題がある)のではないか」「理想が高すぎるのではないか」「何か問題がある人だから、他の企業でも採用されなかったのではないか」 と懸念され、40代の転職活動では非常に不利になってしまいますのでので、よほどの事情がない限り、転職活動は仕事を続けながら行うことがおすすめです。 4.40代の転職活動を成功させるために 40代の転職を取り巻く環境は、厳しいものではありますが、転職を成功させている方はいらっしゃいます。これからいい転職をするために、そのような方が実践されている「40代の転職を成功させるために大切な3つのこと」をご紹介します。 経験を活かし、できることを明確にする 専門性や経験が求められる40代の転職では、自分の経験や専門性を、実績をベースにできるかぎり明確にすることが転職成功のカギとなります。 それがわかりやすく企業に伝われば伝わるほど、自分にとっても、自分の強みを活かすことができ、それを高く評価してくれる企業と出会いやすくなります。 20代や30代と異なり、経験が長い分だけ職務経歴書に記載することが多くなるので、転職活動では企業研究を入念に行い、自分の今までの経験を全部伝えようとするのではなく、「応募企業の強みや業界でのポジションなどを理解し、企業のニーズに沿った強み」をわかりやすくアピールする職務経歴書を作成するようにしましょう。 志望動機を具体的に、現実的に 40代の転職をスムーズに進めるためには、志望動機もより重要です。もちろん志望動機はどの年代でも重要なものですが、特に40代の志望動機では、 ・なぜその応募企業を選んだのか。・その企業で今までの経験をどのように活かし、何を実現したいのか。・今までの経験を活かし、会社に対し、どんな貢献ができるのか。 について、これまでの経験やスキルをもとにより具体的に、そして現実的に記載することが必要です。20代のころは「どの企業にも転用できるような志望動機」で書類選考を通過することができても、40代では通用しません。 1社1社、しっかり企業研究を行い、その企業に合わせ、「このような考えを持っているならば、うちで働くのが一番だし、活躍してくれそうだ」と企業が思うような、各社毎にオリジナルの志望動機をまとめましょう。 「転職で実現したいこと」の優先順位を明確にする 40代になると、自分の今までの経験、実績、報酬に対する自信から、転職条件へのこだわりも無意識のうちに強くなってしまいます。また、家庭などの事情から「これは譲れない」という条件もいつの間にか多くなりがちです。 全てを叶えることができれば理想的ですが、求人数が少ない40代の転職では、こだわりの条件が多ければ多いほど、転職実現度は低くなります。そのため、今の状況を変えたいのであれば、「これだけは譲れない条件」を1~2つ程度明確にし、それ以外は柔軟に検討する姿勢が極めて重要です。 たとえば、「年収だけは維持したい」という場合には、年収が維持できるならば、業界や企業規模、知名度、仕事内容などにはこだわらずに求人を探し、その会社、その求人の良いところを見つけるようにして、自分の選択肢を広げていきましょう。 応募する求人の仕事を具体的にイメージし、面接で確認する また、転職活動では「応募する求人の仕事内容を遂行している自分」をできる限り具体的にイメージし、面接で気になることを積極的に質問して確認しましょう。 このことには2つのメリットがあります。1つめは、きちんと仕事内容を確認しておくことで、業務への理解が深まり、入社後に「こんなはずではなかった」とギャップを感じるリスクを小さくできることです。40代の転職は、多くの方にとっておそらく最後の転職になります。ここでの失敗を避けるためにも、面接でイメージと現実のギャップを埋めておくことはとても重要です。 2つめは、その積極的な姿勢が企業から評価対象になることです。適切な質問は、前向きな意欲の表れとして好印象につながります。また、質問次第では、それが仕事能力の裏付けとなり、高評価にもつながるでしょう。 5.40代からのキャリアの選択にプロのアドバイスを このように40代からのキャリアの選択は、20代や30代のころの転職よりもより計画的に、より深く今後のキャリアを考える必要があります。 経験も積み重なり、20代や30代のころに比べれば考慮すべきことも増えるからこそ、どのように情報を整理し、情報の取捨選択をしていけばよいか、一人ではなかなか難しいこともあるでしょう。 40代からのキャリア選択にこそ、プロのキャリアコンサルタントのサポートは効果的です。プロの力をうまく活用しながら、もうあと20年、気持ちよく仕事ができる選択を見つけていきましょう。 その他参考記事:40代で仕事辞めたい、疲れたと感じる女性必見!今すぐできる対処法とおすすめの仕事5選(ママキャンMamCamp)

仕事がわからない時の聞き方・暗黙のルールを確認しよう
新卒入社から20年近い年月が過ぎ、でも定年まではあと20年近くある、「折り返し地点」ともいえる40代。このタイミングで、「このままでいいのか?」「この後残りの人生どんな生き方・働き方をしたいのか?」と改めて真剣に、キャリアを見つめ直す方も多いのではないのでしょうか。 しかし、その先の老後や家族のことを考えると、その選択で失敗したくない、リスクを極力抑えたいと思うのもこの年代ならではの本音ではないかと思います。そこで今回は、40代からのキャリアの選択で後悔しないために、ぜひ知っておきたいことをキャリアコンサルタントの視点でまとめました。 1. 40代が仕事を辞めたいと思う理由 会社を辞めたい理由を大別すると、どの年代も共通して以下のような理由が一般的です。 【仕事を辞めたい理由】 ・新たなチャレンジをしたい(仕事がつまらない)・評価に納得がいかない(自分の業績が評価されない)・人間関係(特に上司)に問題がある・会社の業績や、この会社での自分の将来に不安がある・働き方を変えたい 20代や30代では、待遇(給与、残業時間)への不満も本音の転職理由の上位に入りますが、待遇に不満があれば40代になる前に転職して状況を変えていることがほとんどですので、40代になって「仕事を辞めたい」と思う理由には、待遇以外の要因が大きくなってくるようです。 また、「働き方を変えたい」という理由も40代になると 「30代まではがむしゃらに働き、残業が多い仕事も厭わなかったけれど、もう少し仕事をペースを落としてプライベートの時間も大切にしたい」「自分の専門分野で独立をしたい」など、仕事人生の後半戦で自分が望む働き方をするために、一歩踏み出す方も多くいらっしゃいます。 いずれにしても、20代のころとは異なり、今の仕事を辞めるリスクも十分に理解している40代。だからこそ、本当に辞めたいと思うときには、上記のいくつかの理由が重なっていることが多いようです。 2. 転職を決める前に確認しておきたいこと ではその「仕事を辞めたい」と思う気持ちを大切に、新たなチャレンジを選んだほうがいいのか。それとも今の会社で、状況を改善する可能性を探ったほうがいいのか。その選択は難しいものですが、この先に後悔しないためにも「仕事を辞めたい」と思ったときには、次のような視点からもう一度客観的に状況を見直してみましょう。 辞めたい理由は、退職しないと本当に解決できないのか? 20代や30代とは違い、経験がある40代だからこそ、「辞めたい」と思った今の時点ですでにあらゆる状況改善の可能性を探り、改善が見込めないと思うからこそ「辞めたい」と考えていらっしゃるのではないかとは思います。しかしもう一度だけ、「辞めたい理由は、会社を辞めないと本当に解決できないのか?」と考えてみませんか。 たとえば、「評価に納得がいかない」という理由の場合、転職して自分の業績を評価してくれる環境に変わることもありますが、それが実現しないこともありえます。 また、「仕事がつまらない、マンネリ化している」という理由も、次の仕事は外から見たら面白そうだったけれど、実際にやってみたらそうでもない可能性もありますし、数年経てばまた「マンネリ」を感じてしまう可能性もあります。 「働き方を変えたい」など、会社を辞めなければ解決できない理由もありますが、なかにはこのように、転職だけで解決するとは限らない、根本的な解決は他にあるかもしれないケースもあります。 キャリア・コンサルティング・ラボに相談される方のお話を伺うと、「辞めたい本当の理由」は表面的な「辞めたい理由」と別のところにあることも実は多いです。また、「その辞めたい本当の理由は、辞めなくても解決できる」と気づき、転職することを辞める方もいらっしゃいます。 「辞めたい本当の理由」は、自分で考えているだけでは気づかず、他人に話をするうちに自分の考えが整理されて、本当の気持ちに気づくこともよくあります。このように「誰かに話す」ことの効果は大きいので、友人で話せる方がいらっしゃったら、ぜひ一度話をしてみてはいかがでしょうか。 この決断で経済的な問題が発生しないか? 40代になると、経済面も重要な判断材料になります。扶養対象となるご家族がいらっしゃる場合は、家族への経済的影響も考慮する必要があるでしょう。 そのため、「仕事を辞める」という決断で経済的な問題が発生しないか、もし発生するならばそれが対応できる範囲かどうかについては、あらゆるリスクを考えて検証しておく必要があります。 その意味でも、転職をするとしても、収入が途絶える期間がないように在職中から転職活動を始め、退職は転職が決まってからにするのがおすすめです。 40代の転職でも、転職により年収アップを実現する方もいらっしゃいますが、現状維持も難しい方も多くいらっしゃいます。もし自分の希望を叶えるために年収が下がってしまうとしたら、いくらまでなら収入ダウンを許容できるのか、自分だけでなく家族のライフイベントも考慮しながら、中長期的な視野で検討しておきましょう。 家族の理解は得られるか? 結婚をしている方の場合、この年代で今の会社を辞めることは、家族にも大きく影響します。収入はもちろん、働き方が変われば、生活パターンへの影響もあるからです。また、それまで有名企業や大手企業に勤めていた場合は、パートナーも福利厚生を始め、様々な恩恵を受けています。会社を辞めて、その恩恵も失うことにもなれば、それに対する抵抗感もあるでしょう。 このように40代で結婚をしている方の場合、「会社を辞める」ことがもたらす家族への影響が大きいからこそ、辞めることに対し家族の理解が得られないケースがよくあります。内定をもらってからご家族に相談する方もいますが、その時点で大反対されて泣く泣く内定を断る…という方も少なくありません。 そのような事態を避けるためにも、様々なご家族の事情もあるかとは思いますが、辞めたいという気持ちが固まった時点でご家族に伝え、理解を得ておくことをおすすめします。 もし反対された場合、それに自分が納得できればよいのですが、自分の思いを我慢してしまうと、その影響はこれから先20年前後も続く仕事人生に影響してしまいます。それを考えれば、ここで自分の気持ちを我慢するのは良い選択とは言い難いでしょう。 実際にはご家族からの反対があったために、転職を諦める方も多いのが事実ですが、相手の気持ちも想像しながら、転職したいという思いに反対されないようにコミュニケーションをしていけばスムーズに進むこともあります。相手の気持ちを理解し、相手に転職への思いを理解してしまうコミュニケーションのポイントは、こちらのコラムで紹介しています。適切なコミュニケーションで、「辞めたい」気持ちへの家族の理解を早めに得ておきましょう。 https://career-lab.biz/column/%e5%ab%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e2%81%89%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%81%ab%e5%8f%8d%e5%af%be%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a6%bb%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%90%91%e3%81%8d%e5%90%88%e3%81%84/ 3.転職活動をする前に知っておきたいこと 転職を決める前にもう一度考え直した結果、やはり仕事を辞めたい理由が転職をしなければ解決できないものであるならば、転職活動はできるだけ早くスタートしましょう。厚生労働省が、平成19年に求人の募集・採用時に年齢制限を設けることや年齢を理由に採否を決めることを禁止したとはいえ、実際には年齢が上がるほど、転職の難易度は高くなってしまうからです。 転職活動を成功させるためにも、転職活動を始める前に40代の人材に対して企業からどのようなニーズがあるのかを確認しておきましょう。 40代の転職で企業から求められるもの 20代や30代は、その成長性を見込んだポテンシャル採用や、次期マネージャー候補としての採用を検討しますが、40代を採用したい場合には、専門性と経験を兼ね備えたマネージャーや管理職、経営幹部としての採用ニーズがほとんどです。ただし、慢性的な人手不足で、20代や30代だけでは必要な人材が採用できない業界・企業では、メンバークラスでも40代を採用するケースもあるでしょう。 いずれにしても、40代の転職で企業が求めるのものは即戦力です。それには、企画力や提案力、プレゼンテーション力、そしてリーダーシップやマネジメント力などを期待されます。すべてを兼ね備える必要はないですが、自分の強みは何なのかをより明確にし、それを必要としている企業を見極めていく必要があります。 また、40代の転職では新しい企業文化に対応できる柔軟性やコミュニケーション能力も求められます。40代を採用する場合、企業は「それまでの経験や知識から、新しい企業、社風に馴染めないのではないか」ということを懸念しますので、新たな環境への意欲や柔軟性が面接で伝わるようにすることも、転職成功のポイントになります。 40代の転職の現実 企業は40代の人材に即戦力を求めているので、高い専門性、実績などがあれば求人はあり、年収アップを実現される方もいらっしゃいます。 しかし、そうでない場合は20代、30代に比べると求人数は少なく、転職活動は長期化する傾向があります。それは、 ・年功序列型の賃金体系が残る企業では、職務能力やスキルなどが同じならば、より労働コストを押さえられること・採用後に自社で長く活躍してくれることを期待していること・新しい企業文化を受け入れる柔軟性を持っていそうなこと などの理由から、同じ職務能力やスキルならば、より若い人材を採用したいと考えるからです。 転職活動は限られた求人から選択することになるため、自分の希望条件にこだわり続けると転職活動が長期化してしまいます。人はどうしても「待っていたら、そのうち自分の希望に合う求人が出てくるのではないか」と期待してしまうのですが、その「自分に合う求人」が見つかる可能性は、20代や30代の頃に比べると格段に低く、出てこない可能性も極めて高いと認識しておきましょう。 また、退職後に転職活動が長期化してしまうと、何もしていない「ブランク期間」が長くなってしまいます。ブランク期間が長いと 「転職活動を計画性がない(=仕事能力にも問題がある)のではないか」「理想が高すぎるのではないか」「何か問題がある人だから、他の企業でも採用されなかったのではないか」 と懸念され、40代の転職活動では非常に不利になってしまいますのでので、よほどの事情がない限り、転職活動は仕事を続けながら行うことがおすすめです。 4.40代の転職活動を成功させるために 40代の転職を取り巻く環境は、厳しいものではありますが、転職を成功させている方はいらっしゃいます。これからいい転職をするために、そのような方が実践されている「40代の転職を成功させるために大切な3つのこと」をご紹介します。 経験を活かし、できることを明確にする 専門性や経験が求められる40代の転職では、自分の経験や専門性を、実績をベースにできるかぎり明確にすることが転職成功のカギとなります。 それがわかりやすく企業に伝われば伝わるほど、自分にとっても、自分の強みを活かすことができ、それを高く評価してくれる企業と出会いやすくなります。 20代や30代と異なり、経験が長い分だけ職務経歴書に記載することが多くなるので、転職活動では企業研究を入念に行い、自分の今までの経験を全部伝えようとするのではなく、「応募企業の強みや業界でのポジションなどを理解し、企業のニーズに沿った強み」をわかりやすくアピールする職務経歴書を作成するようにしましょう。 志望動機を具体的に、現実的に 40代の転職をスムーズに進めるためには、志望動機もより重要です。もちろん志望動機はどの年代でも重要なものですが、特に40代の志望動機では、 ・なぜその応募企業を選んだのか。・その企業で今までの経験をどのように活かし、何を実現したいのか。・今までの経験を活かし、会社に対し、どんな貢献ができるのか。 について、これまでの経験やスキルをもとにより具体的に、そして現実的に記載することが必要です。20代のころは「どの企業にも転用できるような志望動機」で書類選考を通過することができても、40代では通用しません。 1社1社、しっかり企業研究を行い、その企業に合わせ、「このような考えを持っているならば、うちで働くのが一番だし、活躍してくれそうだ」と企業が思うような、各社毎にオリジナルの志望動機をまとめましょう。 「転職で実現したいこと」の優先順位を明確にする 40代になると、自分の今までの経験、実績、報酬に対する自信から、転職条件へのこだわりも無意識のうちに強くなってしまいます。また、家庭などの事情から「これは譲れない」という条件もいつの間にか多くなりがちです。 全てを叶えることができれば理想的ですが、求人数が少ない40代の転職では、こだわりの条件が多ければ多いほど、転職実現度は低くなります。そのため、今の状況を変えたいのであれば、「これだけは譲れない条件」を1~2つ程度明確にし、それ以外は柔軟に検討する姿勢が極めて重要です。 たとえば、「年収だけは維持したい」という場合には、年収が維持できるならば、業界や企業規模、知名度、仕事内容などにはこだわらずに求人を探し、その会社、その求人の良いところを見つけるようにして、自分の選択肢を広げていきましょう。 応募する求人の仕事を具体的にイメージし、面接で確認する また、転職活動では「応募する求人の仕事内容を遂行している自分」をできる限り具体的にイメージし、面接で気になることを積極的に質問して確認しましょう。 このことには2つのメリットがあります。1つめは、きちんと仕事内容を確認しておくことで、業務への理解が深まり、入社後に「こんなはずではなかった」とギャップを感じるリスクを小さくできることです。40代の転職は、多くの方にとっておそらく最後の転職になります。ここでの失敗を避けるためにも、面接でイメージと現実のギャップを埋めておくことはとても重要です。 2つめは、その積極的な姿勢が企業から評価対象になることです。適切な質問は、前向きな意欲の表れとして好印象につながります。また、質問次第では、それが仕事能力の裏付けとなり、高評価にもつながるでしょう。 5.40代からのキャリアの選択にプロのアドバイスを このように40代からのキャリアの選択は、20代や30代のころの転職よりもより計画的に、より深く今後のキャリアを考える必要があります。 経験も積み重なり、20代や30代のころに比べれば考慮すべきことも増えるからこそ、どのように情報を整理し、情報の取捨選択をしていけばよいか、一人ではなかなか難しいこともあるでしょう。 40代からのキャリア選択にこそ、プロのキャリアコンサルタントのサポートは効果的です。プロの力をうまく活用しながら、もうあと20年、気持ちよく仕事ができる選択を見つけていきましょう。 その他参考記事:40代で仕事辞めたい、疲れたと感じる女性必見!今すぐできる対処法とおすすめの仕事5選(ママキャンMamCamp)

40代で仕事のモチベーションが切れた!頑張れない理由と対処法
40代は働き盛りである一方で、仕事のモチベーションが落ちてしまう人が増える世代でもあります。 「40代に突入して、仕事のやる気が出なくなった」「モチベーションが下がって、毎日仕事に行くのが苦痛」 このように感じて、悩んでいる40代も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、仕事のモチベーションがなくなった40代に向けて、年代ならではの原因や対処法を解説します。 モチベーション低下を放置することにはさまざまなリスクがあるので、現状に向き合い状況改善を目指しましょう。 40代で仕事のモチベーションがなくなってしまうケースは多い 以前はあったはずのモチベーションがなくなってしまうと、「このままで大丈夫だろうか」と不安を覚える人も多いでしょう。 しかし、まず知っておいてほしいのは、40代で仕事のモチベーションを失うケースは珍しくないということです。そもそも年齢に関係なく、人間のモチベーションには波があります。常に高いモチベーションを維持し続けるのは、身体的にも精神的にも負担が大きく、現実的ではありません。 そのため、40代でモチベーションが保てなくなっても、焦ったり自分を責めたりしないようにしましょう。原因を特定したうえで、自分のペースで対処していくのが大切です。 仕事のモチベーションが下がる40代特有の理由 40代で仕事のモチベーションが下がるのは、キャリアを重ねてきたからこその悩みや年代特有の問題が原因となっている場合が多いです。ここでは、代表的な5つの理由を解説しましょう。 マンネリによるやりがい喪失 業務経験が豊富な40代は、大抵の仕事に一人で対応できるでしょう。そのため、職場では頼りにされたり憧れられたりする場面が増えますが、一方で自分の体感としては仕事に変化を感じにくくなります。 新たな発見や刺激、成長実感などが少ないため、マンネリ感から仕事のやりがいを見失い、モチベーションが切れやすいです。 責任が増えるプレッシャー 40代では、責任の大きい仕事や役職を任されることが多くなります。これはキャリアアップとも捉えられますが、あまりにも背負う責任が大きすぎるとプレッシャーとなり、モチベーションを低下させるでしょう。 特に、責任感が強い人ほど「結果を出さないと」「他の人に迷惑をかけたくない」と思い詰めてしまい、精神的にしんどくなりやすいです。 また、経験やキャパシティを超えた重すぎる責任を負わされた場合も、やる気の喪失につながります。 板挟みポジションで人間関係のストレスが増える 40代は、中間管理職として上司と部下の間で板挟みになりやすいです。部下のマネジメントを行いつつ、上司や上層部の顔色をうかがう必要もあり、部下の意見と上司の指示の間でジレンマを抱えるケースが少なくありません。 また、上司とも部下とも密にコミュニケーションを取ることが求められるので、人間関係が複雑化しやすく悩みやストレスが増えがちです。 気持ちをわかってくれそうな同僚に相談したくても、昇進や退職などで同じ職場にはいない場合も多く、このような状況も孤立感を深めます。 心身の調子が不安定 40代は心身に変化が見られやすい年代でもあり、心身の不調が仕事のモチベーションダウンの原因である場合も多いです。 身体的な変化でいうと、40代以降はどうしても体力が落ちます。以前よりも疲れを感じることが増え「これ以上無理をしたくない」と考えやすいです。 また、40代から50代にかけての人生の転換期には「このままで良いのか」と不安や葛藤を抱くミッドライフ・クライシスに陥りやすく、精神的に不安定になることがあります。 仕事と家庭の両立が難しい 40代は、子育てや親の介護など家庭面の負担も増えやすく、今まで以上に仕事と家庭の両立が求められます。 一つのことに打ち込みにくい環境や、常にやるべきことに追われる環境に疲れてしまい、仕事のモチベーションが切れてしまう人も多いです。 仕事と家庭の両立のために自分のプライベートを削る場面も多く、十分な休息が取りにくいのも仕事へのやる気を失う理由の一つでしょう。 40代が仕事のモチベーション低下を放置するリスク 仕事のモチベーションが下がっている自覚がありながら、現状に目をつぶって日々働いている人も多いのではないでしょうか。 しかし、40代で仕事のモチベーション低下を放置することには多くのリスクがあります。ここでは、どのようなリスクがあるのかを具体的に解説します。 自己肯定感が下がる 以前は高かった仕事へのモチベーションが下がると、多くの人はそんな自分を責めて自己嫌悪に陥ります。「自分はダメだ」「自分では無理だ」のように考えやすくなり、自己肯定感が下がってしまうでしょう。 また、自己肯定感が下がると何に対しても消極的になるため、より仕事のモチベーションが下がるという悪循環を招きやすいです。 心身の不調につながりやすい モチベーションが上がらず「仕事をしたくない」という気持ちのまま働き続ければ、どんどんストレスが蓄積していきます。 そして、ストレスは「万病のもと」といわれるほど、心身に大きな影響を与えるものです。 現状を放置し続けてストレスが限界を超えると、心身のさまざまな不調や深刻な病気のリスクが高まり、日常生活にも支障が出る危険性があります。 キャリアダウンの可能性 仕事に対するモチベーションが下がると、挑戦意欲やスキルアップを目指す気持ちも薄れます。成長を自ら止めてしまいやすく、希望しないキャリアダウンにつながるリスクがあるでしょう。 また、「今の職場でキャリアダウンしたから転職したい」と思っても、40代の転職では即戦力となるスキルが求められる傾向です。成長できていなければスキル不足と判断され、転職活動が難航する可能性があります。 バーンアウトの恐れ 今まで高いモチベーションを保っていた人ほど陥りやすいのが、バーンアウト(燃え尽き症候群)です。 バーンアウトはモチベーション低下の最終段階ともいわれており、頑張り続けた結果全てのエネルギーを使い果たして、ある日いきなり無気力・無関心になってしまいます。また、ゆくゆくはうつ病に移行するリスクも! 仕事へのモチベーションが下がってバーンアウトの兆候に気づいた場合は、休息やストレス発散、専門家への相談など早期の対策が重要です。 より働きにくくなるリスク モチベーションが下がると、集中力低下により仕事のパフォーマンスが落ちるうえ、孤立感を抱いて周囲の人ともギスギスしやすくなります。 結果的に、自ら働きにくい環境を作ってしまい、職場全体にも悪い影響を与えるリスクが高いです。 「働きにくいからもっとモチベーションが下がる」という悪循環を生み出しやすく、最悪の場合退職するしかない状況になる場合もあります。 40代向け!仕事のモチベーションが上がらないときの対処法 ここでは、40代で仕事のモチベーションが上がらないときの対処法を説明します。すぐに実践できるものもあるので、ぜひ参考にしてください。 無理にモチベーションを上げようとしない 下がったモチベーションを無理に上げようとすると、余計に疲労やストレスが溜まって状況悪化を引き起こしかねません。 モチベーションは「無理に上げよう」とするのではなく、「今より下げないようにしよう」と考えるのも大切です。 今より下げない方法としては、まずはしっかり休息を取りリフレッシュするのが良いでしょう。休日や有給休暇を使って心身を休めるだけで、気持ちが前向きになりモチベーションが回復することがあります。 モチベーション低下の原因を探る なぜ40代で仕事のモチベーションが下がってしまったのか、原因を突きとめるのも重要です。原因がわからなければ、対策や相談がしにくく、問題解決するのに時間がかかってしまいます。 たとえば、どんな場面でより強く仕事に対してネガティブな感情を持つのかを分析してみると、ストレスの源が見つかりやすいです。 同時に「どんな仕事や職場環境なら、モチベーション高く働けるのか」も考えてみると、自分が本当に望む方向性も見えてくるでしょう。 今の仕事や会社を選んだ理由を振り返る 今の仕事を選んだ理由、今の会社に入社しようと思ったきっかけなどを振り返ると、初心を思い出してモチベーションが上がる場合があります。 過去の自分が仕事に何を求めていたのかを深掘りすることで、自分の核となる価値観や働く目的を再認識でき、今後の目標も立てやすくなるでしょう。 また、入社当時と今の気持ちとの間にギャップがある場合も、ギャップから見落としていた問題やストレスの原因に気付けます。 自己管理を徹底する 仕事のモチベーションが下がると、つい日常生活における自己管理まで甘くなりがちです。食事や睡眠をおろそかにしたり、お金を使いすぎてしまったりする人は少なくありません。 しかし、自己管理を怠るとさらに心身の不調につながるリスクが高くなり、より仕事に対するモチベーションが沸きにくい状況を作ってしまいます。 仕事に対してネガティブな感情が大きいときほど、しっかり自己管理をするよう心掛けましょう。 新しい挑戦や学びを始めてみる 資格の勉強をする、副業を始めてみる、趣味の分野で新たな挑戦をするなど、自ら刺激を求めて行動してみるのもモチベーション回復に効果的です。 40代になると、仕事での成長実感の減少はどうしても避けられません。日々の仕事にマンネリ感を抱かないためにも、積極的に新しい情報や取り組みに興味を持ちましょう。 たとえプライベートにおける挑戦でも、自分が「やりたい」と思ったことならやりがいが得られ、人生が充実して仕事のモチベーションアップにつながる可能性があります。 目標を再設定する キャリアの方向性や目標を再設定するのも大切です。方向性・目標は年齢とともに変化することも珍しくないため、定期的な見直しが必要となります。 なお、目標は「明日からこれをやろう」という短期的なものと「将来どうなりたいか」といった中長期的なもの、2つ用意するのが理想です。 短期的な目標を日々こなすことで、モチベーションがないときに同時に下がりやすい自己肯定感を高められます。また、中長期的な目標があると進むべき方向に迷いにくいです。 信頼できる人と話す 信頼できる上司や同僚、家族などに相談するのも、モチベーションアップにつながりやすいです。 人は自分の感情を言語化しようとすることで、頭の中を整理できます。また、ただ話を聞いてもらうだけでも孤独感が和らぎ、ストレス解消になるでしょう。 相手の客観的な意見により、自分一人では気づけなかった問題点や解決策が見つかる場合も多いです。 異動・転職を検討する どうしても仕事のモチベーションが上がらず、自分一人でできる対処法では解決が難しい場合は、異動や転職をして環境を変えるのも一つの手です。 異動・転職によって環境をガラリと変えれば、心機一転できモチベーションを取り戻せる可能性があります。 ただし、40代の異動・転職は、マネジメント能力や専門性などが問われやすいです。モチベーションがなくなった原因を見つめるとともに、これまでの仕事で培ったスキルや実績を的確にアピールするのが、成功するためのポイントとなります。 40代の仕事のモチベーションの悩みはキャリアのプロに相談! 40代のモチベーション低下は、これまでに積み重なった不満やストレス、無意識のうちにしている思考の癖など、いくつもの要因が複雑に絡んで発生している場合もあります。 そのため、一人での対処が難しいときは無理をせず、気軽にキャリアコンサルティングでプロに相談してみるのがおすすめです。 キャリア面談では、現在抱えているモチベーションの悩みを相談できるだけでなく、自分の価値観を再認識したり、将来のキャリアについてのアドバイスが得られたりします。 過去・現在・将来問わず、仕事やキャリアのことを幅広く相談できるので、表面的な問題だけでなく自身の課題に根本から対処が可能です。 40代で仕事のモチベーションが切れたら、立ち止まって考えてみよう 40代は、仕事と生活のバランスを考え直す必要性が出てくる人や、時代の変化に戸惑う人も多く、キャリアの岐路に立たされやすい年代です。 「何だか仕事のモチベーションが出ない」という気付きは、キャリアを見直すタイミングに差し掛かっているという知らせかもしれません。 40代でモチベーション低下に悩んだら、まずは一度立ち止まり、キャリアのプロと一緒に問題解決を目指してみてください。

「仕事辞めたい」と感じる40代がやるべきこと7選!後悔しない対処法
40代で「仕事を辞めたい」と思う人は少なくありません。しかし、退職は自身の生活にも今後のキャリアにも大きな変化をもたらす選択であるため「本当に辞めて後悔しないのか?」と不安や迷いが生じやすいです。 本記事では、40代が仕事を辞めたいと感じる原因や、退職前に確認すべきこと・やるべきことを詳しく解説します。 「仕事辞めたい」という感情をきっかけに、自分の本音や目指すべき方向性を再確認し、納得できる答えを導き出しましょう。 40代で「仕事辞めたい」と思う人は多い 厚生労働省の「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要(個人調査)」によると、「仕事や職業生活において強い不安、悩み、ストレスを感じる事柄がある」と回答した40代は87.1%でした。 この数字は働く全世代のなかで最も高い割合となっており、40代は仕事に不安や悩み、ストレスを抱えている人が多いのがわかります。このデータから、40代で「仕事を辞めたい」と感じている人は少なくないことが推察できるでしょう。 しかし、40代の離職率は平均で6~10%前後であり、20~30代の離職率より低いです。 40代は仕事の悩みやストレスを抱えながらも、年齢的なハードルや年収ダウンのリスクなどを考えて、実際に退職する人は一握りとなっている現実がうかがえます。 「仕事辞めたい」と思っても、急いで退職するのはNG 「仕事を辞めたい」と本気で思うなら、もちろん辞めても構いません。しかし、熟考せず急いで退職してしまうと、のちのち後悔する可能性が高いので注意しましょう。 20~30代に比べると、40代は転職先が決まるまでに時間がかかりやすいです。次の職場を決めずに今の仕事を辞めると、無収入の期間やキャリアの空白期間が長引くリスクがあります。 また、なかなか転職先が決まらない焦りから、自分に合わない会社やブラックな会社を選びやすくなり、再び辞めたくなる恐れも…! 40代の転職は20~30代に比べると難易度が上がりやすいため、戦略的かつ計画的に行うのが大切です。 40代が「仕事辞めたい」と感じる理由とは? 40代が「仕事を辞めたい」と感じる理由はさまざまです。ここでは、代表的な理由を紹介しましょう。 人間関係のストレス 40代になると、今までより仕事の幅が広がったり部下の育成を任されたりする機会が増えます。必然的に仕事で関わる人の数が多くなり、合わない人とも積極的にコミュニケーションを取らざるを得ないので、人間関係のストレスを感じやすいです。 また、勤続年数が長い人の場合は、苦手な人と長年同じ職場で働き続けることでストレスが限界に達してしまうケースもあります。 人間関係に摩擦が生じると働きにくさを感じ、毎日職場に行くことさえ辛くなってしまうでしょう。 評価や給料に不満がある 30代までの評価基準は、主に「仕事の実績」です。しかし40代になると実績に加えて「組織への貢献度」や「マネジメント能力」なども評価され、場合によっては昇給昇進コースから外れてしまうことがあります。 「努力して実績を出しても、それだけでは不十分と評価される」「長年勤務してもなかなか給料が上がらない」という状況では、仕事に対するモチベーションも下がってしまうでしょう。 特に40代は、子供の養育費や住宅ローンなどで経済的負担が増加する年代なので、昇給昇進に納得できないと将来の不安につながりやすいです。 過剰な業務や責任による疲労 40代は仕事の責任や任される役割が増え、それに伴い業務量も増加しやすいです。 責任増加によるプレッシャー、そして業務量増加による残業や休日出勤なども増える傾向にあり、心身ともに疲労が蓄積して仕事を辞めたくなるケースもあります。 また、40代はまだまだ育児で忙しかったり、親の介護が始まったりと、自身を取り巻く状況にも変化が起こりやすいです。その影響により、過剰な業務や責任が伴う職場では働きにくさを感じることがあります。 健康維持が難しい 残業や休日出勤などが多いハードワークでも、20~30代の頃なら乗り切れたかもしれません。 しかし、40代は体力の衰えを感じやすく、ライフワークバランスを欠いた働き方をするとかえってパフォーマンスが落ちてしまう場合があります。 また、40代以降は男女ともに更年期の症状を感じ始める時期です。疲れやすさや集中力の低下を感じ、このような体調の変化からキャリアの見直しを行う人も少なくありません。 キャリアの停滞を感じる 40代は既に十分な業務経験を積んでいるからこそ、新しい刺激や成長実感を得にくいです。一定の「やり切った感」があるため、今後の目標や方向性を見失ってしまい、自身のキャリアが停滞しているように感じる人が増えます。 また、組織構造から今後の昇進の行き先が見え、「自分にはもう進むべきキャリアがない」と感じる場合も多いです。 キャリアの停滞を感じると、仕事のモチベーションややりがいも下がるため、「何だか仕事がつまらない」「仕事を辞めたい」という思いが強くなるでしょう。 仕事を辞めたい40代が確認すべきこと 40代で「仕事を辞めたい」と思ったら、確認すべきことや考えるべきことがたくさんあります。一つ一つの課題に向き合い、自身が置かれている状況を把握しましょう。 心身の調子を崩していないか 退職は、次の職場が決まったタイミングで行うのがベストですが例外もあります。ストレスによって心身に不調が見られる場合は、これ以上状態が悪化する前に辞めたほうが良いこともあります。 ただし、休職で回復できる可能性がある場合は、これらの制度を利用してみるのも一つの手です。 心身の不調を無視して無理を続けると、深刻な疾患を引き起こす恐れもあります。そのため、まずは心と体の状態をチェックし、健康を最優先に考えましょう。 今の職場での状況改善は見込めないか 今の職場への不満や問題だと思う要素については、改善できないか働きかけてみるのも大切です。自身の行動によって職場状況が改善されれば、今の仕事を辞めることなく気持ちよく働き続けられる可能性があります。 また、たとえ退職する場合でも、やれるだけのことをやったうえでの退職は後悔しにくいです。まずは現状の問題を明確化し、改善の可能性を検討してみてください。 退職が本当に悩み解決につながるのか 退職という選択が、「仕事を辞めたい」という思いの解決策に必ずしもなるとは限りません。 たとえば「やりがいがない」という理由で仕事を辞める場合、自分が何にやりがいを感じるのかを明確にしておかなくては、次の職場でも同じ悩みにぶつかる可能性があります。 そのため、仕事を辞めたいと思う原因を徹底的に深掘りして、退職が本当に悩みの根本的解決になるのかをよく考えるのが重要です。感情的にならず、客観的事実や情報に基づいて冷静な判断をしましょう。 自分の市場価値はどれくらいか 40代で「仕事を辞めたい」と思ったら、今の自分の市場価値も要チェックです。市場価値を正確に把握することで、自身の強みを客観的に理解できます。また、今の自分に足りない部分から、伸ばすべきスキルや必要な経験が具体的にわかるケースもあるでしょう。 市場価値の把握は、キャリアを主体的にコントロールするための第一歩といえます。 辞めても経済的に苦しくならないか 次の職場を決めずに仕事を辞めれば、当然収入が途絶えます。また、たとえ次の職場を決めてから退職したとしても、最初から今と同じだけの給料が得られるわけではありません。 経済状況が変わると自分だけでなく家族の生活にも影響が出る可能性があるため、リアルな家計状況を踏まえたうえでお金のこともよく確認しておきましょう。 40代で仕事を辞める場合、一般的には生活費の3〜6ヶ月分の貯金が最低限必要だといわれています。 「仕事辞めたい」と感じる40代がやるべきこと7選 ここでは、「仕事を辞めたい」と感じる40代が退職前にやるべきことを7つ紹介します。納得のいく形で次のステップに進めるよう、一つずつ行動を進めてみましょう。 有給や休職制度を活用する 今抱えている「仕事辞めたい」という感情は、一時の心身の疲れからきている可能性もゼロではありません。そのためまずは、有給休暇を利用してリフレッシュを試みましょう。仕事から完全に離れてのんびり過ごすだけで、疲労や悩みが軽減して「辞めたい」と思わなくなる可能性があります。 また、心身の消耗が激しく、有給の数日間だけでは休養が不十分だと感じる場合は、休職制度を利用してみるのも一つの方法です。 抱えているモヤモヤを整理する 今の職場に対する不満、嫌だと感じることなどを具体的に書き出し、抱えているモヤモヤや自分が置かれている状況を整理しましょう。 これは、冷静さを取り戻して自分を客観視するための作業です。40代の退職で失敗しないためには、「辞めたい」と思った場面で感情的にならず常に冷静でいなくてはいけません。 冷静さを維持できれば、話し合いや手続きが滞りなく進んで今の会社を円満退職できる可能性が高まりますし、客観的視点で次の会社を選べるので転職にも成功しやすくなります。 上司や同僚に相談する 今の気持ちや悩みを、上司・同僚・人事などに相談してみるのも重要です。相談する際は愚痴や不満を言いすぎないように注意し、事実と意思ベースで話を進めましょう。 問題に感じていることを打ち明けると、第三者視点のアドバイスが聞けたり、会社側から改善提案やサポートが得られたりする可能性があります。 また、本当に退職することになった場合でも、事前に相談していると話が円滑に進みやすく、退職トラブルに発展しにくいです。 キャリアプランを再設定する 40代は自身のキャリアに行き詰まり感を感じやすく、退職を検討するときには働く目的や目標を見失っているケースが多いです。 今の会社を本当に辞めるにせよ転職するにせよ、このタイミングで「今後どうなりたいのか」を考え、キャリアプランを再設定しましょう。キャリアプランが明確になることで、「退職か転職か」という悩みの答えが見つかる場合もあります。 5年後、10年後どうなっていたいのかを具体的に想像し、そのうえで必要なスキルや今やるべきことを考えてみてください。 部署異動や転勤を検討する 会社や仕事そのものに大きな不満がない場合は、部署異動・転勤を検討してみるのもおすすめです。 部署異動や転勤ができれば、今の会社に留まりつつ新しい環境で働けます。特に、「仕事を辞めたい」と思う原因が今の職場独自の問題である場合、異動や転勤をすることで状況が好転しやすいです。 ただし、部署異動や転勤の希望は、出せば必ず通るというものではないため会社の状況もよく見極めましょう。 退職のシミュレーションや転職活動をしてみる 「今の仕事を辞めたあと」をイメージして、日常生活や転職先での働き方、お金のことなどを具体的にシミュレーションしておくのも大切です。 高い精度でシミュレーションできれば、経済的な計画を立てやすく、退職や転職に伴う複雑な手続きにもスムーズに対応できます。 また、並行して転職活動も始めていきましょう。「本当に辞めるかまだ決心がついていない」という場合でも、求人を見て他社を知ることで冷静な判断がしやすくなります。 キャリアコンサルティングを受ける 「仕事辞めたい!」と思っても、40代での退職はそう簡単に決心がつくものではありません。 お金の心配はもちろん、「辞めて後悔しないか」「転職に成功できるのか」という不安も膨らみやすく、なかなか答えを見つけられない40代も多いのではないでしょうか。 そんなときは、キャリアコンサルティングでプロのサポートを受けながら、じっくり自分と向き合うのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、転職・退職だけに縛られない幅広い選択肢を一緒に検討してもらえます。たくさんの可能性の中から「本当に納得できる結論」にたどりつく足がかりとなるでしょう。 仕事を辞めたい40代に重要なのは、心の整理と事前の計画 丁寧に自分の気持ちを整理し、現実的な計画を立てて行動を積み重ねるのが、40代以降のキャリアを切り開くポイントです。40代で「仕事辞めたい」と感じたときは、その感情と正面から向き合い、自分のキャリアを見直してみましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、1回から気軽に悩みを相談できます。自己分析やキャリアの棚卸し、キャリアプランの設定も、プロと一緒ならよりスムーズにできるでしょう。 キャリアコンサルティングを有効活用しながら、自分らしい豊かなキャリアの実現を目指してください!
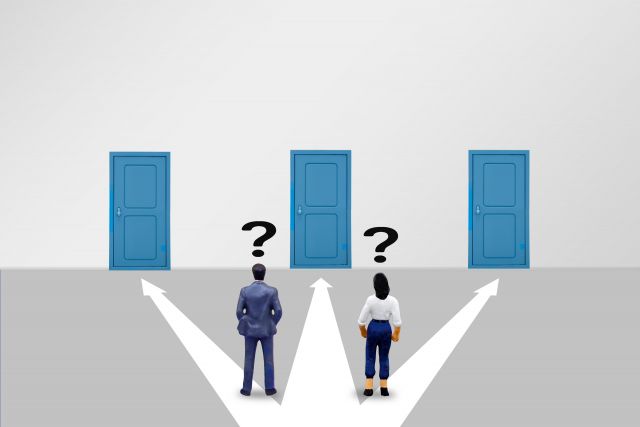
40代のキャリアの行き詰まりを解消する方法!停滞感の理由・よくある失敗も紹介
「40代になって、キャリアに停滞感を感じるようになった」「仕事のやりがいも減ってしまって、焦りや不安が募る…」 このように感じるのは、40代で感じやすい「キャリアの行き詰まり」かもしれません。キャリアの行き詰まりを放置することには、成長機会の損失、仕事のモチベーション低下、将来への不安増大など、多くのリスクがあります。 本記事では、40代でキャリアの行き詰まりを感じる理由や、その対処法を解説します。キャリアに行き詰まった40代がやりがちな失敗も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 40代が感じやすい「キャリアの行き詰まり」とは? キャリアの行き詰まりとは、ポジティブな将来展望を描けなかったり、仕事内容に成長ややりがいを見出せなくなったりして、キャリアが停滞しているように感じる状態です。別名「キャリアプラトー」「キャリアクライシス」とも呼ばれます。 キャリアの行き詰まりは、仕事に慣れた30代・40代のミドル層に発生しやすく、自己肯定感や意欲の低下、漠然とした不安・閉塞感などを引き起こします。最悪の場合、深刻な悩みが心身に悪影響を及ぼし、本意ではない退職やキャリアの断念につながるケースも! のちのち後悔しないためにも、キャリアの行き詰まりを感じたら放置せず、できるだけ早い段階で適切に対処するのが重要です。 40代でキャリアの行き詰まりを感じる理由 働く全年代の中でも、特に40代はキャリアの行き詰まりを感じやすいといわれていますが、それはなぜなのでしょうか?ここでは、40代がキャリアの行き詰まりを感じやすい理由について解説します。 今のキャリアに満足できていないから 偶然の出会いや予期せぬライフイベント、自身の価値観の変化などにより、当初計画していた通りにキャリアが進まないケースはよくあります。そのため、過去に描いていたキャリアビジョンと今のキャリアにギャップがあるのは、大きな問題ではありません。 しかし、そのギャップに納得できておらず現状に不満がある場合は、キャリアの行き詰まりを感じる原因になります。 ギャップを受け入れられないことで「この先どう行動すれば良いのかわからない」という状況にも陥りやすく、出口がないように感じるでしょう。 スキルへの不安やキャリアアップの限界を感じるから 今は変化の激しい時代であり、新しい技術やスキルが次々登場しています。 しかし、変化への適応は年齢を重ねるごとに困難・億劫になりやすく、新たな技術にうまく対応できないと、自身の能力に不安を抱いてキャリアの行き詰まりを感じる要因となるでしょう。 また、40代になると今後の昇進・昇格のペースもクリアに見えてきます。自分のキャリアアップに限界を感じやすく、「これ以上努力したとして、その先に何があるのだろう?」という疑問から充実感が薄れる場合も多いです。 成長実感が減り停滞しているように感じるから 20代・30代は、仕事において「初めての挑戦」をすることも多く、新鮮さや成長実感を得る機会が豊富です。 対して40代に突入すると、既に多くの経験を積んでいるからこそ、新たな挑戦をする機会が減ります。 仕事の精度・スピードは安定して高水準を保ちますが、かつては刺激的だった業務もいつの間にかルーティン化し、面白みを感じにくいです。成長実感も少ないため「このままでいいのだろうか」という不安や焦りにつながりやすく、自分が停滞しているように感じます。 自分の理想と会社から求められる役割にギャップがあるから 40代は、自分の強みや専門性が確立されてきて、仕事へのこだわりも強くなりやすいです。一方で、会社から何らかの役職・ポジションを任せられたり、求められる役割が増えたりしやすい年代でもあります。 ここで、自分が目指したい方向性と会社から求められる役割にギャップが生じると、キャリアに行き詰まりを感じるきっかけになるでしょう。 たとえば、本人は「現場で専門技術を磨きたい」と思っているのに、会社から管理職の役割を与えられるといった状況では、やりたい仕事ができず次第にモチベーションが低下してしまいます。 年齢を理由に目標が立てにくくなるから キャリアの行き詰まりから抜け出すのに、「目標設定」は非常に有効な方法といえます。 しかし、40代は目標を設定するにしても年齢や時間の制約を感じやすく、明確な目標を立てる難易度が高くなる傾向です。 転職を目標にする場合、40代は年齢的なハードルを意識せざるを得ないでしょう。また、今から専門性を深める、昇進を目指すなどするのにも時間の制約があり、結果的にどこを目標とすればいいのかわからなくなる場合があります。 目標を見失うと軸がぶれ、考え方や行動にも迷いが生じやすいです。 40代のキャリアの行き詰まりを解消する方法 キャリアの行き詰まりを感じたら、早めに現状を打破する行動を起こすのが重要です。ここからは、40代のキャリアの行き詰まりから抜け出す方法について解説します。 キャリアコンサルティングを受ける 40代のキャリアの行き詰まりは、複数の原因が複雑に絡んでいる場合も珍しくありません。 一人で一つずつ原因を解明し、そのうえで問題解決を図るのは負担が大きくなりやすいため、キャリアコンサルティングで専門家からアドバイスをもらうのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、現状分析を整理するのに役立ち、自分では気づけない強みや適性、本当にやりたいことなどを客観的な視点で引き出し、悩みの根本的原因にアプローチできます。 具体的なキャリアプランを明確にするのにも役立つので、停滞期を乗り越える第一歩となるでしょう。 キャリアの棚卸しと自己分析を行う キャリアの行き詰まりを解消するためには、自己理解を深めるのが重要です。 まずはこれまでのキャリアを洗い出し、そこから自分の強みやスキルを整理する「キャリアの棚卸し」を行いましょう。その後、キャリアの棚卸しの内容を参考にしながら自己分析を行い、「何のために働くのか」という仕事の軸となる部分を再構築していきます。 また、行き詰まり感によって気持ちがモヤモヤする場合は、モヤモヤの内容や原因を紙に書き出して問題を整理するのも効果的です。 キャリアプランを練り直す キャリアプランの不明確さが行き詰まり感につながっているケースも多いので、40代で一度キャリアプランの練り直しを行うのも有効な方法といえます。 3年、5年、10年と期間を区切り、それぞれに理想像や目標を設定しましょう。最初に10年後の目標を立て、それを細分化する形で5年後、3年後の目標を決めるのもアリです。 目標設定ができたら、目標を達成するために必要な行動を具体的に考え、アクションプランを立てていきます。明確な目標と今やるべき行動が把握できれば迷いが消え、行き詰まりを解消できる可能性が高いです。 新たな挑戦をしてみる 刺激不足や成長実感のなさが行き詰まりを引き起こしている場合は、新しい挑戦をしてみるのが即効性のある解消方法となりやすいです。 挑戦内容は、社内外のどちらに向けたものでも構いません。 たとえば、社内で挑戦をするなら新規プロジェクトへの参画、部署異動を希望してみる、仕事で役立つ新しいスキルの習得などが挙げられます。また、思い切って社外に目を向け、副業を始めてみたり趣味・ボランティアなどの活動を通じて人脈を広げてみたりするのも良いでしょう。 キャリアチェンジを検討する あらゆる方法を試してもキャリアの行き詰まりを解消できない場合や、今の職場での問題解決がどうしても難しい場合は、キャリアチェンジを検討するという方法もあります。 20代・30代に比べると転職のハードルは高くなりやすいものの、40代で転職して成功している人も多いです。また、スキルやノウハウがあるなら、独立するという選択肢もあります。 ただし、40代でのキャリアチェンジは今後の人生を左右する大きな決断となるため、一つ一つの判断は慎重に行いましょう。 40代のキャリアの行き詰まりへの心理的アプローチ 40代のキャリアの行き詰まりは、考え方や視点を変えることで解消できる場合もあります。ここでは、今日から実践してみてほしい行き詰まりへの心理的アプローチを解説しましょう。 周囲と比較しない キャリアの行き詰まりを感じると、焦りや不安から他者と自分を比較しやすくなります。しかし、うまくいっている同僚や友人との比較は劣等感を強め、さらなる不満やモチベーション低下につながる可能性が高いです。 他者は、参考にするだけなら学びや刺激になりますが、比較対象とするとマイナスに作用しやすいため注意しましょう。 「できたこと」にも目を向けて自己肯定感を高める 40代は業務経験が豊富だからこそ、自分に求めるハードルも高くなりがちです。 仕事をきちんとこなせても「これくらいできて当然」のように思ってしまい、物事をポジティブに受け止めるのが難しくなります。 このような状況では自己肯定感がどんどん失われ、行き詰まりを感じやすくなるため、たとえ小さくても「頑張ったこと」「できたこと」に目を向けるのが大切です。 完璧主義を手放す 完璧を求めすぎると、失敗を恐れて新しい挑戦を避けやすくなり、キャリアの行き詰まりから抜け出しにくくなります。 まずは「失敗してもいい」「完璧でなくてもいい」という視点を持つところから始めましょう。 「成果を出せないと失敗」と捉えるのではなく「成果を出せなくても成長につながればOK」と考え方を変えてみてください。 キャリアに行き詰まりを感じる40代がよくやる失敗 キャリアに行き詰まると、不安や焦燥感からNG行動を取ってしまう人もいます。ここでは、キャリアに行き詰まりを感じる40代がやりがちな失敗を紹介するので、ぜひ教訓にしてください。 悩みを一人で抱えて深刻化させる 20代・30代に比べて40代は新しい友人と出会う機会が少なく、仕事や家庭の忙しさから既存の友人とも疎遠になりがちです。そのため、キャリアに行き詰まりを感じても、誰にも相談できないケースが少なくありません。 しかし、悩みを一人で抱えると問題が悪化・長期化しやすく、解決がより難しくなるリスクがあります。 相談相手が見つからないときは公的な相談窓口やキャリアコンサルティングサービスなどを活用し、悩みを一人で抱えないようにしましょう。 学び直しをしない 40代は、変化を避けて新しい行動を取ろうとしない「現状維持バイアス」という心理傾向が強くなりやすいです。 これによりリスク回避できる場面もありますが、過剰な現状維持バイアスがかかると全てにおいて「今のままでいい」と考えて学び直しを拒否し、成長機会を逃す恐れがあるため注意しましょう。 40代がキャリアの行き詰まりから抜け出すためには、新しいスキル・技術の学び直しが欠かせません。「これまでの経験」に「新しいスキル」をプラスすることで、変化の激しい時代にも対応できる人材となれます。 「自分には無理」と諦める キャリアアップやキャリアチェンジを目指す際、40代はどうしても年齢が障壁になりやすいです。また、若い頃に比べると自分自身も気力・体力が低下したと感じる場面も増えるでしょう。 しかし、それらを理由に「だから自分には無理」と行動や挑戦を諦めてはいけません。諦めてしまうと本来ならまだできることもできなくなり、自らキャリアの可能性を狭めてしまいます。 年齢を受け入れるのは大切であるものの、「もう遅い」ではなく「まだできる」と捉え、豊かな人生を築けるよう努力するのが大切です。 40代でキャリアに行き詰まったら、キャリアコンサルティングがおすすめ 40代は毎日の仕事がマンネリ化しやすく、キャリアに行き詰まりを感じがちです。 キャリアの行き詰まりを放置することにはさまざまなリスクがあるため、行き詰まりを感じたときは対処を後回しにせず、できるだけ早く抜け出すための対策を取りましょう。 スピーディな現状打開を実現させるには、キャリアコンサルティングを受けるのがおすすめです。キャリアコンサルティングを活用すれば、対話を通じて悩みの根本的原因や自分の価値観を整理でき、効率よく問題解決を目指せます。 キャリア・コンサルティング・ラボはオンライン形式で面談を受けられるので、公私ともに忙しい40代も気軽に利用できるでしょう。 40代のうちはもちろん、50代・60代になっても輝き続けられるよう、自分のキャリアとしっかり向き合ってみてくださいね!

キャリア面談・キャリアコンサルティングとは?|受ける意味やエージェントとの違い等を解説
「今の仕事、このままでいいのかな……」 「転職を考えてはいるけれど、エージェントに相談すると急かされそうで怖い」 「キャリアコンサルティングって、意識が高い人向けのものじゃないの?」 こうした疑問を持って、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。 ネットで検索すれば「キャリアの重要性」はたくさん出てきますが「今の自分にとって本当にお金を払ったり時間を使ったりする価値(意味)があるのか」という答えは見つかりにくいものです。 実は、キャリア面談・キャリアコンサルティングは「転職したい人」だけのものではありません。 むしろ、「今の会社に残るべきか」「そもそも自分は何に向いているのか」といった答えの出ないモヤモヤを整理するための「キャリアの健康診断」のような場所です。 本記事では、以下のポイントを分かりやすく解説します。 なぜエージェントではなく「キャリア面談」を選ぶ人が増えているのか? 「相談内容がまとまっていない」状態で受けても意味がある理由 具体的にどんな悩みが解消されるのか? 「受けてよかった」と思える面談にするための活用のコツ 最後まで読んでいただくことで、あなたが今抱えている「得体の知れないモヤモヤ」を解消するために次に取るべき一歩がはっきりと見えるはずです。 1|キャリア面談・キャリアコンサルティングとは? キャリア面談(キャリアコンサルティング)を一言で伝えると、「プロの力を借りて自分のキャリアの現在地と目的地を整理する時間」です。 今の時代、終身雇用の崩壊や働き方の多様化により「会社に身を任せていれば安心」というフェーズは終わりました。だからこそ、自分の意志でキャリアを築くために、プロを頼る人が増えています。 キャリア面談は転職を勧められる場ではなく、 ・悩みの正体を言語化する ・まとまっていない考えを整理する ・未来の選択肢を広げる といったことを目的に行われます。 多くの方が「こんなにまとまっていない状態で相談していいのかな?」と心配されますが、実はまとまっていない時こそ、受ける価値が最大化されます。 キャリアコンサルタントは対話を通してあなたの頭の中にある「絡まった糸」を一本ずつ解きほぐすプロです。 「答えをもらいに行く場所」ではなく、「話しながら自分の中にある答えに気づいていく場所」。それがキャリア面談の本質です。 2|【徹底比較】キャリア面談と転職エージェントの違い 「転職の相談なら、無料で求人紹介をしてくれるエージェントで十分では?」と思う方も多いかもしれません。 しかし、両者にはビジネスモデルに決定的な違いがあります。この違いを理解しておかないと、「相談していたはずがいつの間にか転職を急かされていた」といった後悔につながる可能性があります。 両者のビジネスモデル 転職エージェント: 採用を決めた企業から紹介料をもらう仕組みです。そのため、アドバイスの着地点はどうしても「転職(内定)」になりやすく、転職させることがゴールになりがちです。 キャリア面談: あなた(相談者)から直接費用をいただく仕組みです。企業への忖度が一切不要なため、100%あなたの味方として、転職しない選択肢(現職残留や副業など)も含めたフラットな対話が可能です。 どちらが良い、悪いではなく、今のあなたの状況に合わせて適したサービスを使い分けることが大切です。 キャリア面談が向いている人 今すぐ転職するか迷っている、結論を急ぎたくない 自分の強みや価値観をじっくり言語化したい 現職残留や副業など、フラットな選択肢を検討したい 転職エージェントが向いている人 すでに転職の意思が固まっている 具体的な求人情報や、企業の内部情報を知りたい 職務経歴書の添削や面接対策を無料で行いたい 結論として、「意思決定の前段階(自分はどうしたいか)」を整理したいならキャリア面談、「意思決定の後(どう転職するか)」をサポートしてほしいなら転職エージェントを活用するのが、最も効率的で後悔のない選択です。 3|キャリア面談が向いている人の特徴 キャリア面談は、「会社を辞めたい」「精神的に限界だ」といった深刻な悩みがある人だけのものではありません。 最近では、「これからの人生をより納得感のあるものにしたい」という前向きな理由や、「キャリアの健康診断」として利用する方が非常に増えています。具体的には、以下のような思いを持っている方にこそ向いています ①「現状維持」になんとなく不安を感じている人 今の仕事に大きな不満はないが、5年後、10年後もこのままでいいのか不安 世の中の変化に取り残されないよう、自分の市場価値を確かめたい 周りの活躍を見て、焦りやモヤモヤを感じることがある ②転職を考え始めたが確信を持てない人 「転職したい」気持ちはあるが、何が嫌で、次は何を求めているのか言語化できていない 転職エージェントに登録してみたが、紹介される求人にピンとこない 今の会社に残るべきか、外に出るべきか、フラットな意見を聞きたい ③自分の「強み」や「軸」を客観的に知りたい人 自分のスキルや経験を、どうアピールすればいいかわからない 自己分析を一人でやってみたが、結局よくわからず行き詰まっている 友人や上司ではなく、プロの視点からフィードバックがほしい ④「答え」ではなく「納得感」を求めている人 キャリア面談は、「これをやりなさい」という正解を与えてくれる場所ではありません。 対話を通して自分自身の価値観を整理し、「これなら納得して進める」という確信を自分の中から引き出したい人に最も適しています。 4|キャリア面談ではどんな相談ができる? 相談内容は大きく分けて以下の4つのカテゴリーに分類されます。ご自身の「モヤモヤ」に近いものがあるかチェックしてみてください。 ① 「今の仕事」に関する悩み 頑張っているのに正当に評価されない 上司やチームとの人間関係がしんどい 今の仕事にやりがいを感じられず、毎日「辞めたい」と思ってしまう 社外ならではの利点で、社内面談では絶対に言えない「辞めたい」「不満がある」という本音をすべて吐き出せます。 ②将来・キャリアパス」に関する悩み 5年後、10年後の自分がイメージできない 異業種・異職種へのキャリアチェンジが現実的か知りたい 自分の市場価値を客観的に知りたい、強みを言語化したい AIに取って代わられないか、今のスキルで生き残れるか不安 ③ 「やりたいこと」がわからない悩み 自分が何を大切にしたいのか、価値観を整理したい 「これ」といったやりたいことがなく、焦りを感じている 今までなんとなくキャリアを積んできたが、一度立ち止まって棚卸ししたい ④ 「ライフイベントと仕事」の両立 出産や育児、介護を控えて今の働き方を続けられるか不安 ワークライフバランスを改善するために、どんな選択肢があるか整理したい 移住や副業など、新しいライフスタイルに合わせたキャリアを考えたい キャリアコンサルタントは、バラバラになったパズルのピースを一緒に組み立てるプロです。「うまく話そう」とする必要はありません。 愚痴やまとまらない感情をそのまま話すことで、対話を通して自然と「相談すべき本当の課題」が浮かび上がってきます。 5|キャリア面談を受けると何が変わる? キャリア面談を受けたからといって、すぐに答えが出るとは限りません。 ただし、プロとの対話を終えた後、多くの方が「視界がパッと開けた」「肩の荷が下りた」といった、確かな変化を実感されます。具体的には、以下のような変化が期待できます。 ① 「正体不明のモヤモヤ」が「具体的な課題」に変わる 一番の変化は、頭の中を占領していた「なんとなく不安」という霧が晴れることです。「私は今の仕事の『ここ』に不満があり、将来の『これ』を不安に思っているんだ」と正体がはっきりすることで、漠然とした恐怖が消え、冷静に対策を考えられるようになります。 ② 周りの声に振り回されない「自分軸」が見つかる 「今の時代はITスキルが必要だ」「30代なら役職を目指すべきだ」……そんな外側の情報に惑わされていませんか? 面談を通じて自分の価値観を掘り起こすことで、「他人がどう思うか」ではなく「自分が何を大切にしたいか」という判断基準(自分軸)が手に入ります。 ③ 「今、何をするべきか」が明確になり行動が軽くなる 「いつか転職しなきゃ」と悩み続けるのは、非常にエネルギーを消耗します。 思考が整理されると、「今は転職せず、このスキルを磨くことに集中しよう」あるいは「まずは3ヶ月でこれだけ準備しよう」と、今日からの行動が具体的になります。 迷いがなくなるだけで、日々の仕事へのストレスは劇的に軽減されます。 キャリア面談の最大の価値は、結果が「転職」であれ「現職残留」であれ、それを「自分自身で納得して選んだ」と思えることです。 「会社に言われたから」「なんとなく不安だから」という消去法ではなく、自分の意志で選んだという感覚が、これからのキャリアを歩む上での大きな自信に繋がります。 6|「意味がない」と感じないための活用のコツ 「キャリア面談を受けてみたけれど、あまり意味がなかった」という事態を避けるためには、いくつか知っておきたい活用のコツがあります。 プロのコンサルタントはあなたの味方ですが、最終的に人生の舵を握るのはあなた自身です。以下の3点を意識するだけで、面談から得られる気づきはぐっと深まります。 ① 「正解」を求めない キャリア面談の最大の落とし穴は、「プロなら私にぴったりの答えを教えてくれるはずだ」という期待です。 コンサルタントは、あなたの価値観を映し出す「鏡」のような存在です。「答えをもらいに行く」のではなく、「プロとの対話を通じて、自分の中にある答えに気づきに行く」というスタンスで臨むと、納得感が大きく変わります。 ② 今の気持ちを「箇条書き」でメモしておく 相談内容がまとまっていないのは全く問題ありません。ただ、面談の前に5分だけ時間を取って、「今、何がモヤモヤしているか」「何にイライラしているか」を、単語や箇条書きでメモしておくことをおすすめします。 「給与が不満」「人間関係がしんどい」「5年後が不安」など、きれいな文章にする必要はありません。そのメモがあるだけで、当日の対話がスムーズになります。 ③ 「かっこいい自分」を見せようとしない キャリアコンサルタントは、あなたの評価をする上司でも、選考を行う人事でもありません。利害関係のない第三者だからこそ、「本当は楽をしたい」「今の会社が嫌でたまらない」といった、泥臭い本音をさらけ出すことが大切です。 本音を隠したままだと、アドバイスも表面的なものになってしまいます。100%あなたの味方であるプロを信じて、ありのままを話してみるのが最大のコツです。 7|キャリア面談はいつ受けるのがベスト? 「まだモヤモヤする程度だし、相談するほど深刻ではないかも……」 そう思って先延ばしにしてしまう方は少なくありません。しかし、キャリア面談のベストタイミングは、実は「モヤモヤし始めた、その瞬間」です。 早めにプロを頼るべき理由には、明確なメリットが3つあります。 ① 「辞めるか、耐えるか」の極端な二択を防げる 悩みが深くなりストレスが限界に達すると、人の視野は驚くほど狭くなります。「今すぐ辞めるか、一生我慢するか」という極端な二択でしか考えられなくなってしまうのです。 まだ心に余裕があるタイミングなら、「今の会社で部署異動を希望する」「副業でスキルを試す」といった、第三、第四の選択肢を冷静に検討できます。 ② 思考の「軌道修正」が最小限で済む キャリアの悩みは、雪だるま式に大きくなる傾向があります。小さな違和感を放置して数年経つと、軌道修正に大きなエネルギー(年齢、スキル、年収の壁など)が必要になることも。 モヤモヤが小さいうちに「自分は何を大切にしたいのか」を確認しておくことで、遠回りを防ぎ、最短距離で理想のキャリアに近づくことができます。 ③ 「決断」の質が上がる 感情が昂った状態(怒り、悲しみ、焦り)での決断は、後悔に繋がりやすいものです。 フラットな状態の時にプロと一緒に思考を整理しておけば、いざ「本当に転職しよう」と思った時にも、「自分はこれを大切にするために動くんだ」という確固たる根拠を持って、迷いなく行動できるようになります。 キャリアに関する「モヤモヤ」は、あなたの心が「今の状況をアップデートしたい」と出しているサインです。 「こんなことで相談してもいいのかな?」と迷う必要はありません。むしろ、深刻な「お悩み相談」になる前に「これからの作戦会議」としてキャリア面談を活用してみてください。早めに言葉にしておくだけで、驚くほど気持ちが楽になるはずです。 8|後悔しないキャリア面談選びのポイント キャリア面談を提供するサービスは増えていますが、どこでも同じというわけではありません。せっかくの時間とお金を無駄にしないために、選ぶ際のチェックポイントを3つお伝えします。 ① 「転職を前提としていないか」を確認する 第2章でお伝えした通り、転職エージェントが運営する面談は「求人紹介」がゴールになりがちです。 今のあなたが「まだ転職するか決めきれない」「まずは思考を整理したい」という状態であれば、相談料を支払って受ける「独立系・個人向け」のサービスを選びましょう。結論を急かされず、あなたのペースを尊重してもらえる環境かどうかが、納得感に直結します。 ② 「アドバイス」よりも「対話」を重視しているか キャリア面談には、大きく分けて「教える(ティーチング)」スタイルと「引き出す(コーチング・対話)」スタイルがあります。 「こうすべきだ」と一方的にアドバイスを受ける場ではなく、あなたの言葉を丁寧に聴き、問いかけを通じて「あなたの中にある答え」を一緒に探してくれるサービスを選んでください。自分の気持ちが置き去りにされないことで、面談の満足度は大きく変わります。 ③ 「プロとしての専門性」と「安心感」があるか 相手がキャリアコンサルタント(国家資格)などの専門資格を持っているか、また守秘義務が徹底されているかを確認しましょう。 また、最近はオンライン面談が主流ですが、「事前の説明が丁寧か」「単発でも受けられるか」といった、利用者への配慮があるかどうかも、信頼できるサービスを見極める指標になります。 まとめ キャリア面談・キャリアコンサルティングは決して転職するためだけの手段ではありません。 むしろ、日々の忙しさの中で後回しにしてしまいがちな「自分はどう生きたいのか」「今の仕事を通して何を実現したいのか」という本音を一度立ち止まって整理し、自分なりの答えを見つけるための大切な時間です。 「まだ何も決まっていない」 「何を相談すればいいかわからない」 「今の会社を辞める勇気も、続ける自信もない」 そんな、言葉にならない状態でも利用する価値は十分にあります。一人で抱え込んで同じ場所をぐるぐると回り続ける時間はもう終わりにして、プロと一緒に思考の棚卸しをしてみませんか? キャリア面談を試してみませんか? ここまで読んで、 「今の仕事、このままでいいのかな?」 「誰かと話しながら整理できたら、少しは楽になるかも……」 もしそう思い当たることがあるのなら、それはあなたが次のステージへ進もうとしているサインです。 私たちキャリア・コンサルティング・ラボは、転職を前提としないキャリア面談を提供しています。今すぐ結論を出す必要はありません。今感じている迷いや不安を、そのままお持ちください。 キャリア・コンサルティング・ラボの面談が選ばれる理由 100%中立・転職前提ではない安心感 求人を無理に勧めることは一切ありません。「今の会社に残る」という選択肢も含め、フラットに考えます。 「まとまっていない」をプロが言語化: 相談内容がはっきりしていなくても大丈夫です。対話を通じて、あなたの頭の中にある「絡まった糸」を一本ずつ解きほぐします。 1回60分、自宅からオンラインで: 単発のお申し込みも歓迎です。忙しい日々の中でも、自分のためだけの時間を確保できます。 キャリア面談は「今すぐ何かを決めるための場」ではありません。 「一人で考え続けるのが少しつらくなってきた」 「頭の中を一度プロの視点で整理したい」 そう感じたタイミングでの選択肢の一つとして、検討してみてください。 キャリア面談の詳細を見る※転職を勧めることはありません。ご自身のペースで考えることを大切にしています。

40代のキャリアチェンジを成功させる方法!転職しやすい仕事の特徴も解説
かつての日本には「転職は35歳まで」とする説がありました。そのため今でも「40代からのキャリアチェンジは難しいのでは?」と不安に思う人が少なくありません。 しかし「35歳転職限界説」は過去の考え方であり、現代においては40代からでもキャリアチェンジを成功させることが可能です。 この記事では、40代のキャリアチェンジが難しいといわれる理由や転職を成功させる方法、キャリアチェンジにおすすめな仕事の特徴などを詳しく解説します。 40代のキャリアチェンジ、可能だが難易度は高い 冒頭でもお伝えした通り、今は40代からでもキャリアチェンジが可能です。ただし、転職市場ではどうしても若手が有利になりやすい面があるため、20代・30代に比べるとやはり40代はキャリアチェンジの難易度が高くなります。 また、40代は今の会社で一定のキャリアや地位を築いているケースも多く、キャリアチェンジすることで年収・待遇が下がるリスクもゼロではありません。 前職と同水準の年収を希望する場合、キャリアチェンジはより難しくなりやすいです。 40代のキャリアチェンジが難しいといわれる理由 40代のキャリアチェンジが難しいとされる理由は、他にもあります。ここでは、40代のキャリアチェンジが難しいといわれている理由を詳しく見ていきましょう。 年齢制限で応募できない求人が増える 「長期的なキャリアの形成」を理由に、求人に年齢制限を設ける会社は少なくありません。「長期的なキャリアの形成」が理由の場合、応募できるのは30代までとされることが多いです。また、例外を除けば原則として求人に年齢制限を設けるのは法律で禁止されていますが、実際には企業で採用したい年代をある程度想定していることもよくあります。その多くは20~30代です。 その結果、20代・30代に比べると40代は応募できる求人が少ない、あるいは応募しても他の候補者との選考のなかで厳しい状況になりがちなため、キャリアチェンジが難しいといわれています。 もちろん40代向けの求人もありますが、そのような求人では管理職の経験や専門スキルが求められがちです。未経験の業界・職種への挑戦は難しく、選択肢が限られやすくなります。 専門スキルやマネジメント経験が求められる 企業の採用方法には、大きく分けて「ポテンシャル採用」と「即戦力採用」があります。 ポテンシャル採用では応募者の「伸びしろ・意欲」が重視されるのに対し、即戦力採用では応募者の「スキル・経験」が重視されるのです。 そして、40代の転職では多くの会社で即戦力採用が用いられます。一から育てる人材としてではなく、入社後すぐに戦力になる人材が求められ、専門スキルやマネジメント経験といった実績が必須になりやすいため、キャリアチェンジの難易度が高くなる傾向です。 柔軟性や適応力を転職先から懸念されやすい 40代は、既に十年以上に及ぶキャリアを築いており、自分なりの仕事への向き合い方・進め方が確立されているでしょう。 これまでの経験や独自の仕事術は、キャリアチェンジの場面で企業から高く評価してもらえることも多いです。 しかし一方で、「自分の経験ややり方に固執するあまり、転職後の職場環境や業務手順に適応できないのでは?」と、企業から懸念を抱かれる場合もあります。 40代のキャリアチェンジでは、新しい業務を学ぼうとする姿勢や謙虚さも重要視されるポイントです。 40代からキャリアチェンジに挑戦するための準備 40代のキャリアチェンジを成功させるためには、入念な準備が必要です。ここでは、スムーズなキャリアチェンジに欠かせない、事前の心構えや行動を解説しましょう。 長期戦になる覚悟をする 前述した通り、40代になると応募できる求人数が減ります。自分のスキルや希望に合う求人がなかなか見つからず、転職活動が長期化するケースも珍しくありません。 そのため、前もって長期的なキャリアチェンジの計画を立てておくのが重要です。「時間がかかるもの」だと思っておけば、転職活動が長引いても焦らずに済むでしょう。 また、当初の計画以上に転職活動が長引く可能性も十分あるので、収入を途絶えさせないためにも今の会社に在籍しながらキャリアチェンジを検討するのがおすすめです。 徹底的に自己分析を行う 高難易度の40代のキャリアチェンジでは、自分が持つ強みを採用担当者に正確に伝えられるかが非常に重要になります。具体的な転職活動を行う前に、必ず丁寧に自己分析しましょう。 自己分析を怠り自己理解が浅いままでは、転職活動で良い結果が出にくいですし、たとえ採用されたとしても後々ミスマッチを起こすリスクが高いです。 まずは、これまでの職務経験や実績を振り返る「キャリアの棚卸し」を行い、そこから身につけたスキル、強みや弱み、興味のある分野、価値観などを深掘りしてみてください。 自分の市場価値を知る 自己理解が深まったら、それをもとに自分の転職市場価値を把握します。 自分のスキルや経験が外部からどのように評価されるのかを正しく理解できれば、現実的な視点でキャリアチェンジを考えられ、戦略的なプランが立てられるでしょう。 市場価値を知る方法としては、転職エージェントやキャリアコンサルタントから評価をもらう、提示される企業のオファーから判断するなどが挙げられます。この他、近年は市場価値を数値化してくれる診断ツールを活用する方法も人気です。 キャリアチェンジ後のビジョンまで明確にする キャリアチェンジを考えるうえで重要なのが、キャリアビジョンです。 キャリアビジョンとは、仕事や人生における「将来自分はこうなりたい」という理想像や目標を指します。仕事だけでなくプライベートも含めた人生全体の未来像を描くことで、目指すべき方向性が明確になり、主体的にキャリアを選択・形成できるようになるのです。 自己分析の結果をもとに将来の自分を具体的にイメージし、理想の将来像から逆算した行動計画を立ててみましょう。 希望条件に優先順位をつける キャリアチェンジで今より条件の良い環境に身を置きたいのは、誰もが同じ。しかし、漠然と条件の良い会社を求めると「完璧な条件の会社」にこだわりすぎて就職活動が難航したり、明確な軸がない分「何となく」で会社を選んでミスマッチが起きたりします。 自分の理想を全て叶える会社はなかなか見つからないので、前もって「絶対譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確にしておきましょう。 希望条件に優先順位をつけると、企業選びがスムーズになり、本当に自分に合う環境が見つかりやすいです。 40代のキャリアチェンジを成功させる方法 40代のキャリアチェンジは簡単ではありません。しかし、きちんと手順を踏んでポイントを押さえれば、成功できる可能性は十分あります。 ここでは、40代のキャリアチェンジを成功させる方法について解説しましょう。 経験やスキルを活かせる職種を選ぶ これまでの経験やスキルが活かせる職種を選ぶと、自分の強みと企業が求めるものがマッチしやすく、キャリアチェンジに成功できる可能性が高まります。 たとえ未経験の職種に挑戦する場合でも、過去の経験により培われたコミュニケーション能力やタスク管理能力などは活かせるでしょう。 自分が持つスキル・能力を正確に分析したうえで、キャリアチェンジ後にも活かせそうかを考えるのが重要です。 応募先の企業をよく研究する 40代のキャリアチェンジでは、応募する企業を徹底的に研究し、本当に自分に合うのかをよく分析してください。 企業の事業内容やビジョンなどを深く理解することで、「なぜその企業でなければならないのか」という理由が明確になり、面接でも説得力のある回答ができるようになります。 徹底した企業研究は、キャリアチェンジに失敗しないための有効な対策の一つです。イメージと現実のギャップを埋められれば、キャリアチェンジ後に「思っていたのと違った…」とミスマッチを感じるのも防げるでしょう。 ポータブルスキルを武器にする 仕事で役立つスキルには、特定の仕事で役立つ「テクニカルスキル」と、業種・職種・業界を問わずどんな仕事でも役立つ「ポータブルスキル」があります。コミュニケーション能力、問題解決能力、情報収集力、論理的思考力などが、ポータブルスキルの代表例です。 これまでのキャリアで培った豊富なポータブルスキルは、20代・30代にはない「40代ならではの強い武器」になります。 自分にどんなポータブルスキルがあるかを把握し、具体的に言語化できるようにしておきましょう。 面接では人間性の良さもアピールする 「固定観念に縛られず、新しい環境に適応してくれるだろうか」「上司や同僚が年下でも、円滑に関係構築できるだろうか」 40代のキャリアチェンジでは、企業からこのような点を懸念されやすいです。そのため面接では、実績やスキルだけでなく、柔軟性や適応力といった人間性の面もアピールする必要があります。 ただの性格自慢にならないよう具体的なエピソードを交え、企業が求める人物像に合致するように話すのがポイントです。 キャリアコンサルティングを活用する 40代は、これまでの長いキャリアがあるからこそ、自己分析が複雑になりがち。 また、「40代でキャリアチェンジして本当に後悔しないか?」と不安になったり、転職活動が難航して「どうすればうまくいくのか」と悩んだりするケースも多いです。 そのため、無理に一人で全てを解決しようとせず、キャリアコンサルティングをうまく活用するのが良いでしょう。 キャリアコンサルティングでは「キャリアチェンジすべきか」という疑問から、具体的な転職に関する悩みまで、徹底的にサポートしてもらえます。キャリアの棚卸しや自己分析のサポートも任せられるので、キャリアチェンジがスムーズに進みやすいです。 40代のキャリアチェンジに適した仕事の特徴 年齢問わず活躍できて評価してもらえる仕事を選ぶと、40代のキャリアチェンジのハードルはぐっと下がります。ここでは、40代のキャリアチェンジに適した仕事の特徴を紹介しましょう。 働き方の選択肢が多い仕事 40代は育児の真っ最中という人や、親の介護が始まる人も多い年代です。また、ゆくゆく年齢を重ねて、今の働き方を続けるのが難しくなる可能性も考えられます。 将来にかけて私生活での変化が大きくなりやすいので、キャリアチェンジでは働き方の選択肢が多い仕事を選んだほうが後々「よかった」と思えるかもしれません。 今は多様な働き方ができる時代なので、新しい働き方にも目を向けてキャリアチェンジを考えましょう。 人手不足で求人が豊富な仕事 人手不足な仕事は、求人が豊富なうえ年齢制限を設ける会社が少ない傾向です。選考を突破できる確率も高く、40代という年齢が不利になりにくいでしょう。 「人手不足な仕事は、きつかったり待遇が悪かったりするのでは?」と心配する人も多いですが、人手不足の仕事が全てそうとは限りません。 一般的なイメージだけで応募できる求人の幅を狭めないよう、条件や待遇をしっかり確認したうえで、自分に合いそうかを考えるのが重要です。 同世代が多く活躍している仕事 社内に同世代の人が多いと、価値観や境遇を共有しやすく、キャリアチェンジ後も早く新しい環境に馴染めます。わからないことも質問しやすいので、スムーズに連携を取りながら仕事を進められるでしょう。 また、同世代の人が働きやすいと思う職場環境は、自分にとっても働きやすい環境である可能性が高いです。 求人情報に会社の年代構成が掲載されていない場合は、転職活動の面接で質問してみてください。 実力重視の傾向を持つ仕事 徐々に薄れつつありますが、日本にはまだまだ年功序列の文化を持つ会社もあります。勤続年数で評価する仕事に40代からチャレンジしても、その後キャリアアップしにくく不満を抱く可能性が高いです。 そのため40代のキャリアチェンジでは、本人の努力や実績、取得資格といった実力で評価してくれる仕事のほうが良いでしょう。 転職先選びの際には、企業の評価基準もしっかり把握しておくのが大切です。 40代でもキャリアチェンジは可能!まずは一歩踏み出そう 40代のキャリアチェンジが、20代・30代に比べて難しいのは事実です。しかし難しい=不可能ではなく、40代からでもしっかり準備を整えて適切に行動すれば、納得のいくキャリアチェンジができます。 今は、キャリアの悩みを気軽に相談できるキャリアコンサルティングサービスもあるので、有効活用しながら効率的にキャリアチェンジを進めていきましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボは、40代のキャリアチェンジにまつわる悩みも多数サポートしてきた実績があります。キャリアチェンジに悩みや不安がある方は、ぜひ一度相談してみてくださいね。

