
キャリア迷子?30代が抱える悩みと今後を楽しむための対処法
「キャリア迷子」という言葉を耳にしたことのある方は、多いのではないでしょうか。 「キャリア迷子」とは、キャリアに悩みを抱えて今後の展望が描けない状態のことで、リクルートワークス研究所の調査によると日本人の約8割に該当するという結果が出ました。そして年代別では30代が一番高い割合を示したそうです。 「自分の今後のキャリアが心配だ…」「30代だけどキャリア迷子で大丈夫なの?」 という方に、今回は30代で「キャリア迷子」になる原因や対処法をご紹介します。 キャリア迷子に陥る原因は? なぜキャリア迷子に陥るのでしょうか。 その根本的な原因は、自分のキャリアに自信がないということが大きく関係しています。ここでは、キャリア迷子になる原因を4つご紹介します。 人と比べて専門性がない 30代でキャリア迷子であると感じる方の多くは、今までのキャリアに統一性がないという方が多いと言われています。 20代で複数回職種を変えて転職を経験した方はもちろん、社内異動でさまざまな部署を回ったという方もいらっしゃるでしょう。 同じ30代でも事務職で内勤から営業職で外回りなどを経験した方と、新卒から人事一筋でキャリアを歩んできた人との間では専門性が大きく異なります。そういった専門性を持った方と自分を比べて、なんとなく自分の専門スキルはなんだろうとキャリアについて悩みを感じる方は少なくありません。 今まで仕事は頑張ってきたけど、「何ができるか」「何が専門か」と聞かれると困ってしまう…そんな状況が原因になっているようです。 今後のキャリアパスが不透明 一方で、ずっと同じ部署や職種を経験している方にも悩みの種が。傍目には一貫した経験がある状況ですが、「この部署やこの業務しかしていないけれど、本当にこのままでいいのか」「ここにいると、どうなるのか」とキャリアパスに疑問を感じたり、キャリアパスを不透明に感じてしまう方もいるようです。 例えばわかりやすく年功序列の企業であれば、「40代まで頑張れば部長になれる」など明確なキャリアパスがイメージできるかもしれません。 しかし現在は、年功序列が明確な企業は少なくなっているため、このまま仕事を続けていて定年まで平社員かもしれないと不安になります。 そういった環境では、自分のキャリアはこのまま終わっていいのか?とキャリア迷子に陥ってしまうのではないでしょうか。 やりたい仕事がない 「やりたい仕事がない」というのは、30代の方だけの悩みではありません。世の中では「いろいろ思うことはあるけれど、給与のために仕方なく今の仕事をやっている」という人も多いので、焦ることはないのです。 しかしコロナの影響もあり、自由な働き方が広がっているので自分の好きなことを仕事にしている人の話を、周囲やネットニュースなどで目にする機会が増えたかもしれません。 そういったこともあり、自分はやりたいことがないけど大丈夫かなと不安になってしまいます。 やりたい事というのは、必ずしも仕事の中で見つけなければいけないものではありません。必死になって仕事の中にやりたいことを探すのではなく、趣味などでもいいのです。 あなたの人生の中で「仕事」というものの立ち位置を、もう一度考えてみてもいいかもしれません。 仕事とプライベートの両立ができていない 30代で仕事が忙しく、プライベートの時間がうまく取れていないという方は、仕事とプライベートのバランスを見直したいと思っているのではないでしょうか。 20代から30代まで仕事に打ち込んできたけれど、今後もずっと今の働き方はできないと感じることもあります。仕事を頑張りすぎてプライベート時間を取るのが難しくなると、何のために働いているのだろうという気持ちになりますよね。 また、30代で結婚などライフイベントの発生で、働き方を見直したくなるということもあるでしょう。 そんな思いから、「本当に自分の人生、このままでいいのか」とキャリア迷子になってしまう方もいらっしゃるかもしれません。 そんなときには、今の仕事で、仕事とプライベートを両立できているのであれば問題ありませんが、少しでも疑問を感じるのであれば残業時間や業務量など、働き方を見直す必要があります。 毎日は無理でも水曜日はノー残業デイにするなど、自分の中でルールを作ってみるのもおすすめですよ。 キャリア迷子になりそうな時の対処法 キャリアに対して今後の不安があるときは、まず何か行動を起こしてみるのが不安を軽減する近道になります。キャリアなどこれからずっと続いていくものに対して、何もしていないという状態が一番不安を感じやすいからです。 仕事に関係するものから、仕事に関係ないものまで、おすすめの対処法をご紹介します。 新しいスキルの習得に挑戦する 専門性がない、自分のできることがわからない、など自分に自信が持てずキャリア迷子になってしまっている方は、新しいスキルの習得に挑戦してみるのはいかがでしょうか。 とりあえず興味のあることや、今の仕事の延長線上にある資格などの勉強をしてみると、この分野をもっと知りたい!など興味が湧くかもしれません。興味の湧くことがあればそこに対してスキルを磨いていくことで、今後のキャリアの選択肢が広がっていきます。 もし転職など環境を変える選択をする際にも、先に知識やスキルと付けていくことで大きなアドバンテージになるからです。 興味のあることが見つからなかったとしても、新しいことを学んでいるという状態は停滞していると感じていた自分自身に対して、ちゃんと新しいことに挑戦しているという感覚を持つこともできます。その自己肯定感が、キャリア迷子から抜け出すきっかけになるかもしれません。 会社以外での活動を始めてみる キャリアに悩んで仕事のことばかり考えてしまっている方は、一度仕事のことや会社関係者とは違うコミュニティでの活動をしてみるのがおすすめです。 無理して趣味を作らなくてもいいですが、違った環境の方と話したり交流することで新しい発見や価値観が芽生えるかもしれません。お酒を飲むのが好きな方であればいつも同僚と行く店ではなく、ちょっと足を伸ばして初めてのエリアに飲みに行ってみるのもいいでしょう。 何かを始めるのに初期投資をしてしまうと、それが自分にあまり合わなかったとしても、「お金かけたし、続けないと…」と義務のようになって余計負担に感じてしまいます。 釣りを始めるぞ!ゴルフを始めるぞ!と気合を入れすぎず、いつもの習慣にプラスαで変化を与えていくのはいかがでしょうか。 自己分析をして今の自分を知る 今後のキャリアに悩んでしまい何も行動を起こせないという方は、現在の自分を知ることをおすすめします。 自己分析というと大学生が就職活動をするときに行うようなイメージですが、仕事を経験した30代になってもう一度しっかりと自己分析すると、就職活動のころとは違う新たな発見や気づきがあると思います。 学生時代に目標としていた姿と、30代になって今目標としたい姿は大きく異なっていることもよくあります。 今の自分には何ができるのか、それは理想の自分とはかけ離れているのか、さまざまな視点で客観的に自分を見返すことができます。 特に、社内でも管理職のポジションに就いている方であれば、客観的に誰かから意見をもらうことも減っているのではないでしょうか。そのような方にはとてもいい機会になるはずです。 また、なぜ今の会社に入社して、どのようになりたかったのかという初心を思い出すこともできます。初心を思い出し、またここで頑張るぞとなるのか自分の理想と大幅にずれてしまっているから軌道修正が必要だと感じるのかはわかりません。 しかしどちらにしても、30代で自己分析をしっかりと行うことは何かしらの転機になるはずです。 今後のキャリアプランを練る キャリアに悩み、もうどうしたらいいかわからない!という方はプロと一緒にキャリアプランを練ってみてください。 キャリアプランを練るだけでプロに頼るの?と思う方が多いかもしれません。しかし自分ひとりで考えていると、見落としてしまうこともありますし、堂々巡りになってしまうこともよくあります。また、自分のキャリアの価値を、過小評価してしまう方も多くいます。 ひとりで悩んでキャリア迷子になっているあなただからこそ、プロと二人三脚でキャリアプランを練ることをおすすめします。 友人などに相談するのも一つの手段ですが、30代になると友人にキャリアの悩みを相談するのを躊躇う方も多くいます。周りに劣等感を感じている方などは、特にひとりで溜め込んでしまうでしょう。 また、正直なところ、友人からのアドバイスは素直に受け入れられないということもあるのではないでしょうか。 プロに相談というと転職を進められそうなイメージですが、転職エージェントなどを仕事を斡旋するサービスで相談するのではなく、キャリアコンサルタントにキャリアの相談をするだけのサービスもあります。 「現職にとどまった方がいい」という選択肢も含めて、中立で客観的な立場からの意見やアドバイスをもらうことができるので、悩んでいる時間がもったいない!と感じる方はぜひプロへの相談を検討してみてください。 これからの30代を楽しむためには? キャリアに悩んでばかりで30代を楽しめていないのは、とても勿体無いことです。 これから40代目前の方も30代になったばかりの方も、これからを楽しむために必要な考え方をご紹介します。 自分の軸になるものを知っておく 30代だからこそ今までの経験から、「これは譲れない」というものができてきたのではないでしょうか。 自分では気づいていなくても、日々選択を行う上で何か自分の軸になるものがあるはずです。これまで何かを決断するときに、最終判断をしていた軸を思い出してみるのもいいかもしれません。 例えば、今の会社に入社した理由は「転勤がなかったから」なのであれば、住まい環境などプライベート重視しているのかもしれません。プライベート重視ということは、家族との時間や自分の趣味の時間を重要視しているのではないでしょうか。 そういった過去の経験から深掘りしてくことで、自分が潜在的に大切にしているものに気づくことができます。 何か転機があったのであれば、その選択はなぜだったかを思い出すようにしてみてください。 旅行や趣味に時間とお金をかける キャリア迷子について考えすぎるのは良くありません。キャリアについてはっきりとした正解はないからです。 自分自身で、これでいいんだと思える選択をするのが正解となります。 悩みすぎて塞ぎ込んでしまう前に、今の年齢でできる旅行や趣味に時間をかけてみるのはいかがでしょうか。もし挑戦したことのないアクティビティなどあればどんどん挑戦していくことで、気分転換になります。 例えば、年齢制限のあるダイビングなどもいいでしょう。今だからこそできるということを探してみてください。そういった経験の中から、興味のあることが見つかるかもしれません。 また気分転換をすることで、旅行などの「趣味のために仕事をする」という気持ちになるかもしれませんし、「趣味の絵を副業にしていきたい」など新しいキャリアの道が拓かれるかもしれません。 いずれにせよ、何かしら日々の生活に変化を起こしてみることが大切です。 運動習慣をつけておく どういうキャリアを歩んでいくとしても、自分の健康に気を遣っていかなければなりません。 今までデスクワークのみで基本的に座っての作業だった方などは、これを機に運動習慣を取り入れてみるのもおすすめです。 体を動かしてみるとストレスが軽減されたり、頭がすっきりしたりする効果があります。キャリア迷子になっていたとしても、実はちょっと考えすぎだったなと思えるかもしれません。 適度な運動習慣が、あなたの人生において悪影響を及ぼすことはありません。どうせ何かするのであれば、まずはウォーキングなどの軽い運動から始めてみてはいかがでしょうか。 家族との時間を大切にする ぜひ家族との時間を見直してみてください。ちゃんとご家族と一緒に食事をしていますか?毎日会話はありますか?少しいつもより一緒に過ごす時間を増やしてみてください。 仕事ばかりであまり実家に帰ってないという方は、ぜひ親孝行してみてください。今しかできないことをしておくことも、大事です。 また家族や両親をコミュニケーションをとることで、得られる気づきもあります。ご両親がとても仕事を頑張ってくれていたことや、実は転職も経験していたことなど30代になった今だからお互いに話せることもあるはずです。 あなたが何かしら決断を迷っているのであれば、背中を押してくれる相手になるかもしれません。 新たな挑戦に踏み切る 30代で新たな挑戦をすることを躊躇う方もいるはずです。しかし新しい挑戦をするにあたって、年齢を気にすることは全くありません。 人生100年時代と言われているほどなので、これからの方がずっとずっと長いのです。今モヤモヤ悩みがあるのであれば思い切って何かに挑戦してみるのもありでしょう。 転職や起業など大きく環境を変えてみるのもいいですし、思い切って地方移住するという選択もあります。 深刻に考えすぎない キャリア迷子という言葉を使うと、早くどうにかしないと!と悩んでしまうでしょう。しかし30代であればまだまだキャリアは続いていきます。 また、本記事では30代にフォーカスしてご紹介しましたが、キャリアに悩むタイミングは人それぞれです。20代後半や40代以降の方にも当てはまる内容が多く含まれていますので、ぜひご自身の状況と照らし合わせてご活用ください。 今深刻に考えすぎて焦って決断してしまうと後悔してしまうかもしれません。 あまり悩みすぎず、まずは気分転換や人に相談することで客観的に自分の状態を知るところから始めてみてください。

部下にストレスを感じて限界…合わない部下への対処法
部下の中には、うまく意思疎通できなかったりこちらをイライラさせたりする「ストレスになる部下」がいます。このような部下をもつと上司は仕事のストレスが倍増し、時には「もう限界!」と思うこともあるでしょう。 この記事では、ストレスになる部下の特徴や対処法、ストレスが限界に達したときに取るべき行動などを解説します。 ストレスを限界に到達させる部下の特徴 「ストレスになる部下」といっても、さまざまなタイプがいます。まずは、ストレスを限界に到達させる部下の特徴から見ていきましょう。 いつまでたっても仕事ができない 部下は自分よりも経験が浅いのですから、できない仕事があっても無理ありません。 とはいえ、過去に教えたことを何度も聞いてくる、同じミスを繰り返すなど、全く成長が見えない状態が続くと、やる気がないように思えて部下にストレスを感じるでしょう。 いつまでたっても仕事ができない部下は責任感も乏しく、目標達成意欲や自発性も低い傾向にあります。なかなか自分から動いてくれないため上司側は手を焼き、対応に困るはずです。 指示・指摘に従わない こちらの指示や指摘に従ってくれない部下もストレスの根源です。指示や指摘に従うことを想定して業務のスケジュールを立てても、部下が従わなければ計画が狂ってしまいます。 部下が従ってくれないストレスだけでなく、仕事がスムーズに進まないストレスも加わるので、精神的に限界を感じやすいです。 しかし、部下が指示に従わないのは「上司への不信感」が原因かもしれません。まずは本人とじっくり話をして、「なぜ従わないのか」を明らかにしましょう。 言い訳や文句が多い 仕事を頼んだり指摘をしたりすると、毎回のように「いや、でも…」「えぇ…マジですか…」と言い訳や文句をつけてくる部下もいます。本当に理由があるときならまだしも、常にこんな調子だと会話するたびにストレスがたまり、そのうち相手への不満が限界に達するでしょう。 また、コミュニケーションがすんなりいかないため次第に接触がおっくうになり、深刻なコミュニケーション不足に発展するケースも少なくありません。 一般常識がない あいさつや報連相、ミスをしたときの謝罪、言葉遣いなどは、社会人になる前から身に付けておいてほしい一般常識です。 しかし、一般常識さえ持っていない部下も少なからず存在し、そのような部下がいると上司は業務に関する指導だけでなく、社会人としての自覚やモラルまで指導する羽目になります。 指導範囲が広がって大変なだけでなく「どうして当たり前のことができないのだろう」というイライラも感じやすくなるため、部下へのストレスが限界に達しやすくなるのです。 コミュニケーション能力に欠ける コミュニケーションが得意な部下もいれば苦手な部下もいて当然ですが、苦手すぎて仕事に必要な会話さえ成り立たないレベルだと、上司はストレスを感じます。 部下のコミュニケーション能力が著しく低いと、会話のキャッチボールが成立せず「本当に理解しているのかな」「何を考えているんだろう」と不安になることもしばしば。 部下が仕事のやり方に悩んでいたり、トラブルを抱えていたりしても上司は気づいてあげられないので、後々大きな問題に発展する場合もあります。 勤務態度に問題がある 遅刻や欠勤が多い、仕事をサボる、大変な仕事を人に押し付けるなど、勤務態度に問題がある部下は、対処が難しく上司の頭を悩ませる存在。部下の「問題行動」だけにイライラするのではなく「問題行動を取るような人間性」ごと苦手になってしまうので、部下との関係もギクシャクしやすいです。 部下の問題行動の尻拭いは上司である自分がやることになる場合が多いので、回数が重なればストレスが限界を迎えるでしょう。 部下にストレスを感じたときは自分の行動もチェック 上司に大きなストレスを与える部下には問題がありますが、場合によっては部下をうまく扱えていない上司側にも問題があることも。そのため、部下にストレスを感じたときは、上司である自分の行動に問題がなかったか振り返ってみるのも大切です。 ここからは、部下との人間関係で悩んだときに確認してほしい5つのポイントを解説します。 指示や判断は的確か 素直に従わない部下や文句が多い部下、勤務態度に問題がある部下などは、あなたの指示や判断に納得できていないから、問題行動を取るのかもしれません。 また、たとえ指示は的確でも、詳細な説明を行わず部下の納得を得ないまま物事を進めたり、部下の反感を買うような直接的な言い方をしたりしていると、関係に亀裂が生じやすいです。 部下は、あなたの普段の振る舞いや仕事ぶりから「尊敬できるか」「慕っていい人物か」を判断しています。これまでの指示や判断を見直し、今後に活かせる部分があるなら改善していきましょう。 感情的になっていないか 忙しいと強い口調になる、ミスをした部下を大声で叱責するなど、職場で感情的になっていませんか。 感情的な上司は、部下から恐怖心や苦手意識を持たれます。部下は「怒られたくない」という気持ちから上司の機嫌を伺うようになり、委縮するあまり仕事に必要な会話まで控えやすくなるのです。 感情的な自覚がある人は、自分がどんな場面で感情的になりやすいかを分析し、気持ちをうまくコントロールできるようになりましょう。 計画や目標を共有しているか 現時点の計画や目標、今後のビジョンなどは、部下にもしっかり共有しなくてはいけません。 どのように仕事を進めていくのか、どこがゴールなのかが不確かだと、部下のモチベーションが続きにくいためです。また、計画や目標を曖昧にしか伝えないと、部下は「自分は頼りにされていないんだ」と思い、さらにやる気をなくしてしまいます。 一つの計画・目標を共有することで自然と仲間意識が生まれ、それが部下の意欲や責任感につながるケースも多いので、情報共有は徹底しましょう。 自らも行動しているか 上司の中には、部下にばかり仕事を任せて自分はうまく手を抜いている人もいます。しかし部下は上司をよく見ており、「上司の仕事に対する姿勢」は部下にも伝染するものです。 部下とギクシャクしてストレスを感じる原因は、深く掘り下げると「自分が取るべき行動を取っていないこと」にあるのかもしれません。 上司としての自分を振り返り、自ら率先して行動できていたか、困っている人や忙しい人を積極的にサポートしていたかなどを客観視してみましょう。 部下に公平に接しているか 他にも部下がいる場合、ストレスを感じる部下とそれ以外の部下とで対応に差をつけてはいけません。 上司も人間なので、相性が良い部下と悪い部下がいるのは仕方がないことです。ですがそれを目に見える形で表現してしまうと部下の目には「ひいき」のように映り、部下からの信頼を失います。 上司の不公平な態度は、部下の問題行動や反抗的な態度をエスカレートさせやすいため、どの部下にも平等に接するよう心がけてください。 ストレスを感じる部下への対処法 ストレスを抱えているときに一番やってはいけない行動は「ストレスを無視する」です。ストレスを放置すると、心身や仕事の効率に悪影響を及ぼす場合があります。 ここでは、部下にストレスを感じたときに試してほしい対処法を解説するので、ぜひ今日から実践してみてください。 ストレスの原因を見つける 部下に対してストレスを感じていても、どんなところが苦手なのか、何をされると嫌なのかがぼんやりしている場合も多いです。 しかし、ストレスの原因を把握しないと今後の対処法も見つけにくくなるので、まずは部下をよく分析しましょう。 上司だからと遠慮せず、一人の人間として部下を見て「合わない」「嫌い」「苦手」と思う部分を紙に書き出してみてください。書き出したものをもとに「自分は何をされると強くストレスを感じるのか」を考え、原因を探っていきます。 積極的に部下とコミュニケーションを取ってみる 部下とギクシャクする関係性にストレスを感じている場合は、こちらから歩み寄ってコミュニケーションを増やしてみてください。コミュニケーション不足を解消するだけで、部下の態度や仕事への取り組み方が改善するケースも多いです。 1on1ミーティングを実施してストレスになる部下とじっくり話してみるのも効果的ですが、いきなり2人はちょっと…という場合は、特別な頼みごとをしてみましょう。 部下の負担にならない程度のちょっとした個別の頼みごとをすると、必然的に話す機会が増えるうえ、暗に「頼りにしている」と伝えられるので関係が円滑になりやすいです。 第三者の力を借りる 「部下とのコミュニケーションを増やしたほうがいいとわかっていても、ストレスが限界に近くて難しい」このような場合は、第三者に間に入ってもらってコミュニケーションを取るのがおすすめです。 他の人も輪に入れて話すなら、2人きりで話すよりも会話が弾みやすく、自然なコミュニケーションが取れます。 また、誰とでも公平に接しているように見えるので、部下からの印象も悪くならないでしょう。 悪い部分は注意・指摘する 「部下と良好な関係を築いてストレスを軽減させたい」と考える上司は、部下に気を使って注意や指摘を控える傾向にあります。 しかし、部下の指導は上司の役目なので、部下の悪い部分はきちんと注意・指摘しましょう。 また、注意や指摘をした際、たとえ部下が腑に落ちない様子でも感情的になってはいけません。感情的に伝えると部下は委縮したり反感をもったりするので、冷静かつ淡々と「どこが間違っていたのか」「どうすればよかったのか」を伝えるのがコツです。 無理に好きになろうとしない 部下がストレスを与えてきたとしても、自分が上司でいる以上は相手を冷遇できません。とはいえ、それはどんな部下も肯定し、好きになることとは別です。 あなたは確かに「上司」ですが、それ以前に「一人の人間」であり、当然他人との相性の良し悪しや好き嫌いがあります。ストレスを感じる部下に苦手意識を持っている場合、無理に好きになろうとすると余計にストレスがたまるので、本音は本音として受け止めましょう。 合わない部下に悩む上司に求められるのは、「部下を好きになること」ではなく「仕事と割り切って丁寧に接すること」です。 部下へのストレスが限界なときは いろいろ実践してみても部下との関係がうまくいかず、ストレスが限界なときもあるでしょう。そんなときは自分を守ることに重きを置き、以下の行動を取ってください。 接触を最低限にする 部下へのストレスが限界なときは、相手との接触を必要最低限にするのがおすすめです。交流は仕事の話や相手から話しかけられたときだけにし、自分からは接点を持たないようにしましょう。 部下との相性が悪い場合は、無理にコミュニケーションを取るのではなく、お互いに距離を置いたほうがうまくいく場合もあります。 ただし、交流が少ないうえ態度まで硬いと部下も違和感を持つので、接する際は柔らかい言葉や口調を意識してください。 上司や管理職に相談する ストレスが限界に達するほど部下の態度や行動に問題がある場合は、自分の上司・管理職に相談してみてください。相談することで配置換えを検討してもらえたり、第三者から部下に直接注意してもらえたりする可能性があります。 また、すぐには対処してもらえない場合でも、状況を報告しておけばいざというときに力を貸してくれるでしょう。 部下への接し方で上司から具体的なアドバイスがもらえる場合もあるので、悩みを社内の人と共有してみてください。 部下へのストレスを限界までためない工夫が大切 部下といっても、もともとは「異なる考え方や価値観を持つ他人」であり、接する中でストレスを感じることもあります。部下に対してストレスを感じたときは、できるだけ早く原因を特定し、ストレスを軽くする付き合い方や考え方を身に付けてください。 また、誰かに話を聞いてもらって、限界に届く前にストレスを発散させるのも欠かせません。 話す相手は家族や友人でもOKですが、話を聞いたうえで具体的なアドバイスが欲しい場合は、キャリアコンサルタントに相談してみるのがいいでしょう。 キャリアコンサルティングでは、人間関係の悩みや部下のマネジメント方法についても相談できます。うまくストレスの原因を見つけられないときも、一緒に状況を整理して原因を探してくれるので、悩める上司の「心強い味方」となってくれるはずです。

40代でキャリア迷子になってしまったらぜひ知っておきたいこと
「40代だけど今後のキャリアがわからない」「40代だともう転職は難しそう」 そのように感じている方は多いのではないでしょうか。実はあなたが思っているよりも、40代でキャリア迷子になっている方は大勢いるのです。 20代・30代の頃は目の前の仕事に夢中だったけど、40代で部下を持つ立場になるとやりたいことがわからなくなるという状況にも陥りやすくなります。プライベートでもお子さんがいたり、老後のことを考えたりなど簡単に仕事を辞めることも難しいのではないでしょうか。 今回は、40代でキャリア迷子になる理由や、転職を検討する際に知っておくべきことをご紹介していきます。 40代でキャリア迷子になる理由 若い頃に思い描いていた40代は、もうキャリアに対して迷いがなさそうだとイメージしていましたよね。でも実際は、40代だからこそキャリア迷子に陥るということもあるのです。 では、どのような理由でキャリア迷子になってしまうのでしょうか。 ロールモデルがいなくなってくる 20代・30代の頃は、まだ管理職などの役職者の上司がいて仕事を教えてもらうことがあったり、ロールモデルとして尊敬できる先輩がいたのではないでしょうか。 子どもがいてもバリバリ働く先輩がいたり、仕事ができる頼れる上司がいたりしたはずです。 40代になると、もう上は50代の上司だけになってきます。50代の働き方をみていると、もう少しで定年なので仕事に前向きでイキイキしている人が少なく感じるのではないでしょうか。 40代のあなたからすると、定年まで勤め上げるとするとあと10〜20年は働いていくことになります。そのような中で50代の諸先輩方はもう落ち着いていて、ロールモデルになりづらいのが現状です。 定年後も見据えてキャリアを描いている上司などが周りにいるのであれば、ぜひその人に話を聞いて今後の参考などにしていきたいですね。 やりたいことがわからなくなってくる 30代まで仕事に向き合いキャリアを歩んできた人にとって、40代は少し業務的にも落ち着いてきているのではないでしょうか。 仕事を一通りできるようになり、どんどん部下に任せていかないといけない年代になってきているはずです。 自分自身で必死に取り組まないといけないような業務が少なくなり、部下の責任を取らないといけない立場の方も多いのではないでしょうか。 そうなってくると、自分自身は何をしたいのかわからなくなってきますよね。あなたのキャリアなのに、他の人のために時間を使っているような感覚になるのではないでしょうか。 若手の頃は「これができるようになりたい」「上司に認められたい」などのモチベーションがあったかもしれませんが、40代になってワクワクするような新しい仕事を任せてもらえたり、上司に評価をされたりということが減ってしまっている人も多いと思います。 やりたいことが明確でなかったり、環境に不満が出てくると普段の業務に対してもモチベーションが保ちづらくなるでしょう。 キャリアの選択肢が少なくなってくる 40代までしっかりとキャリアを歩んできたあなたにとって、今になってキャリアチェンジは少しハードルが高くなっているはずです。 もちろん40代でも、未経験の職種に挑戦することはできます。しかし、そこに挑戦するにあたっての精神的・体力的・金銭的なハードルがとても高く感じるのではないでしょうか。 積み上げてきたものがあるからこそ、それを手放したり方向転換することに対して踏み出すことにはリスクがつきまといます。お子さんがいる方や、住宅ローンの支払いが残っているという方も大勢いるでしょう。そうなってくると自分の興味関心だけでキャリアチェンジをしたり、今の会社を簡単に退職したりという選択はできなくなってきます。 実際にキャリアの選択肢が少なくなっているということではありませんが、簡単に選ぶことのできる選択肢はあまりないと言えるでしょう。 将来のお金の不安 20代など若い頃であれば、仕事で失敗しても周りや両親を頼ったりすることで生活はなんとかなるという気持ちを持つことができますが、40代になってくると両親も高齢ですし、周りを頼ることも難しくなってきます。 今の生活が安定したものであるなら、なおさら収入を減らしたり不安定なキャリアを選択するというのは難しくなるのではないでしょうか。 もう一生分の貯蓄ができているという方であれば話は違いますが、ほとんどの方が働きながら生計を立てているはずです。現在受け取ることのできる年金の額も年々減ってきてしまっているので、老後の生活資金なども心配ですよね。 今後が心配という状況で仕事まで不安定になるわけには…と考えるのではないでしょうか。40代になると自分のキャリアの選択が周りの人に大きな影響を与えるという観点からも、選択肢が減っていってしまいます。 キャリア迷子にならないためには? キャリア迷子になる人が大勢いたとしても、自分自身はキャリア迷子になりたくないですよね。 ここではキャリア迷子にならないためにできることをご紹介します。 何のために働いているかを明確に キャリア迷子になる状態は、「何のために働いているのか」という問いに迷いがでている時です。日々日々意識するのは難しいかもしれませんが、自分自身が納得できるような理由を言語化してみてください。 「もう働きたくない…」「仕事辞めたい…」と考える日もありますよね。そんな時でも、なぜ働かなければならないのかということが自分の中で明確にあるのであれば、その気持ちを落ち着かせることもできるのではないでしょうか。 家族の生活を守るため、自分のスキルを上げるためなど人によってさまざまな理由があるでしょう。 仕事を楽しまないといけないと思いすぎたり、やりたいことがないといけないと思いすぎると大きなストレスにつながってしまいます。 仕事終わりのお酒が美味しいからというようなものでもいいので、「しんどくてもコレがある」というものを何か思い浮かべられるようにしてみてください。 周りの人に影響されすぎない 40代になると、これまでに多くの人のキャリアアップやキャリアチェンジ、そして社内でのキャリアパスも見てきましたよね。 「あの人は30代で転職して成功してるらしい」など、元同僚の噂話を耳にすることもあるはずです。そういった人の話をきいていると、「自分は何をやっているんだろう?」と思ってしまうのではないでしょうか。多くの人は、人と自分を比べて優劣をつけてしまいます。 人と比べて羨ましくなっても、その人の幸せがあなたにとっての幸せになるかはわからないのです。 転職してイキイキ働いている人を羨ましく思うかもしれませんが、実際は家でも仕事をして休みなく働いていて体力的にも厳しい環境に置かれているかもしれません。起業してうまくいっているように見えても、プライベートでは悩みを抱えているかもしれません。 あなたが目にしたり、耳にしたりする情報は、その人の充実してるように見えるほんの一面でしかないのです。そのような情報で羨ましがったり、多くを望んだりするのは、無駄な悩みになるのではないでしょうか。 まだまだこれから長いキャリアを描いていくのですから、自分自身の軸をしっかりと持って周りに影響されすぎずにいたいですね。 スキルの棚卸しをしておく 「自分には何ができるんだろう?」と感じたら、今までの経験からスキルの棚卸しをしておくことがおすすめです。 「いや、何もスキルなんてありません」と思う方もいるかもしれませんが、何も特別なスキルを指しているわけではありません。 おそらくスキルと言われると、建築士・会計士などの士業や特別な資格をイメージする方が多いのではないでしょうか。 そのような特別なスキルはなくても、日々の業務であなたが難なくできているものがあるはずです。例えば、電話が鳴れば難なく取り継ぎができる方は電話対応のスキルがありますし、営業をしている方であればコミュニケーションスキルがありますよね。 あまり難しく考えすぎずに、幅広くあなたができることを書き出してみてください。自分では普通だと思っていることが、他の会社ではとても求められている可能性もあるのです。 自分に自信がなくて、何もできないと感じてしまっている方はまず今まで仕事を頑張ってきた自分を認めてあげてくださいね。 40代で転職するなら知っておくべきこと 40代での転職だと、今まで積み上げてきたものもありますし、プライベートも守らなければならないものがあったりと、慎重になるのではないでしょうか。 ここでは、40代で転職するなら知っておくべきことをご紹介していきます。 業務未経験だと職種が限られる 40代になると、20代・30代の頃よりも業務未経験の職種へ転職することが難しくなってきます。もちろん職種次第で入社できるところもありますが、正社員スタートが難しくなったり、あなた自身も周りとの年齡差で悩みを抱える可能性があります。 求人の段階でも、未経験歓迎だと長期育成の観点から35歳くらいまでに絞られているものが多くなります。また年齢制限なしだとしても、他の転職希望者があなたよりも若手だった場合は書類の段階でスクリーニングされてしまうと考えた方がよいでしょう。 未経験でも応募できる求人だと、工場勤務などの肉体労働系や運送業がありますが体力的に厳しいと感じるものが多いかもしれません。 例えば、未経験で営業からエンジニアになりたいと思った場合は、今の会社を続けながら副業で知識をつけたり実績を作ったりしてから、転職活動するのが無難です。 年齢で明確に分けられているということではないですが、40代で未経験の職種に挑戦するのであれば、ある程度準備をして転職市場で戦えるだけの武器を用意する必要があります。 経験を生かした転職は可能 40代で転職なんて…と考えている人は多いはずです。新卒から一社で働き続けている人であれば、なおさら今の職場を離れることに対して不安を感じるでしょう。 しかし、40代まで同じ会社でキャリアを歩んできた方であるからこそ違う会社に行ってもその経験や知見を生かして活躍することもできるのです。 20年近く同じ会社にいたのであれば、事業がうまく行っている時も少し厳しい時も経験してきたのではないでしょうか。 外に目を向けてみると、あなたが経験してきたフェーズにいる企業はたくさんあるのです。新規事業立ち上げや、新しいシステムの導入などあまり気にせず対応してきたことでもその経験を欲しがっている企業がいるかもしれません。 40代だからもう転職は出来ないのではなく、40代だからこそできる転職があります。今よりも収入を上げたい、また違う環境に挑戦したいという想いを叶えられる可能性があるのです。 詳しい人に相談することも重要 40代になってくると、気軽に自分の今後のキャリアを人に相談することも少なくなるのではないでしょうか。周りが後輩ばかりになっていたり、逆に上司は気軽に相談できるような役職ではなかったりする方も多いはずです。 家族や友人に相談することもできますが、転職に対してネガティブな印象を持っている場合には、キャリア云々ではなく頭ごなしに否定されてしまう可能性もあります。 少しでも転職が気になるのであれば、プロのコンサルタントに相談することがおすすめです。そもそもなぜ転職したいのか、転職して叶えたいことなどを整理してもらえるようなサービスを利用してみてください。 今の転職市場であなたがどのような評価をされるのか、また企業の求人数はどのように変動しているかなど、自分自身で得られる情報にも限界がありますよね。 40代だからこそ、並べられた仕事の中から自分ができそうなものを選ぶのではなく、情報収集を行い、しっかりと自分の理想の働き方や想いを整理することで納得感のある転職活動を行う必要があります。 プロと話した結果、今の職場にいることを選択しても退職を選択しても後悔しないように行動を起こしてみてください。

社会人としてこのままでいいのか不安な時に試したい5つの方法
仕事をしていて、ふと「このままでいいのか」と不安に思うことは誰にでもあります。 今の仕事や環境の何が不満というものがなかったとしても、やりたいことを見つけて転職や独立する友人知人、社内でバリバリと活躍する同僚や後輩をみたり、将来のことを考えたりすると、自分はこのままでいいのかとつい考え込んでしまう…それは誰もが経験することでしょう。 将来への小さな不安は日常生活に紛れてしまうことも多いですが、モヤモヤした不安がいつまでも消えないこともよくありますよね。そんなときには、こんな行動を試してみませんか。 1. 不安を感じる自分の気持ちを整理してみる 「不安」は漠然としたままでは、どうしていいかわからないものですが、その原因がわかれば、「不安」の解消法も見えてきます。解消法が見えてきたら、あとはそれを試していくことで、たとえ解決しなかったとしても何かしら状況は変わっていきます。 つまり、不安を感じる自分の気持ちを整理し、その原因に向き合うことは、漠然とした不安を解消する第一歩です。 ここでは「このままでいいのか不安」と思う原因としてよくあるものをご紹介します。自分が当てはまるものはないか、もしくは自分には他の気持ちがあるのか、今を見直すきっかけにしてみましょう。 仕事にモチベーションを感じない 仕事にも慣れ、なんとなくこなせるようになってきて、辞めたいと思うほど何かが嫌なわけではないし、職場に問題があるわけでもない。上司との関係も可もなく不可もなく、「まあこんなものだろう」という程度。 このような「職場や上司にストレスを抱えるほどでもなければ、ワクワクもしない」状況が続くと、仕事に対するモチベーションも下がってきてしまうのではないでしょうか。 「辞めたい」「もう無理」という気持ちが強くなれば、転職活動を始めるエネルギーにもなりますが、辞めるほどまで気持ちが強くないうちは、かえって不完全燃焼のような、漠然とした「このままでいいのか?」という思いが募ってしまうかもしれません。 ただ、仕事に対するモチベーションは、仕事が変わるか、仕事に対する自分の見方が変わると変わってきます。仕事を変えることは、転職だけでなく社内での担当替えや異動などでも実現できますし、自分の仕事に対する見方も、自分の視野や世界を広げたり、誰かと話したりすることで変わっていく可能性が大いにあります。 仕事そのものか、仕事に対する見方か、どちらかを変えられないか、試してみてはいかがでしょうか。 今の会社をずっと続けられるのか不安 環境変化の激しい現代では、超大手企業といえど一生安泰というわけにはいきません。 赤字によるリストラだけでなく、企業は黒字でも人件費削減のために大規模な早期退職を募るようになっています。2025年には労働人口の6割が45歳以上となり、役職に就かない中高年がさらに増えることから、定年延長と共に進む「希望退職」「早期退職」の流れは、今後も続くと予想されます。 転職したいわけじゃないのに、このままこの会社にはいられないかもしれない。その時、自分はどうしたらいいのか。 仕事に対する不安とは別に、「今の会社でずっと働き続けることができるのだろうか」という会社への不安がある方もいらっしゃるでしょう。 ただし、この「働き続けることができるのか?」という問いの答えは、誰にもわからないものです。未来は誰にもわかりません。将来に対する不安は、感じ始めると次から次に別の不安が生まれてしまうものなので、「今、ここ」に意識を集中できるような何かを始めてみるといいかもしれません。 将来への蓄えなど経済的な心配がある 人生には、「住宅資金」「教育資金」「老後資金」と三大支出があります。「住宅資金」は「一生賃貸でもいい」という考え方もありますし、「教育資金」は子どもを持たないという選択もありますが、「老後資金」だけは誰もが避けては通れない問題です。 「老後資金」については、2019年に金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」が「老後20~30 年間で約1,300 万円~2,000 万円が不足する」という試算を発表したことにより、「老後には2000万円が必要」と不安になった方も多いのではないでしょうか。 ただしこの不足分は平均貯蓄額を上回るため、多くの世帯では年金と退職金でやりくりができているといわれます。しかし今後、平均寿命が延びる一方で、退職金が減少傾向にあり、年金支給額が減額されると推測されます。また自分の将来だけでなく、親や家族の問題が自分の家計に影響してくることもあります。 このような経済的な不安は、きちんとマネープランを考えて貯蓄や投資信託、NISAや個人年金など、自分に合った備えを始めることで解消していきます。情報収集を始め、マネープランを学ぶことから始めてみるとよいでしょう。 同じ生活の繰り返しで刺激がない 「毎日が同じ生活の繰り返しでつまらない」「生活がマンネリしていて、何の変化も刺激もない」「生活のために働いているけれども、特に何の目標もやりがいも楽しいこともない」 そんな毎日が続いて、「このまま同じ生活を続けていてもいいのだろうか」という漠然とした不安になることもあります。 自分がどうなっていきたいのか目標があったり、何か楽しみを見つけられるとこの状態は変わっていきますので、次に紹介する「今までやりたかったこと、新しいことを始めてみる」方法を試すと、何かが変わってくるかもしれません。 2. 自分が今までやりたかったこと、新しいことを始めてみる 自分のやりたいことや好きなこと、楽しいと思えることができていたら、「このままでいいのか」と不安に感じることはおそらくないでしょう。 だから今、「このままでいいのか」と漠然とした不安があるのは、それが何らかの理由でできていないか、自分にとってそれが何なのかわからないか、そんな状況ではないでしょうか。 そんなときは、どんなにささやかなことでもいいので、「今までやりたかったこと」をしてみましょう。 「やりたかったこと」を行動に移すという、小さなサイクルを繰り返していると、「自分はやりたいことを行動に起こせる」という感覚が身についてきます。 「自分は、やりたいことができるんだ」と、気持ちのスイッチとセルフイメージが切り替われば、様々な「やりたいこと」や「好きなこと」が浮かんでくるようになるでしょう。 自分が本当にやりたいことや好きなことは、意外に見つけるのが難しいもので、「これだ!」と思っていたことでも、実際にやってみると「何か思っていたのと違う」ことはよくあります。だからこそ、本当にやりたいことを見つけるには、興味を持ったことを少しずつでもどんどん試してみる、そんな行動力が大切なのです。 たとえば、以下のようなことに興味はありませんか。 少しでも心が動いたものがあれば、まずは行動を起こすことから始めてみましょう。 ジョギングやヨガなど運動を始める 適度な運動は、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニン神経と脳を活性化させます。セロトニンは、精神の安定や安心感、平常心、頭の回転をよくして直観力を上げるなどの働きをするもので、不足すると慢性的ストレスを感じるようになり、向上心の低下、仕事への意欲低下、協調性の欠如などの症状がみられるようになります。 運動のなかでもジョギングやサイクリング、水泳などの比較的簡単な有酸素運動は、セロトニン神経を活性化させますし、自宅でもYoutubeを見ながらでもできるヨガも、セロトニンを分泌する効果が高いといわれています。 体を動かすことでセロトニン神経が活性化して、「このままでいいのか」という漠然とした不安が解消されて、いつの間にか前向きな気持ちになれるかもしれません。 習い事や資格取得の勉強を始める 習い事や資格取得の勉強を始めると、「●曜日は習い事の日」「×月▲日は試験」といった具合に生活にリズムや張り合いが生まれ、目標もできます。 また文部科学省によると、人間の意識はある瞬間では一つのことにしか向けることができないといわれていますので、習い事で好きなことに熱中する時間や、試験の勉強に集中する時間を作ることで、不安を感じる時間を減らすこともできるでしょう。 キャリアアップのために仕事に関する習い事や資格でも、料理や音楽、アートなど、趣味を広げるための習い事でも、新たな知識や新たな人との出会いを通じて、自分の世界が広がります。その楽しさに、「このままでいいのか」という不安も忘れられるのではないでしょうか。 副業を始める 「どうせ何かを始めるのなら、経済的な不安を解消できることを」と思う方もいらっしゃるでしょう。今は副業OKの会社も増えていますので、空いた時間に副業を始めるという方法もあります。 「副業ができるほど、スキルやキャリアもないし…」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、最初から稼ぐことを目標にしなければ、今は副業も始めやすい環境が整っています。 何かを作ることが好きならば、自分で作ったものをオンラインで簡単に販売できるサイトもありますし、隙間時間を売買してちょっとした頼みごとを依頼するようなサイトもあります。また、クラウドソーシングサイトも数多くありますので、それに登録して簡単な業務から始めてみるのでもいいでしょう。 自分の興味のある分野で副業を始めれば、収入だけでなく楽しみにもつながります。自分の世界も広がり、もしかしたら将来につながる新たな可能性も見つかるかもしれません。 新しいチャレンジを上司に希望してみる もし、上司が理解のある人であれば、新たなことにチャレンジしてみたいと上司に相談してみるのもおすすめの方法です。 たとえ同じ部署であっても、担当領域が少し変わるだけでも業務に変化が生まれ、視野が広がります。「同じ仕事ばかりでつまらない」「毎日刺激がない」などが不安の原因であれば、新たなチャレンジをすることが不安を解消する突破口になるはずです。 部下の「新しいチャレンジをしてみたい」という思いを大切にしてくれる上司は、わりといるものです。「これがやってみたい」と思っていたことがもしあれば、勇気を出して相談してみましょう。 3. 友人や先輩など、人と話してみる 親しい人と近況を情報交換するだけでも、気持ちがすっきりしたり、整理できたりしますよね。これは人は誰かと話をすることで、自分が何を考え、どう感じているのかを頭の中で整理することができるからで、「オートクライン効果」と言われています。 このままでいいのか不安なときは、友人や先輩など、誰か話せる人に聞いてもらうのもよいでしょう。 オートクライン効果だけでなく、相手からの思わぬ情報に刺激を受けたり、「そういう考え方もあるのか」とちょっと前向きになれたり、何か「スイッチ」が入ることもあります。また、相手も実は同じような不安を持っていて、「自分だけじゃないんだ」と安心する…なんてこともあるでしょう。 コロナ禍のなか、外食するのは難しい時期かもしれませんが、オンライン飲み会などを活用しながら、話を聞いてもらってはいかがでしょうか。 4. マインドフルネスを試してみる 将来のことに目を向けると、先が見えなくて不安になります。でも先のことは誰にもわかりません。そんなときは、「今ここ」に意識と五感を集中することで心を整えることもできます。 それが、マインドフルネスです。マインドフルネスの実践方法である「マインドフルネス瞑想」は、過去の経験や先入観、将来への不安などにとらわれることなく、自分の五感に意識を集中させ、「今の気持ち」「今の身体状況」をあるがままに受け入れるものです。 その効果として、ストレスの軽減や集中力の強化などが得られるとされることから、世界中で注目され、アップルやグーグル、フォードなどの世界的大企業が社員研修の一環として取り入れられています。 マインドフルネス瞑想はお金もかからず、自宅でも一人でも簡単に始められます。やり方についてはネットでも詳しく紹介された情報を得られますので、興味がある方はぜひ調べてみてください。 5. これからのキャリアについて真剣に考えてみる 「このままでいいのか不安」という思いの根底には、自分がどうしたいのか、どうなりたいのか、これでいいのかわからないという状態があるのではないでしょうか。それを解消するには、これを機にこれからのキャリアについて真剣に考えてみるのもおすすめです。 「キャリアについて考える」と聞くと、どのようにキャリアアップしていくか?というイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、キャリアとは本来、出世や仕事の成果や実績を表す言葉ではなく、働くことに関わる「継続的なプロセス」であり、働くことにまつわる「生き方」そのものです。 ですから、 ・どんな環境で働いていたいのか・ワークライフバランスをどのようにしていきたいのか・どのような働き方がしたいのか・どのように収入を得ていたいのか など、「自分がこれからどう働いていきたいか?」を考えることが、キャリアを考えることになります。 「自分がどう働いていきたいか?」に対して自分なりに方向性が見えてくると、そのために何をすればいいのかも明らかになってきます。「これから何をすればいいのか」というアクションプランを考えるようになれば、「このままでいいのか」という不安も消えていくでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、このような「このままでもいいのか」という漠然とした不安を整理し、これからの働き方を見つけるサポートをもしています。キャリアについて考えることは一人でもできますが、キャリアコンサルタントと話すなかで現状を捉えなおし、「今の環境でも、できることがまだたくさんあった」と新たな気づきを得る方も多くいらっしゃいます。 「このままでもいいのか」という不安をきっかけに、これからの働き方を一度考えてみてみたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

仕事にやりがいも成長もいらない?「仕事のやりがい」問題が気になったら…
仕事にやりがいや成長はつきもの、あって当然と思われる風潮ってありますよね。 1日8時間以上もの時間を費やし、人生の大半を占めるのだから、やりがいを感じられる仕事についたほうがいいという考え方です。さらに、「仕事を通じて成長したい」というのは、就職活動や転職活動で企業に好印象を与える決まり文句でもあり、「仕事で成長とかしなくていいし」と口にしようものなら、「やる気のない奴」の烙印を押されてしまう可能性は高いでしょう。 でも、仕事にやりがいや成長を他人から求められるのって疲れてしまうし、何だか違和感がある…そう感じたことはありませんか。 そんな「仕事のやりがい」や「仕事での成長」問題のモヤモヤに、向き合ってみましょう。 仕事のやりがいや成長とは? さて、「仕事のやりがい」や「仕事を通じて成長する」という言葉を聞いたとき、その「やりがい」や「成長」にはどんなイメージを持ちますか。 「仕事のやりがい」ときくと、なんとなく目覚ましく活躍している状態や質の高い提案をして、プレゼンでどんどん企画を通すようなイメージをしてしまったり、「仕事での成長」と言われれば、どんどんスキルアップ、レベルアップしてできないことができるようになり、出せる成果が大きくなるという姿を描いてしまったりしませんか。 自分の仕事が、社内外で高く評価されていたり、「この仕事は自分しかできない」と思えるような成果を出し、周囲からも認められていたり、という具合です。自分ではそうは思っていなくても、「上司から求められるのは、そんな感じだ」という方も多いかと思います。 しかし、大辞林を調べてみると、「やりがい」とは「物事をするにあたっての心の張り合い」と説明されています。この言葉の意味通りに「やりがい=心の張り合い」と考えると、仕事のやりがいも、人それぞれでいろんな「心の張り合い」があっていいのです。 「成長」についても同様です。「成長」も、その意味を調べてみると、「1.人や動植物が育って大きくなること。おとなになること」「2. 物事の規模が大きくなること」とあります。物事の規模でなく、「人」にフォーカスすれば、つまり「おとなになること」です。人としての成熟は、決して仕事の業績だけで測れるものではありません。仕事で成果を上げるとか、仕事の質が高くなる、早くなる、〇〇ができるようになるなどは、もちろん素晴らしいことですが、決してそれだけではないのです。 なぜ、仕事にやりがいや成長が必要だといわれるのか しかし、会社で期待される「やりがい」の答えも、何かハイレベルな仕事の成果や質に関するものであることが多いのではないでしょうか。そして、会社で上司から「成長しろ」といわれるときの「成長」はこんな意味ではありませんよね。 なぜそれが求められるのかといえば、企業は、経済成長を続けることが前提の資本主義のなかで企業活動を行っているので、成長をし続けるためには組織で働く人も、「業績をあげ続けること」「より高い成果、より大きな成果を出せる人材になること」「できないことができるようになること」が必要だからです。 だから組織では、成長意欲が高い人が採用され、評価されるようになっています。でもそれはあくまで、「会社としての言い分」。それに共感し、応えようと思うことも、「自分はそうではないな」と思うことも、どちらでもよく、決めるのは自分次第です。 仕事のやりがいや成長は自分自身で決めるもの 本来の意味を考えれば、「やりがい」は心の張り合いですから、自分自身の心にちょっとした張り合いが生まれればどんなことでも「やりがい」です。たとえば、 ・目の前のお客様に、「ありがとう」と喜んでもらえた。・誰かの役に立っていると実感できた。・一生懸命仕事をして、今日も社食のお昼がおいしく食べられた。・気の合う同僚と、和気あいあいと働けている。・尊敬できる上司と一緒に仕事ができている。・オフィス環境が良くて、毎日快適に働けている。 などのこうした日々のちょっとした「心の張り合い」だって、十分仕事の「やりがい」なのです。 「成長」だって同様です。仕事を通じて、どんどん何かができるようになり、出せる成果が大きくなり、質が良くなることだけが成長ではありません。 ・人との距離の取り方がうまくなった(適度に距離を取るということも含めて)。・自分の心を穏やかに保てるようになった。・嫌なことがあっても気にしなくなった。・立ち直りが早くなった。・要領よくやることを覚えた。・嫌なことをスルーし、ストレスをためないスキルがついた。 このように、自分が心地よく生きるための人としての「成長」も、仕事を通して得られる成長です。 いかがでしょう?このように考えると、身の回りにも「やりがい」や「成長」が見えてきませんか。 「やりがい」も「成長」もどちらも自分自身の内面の問題ですから、何をやりがいとし、何を成長とするかは本来、自分自身で決めるものです。そして自分自身の問題だからこそ、他人にとやかく言われる筋合いは本来ありません。 自分のやりたい仕事をやって、充実した成果を出していて、しかもそれが評価されていて、満足な報酬を得ている。そしてどんどん重要な仕事を任されるようになり、キャリアアップしている。 このような状態に「やりがい」や「成長」を感じる人もいますが、「やりがい」も「成長」もそれだけではないのです。ですからこうした「やりがい」や「成長」のイメージに縛られてしまっていると、日々の仕事に溢れているちょっとした心の張り合いや人としての成長を見落としてしまいます。 上司から求められる「成長」ばかりが、必要な成長ではない。そう考えると、少し気持ちも楽になるのではないでしょうか。 仕事にやりがいはいらなくたっていい もちろん、別の考え方もあります。「そもそも、仕事にやりがいはいらない」というものです。 確かに1日8時間かそれ以上の時間を仕事に費やしますが、人生で大切なのはもちろん仕事だけではありません。仕事だけが成長感や充実感、達成感を感じる場ではありません。いくら人生のうちの長い時間を費やすからといって、「仕事」にやりがいを感じなければいけない理由は何もないのです。 仕事を「仕事以外の場所にある、自分の心の張り合いを支える収入の糧として、割り切って取り組むもの」として捉えると、楽になることはたくさんあります。 たとえば以前、ある国民的男性アイドルグループの大ファンで、「毎年開催される全国ツアーを、各地に観に行くのが生きがい」という女性にお会いしました。 彼女は、そのために「コンサートツアーに参加しやすい仕事」という軸で仕事を選び、実際に毎年全国各地で開催されるコンサートに行ける今のライフスタイルを実現し、自分のやりたいことができる仕事にとても満足していました。 「仕事はもちろん、一生懸命やります。でも私にとって仕事は、生活費とコンサートに行ける費用が稼げればいいものなので」と自分の人生の価値基準が明確な彼女は、「仕事にやりがいが必要なのか?」という問題に悩むことはありません。 彼女は「自分の趣味(推し)のため」でしたが、これが「他にやりたいことのため」「子どものため」「家族と過ごす時間のため」など、何でもいいでしょう。 自分の人生にとって大切な「心の張り合い」は仕事以外の場にあり、仕事はそのための生活の糧としてあるだけ。別に、仕事で成長感や達成感、充実感なんてなくていい。それも、とても素敵な考え方なのです。 「仕事のやりがいと成長」問題には、人それぞれの答えがある 仕事にやりがいはいるのか、いらないのか。仕事で成長したほうがいいのか、いらないのか。その問いには万人共通の正解はなく、人それぞれに答えがあります。 仕事にやりがいを感じたい人もいれば、そんなものは仕事にいらないという人もいます。仕事を通じて成長し、自己実現したい人もいれば、そんなものは必要ないという人もいます。 大事なのは、どちらもその人にとって「正解」なので、他人が否定したり、とやかく言ったりする問題ではないということです。 他人の答えは、自分の価値観や判断軸を考える上での参考にはなりますが、自分にも同じように当てはまるわけではありません。同じように、自分の価値観が他人にも同じように当てはまるわけでもありません。 ただ、いずれにしても「やりがい」や「成長」を考える上でとても大切なことが2つあります。 「やりがい」は他人と比べると見失いがちになる それは、「やりがい」は他人と比べると見失いがちになってしまうということです。「やりがい=自分の心の張り合い」であり、人それぞれに答えがあるからこそ、他人の状況と比べていると、いつまでたっても「やりがい」は見つからず、感じにくくなってしまう可能性があります。 たとえば、自分は年収450万で仕事も楽しいし、成長も感じているのに、年収600万円の友人と比べてしまい、収入の差をネガティブに受け止めてしまうと、今まで感じていた楽しさや成長に疑問を感じてしまうかもしれません。 SNSで友人が仕事の充実した生活を発信しているのをみて、「それに比べて、自分は…」と思ってしまうかもしれません。 目の前のお客様には「ありがとう」と言ってもらえて、嬉しいとは思うのに、社内でもっと営業の業績を上げている同僚と比べてモヤモヤしてしまったり…ということはありませんか。 他人との比較を判断基準にしてしまうと、必要以上に「足りない」と感じてしまったり、あるいは、どんな状況にも必ず「上には上」がいますから、どこかで満たされなくなったりしてしまいます。 「他人と比べない」というのは、簡単にみえてなかなか難しいですが、ぜひ自分の心にまっすぐに向き合ってみましょう。 「成長」は「現状維持」のなかにもある 成長を前提とした資本主義の中で活動する企業では、成長意欲が高い人が採用され、評価されますが、そうした企業の期待に応え続けられる人、応え続けることにやりがいを感じる人ばかりではないですし、そのような人ばかりでも組織は成り立ちません。 Twitterでこのような投稿が話題になったことがあります。 https://twitter.com/rexcoaster/status/1420572222905753600 まさにこの通りで、「10を10として維持する」という、表面的な仕事としては「成長」ではなく「現状維持」をきちんとしていく多くの人がいてこそ、組織は成り立ちます。組織にとっては、どちらも大切なのです。 「10を10として維持する」ことのなかにある「やりがい」や「人としての心の成長」は、たとえ組織としてそれを評価する軸がなかったとしても、尊いものです。その大切さにも、目を向けていきましょう。 自分の内発的動機付けや外発的動機付けを考えると自分にとっての「やりがい」や「成長」がみえてくる 前述のように、企業は組織として成長を前提としている資本主義のなかで活動をしているからこそ、その構成要員である社員にも成長を求めます。 しかし、「やりがい」や「成長」は企業が求めるものがすべてではありません。 業績をあげ続けることや、より大きな成果を上げることが、「自分が好きなことをやっていたら、結果的に業績があがったり、大きな成果を上げていた」というのであれば理想なのですが、「周囲の期待に応えたいから」「周囲の評価を得たいから」という外発的動機付けによるものであれば、どこかで無理をし過ぎて苦しくなる時がやってくるかもしれません。 では自分にとっての「やりがい」や「成長」はどこにあるのか。それは何なのか。それは、自分の内発的動機付けや外発的動機付けを整理すると見えてきます。 「仕事に成長はいらない。でもなんか現状にはモヤモヤする」もし、そんな思いがよぎったら、自分の動機付けを整理し、働くことや仕事に対する考え方を整理してみませんか。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、このような「働くことや仕事に対する考え方を整理し、自分にとって大切にしたいことを実現する働き方や仕事を探す」ためのサポートも行っています。一人で整理することが面倒になったら、ぜひプロのサポートも活用してみてくださいね。

後輩よりも仕事ができないのが辛い時の対処法
「出来のいい後輩」はどこにでもいます。自分のほうが社歴は長いのに、後輩よりも仕事ができないという現実に、みじめになったり、職場で比べられて辛い思いをしたりすることはありませんか。 「自分はこの会社に要らない人間なのでは…」と思ってしまうその前に、こんなふうに考えてみましょう。 975

仕事の人間関係がストレス!割り切るポイントと解消法
「人間関係の悩み」は、仕事のストレスになりやすい要素の一つ。 「職場の人間関係にうまく馴染めない」「社内に苦手な人がいて折り合いが悪い」 ビジネスパーソンなら誰でも一度は、このような人間関係のストレスを感じた経験があるのではないでしょうか。 本記事では、仕事の人間関係にストレスを抱えている人に向けて、気持ちを割り切るポイントやモヤモヤしたときの解消法などを解説します。 人間関係は仕事のストレスに直結しやすい 令和5年に厚生労働省が実施した「労働安全衛生調査」にて、「職場にストレスと感じる事柄がある」と回答した人は82.7%もいました。その中で「対人関係がストレス」と答えた人の割合は29.6%となっており、働く多くの人にとって人間関係が仕事のストレスになっているのがうかがえます。 また、対人関係にストレスを感じると答えた人の男女比は男性が26.3%、女性が33.7%であり、男性よりも女性のほうが仕事の人間関係にストレスを感じやすいようです。 同年実施の「雇用動向調査」においても、「職場の人間関係が好ましくなかった」という転職理由は上位にランクインしていて、人間関係のストレスでキャリアチェンジする人も少なくない事実が浮き彫りとなっています。 仕事の人間関係にストレスを感じるのはなぜ? なぜ、仕事の人間関係はストレスになりやすいのでしょうか。ここでは、考えられる理由を解説します。 職場はコミュニケーション不足が起きやすいから 大前提として職場は仕事をする場所。そのため、各々が自分の仕事に没頭するあまりコミュニケーション不足が起きやすく、第一印象や先入観でお互いを理解した気になりやすいです。 しかしそうすると、自分がイメージしていたものとは異なる言動を相手が取った際に不信感や違和感が生まれ、悪い印象を持つきっかけに。 お互いをきちんと理解できていないため意思の疎通もうまくいきにくく、意見が割れたり対立が起きたりしてストレスを感じることがあります。 自分の意見が言えないから 家族や友達と話すときとは異なり、あらゆる人に配慮する必要がある仕事中は、思っていることをストレートに言えない場面も少なくありません。 そのため、自分の意見を言えないまま望まない方向に業務が進んで、ストレスを感じるケースがあります。 また、自分の意見が言いにくい環境は、わからないことがあっても質問できなかったり、相手にやめてほしいことを伝えられなかったりする状況を招くリスクも。仕事に支障が出る、いつまでも不快な思いをし続けるなどして、人間関係に強いストレスを感じる可能性があります。 苦手な人とも関わらなくてはいけないから プライベートでは、付き合う人を自由に選定して苦手な人を避けられます。しかし仕事においては、自分の意思で付き合う人を選べないため、苦手な人とも必要に応じて関わらなくてはいけません。職場にはさまざまな価値観・タイプの人がいるので、中には「合わない」「苦手」と感じる人もいるでしょう。 しかしそう感じる相手であっても、うまくコミュニケーションや連携を取る必要があるため、仕事の人間関係はプライベートの人間関係よりもストレスが生じやすいです。 仕事はお互いの人間性が出やすいから 職場は、意外と人間性が出る場所です。トラブル発生時の行動や誰もが嫌がるような仕事への向き合い方、困っている人がいたときの対応などから、普段は隠されている本当の性格が見えることがあります。 また、毎日顔を合わせて長時間一緒に働くことで、気分屋な一面や効率の悪さが露見する場合もあるでしょう。 仕事の人間関係がストレスになりやすいのは、そもそも職場が「お互いの嫌な部分が目につきやすい場所」であるのも一因だと考えられます。 ハラスメントがあるから パワハラやいじめがある職場で、過度な叱責や不当な扱いを体験することは、深刻なストレスにつながるでしょう。自分自身がハラスメントの被害者になった場合はもちろんですが、直接的な被害はなくても近くで見ているだけで精神的負担は相当なものです。 ハラスメントが横行する職場では、誰を信じていいのかもわからなくなりやすいので、孤立感が強まります。 職場の人とのちょっとした交流にも緊張してホッとできる瞬間が少ないため、ストレスがどんどん蓄積しやすいです。 仕事の人間関係にストレスを抱えやすい人の特徴 仕事の人間関係にストレスを抱えやすい人には、よく見られる特徴がいくつかあります。代表的な3つを紹介するので、自分に当てはまっていないかチェックしてみてください。 人とのコミュニケーションが苦手 コミュニケーションに苦手意識がある人は、自ら積極的に人と交流しようとしないため、相手の人柄をよく理解しないまま勝手なイメージを固定化しやすいです。思っていることがあってもそれを伝えられず、自分の意見や感情を内に溜め込んでストレスを抱えてしまいます。 また、たとえ長く働いても人と交流を持たなければ信頼関係は育たないので、仕事中に緊張や不安が生じやすく、それもストレスになるでしょう。 真面目で厳格な性格 いい加減なことを嫌う真面目な性格は長所でもありますが、自らの几帳面さを他人にも求める傾向が強いので、他人の予想外の言動にイライラを募らせやすいです。 「一般的に考えてこうあるべき」のように一般論や自分の考えに固執しがちで融通が利きにくいため、時に相手やその場の空気に合わせなくてはいけない仕事の人間関係にストレスを感じるでしょう。 仕事が理想通りに進まないと厳しい態度で周囲に接することもあり、自ら人間関係を悪くしてストレスを抱えるかもしれません。 共感力が高すぎる 共感力が高い人は、他人との境界線があいまいになりがち。相手の身に起きた出来事や感情を自分のことのように捉え、良い影響も悪い影響もダイレクトに受けて人間関係に疲れを感じやすいです。 また、共感力が高い人は他人に寄り添う能力があるからこそ「相手は困っているだろう」「助けてほしいと思っているだろう」と察して要望全てに応えようとします。 自分のことを後回しにしてでも他人を優先させる傾向が強いので、仕事の人間関係で不満やストレスを溜めやすいです。 ストレスをなくすには仕事の人間関係を割り切るのがカギ 上手に気持ちを割り切れると、仕事の人間関係におけるストレスはぐんと減ります。ここからは、仕事の人間関係を割り切るための5つのポイントをお伝えしましょう。 仕事とプライベートは別だと考える まずは気持ちを整理して、仕事とプライベートにしっかり線引きをしましょう。仕事とプライベートを別物として割り切ることで、こだわりや感情にとらわれにくくなります。 「職場で最もやるべきことは仕事であり、友達作りではない」と思えれば、他人の目や評価を気にする回数も減るでしょう。 「相手から嫌われたらどうしよう」という恐怖も和らぎやすいので、今より自己主張できたり嫌なことをきちんと断れたりして、人間関係のストレスが減る可能性が高いです。 他人に期待しすぎない 他人に対し「〇〇の仕事を手伝ってもらいたい」「短所を直してもらいたい」のように思うのは、過度な期待です。 そして、他人に対して期待しすぎてはいけません。過度な期待は、叶わなかったときの絶望感も大きく、さらにストレスを強めてしまいます。 期待をするべき相手は、他人ではなく自分です。他人に何かしてもらおう、変わってもらおうとするのではなく、自分が成長や変化するにはどうすればいいかを考えましょう。 事実だけに目を向ける 人間は、誰しも良い面・悪い面の両方を持っています。他人の嫌な部分を一度見ただけで「嫌な人」と決めつけてしまうと、職場中が嫌いな人だらけになり、余計に人間関係のストレスが増えるでしょう。 そのため、他人の嫌な面に触れても「相手にはこんな悪いところもあるんだ」と事実だけを受け止め、自身の感情と深く結び付けないように意識するのがコツ。 「嫌い」「苦手」「合わない」など、ネガティブな感情を発生させないように工夫すれば、自然と人間関係のストレスは軽減します。 人間関係は「広く浅く」を意識 仕事の人間関係を割り切るなら、特定の人とだけ深く関わったり、他人との交流を断ち切って孤立したりするのではなく、広く浅い関係を構築するのがおすすめです。 広い人間関係を築いておけば、仕事上のトラブルに見舞われた際にも周囲に助けを求めやすくなります。 また、あえて深く交流しないことで、お互いに自分のペースを乱さずに済み、適度な距離感を維持できるでしょう。 人間関係に完璧を求めない さまざまな人がいる職場では、全員と良好な人間関係を築くのは不可能だと理解して、完璧を求めないようにするのも大切です。 全員と良好な関係を結べるのが理想ではあるものの、人間には相性があるのでどうしても難しい場合もあります。また、無理に全員から好かれようとすれば自分を抑制する場面が増え、ストレスは強くなるでしょう。 苦手だと思う気持ちや折り合いが悪い現状もありのまま認め、時には現状維持でも良しとする柔軟性が必要です。 仕事の人間関係のストレスを解消する方法 どれだけ割り切っていても、仕事の人間関係にストレスを感じることもあるでしょう。ここではそんなときに試してほしい、ストレス解消法を紹介します。 ストレスを感じたときは状況と感情を客観視する 誰かにイラっとしたときや、モヤモヤした感情が溜まっているときは、一度今の状態と自分の感情を客観視してみてください。 「何にストレスを感じ、そのとき自分はどんな気持ちになったのか」「今なおストレスはあるのか」「今後ストレスが改善される可能性はあるか」といったように、ストレスを感じた瞬間から現在までを時系列で考えます。 状況と感情を丁寧に分析すると気持ちが落ち着き、「よくよく考えてみたら、意外と大したことじゃないかも」と思えて、ストレスが消えていくケースも少なくありません。 苦手な人とは必要に応じて距離を取る 苦手な人と一緒にいるだけでストレスを感じるときは、仕事に支障をきたさない程度にうまく距離を取るのも大切です。 人間関係のストレスは、苦手な人と接触する機会が減れば自然と低減します。 露骨に相手を避けたり、業務上必要な連絡まで怠ったりするのはNGですが、苦手な人との私的な交流機会が減るだけで仕事の人間関係はやりやすくなるでしょう。 一日の中に気分転換やリラックスできる時間を設ける 気分転換やリラックスできる時間を一日の中のどこかに設け、こまめにストレス発散できるルーティンを作りましょう。ストレスは蓄積させればさせるほど解消が難しくなるので、できるだけその日のうちにリフレッシュしたほうがいいです。 また、時には長期休暇を取り、日常的な気分転換だけでは発散できなかったストレスを思いきり開放させるのも大切です。 身近な人に相談する 友だちや職場の上司、家族などに、仕事の人間関係について相談してみるのも有効なストレス解消法といえます。 信頼できる人に自分の本心を打ち明けることで、気持ちが軽くなったり客観的視点を得るきっかけになったりする可能性が高いです。その後話題が変わったとしても、楽しく盛り上がればいい気分転換になるでしょう。 大きなストレスを抱えると一人でふさぎ込みがちになりますが、不安や孤独感を解消させるためにも、できるだけ積極的に他人と交流してください。 キャリアコンサルティングを受けてみる 「何をやっても仕事のストレスが大きくてつらい」「仕事の人間関係がストレスすぎて、転職を考えている」 このような場合は、キャリアコンサルティングを受けてみるのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、キャリアに関する悩みはもちろん、人間関係の悩みにも丁寧にアドバイスしてもらえます。 プロ目線の具体的なアドバイスを参考にすれば、ストレスの原因に的確にアプローチしやすく、悩み解決の突破口が開けるはずです。 上手に人間関係を構築して、仕事のストレスを低減させよう 多くの人と協力しながら進めなくてはいけない仕事では、人間関係のストレスが必ず発生します。 しかし、自らの考え方や行動を変えて上手に人間関係を構築できれば、仕事のストレスは大幅に減少するはずです。 無理にストレスに強くなろうとするのではなく、ストレスが発生しにくい環境を自分で整えて、気持ちよく働けるように工夫しましょう。キャリア・コンサルティング・ラボでは、そのお手伝いをするための相談を受け付けているので、ぜひ気軽に利用してみてくださいね!

なんでこんな仕事してるんだろう?というモヤモヤ感の解消法
私、何やっているんだろう? 何のために働いているんだろう? なんでこんな仕事しているんだろう…? 仕事は、いつでも順風満帆というわけにはいきませんから、時にはそんなモヤモヤとした壁に突き当たることもあります。 どんよりと気持ちが沈んで、何も手がつかないような気分から少し抜け出したいなら、こんな小さな行動から始めてみませんか。 840

入社3ヶ月の壁・仕事ができないのが辛いときの乗り切り方
転職入社して3ヶ月。仕事にも職場にも少しずつ慣れてきたのに、思っていたより仕事ができなくて、なんだか辛い…。 入社してすぐは、「まだ慣れないから」「仕事を覚えるまでは」と「できない理由」もあったけれど、3か月経ち仕事も少しずつ覚えてきたのにうまくできない、あるいは仕事がなかなか覚えられない…となると、朝会社に行くのも憂鬱な気分になってしまいます。 入社3ヶ月目に感じるこの壁を、どう乗り越えればよいのか。この状況への向き合い方を確認していきましょう。 924

「上司と合わないから辞める」の前にできること・すべきこと
上司は部下を選べることもありますが、部下は上司を選べません。 理不尽な対応や仕事を任せてもらえない等、どうしても合わない上司との人間関係に疲れ、退職したくなることもあるでしょう。 しかし、「上司と合わない。」と退職する前にできること、すべきことがあります。辞める前に、一歩踏みとどまってみませんか。 674

やってられない!職場に嫌気がさしたときにおすすめの3つの行動
上司は部下を選べることもありますが、部下は上司を選べません。 理不尽な対応や仕事を任せてもらえない等、どうしても合わない上司との人間関係に疲れ、退職したくなることもあるでしょう。 しかし、「上司と合わない。」と退職する前にできること、すべきことがあります。辞める前に、一歩踏みとどまってみませんか。 783

入社10年目でもう仕事を辞めたいと思ったら…知っておきたい対処法
上司は部下を選べることもありますが、部下は上司を選べません。 理不尽な対応や仕事を任せてもらえない等、どうしても合わない上司との人間関係に疲れ、退職したくなることもあるでしょう。 しかし、「上司と合わない。」と退職する前にできること、すべきことがあります。辞める前に、一歩踏みとどまってみませんか。 2895
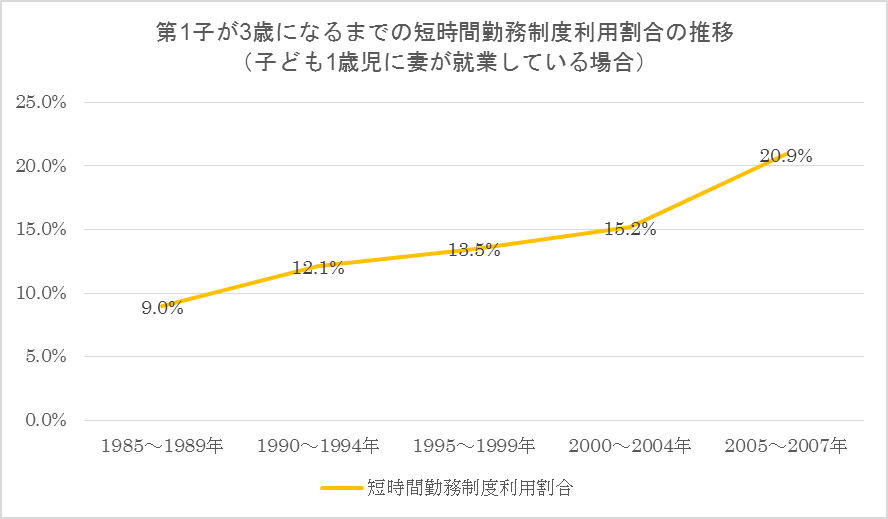
「時短勤務って迷惑!」と言われない人がしている3つの気遣い
上司は部下を選べることもありますが、部下は上司を選べません。 理不尽な対応や仕事を任せてもらえない等、どうしても合わない上司との人間関係に疲れ、退職したくなることもあるでしょう。 しかし、「上司と合わない。」と退職する前にできること、すべきことがあります。辞める前に、一歩踏みとどまってみませんか。 680

仕事の辞め癖と逃げ癖、その末路には何がある?
上司は部下を選べることもありますが、部下は上司を選べません。 理不尽な対応や仕事を任せてもらえない等、どうしても合わない上司との人間関係に疲れ、退職したくなることもあるでしょう。 しかし、「上司と合わない。」と退職する前にできること、すべきことがあります。辞める前に、一歩踏みとどまってみませんか。 1012

仕事がわからない時の聞き方・暗黙のルールを確認しよう
上司は部下を選べることもありますが、部下は上司を選べません。 理不尽な対応や仕事を任せてもらえない等、どうしても合わない上司との人間関係に疲れ、退職したくなることもあるでしょう。 しかし、「上司と合わない。」と退職する前にできること、すべきことがあります。辞める前に、一歩踏みとどまってみませんか。 711

キャリアに悩む50代必見。モヤモヤの原因と中年の危機を乗り越えるヒント
50代に入り、ふと「このままでいいのか」と考えることが増えたという方は多いのではないでしょうか。 仕事での役割や家庭環境、体力などが変化しやすい50代は、約5割〜8割の就労者が漠然とした不安や虚無感、葛藤を抱えるといわれています。 本記事ではキャリアに悩む50代に向けて、よくある悩みの原因や具体的な乗り越え方について解説します。悩んだときのNG行動も紹介するので、ぜひ参考にしてください。 「中年の危機」の50代はキャリアに悩みやすい時期 50代でキャリアの悩みを抱える人が増えるのは、この時期に多くの人が「ミッドライフ・クライシス」に陥ることが一因として挙げられます。 ミッドライフ・クライシスとは、人生の折り返し地点で感じる不安や葛藤のこと。別名「中年の危機」「第二の思春期」とも呼ばれます。 50代は、身体的な変化や子育て終了による喪失感、キャリアの停滞など、自分のアイデンティティが揺らぐような大きな出来事が起こりやすいです。 その中で、過去の選択に対する後悔や将来に対する不安が生まれてミッドライフ・クライシスになり、あらゆる場面でパフォーマンス低下を招きます。 50代によくあるキャリアの悩みとは まずは、50代によくあるキャリアの悩みの原因をチェックしていきましょう。原因がわかれば、効果的な対処法も見つけやすくなるはずです。 責任増大または役職定年 50代は、職場で求められる役割や背負う責任が大きく変わる時期です。 たとえば「ベテラン」や「役職者」として大きな責任を背負い、心身ともに疲弊してしまうケースは少なくありません。対して、一定の年齢でポストを退く「役職定年」がある会社では、50代中盤から責任や権限、給与が大幅に下がり、モチベーションが下がってしまうこともあります。 どちらにせよ、本人の意図に反する形で責任が増えたり減ったりするため、キャリアの悩みにつながりやすいです。 給与の伸び悩み 役職定年やポスト減少に伴い50代で発生するのが、給与の伸び悩み。また、たとえ今のポストを維持できたとしても、50代は昇進や昇給の限界を迎えやすいです。 組織の構造的な問題により、50代の収入は下がる可能性はあっても、上がる可能性は低いといわれています。 一方、50代は子どもの教育費、住宅ローン、健康管理費などにお金がかかり、生活費は全年代の中で最も高いです。「入ってくるお金は減るのに出ていくお金は増える」という状況は、将来の不安へとつながるでしょう。 専門性の陳腐化 50代はこれまでの経験を活かした知識・技術を持っている人が多いですが、技術革新のスピードが早い現代においては、その専門性が求められにくくなっています。 以前は希少とされた専門性も、テクノロジーが進化した現代では価値が下がり、これまで武器にできていたスキルが急に市場で通用しなくなるケースがあるのです。 専門性が陳腐化すると、新しい職場環境にも対応しにくく、キャリアの停滞やモチベーション低下を引き起こす原因になるでしょう。 健康リスク 長年の業務による疲弊、体力や集中力の低下、生活習慣病の兆候、更年期症状の出現などなど…。50代では、心身のあちこちに変化が現れ、不調を感じる日が増えるかもしれません。 しかし「これまで通りのスタイルで働くのがきつい」と感じても、働き方を変えれば収入が下がるリスクが高く、つい無理をしてしまうという人も多いでしょう。 50代は仕事と健康の両立を目指す必要がありますが、これまで仕事一筋だった人ほど、両立に悩みがちです。 将来や定年後のキャリアについて 年金や老後資金への不安、今のスキルが今後も社会で通用するかなど、50代では将来への不安もより現実的で重くなります。 また、50代に突入すると、自身の「定年退職」について考える機会も増えるでしょう。 今はキャリアが長期化しており、60代以降も働くのが主流になっています。年齢を重ねても働ける環境があるのは嬉しい反面、再就職・再雇用がうまくいくか」「健康面に不安がある中で定年後も働けるか」といった心配も生まれやすいです。 50代のキャリアの悩みを軽減させるポイント5つ キャリアの悩みを抱えやすい50代ですが、ほんの少し行動や考え方を変えるだけで悩みを軽減できる場合もあります。ここでは、悩み軽減につながる5つのポイントを解説しましょう。 経済対策をしておく お金の心配は尽きないものの、不安が強いとキャリアの悩みは深刻化します。悩みを大きくしないためには、自分なりの経済対策方法を見つけておくのが大切です。 手軽に取り組みやすい経済対策の一つとして挙げられるのが、家計のダウンサイジング。ダウンサイジングにより家計のコストを削減できれば、収入が横ばいでも金銭的なゆとりが生まれるでしょう。 今のうちから無駄を省いた生活を定着させておくことで、定年して収入が減っても生活を維持しやすくなります。 この他、積立NISAやiDeCoなどの活用、年金の繰り下げ受給の検討などをするのもおすすめです。 「いそかつ」で自分を見つめ直す 「いそかつ」とは「五十路での活動」の略で、50代のビジネスパーソンがこれまでの仕事人生を棚卸しし、自分の価値観やスキルを見つめ直すことを指します。 50代までの職務経験・得意分野・喜びを感じた出来事などを振り返り、そこから人生100年時代を見据えて必要な仕事・生活・学びを再構築していくのです。 「これまで」の整理と「これから」の目標設定を同時に行うことで、今後の働き方の軸が見えてきやすく、現状のキャリアの悩みを解決する道筋が見つかるでしょう。 スキルの強化や習得 今持っているスキルの強化や新たなスキルの習得に取り組み、専門性を高めるのも重要です。 50代はすでに「長年の豊富な経験」という武器を持っています。現状の武器に新たなスキルをプラスすることで、「長年の経験と新技術を持つ人材」として市場価値が高まり、企業から重宝されやすくなるでしょう。 専門性があれば、今の職場で活躍できるだけでなく、長期的に活躍できるキャリアの土台にもなります。充実したセカンドキャリアや、将来の安定収入につながる可能性が高いです。 健康管理の徹底 50代は、心身から発せられる「SOSサイン」を敏感にキャッチしなくてはいけません。健康面に問題があればキャリアの選択肢も限られてしまい、人生の充実度や幸福度にも影響します。 現状、健康に過ごせている場合でも、生活習慣病の予防と筋力維持はマストです。無理のない範囲で適度な運動や食事の栄養バランス管理を行い、健康維持に努めましょう。 また、定期的な健康診断や自分自身による日々の体調観察を欠かさないのもポイントです。 マインドセットの転換 「まだ頑張らなければ」という強迫観念が、キャリアの悩みを引き起こしているケースも少なくありません。 しかし、がむしゃらに働いたり、小さな子どもを育てるのに奮闘したりといったことがひと段落する50代は、必要以上に頑張るのではなく自分を労わる方向へと徐々にシフトしていきましょう。 50代は「人生の後半戦の始まり」ともいわれています。社会の一員としてキャリアを重ねるのも重要ですが、自分の人生をしっかり楽しむのも同じくらい重要です。 50代のキャリアの悩みを乗り越える方法 ここからはより具体的に、キャリアの悩みを乗り越える方法について解説します。 キャリアコンサルティングを受ける 「将来に漠然と不安がある」「このままでいいのかとモヤモヤする」 50代が抱えるキャリアの問題は多岐に渡るからこそ、本人だけでは核心に迫れずこのような思いを抱えてしまう人も多いです。そんなときは、キャリアの悩みを専門とするプロに相談し、一緒に問題解決のヒントを見つけましょう。 50代のキャリアコンサルティングでは、長年の経験を強みとして再定義し、この年代ならではの課題や将来設計に対して的確なアドバイスを行います。 キャリアコンサルティングが、今後のキャリアを自分でコントロールするための「最初の一歩」になるはずです。 キャリアの棚卸しをする キャリアの棚卸しをするのも、悩み解決に有効な方法の一つです。キャリアの棚卸しを行うと、自分の市場価値を客観的に把握でき、強みの「見える化」ができます。 すでに持っているスキルや経験を整理することで、自信が向上して不安軽減につながったり、定年後の働き方のイメージがより具体的になったりするでしょう。 「何をしてきたか」「何ができるか」「何をしたいか」という3つを軸にキャリアの棚卸しを進めると、今後の方向性が見えやすいです。 セカンドキャリアのプランを立てる 現在の会社での再雇用・異業種への挑戦・起業・アルバイトなど、セカンドキャリアにはいくつもの選択肢があります。 充実した未来にするために、50代のうちからセカンドキャリアの方向性を定めて準備しておきましょう。 セカンドキャリアのプランを立てるには、まず「何歳まで働くか」「どのような生活がしたいか」というゴールを設定します。そのゴールから逆算して、今のうちに不足スキルを補ったり、マネープランを再設計したりしてみてください。 転職・働き方の変更を検討する 体力や将来への不安が強い場合は、退職・転職を検討するのもありです。長く社会で活躍し続けるためには、50代で「細く長く働ける環境を選ぶ」のも一つの選択肢といえます。 50代での転職は高い即戦力性が求められ、成功率はあまり高くありません。しかし、今は50代に特化した転職支援サービスも登場しており、やり方やスキル次第で50代での転職も十分可能です。 また、今の職場に在籍したまま、時短勤務やリモートワークといった別の働き方に切り替えるという方法もあります。 社会的つながりを増やす 50代のキャリアの悩みは、役割・責任減少によるストレスが原因である場合も多いため、社外に居場所を作るのも効果的です。 社会的つながりが増えることで精神的に安定し、悩みやストレスが軽減する可能性があります。また、異業種の人との交流から、悩み解決のヒントが得られる場合もあるでしょう。 社会的つながりを増やす方法としては、習い事やボランティア、副業などが挙げられます。 特に副業は、定年後の収入源確保や自身のスキルを活かした生きがい発見につながりやすく、50代からのキャリア形成に良い影響をもたらしやすいです。 キャリアに悩む50代がやってはいけないこと 最後は、キャリアに悩む50代がやってはいけないことを紹介します。無意識にやってしまうことも多いため、注意が必要です。 過去に固執する 過去の肩書や成功体験にこだわると、プライドが邪魔をして現実を正しく受け止められません。また、若かった頃の能力や体力、地位を現在の自分と比較するのも、悲観や絶望につながりかねません。 今につながっている過去も大切であるものの固執せず、「今」や「これから」に意識を向けましょう。 年下上司や周囲の意見を謙虚な姿勢で受け入れ、新しいことを学ぼうとする意欲を見せるのが大切です。 「人生失敗」「手遅れ」と諦める 若い頃のようなキャリアの爆発的上昇は、50代では見込めません。そのため、中には「人生失敗」「手遅れ」など、諦めに似たモヤモヤを抱く人もいるでしょう。 しかし実際のところ、本当に取り返しのつかないような事態に陥っているケースは極めて稀で、多くはミッドライフ・クライシスがもたらす心理状態の一つです。 ここで諦めてしまえば、将来の可能性を狭めてしまうリスクがあるため、冷静な視点でキャリアや人生の再構築を考えてください。 健康を犠牲にする 悩みを払拭するために、今まで以上に仕事に打ち込もうとする50代もいます。 しかし、体力が落ちている50代にとって無理は禁物。疲れているのに無理をすると不安やストレスがさらに増幅し、余計に悩みが大きくなります。 悩みを直視し続けると精神的に疲弊するため気分転換は必要ですが、健康を犠牲にする方法は適切とはいえません。運動や没頭できる趣味、入浴など、自分にとってプラスになる方法を選びましょう。 今の悩みを乗り越えて、50代以降のキャリアを充実させよう 50代はミッドライフ・クライシスに陥りやすく、自己評価が下がってキャリアの悩みを抱えやすいです。 しかしこのような状況は、さまざまな変化をきちんと受け止めて、着実に次のステージへ進むための準備をしているともいえます。 自分らしい人生の第2章を再設計するチャンスでもあるため、今の感情をまずは認めて、そこから乗り越え方を見つけていきましょう!

40代独身女性が働き方に違和感を持つ理由。疲れたときの対処法
「40代になって、今の働き方に違和感を覚えるようになった」「今の働き方に疲れた40代独身女性はどうすればいい?」 独身、子育て中、介護中、転職中、起業など、40代の女性は一人ひとりのライフステージが大きく異なります。 そのため「自分軸を大切にした働き方」を模索する必要がありますが、なかなか自分らしい働き方が見つからず、悩んでしまうこともあるでしょう。 本記事では40代独身の女性に向けて、働き方に違和感を持つ理由や押さえておきたい知識、疲れたときの対処法などを解説します。 40代の独身女性が働き方に違和感を持つ理由6選 まずは、今の働き方にモヤモヤする原因から探っていきましょう。40代の独身女性が働き方に違和感を持つ主な理由は、以下の通りです。 職場の人間関係にストレスがある 40代は、上司と部下の間で板挟みになって、人間関係のストレスが増えやすいです。折り合いの悪い相手と長年同じ職場で働くことで、ストレスが限界に達するケースもあります。 また、独身女性は「未婚」を理由に、職場内でシングルハラスメントを受けることも。 シングルハラスメントとは、未婚者・独身者に対する不用意な言動のことを指します。「まだ結婚しないの?」と聞く、「結婚してこそ一人前」と独身者を否定する、「独身だから時間の融通が利くでしょ」と優先的に業務を押し付けるなどの行為は、シングルハラスメントの代表的事例です。 体力的に限界 ホルモンバランスの変化や体力の低下により、40代は無理が利きにくくなる年齢です。残業や休日出勤といった時間外労働が多い職場で働いている女性や、運動量の多い仕事に就いている女性は、40代で体力の限界を感じて働き方に違和感を持つ場合があります。 また、現時点では問題なくハードワークをこなせていても、未来を想像して「今の働き方を続けられるか」という不安を抱くかもしれません。 40代以降の働き方は「頑張り続ける」よりも「持続可能か」が重要なポイントとなるため、限界を超える前に働き方を見直すのがおすすめです。 経済的に不安 「思ったように給料が上がらなかった」「出世コースから外れてしまい、今後の昇給が見込めない」このような経済的な不安から、働き方に違和感や不満を持つ場合もあるでしょう。 独身者は、日々の生活費から老後の資金まで全て一人で賄う必要があるからこそ、収入に関してよりシビアになるものです。 しかし収入に関する不安は、今の仕事にプラスアルファで副業をする、資産運用を行うなど、働き方を変える以外の方法でも解消させられる可能性があります。具体的な目標額を設定し、目標に応じた適切な行動を取ることで、将来の安心へとつながりやすいです。 会社や自分のキャリアの将来性が見えない リスク管理が欠如している、意思決定が遅い、顧客数や売上の低迷が続いているなどの理由により、今の会社の将来性を不安視している女性もいるのではないでしょうか。また、会社の将来性にはそこまで問題がなくても、「今の職場では自身の将来・キャリアが見えない」と感じ、不安が募るケースも少なくありません。 将来性が見えないまま働くと、モチベーションの低下やキャリアの停滞、市場価値の低下といった重大なリスクにつながる恐れがあります。 残りの社会人人生を豊かにするためにも、40代で働き方やキャリアを見直すのは有効といえるでしょう。 今の仕事にやりがいや成長を感じなくなった 40代独身女性は社会人経験が長いからこそ、仕事でやりがいを感じる機会が減り、成長実感を得にくいです。 順調に仕事をこなしていてもどこか「つまらない」と感じたり、ある日急に「新しい挑戦や働き方を模索したい」という衝動が湧いたりするかもしれません。 また、年齢を重ねるにつれて会社の価値観と自分の考え方にズレが生じ、仕事へのやりがいを失くしてしまうこともあります。 自分の中でキャリアの優先度が変わった 仕事に対する考え方は、時間の経過とともに変わります。そのため、勤続年数を重ねるうちに、自分の中でキャリアの優先度が変わる場合もあるでしょう。 20代のうちはキャリアが最優先だったとしても、40代では「もっと私生活も大切にしたい」「キャリア構築より専門性を発揮したい」など、考え方が変わることは珍しくありません。 特に近年は価値観が多様化し、それに伴い新しい働き方も次々登場しています。かつては一辺倒になりがちだった独身女性の働き方にバリエーションが加わったことで、キャリアの優先順位を見直す人は多いです。 働き方を変えたい40代独身女性が押さえておきたいポイント 情報不足の状態で働き方を変えようとするのは危険です。ここでは、働き方を変えたい40代独身女性が押さえておくべきポイントについて解説します。 40代女性の平均年収は300万円台 国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、40代女性の平均年収は343万円です。 なお、同世代男性の平均年収は600万円台であり、日本の男女間賃金格差は縮小傾向にあるものの、依然として開きが大きい現実が浮き彫りになっています。 40代の独身女性が働き方の変更を検討する際には、収入面や退職金などについてよく考慮しましょう。 もちろん「収入が高い仕事=良い働き方」ではありませんが、生活と心を安定させるためにはある程度の収入が欠かせません。 転職では「即戦力+マネジメント能力」が求められる 若手人材に比べると難易度は高くなりやすいですが、40代での転職は十分可能です。40代の独身女性が働き方を変えたいなら、転職を視野に入れるのもありでしょう。 ただし40代での転職は、これまでの経験・スキルを即戦力として活かすことが前提とされます。また、マネジメント能力や組織構築能力が重視される傾向です。 そのため、同業種もしくはスキルを活かせる異業種への転職が有利となります。自分が評価されやすい業界・職種を分析し、戦略的に活動するのが転職成功のコツです。 スキルアップや資格取得に積極的な姿勢が必要 AIやテクノロジーの進化により、従来のスキルだけでは将来的に戦力外となるリスクもゼロではありません。働き方を変えるためには、これまでの経験に加えて、新たなスキルや資格の取得に挑戦してみるのもおすすめです。 年齢を重ねても新しいことを学ぼうとする姿勢は、社内評価や転職活動でも高評価につながります。能力が向上すればキャリアの選択肢が増え、理想の働き方を実現できる可能性が高いです。 専門性が高い人材は常に一定の需要があるので、50代・60代以降も長く活躍しやすいでしょう。 40代の独身女性によく見られる働き方のパターン 「今の働き方には違和感があるけど、自分に合う働き方がわからない」という方もいるのではないでしょうか。 ここでは、40代の独身女性によく見られる働き方のパターンを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 会社員として働く 会社員は、40代独身女性に最も多い働き方といえるでしょう。 安定した雇用と収入が見込めるうえ、退職金をはじめとする福利厚生の充実、社会的信用の高さなどが会社員として働くメリットです。 かつては働き方の自由度が低いのが大きなデメリットとなっていましたが、近年は多様な働き方を認める職場も増えてきました。ただし、結果や成果を求められ、責任が重くなりやすい傾向にあります。 専門職・資格職に就く 医師、弁護士、公認会計士、保育士、介護福祉士、デザイナーなどのような、専門職・資格職に就いている40代独身女性も多いです。 専門職や資格職では、高度な知識・技術・経験が求められるため、高待遇や高収入に期待できます。専門スキルを活かして社会貢献できるため、やりがいにもつながりやすいです。 一方で、専門分野が限定されているからこそ、キャリアチェンジが難しくなりやすいというデメリットもあります。 パート・派遣・契約社員 パート・派遣・契約社員は、ワークライフバランスを重視している40代独身女性に多い働き方です。 かつては、非正規雇用というだけでネガティブなイメージを持たれがちでしたが、現在は「待遇・処遇の改善」「多様なキャリア形成の認知」などによって、価値を正当に評価されつつあります。柔軟な働き方ができ、自分の生活リズムも大切にできるところが魅力です。 しかし、正社員に比べるとやはり低賃金・不安定な雇用になりやすい点は、理解しておきましょう。 フリーランス・自営業 特定の会社に雇われず、自分のスキルや能力だけで生計を立てている40代独身女性もいます。 フリーランスや自営業は、自由度が高いのが最大の強み。「どのような仕事を請け負うか」「いつ・どこで働くか」などは、基本的に全て自分で決められます。 ですが自由度が高い分、契約や営業、健康保険、年金などあらゆる手続きを自分で行わなくてはいけません。また、収入に波があるため、社会的信用も低めです。 Wワーク かつて民間企業では副業禁止が一般的でしたが、2018年に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表したのをきっかけに、一気に副業解禁の流れが加速しました。 今では、2つの仕事を掛け持ちして収入を得る働き方もスタンダードとなっています。 単に収入アップにつながるだけでなく、一方の仕事が不安定になっても、もう一方があるため収入が途絶えるリスクが低いのがWワークの強みです。2つの仕事を両立させるバランス調整が必須なため、時間やスケジュール管理が得意な人に向いています。 今の働き方に疲れた40代独身女性におすすめの対処法 ここでは、今の働き方に疲れ、現状を変えたいと思う40代独身女性におすすめの対処法を解説します。 有給休暇でリフレッシュを図る 疲労解消に最も効果的なのは、休息です。「今すぐ何かしらの対処法を取らないと」と焦るかもしれませんが、まずはゆっくり休むのも立派な対処法の一つといえます。 有給休暇を取って仕事から物理的に離れ、心身の疲労回復を図りましょう。 また、休んでいる間は、仕事や働き方について考えたり、仕事に関するデータ・資料・情報などを見たりするのも控えてください。 悩みや理想の働き方を明確にする 自分が今の働き方のどこに違和感を持っているのか、どんな働き方なら気持ちよく働けるのかなどを、紙に書き出してみるのがおすすめです。 頭の中にある悩みや感情、不安などを全て書き出すと、客観的に自分を見つめ直せます。溜め込んでいた気持ちを外に出すことで、抱えているストレスの軽減にもつながるでしょう。 なお、単に書いて終わりではなく、最後には読み返すのを習慣にすると、自己理解がより深まります。 収支のバランスを見直し、貯蓄を増やす 本当に働き方を変えるのかまだ決断できていない状態でも、収支のバランスを見直してコツコツ貯蓄を増やしておきましょう。 貯蓄があれば「働き方を変えるために転職しよう!」と決心した際も、すぐに行動に移せます。また、たとえ今の働き方を維持する場合でも、貯蓄はあって困るものではありません。 支出を思いのままに管理できるのは独身ならではの強みでもあるため、取り組み次第で大きな貯蓄を達成できる可能性があります。 キャリアコンサルティングを受ける 40代の独身女性は、さまざまな働き方の選択肢を持っています。各働き方について自分一人で綿密な情報を集めるのは困難なため、キャリアのプロを頼るのがおすすめです。 キャリアコンサルティングは、主に「自分らしく働く」ことに焦点を当てています。 必ずしもキャリアアップや転職を目指すわけでなく、一人ひとりに合った情報提供・アドバイスをしてくれるため、気持ちよく働ける方法が見つかりやすいです。 職場環境を変える行動を取る 部署異動や転職、独立などにより今の環境を変えるのも、働き方を変える方法の一つです。 自身の体力や今後の展望を考慮しつつ、専門資格の取得や副業、非正規雇用などを含めた柔軟な選択肢を検討しましょう。 これまでの経験の棚卸しや強みの明確化を行い「自分に何ができるのか」と「これからどうなりたいのか」を両立して考えるのがポイントです。 40代はキャリア再設計のチャンス!独身女性に合う働き方を見つけよう 今の働き方に対する違和感や不満は「わがまま」や「逃げ」ではなく、納得いく働き方を再構築するチャンスです。 定年を迎えても働き続けることを選ぶ人が増えた現代において、40代はちょうどキャリアの転換点。一度立てたプランを再設計するのに適した時期といえます。 キャリア・コンサルティング・ラボは、40代独身女性が抱えるさまざまな働き方に関する悩みを解決に導いてきた実績があります。プロの力も借りながら、自分らしい働き方の実現を目指していきましょう!

40代女性に適した働き方とは?理想の働き方を叶える方法
40代は女性にとって、私生活・体調・価値観などがガラリと変わる、ターニングポイントとなりやすい時期です。 そして、さまざまな変化の中で「今の働き方を続けていいのかな」「もっと自分に合う働き方があるかも」と考えることもあるでしょう。 たとえ小さくても、疑問や違和感を持ったときは、働き方を見直すチャンス。 本記事では、40代女性が直面しやすい働き方の問題や適した働き方の例、理想の働き方を叶える方法などを解説します。 40代女性には豊富な働き方の選択肢がある 「自分に合った働き方がしたくても、40代から働き方を変えるのは難しいのでは…」 このように考える女性も多いのではないでしょうか。 確かに、転職やキャリアチェンジを通じて働き方を変えたい場合、転職市場では若手人材のほうが有利になる傾向があるため難易度は高くなりやすいです。しかし、今はミドル世代の人材を求める企業も増えており、高年収や好条件での転職も不可能ではありません。 また、働き方を変える方法は転職だけでなく、今の職場にはたらきかける、副業を始めるなどいくつもあります。40代女性には豊富な働き方の選択肢があるため、その中から「本当に自分に合う選択」をするのが大切です。 40代女性が直面しやすい働き方の問題 現代の女性の働き方は多様化していますが、まだまだ課題や問題があるのも事実です。まずは、40代女性が直面しやすい働き方の問題について見ていきましょう。 プライベートとのバランスが取りにくい 40代は、子育てや介護といった「人生を左右する大きなライフイベント」が多く発生しやすい時期です。 このようなライフイベントによる負担は、本来女性だけが負うべきではありません。しかし、令和になった現代でもまだ女性だけに負担が集中しやすい状態が続いており、40代女性は今まで通りの働き方を続けるのが困難になるケースがあります。 仕事とプライベートのバランスがうまく取れないとストレスや疲労が蓄積し、仕事のパフォーマンス低下、心身の健康悪化など悪循環を引き起こすリスクが高いです。 給与が低い 子どもの教育費や住宅ローン、親の介護費、老後資金の準備など、40代は「人生で最も金銭負担が重い時期」だといわれています。 そのため、給与が低い、または今後も昇給が見込めないという状況は、20代や30代のとき以上に深刻な死活問題と捉えられるでしょう。 40代はすでに十分な業務経験を積んでいるからこそ、給与が低いと「経験やスキルを正当に評価してもらえない」という不満にもつながりやすくなります。 昇進できない 「どんどんキャリアを伸ばしていきたい」と考える、キャリア志向の女性もいるでしょう。様々な企業で女性が活躍するようになってきていますが、一方で女性のキャリアアップには、未だに多くの課題が残されているのも現実です。 企業によっては、女性というだけで昇進が阻まれる「ガラスの天井」が依然として存在する場合があります。また、「家庭があると管理職はできないだろう」「責任のある仕事は男性のもの」のような時代遅れの固定観念によって、出世コースから外されてしまうケースも。 今の働き方ではキャリアアップが叶わない場合、働き方の変更を検討するのは自然なことといえます。 体調・体力面に不安が出てきた 40代の女性は、ホルモンバランスの変化により以前より疲れやすくなったり、筋肉量が減少して体力が落ちたりします。以前は問題なくこなせていた働き方でも「きつい」と感じることが増え、働き方を見直す40代女性は少なくありません。 しかしこのような場合には、働き方の変更を検討する以外にも「体力向上」によって問題を解決できる場合があります。 筋トレやストレッチを継続してみる、生活習慣を改善してみるなど、まずは無理なく続く行動に取り組んでみるのがおすすめです。 40代女性が働き方を変えるメリット・デメリット 40代女性が今から働き方を変えることには、メリットがある一方でデメリットもあります。フラットな視点でベストな選択をするためにも、メリット・デメリットを把握しておきましょう。 40代女性が働き方を変えるメリット 40代の女性が働き方を変えるメリットは、以下の通りです。 今の自分に合ったベストな働き方ができる 既存の職場のストレスから解放される 新たなチャレンジにより自己成長につながる 収入アップ・キャリアアップできる可能性がある 若いときに「良い」と思った働き方が、年齢を重ねてからも自分にとって最適とは限りません。働き方を変えると、「40代の今の自分」に合う働き方を選択できるのは大きなメリットといえるでしょう。 また、今までの経験やスキルが評価されて、収入・キャリアアップにつながる可能性もあります。 40代女性が働き方を変えるデメリット 40代の女性が働き方を変える際に起こり得る、以下のデメリットにも目を向けておきましょう。 シミュレーションが甘いと「働き方迷子」になる 転職をする場合、即戦力や専門性が求められる キャリアダウンや年収低下の可能性がある 前もって念入りにシミュレーションしておかないと、働き方を変えても新しい働き方に馴染めないというリスクがあります。そうすると自分らしい働き方がわからない「働き方迷子」になってしまい、キャリアの方向性を見失うでしょう。 また、今とは異なる働き方を選ぶことで、キャリアや年収に影響が出る場合もあります。 40代女性の主な働き方 個人の価値観や家庭の事情など、一人ひとりが抱える背景は異なるので、40代女性に適した働き方は一つではありません。 自分に合う働き方を考える際は、まずどのような働き方があるかを知るのが重要です。ここでは、40代女性におすすめの働き方の例を紹介します。 家庭との両立を目指す働き方 育児や家事、介護などをしながら働く働き方です。 かつての日本には「男は仕事、女は家庭」という価値観が根付いていましたが、今は共働き世帯が主流となっており、家庭と仕事を両立しやすい労働環境を目指す職場も増えています。 家庭との両立を目指す働き方の代表としては、フレックスタイム制や在宅勤務・テレワーク、時短勤務などが挙げられるでしょう。 フルタイム勤務している女性も多いですが、少しでも自由な時間を確保するため、あえてパート勤務や派遣社員、契約社員といった働き方を選ぶ女性も多いです。 プライベート重視の働き方 独身や子なし夫婦の40代女性に人気なのが、プライベートの時間を大切にできる、ワークライフバランスのとれた働き方です。 仕事よりも趣味や交友関係、休息といった私生活に重きを置き、その時間を確保するために効率的な働き方や時間固定の働き方を選ぶスタイルを指します。 「残業の少なさ」や「休日の多さ」などに注目すると、プライベートの時間を確保しやすく少ないストレスで働けるでしょう。具体的な働き方としては、リモートワークやフレックスタイムなどが挙げられます。 また、事務職や工場職など、業務時間内に仕事が完結しやすく残業が少ない職種を選ぶのもポイントです。 理想のキャリアに合わせた働き方 「キャリア重視」というと、上昇志向が高くバリバリ働くイメージがあるかもしれませんが、現代女性のキャリアモデルは一つだけではありません。 バリバリ働いてキャリアを積む「バリキャリ」の他、マイペースに働きつつキャリアを築く「ゆるキャリ」、キャリアと私生活の両方を充実させる「フルキャリ」といったように、多様化かつ細分化しています。 なお、キャリアの分類は固定的なものではなく、人生のフェーズに応じて柔軟に変化させてOK。「今の自分にとって理想のキャリア」を明確にし、それに合わせて働き方を選ぶのが大切です。 専門性を高める働き方 「今の専門職をより追求したい」「現場のスペシャリストを目指したい」のように、今以上に専門性を追求する働き方もあります。 給与や昇進ももちろん大切ですが、長く働くうえではやりがいも同じくらい大切です。専門性を高めて活躍できる人材になることは、多くのキャリアパーソンにとって大きなやりがいとなるでしょう。 日々の業務での実践を軸にしつつ、外部研修を受けたり資格取得を目指したりすることで、専門性は高まっていきます。この他、場合によっては今より専門的な部署への異動・転職を検討するのもありです。 Wワークをする働き方 政府主導の「働き方改革」によって副業を解禁する企業が増え、現代はかつてに比べると副業がしやすくなりました。 「収入を増やしたい」「スキルアップに活かしたい」「視野を広げたい」など理由はさまざまですが、メインの仕事に加えてサイドジョブを持つ40代女性も増えています。 また、メインとなる仕事を決めずに複数の本業を持つ「複業」という働き方もあります。興味のあるさまざまな分野の仕事に挑戦できる他、収入源の分散によるリスクヘッジにもなるのが複業のメリットです。 40代女性が理想の働き方を実現する方法 理想の働き方のイメージや今の働き方を変えたい想いはあるものの、どうすれば現実を変えられるのかがわからない…という40代女性もいるでしょう。 ここでは、40代女性が理想の働き方を実現する方法について解説します。 理想の働き方を明確にする 理想と現実のバランスを大切にしながら、希望する働き方を明確にしていきましょう。 「こんな働き方がしたい」というイメージをまずは膨らませ、そこから現実的に可能か、不可能な場合は妥協点はどこかなどを探るのが有効です。 また、なかなかイメージがわかないときは「嫌な働き方」を考え、その対極にある要素を探すという方法もあります。 理想の働き方が明確かつ現実的であればあるほど、将来のシミュレーションも正確にでき、自分に合う働き方を実現しやすいです。 今の職場で理想を実現できないか試みる 成功事例も多くあるものの、40代女性の転職では専門性やスキルが求められやすく、難易度は高めです。 そのため、いきなり転職を決意するのではなく、ひとまず今の職場で自分の理想を実現できないか試みるのがいいでしょう。 働く女性を支援する制度や企業内の制度を活用する、働き方について上司に相談してみる、柔軟な働き方ができる部署への異動を検討するなど、さまざまな行動に取り組んでみてください。 難しい場合は未来を見据えて準備する 「今の職場では理想の働き方を実現できない」と判断した場合には、転職や独立といった選択肢が現実味を帯びてきます。 しかし、このタイミングでもいきなり行動せず、未来に向けた準備を整えるのが先です。 転職したい業界の動向について情報収集する、転職・独立に有利な資格を取得する、いくらと決めて貯蓄を増やすなど、転職・独立の成功には念入りな準備が欠かせません。 転職・独立を一旦ゴールとして定め、「ゴールに向かうには今何が必要か」を考えると、やるべき準備が見えてきます。 転職や独立で環境を変える 準備が整ったら、転職や独立に向けて具体的に動いていきましょう。 収入やキャリアに空白期間を作らないよう、今の会社で働きながら並行して活動するのがベターです。安定した収入は精神的安心感をもたらし、自分に合う働き方ができる環境を納得いくまで吟味できます。 事前の情報収集や自己分析を徹底的に行ったうえで戦略的に行動するのが、転職・独立成功のポイントです。 Wワークに挑戦する 今の仕事にプラスで新しい仕事を始めるという働き方もあります。転職や独立の準備の一環として、Wワークが選択されるケースも多いです。 ただし、スケジュールをつめ込みすぎるとオーバーワークで疲弊してしまうため、本業や私生活とのバランスはよく考えましょう。 また、Wワークをすると税金の手続きが今までとは変わる可能性があるため、税金や確定申告についても調べておくのが大切です。 40代女性が働き方に悩んだときは…プロに相談するのがおすすめ 40代は、男性・女性問わずキャリアの壁にぶつかりやすい時期です。 働き方の悩みから抜け出せないときは、その悩みを一人で抱えず、キャリアのプロと一緒に解決を目指すのが良いでしょう。 キャリア・コンサルティング・ラボは「どうすれば自分らしく働けるか」に焦点を当てて、あなたにぴったりの働き方や具体的な実現方法を考えます。 40代女性は、多くの働き方の中から「自分に合うもの」を選ばなくてはいけません。悩んだり迷ったりして当然なので、プロの力も借りながら理想の働き方を実現させてくださいね!

40代で仕事のモチベーションが切れた!頑張れない理由と対処法
40代は働き盛りである一方で、仕事のモチベーションが落ちてしまう人が増える世代でもあります。 「40代に突入して、仕事のやる気が出なくなった」「モチベーションが下がって、毎日仕事に行くのが苦痛」 このように感じて、悩んでいる40代も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、仕事のモチベーションがなくなった40代に向けて、年代ならではの原因や対処法を解説します。 モチベーション低下を放置することにはさまざまなリスクがあるので、現状に向き合い状況改善を目指しましょう。 40代で仕事のモチベーションがなくなってしまうケースは多い 以前はあったはずのモチベーションがなくなってしまうと、「このままで大丈夫だろうか」と不安を覚える人も多いでしょう。 しかし、まず知っておいてほしいのは、40代で仕事のモチベーションを失うケースは珍しくないということです。そもそも年齢に関係なく、人間のモチベーションには波があります。常に高いモチベーションを維持し続けるのは、身体的にも精神的にも負担が大きく、現実的ではありません。 そのため、40代でモチベーションが保てなくなっても、焦ったり自分を責めたりしないようにしましょう。原因を特定したうえで、自分のペースで対処していくのが大切です。 仕事のモチベーションが下がる40代特有の理由 40代で仕事のモチベーションが下がるのは、キャリアを重ねてきたからこその悩みや年代特有の問題が原因となっている場合が多いです。ここでは、代表的な5つの理由を解説しましょう。 マンネリによるやりがい喪失 業務経験が豊富な40代は、大抵の仕事に一人で対応できるでしょう。そのため、職場では頼りにされたり憧れられたりする場面が増えますが、一方で自分の体感としては仕事に変化を感じにくくなります。 新たな発見や刺激、成長実感などが少ないため、マンネリ感から仕事のやりがいを見失い、モチベーションが切れやすいです。 責任が増えるプレッシャー 40代では、責任の大きい仕事や役職を任されることが多くなります。これはキャリアアップとも捉えられますが、あまりにも背負う責任が大きすぎるとプレッシャーとなり、モチベーションを低下させるでしょう。 特に、責任感が強い人ほど「結果を出さないと」「他の人に迷惑をかけたくない」と思い詰めてしまい、精神的にしんどくなりやすいです。 また、経験やキャパシティを超えた重すぎる責任を負わされた場合も、やる気の喪失につながります。 板挟みポジションで人間関係のストレスが増える 40代は、中間管理職として上司と部下の間で板挟みになりやすいです。部下のマネジメントを行いつつ、上司や上層部の顔色をうかがう必要もあり、部下の意見と上司の指示の間でジレンマを抱えるケースが少なくありません。 また、上司とも部下とも密にコミュニケーションを取ることが求められるので、人間関係が複雑化しやすく悩みやストレスが増えがちです。 気持ちをわかってくれそうな同僚に相談したくても、昇進や退職などで同じ職場にはいない場合も多く、このような状況も孤立感を深めます。 心身の調子が不安定 40代は心身に変化が見られやすい年代でもあり、心身の不調が仕事のモチベーションダウンの原因である場合も多いです。 身体的な変化でいうと、40代以降はどうしても体力が落ちます。以前よりも疲れを感じることが増え「これ以上無理をしたくない」と考えやすいです。 また、40代から50代にかけての人生の転換期には「このままで良いのか」と不安や葛藤を抱くミッドライフ・クライシスに陥りやすく、精神的に不安定になることがあります。 仕事と家庭の両立が難しい 40代は、子育てや親の介護など家庭面の負担も増えやすく、今まで以上に仕事と家庭の両立が求められます。 一つのことに打ち込みにくい環境や、常にやるべきことに追われる環境に疲れてしまい、仕事のモチベーションが切れてしまう人も多いです。 仕事と家庭の両立のために自分のプライベートを削る場面も多く、十分な休息が取りにくいのも仕事へのやる気を失う理由の一つでしょう。 40代が仕事のモチベーション低下を放置するリスク 仕事のモチベーションが下がっている自覚がありながら、現状に目をつぶって日々働いている人も多いのではないでしょうか。 しかし、40代で仕事のモチベーション低下を放置することには多くのリスクがあります。ここでは、どのようなリスクがあるのかを具体的に解説します。 自己肯定感が下がる 以前は高かった仕事へのモチベーションが下がると、多くの人はそんな自分を責めて自己嫌悪に陥ります。「自分はダメだ」「自分では無理だ」のように考えやすくなり、自己肯定感が下がってしまうでしょう。 また、自己肯定感が下がると何に対しても消極的になるため、より仕事のモチベーションが下がるという悪循環を招きやすいです。 心身の不調につながりやすい モチベーションが上がらず「仕事をしたくない」という気持ちのまま働き続ければ、どんどんストレスが蓄積していきます。 そして、ストレスは「万病のもと」といわれるほど、心身に大きな影響を与えるものです。 現状を放置し続けてストレスが限界を超えると、心身のさまざまな不調や深刻な病気のリスクが高まり、日常生活にも支障が出る危険性があります。 キャリアダウンの可能性 仕事に対するモチベーションが下がると、挑戦意欲やスキルアップを目指す気持ちも薄れます。成長を自ら止めてしまいやすく、希望しないキャリアダウンにつながるリスクがあるでしょう。 また、「今の職場でキャリアダウンしたから転職したい」と思っても、40代の転職では即戦力となるスキルが求められる傾向です。成長できていなければスキル不足と判断され、転職活動が難航する可能性があります。 バーンアウトの恐れ 今まで高いモチベーションを保っていた人ほど陥りやすいのが、バーンアウト(燃え尽き症候群)です。 バーンアウトはモチベーション低下の最終段階ともいわれており、頑張り続けた結果全てのエネルギーを使い果たして、ある日いきなり無気力・無関心になってしまいます。また、ゆくゆくはうつ病に移行するリスクも! 仕事へのモチベーションが下がってバーンアウトの兆候に気づいた場合は、休息やストレス発散、専門家への相談など早期の対策が重要です。 より働きにくくなるリスク モチベーションが下がると、集中力低下により仕事のパフォーマンスが落ちるうえ、孤立感を抱いて周囲の人ともギスギスしやすくなります。 結果的に、自ら働きにくい環境を作ってしまい、職場全体にも悪い影響を与えるリスクが高いです。 「働きにくいからもっとモチベーションが下がる」という悪循環を生み出しやすく、最悪の場合退職するしかない状況になる場合もあります。 40代向け!仕事のモチベーションが上がらないときの対処法 ここでは、40代で仕事のモチベーションが上がらないときの対処法を説明します。すぐに実践できるものもあるので、ぜひ参考にしてください。 無理にモチベーションを上げようとしない 下がったモチベーションを無理に上げようとすると、余計に疲労やストレスが溜まって状況悪化を引き起こしかねません。 モチベーションは「無理に上げよう」とするのではなく、「今より下げないようにしよう」と考えるのも大切です。 今より下げない方法としては、まずはしっかり休息を取りリフレッシュするのが良いでしょう。休日や有給休暇を使って心身を休めるだけで、気持ちが前向きになりモチベーションが回復することがあります。 モチベーション低下の原因を探る なぜ40代で仕事のモチベーションが下がってしまったのか、原因を突きとめるのも重要です。原因がわからなければ、対策や相談がしにくく、問題解決するのに時間がかかってしまいます。 たとえば、どんな場面でより強く仕事に対してネガティブな感情を持つのかを分析してみると、ストレスの源が見つかりやすいです。 同時に「どんな仕事や職場環境なら、モチベーション高く働けるのか」も考えてみると、自分が本当に望む方向性も見えてくるでしょう。 今の仕事や会社を選んだ理由を振り返る 今の仕事を選んだ理由、今の会社に入社しようと思ったきっかけなどを振り返ると、初心を思い出してモチベーションが上がる場合があります。 過去の自分が仕事に何を求めていたのかを深掘りすることで、自分の核となる価値観や働く目的を再認識でき、今後の目標も立てやすくなるでしょう。 また、入社当時と今の気持ちとの間にギャップがある場合も、ギャップから見落としていた問題やストレスの原因に気付けます。 自己管理を徹底する 仕事のモチベーションが下がると、つい日常生活における自己管理まで甘くなりがちです。食事や睡眠をおろそかにしたり、お金を使いすぎてしまったりする人は少なくありません。 しかし、自己管理を怠るとさらに心身の不調につながるリスクが高くなり、より仕事に対するモチベーションが沸きにくい状況を作ってしまいます。 仕事に対してネガティブな感情が大きいときほど、しっかり自己管理をするよう心掛けましょう。 新しい挑戦や学びを始めてみる 資格の勉強をする、副業を始めてみる、趣味の分野で新たな挑戦をするなど、自ら刺激を求めて行動してみるのもモチベーション回復に効果的です。 40代になると、仕事での成長実感の減少はどうしても避けられません。日々の仕事にマンネリ感を抱かないためにも、積極的に新しい情報や取り組みに興味を持ちましょう。 たとえプライベートにおける挑戦でも、自分が「やりたい」と思ったことならやりがいが得られ、人生が充実して仕事のモチベーションアップにつながる可能性があります。 目標を再設定する キャリアの方向性や目標を再設定するのも大切です。方向性・目標は年齢とともに変化することも珍しくないため、定期的な見直しが必要となります。 なお、目標は「明日からこれをやろう」という短期的なものと「将来どうなりたいか」といった中長期的なもの、2つ用意するのが理想です。 短期的な目標を日々こなすことで、モチベーションがないときに同時に下がりやすい自己肯定感を高められます。また、中長期的な目標があると進むべき方向に迷いにくいです。 信頼できる人と話す 信頼できる上司や同僚、家族などに相談するのも、モチベーションアップにつながりやすいです。 人は自分の感情を言語化しようとすることで、頭の中を整理できます。また、ただ話を聞いてもらうだけでも孤独感が和らぎ、ストレス解消になるでしょう。 相手の客観的な意見により、自分一人では気づけなかった問題点や解決策が見つかる場合も多いです。 異動・転職を検討する どうしても仕事のモチベーションが上がらず、自分一人でできる対処法では解決が難しい場合は、異動や転職をして環境を変えるのも一つの手です。 異動・転職によって環境をガラリと変えれば、心機一転できモチベーションを取り戻せる可能性があります。 ただし、40代の異動・転職は、マネジメント能力や専門性などが問われやすいです。モチベーションがなくなった原因を見つめるとともに、これまでの仕事で培ったスキルや実績を的確にアピールするのが、成功するためのポイントとなります。 40代の仕事のモチベーションの悩みはキャリアのプロに相談! 40代のモチベーション低下は、これまでに積み重なった不満やストレス、無意識のうちにしている思考の癖など、いくつもの要因が複雑に絡んで発生している場合もあります。 そのため、一人での対処が難しいときは無理をせず、気軽にキャリアコンサルティングでプロに相談してみるのがおすすめです。 キャリア面談では、現在抱えているモチベーションの悩みを相談できるだけでなく、自分の価値観を再認識したり、将来のキャリアについてのアドバイスが得られたりします。 過去・現在・将来問わず、仕事やキャリアのことを幅広く相談できるので、表面的な問題だけでなく自身の課題に根本から対処が可能です。 40代で仕事のモチベーションが切れたら、立ち止まって考えてみよう 40代は、仕事と生活のバランスを考え直す必要性が出てくる人や、時代の変化に戸惑う人も多く、キャリアの岐路に立たされやすい年代です。 「何だか仕事のモチベーションが出ない」という気付きは、キャリアを見直すタイミングに差し掛かっているという知らせかもしれません。 40代でモチベーション低下に悩んだら、まずは一度立ち止まり、キャリアのプロと一緒に問題解決を目指してみてください。

「仕事辞めたい」と感じる40代がやるべきこと7選!後悔しない対処法
40代で「仕事を辞めたい」と思う人は少なくありません。しかし、退職は自身の生活にも今後のキャリアにも大きな変化をもたらす選択であるため「本当に辞めて後悔しないのか?」と不安や迷いが生じやすいです。 本記事では、40代が仕事を辞めたいと感じる原因や、退職前に確認すべきこと・やるべきことを詳しく解説します。 「仕事辞めたい」という感情をきっかけに、自分の本音や目指すべき方向性を再確認し、納得できる答えを導き出しましょう。 40代で「仕事辞めたい」と思う人は多い 厚生労働省の「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要(個人調査)」によると、「仕事や職業生活において強い不安、悩み、ストレスを感じる事柄がある」と回答した40代は87.1%でした。 この数字は働く全世代のなかで最も高い割合となっており、40代は仕事に不安や悩み、ストレスを抱えている人が多いのがわかります。このデータから、40代で「仕事を辞めたい」と感じている人は少なくないことが推察できるでしょう。 しかし、40代の離職率は平均で6~10%前後であり、20~30代の離職率より低いです。 40代は仕事の悩みやストレスを抱えながらも、年齢的なハードルや年収ダウンのリスクなどを考えて、実際に退職する人は一握りとなっている現実がうかがえます。 「仕事辞めたい」と思っても、急いで退職するのはNG 「仕事を辞めたい」と本気で思うなら、もちろん辞めても構いません。しかし、熟考せず急いで退職してしまうと、のちのち後悔する可能性が高いので注意しましょう。 20~30代に比べると、40代は転職先が決まるまでに時間がかかりやすいです。次の職場を決めずに今の仕事を辞めると、無収入の期間やキャリアの空白期間が長引くリスクがあります。 また、なかなか転職先が決まらない焦りから、自分に合わない会社やブラックな会社を選びやすくなり、再び辞めたくなる恐れも…! 40代の転職は20~30代に比べると難易度が上がりやすいため、戦略的かつ計画的に行うのが大切です。 40代が「仕事辞めたい」と感じる理由とは? 40代が「仕事を辞めたい」と感じる理由はさまざまです。ここでは、代表的な理由を紹介しましょう。 人間関係のストレス 40代になると、今までより仕事の幅が広がったり部下の育成を任されたりする機会が増えます。必然的に仕事で関わる人の数が多くなり、合わない人とも積極的にコミュニケーションを取らざるを得ないので、人間関係のストレスを感じやすいです。 また、勤続年数が長い人の場合は、苦手な人と長年同じ職場で働き続けることでストレスが限界に達してしまうケースもあります。 人間関係に摩擦が生じると働きにくさを感じ、毎日職場に行くことさえ辛くなってしまうでしょう。 評価や給料に不満がある 30代までの評価基準は、主に「仕事の実績」です。しかし40代になると実績に加えて「組織への貢献度」や「マネジメント能力」なども評価され、場合によっては昇給昇進コースから外れてしまうことがあります。 「努力して実績を出しても、それだけでは不十分と評価される」「長年勤務してもなかなか給料が上がらない」という状況では、仕事に対するモチベーションも下がってしまうでしょう。 特に40代は、子供の養育費や住宅ローンなどで経済的負担が増加する年代なので、昇給昇進に納得できないと将来の不安につながりやすいです。 過剰な業務や責任による疲労 40代は仕事の責任や任される役割が増え、それに伴い業務量も増加しやすいです。 責任増加によるプレッシャー、そして業務量増加による残業や休日出勤なども増える傾向にあり、心身ともに疲労が蓄積して仕事を辞めたくなるケースもあります。 また、40代はまだまだ育児で忙しかったり、親の介護が始まったりと、自身を取り巻く状況にも変化が起こりやすいです。その影響により、過剰な業務や責任が伴う職場では働きにくさを感じることがあります。 健康維持が難しい 残業や休日出勤などが多いハードワークでも、20~30代の頃なら乗り切れたかもしれません。 しかし、40代は体力の衰えを感じやすく、ライフワークバランスを欠いた働き方をするとかえってパフォーマンスが落ちてしまう場合があります。 また、40代以降は男女ともに更年期の症状を感じ始める時期です。疲れやすさや集中力の低下を感じ、このような体調の変化からキャリアの見直しを行う人も少なくありません。 キャリアの停滞を感じる 40代は既に十分な業務経験を積んでいるからこそ、新しい刺激や成長実感を得にくいです。一定の「やり切った感」があるため、今後の目標や方向性を見失ってしまい、自身のキャリアが停滞しているように感じる人が増えます。 また、組織構造から今後の昇進の行き先が見え、「自分にはもう進むべきキャリアがない」と感じる場合も多いです。 キャリアの停滞を感じると、仕事のモチベーションややりがいも下がるため、「何だか仕事がつまらない」「仕事を辞めたい」という思いが強くなるでしょう。 仕事を辞めたい40代が確認すべきこと 40代で「仕事を辞めたい」と思ったら、確認すべきことや考えるべきことがたくさんあります。一つ一つの課題に向き合い、自身が置かれている状況を把握しましょう。 心身の調子を崩していないか 退職は、次の職場が決まったタイミングで行うのがベストですが例外もあります。ストレスによって心身に不調が見られる場合は、これ以上状態が悪化する前に辞めたほうが良いこともあります。 ただし、休職で回復できる可能性がある場合は、これらの制度を利用してみるのも一つの手です。 心身の不調を無視して無理を続けると、深刻な疾患を引き起こす恐れもあります。そのため、まずは心と体の状態をチェックし、健康を最優先に考えましょう。 今の職場での状況改善は見込めないか 今の職場への不満や問題だと思う要素については、改善できないか働きかけてみるのも大切です。自身の行動によって職場状況が改善されれば、今の仕事を辞めることなく気持ちよく働き続けられる可能性があります。 また、たとえ退職する場合でも、やれるだけのことをやったうえでの退職は後悔しにくいです。まずは現状の問題を明確化し、改善の可能性を検討してみてください。 退職が本当に悩み解決につながるのか 退職という選択が、「仕事を辞めたい」という思いの解決策に必ずしもなるとは限りません。 たとえば「やりがいがない」という理由で仕事を辞める場合、自分が何にやりがいを感じるのかを明確にしておかなくては、次の職場でも同じ悩みにぶつかる可能性があります。 そのため、仕事を辞めたいと思う原因を徹底的に深掘りして、退職が本当に悩みの根本的解決になるのかをよく考えるのが重要です。感情的にならず、客観的事実や情報に基づいて冷静な判断をしましょう。 自分の市場価値はどれくらいか 40代で「仕事を辞めたい」と思ったら、今の自分の市場価値も要チェックです。市場価値を正確に把握することで、自身の強みを客観的に理解できます。また、今の自分に足りない部分から、伸ばすべきスキルや必要な経験が具体的にわかるケースもあるでしょう。 市場価値の把握は、キャリアを主体的にコントロールするための第一歩といえます。 辞めても経済的に苦しくならないか 次の職場を決めずに仕事を辞めれば、当然収入が途絶えます。また、たとえ次の職場を決めてから退職したとしても、最初から今と同じだけの給料が得られるわけではありません。 経済状況が変わると自分だけでなく家族の生活にも影響が出る可能性があるため、リアルな家計状況を踏まえたうえでお金のこともよく確認しておきましょう。 40代で仕事を辞める場合、一般的には生活費の3〜6ヶ月分の貯金が最低限必要だといわれています。 「仕事辞めたい」と感じる40代がやるべきこと7選 ここでは、「仕事を辞めたい」と感じる40代が退職前にやるべきことを7つ紹介します。納得のいく形で次のステップに進めるよう、一つずつ行動を進めてみましょう。 有給や休職制度を活用する 今抱えている「仕事辞めたい」という感情は、一時の心身の疲れからきている可能性もゼロではありません。そのためまずは、有給休暇を利用してリフレッシュを試みましょう。仕事から完全に離れてのんびり過ごすだけで、疲労や悩みが軽減して「辞めたい」と思わなくなる可能性があります。 また、心身の消耗が激しく、有給の数日間だけでは休養が不十分だと感じる場合は、休職制度を利用してみるのも一つの方法です。 抱えているモヤモヤを整理する 今の職場に対する不満、嫌だと感じることなどを具体的に書き出し、抱えているモヤモヤや自分が置かれている状況を整理しましょう。 これは、冷静さを取り戻して自分を客観視するための作業です。40代の退職で失敗しないためには、「辞めたい」と思った場面で感情的にならず常に冷静でいなくてはいけません。 冷静さを維持できれば、話し合いや手続きが滞りなく進んで今の会社を円満退職できる可能性が高まりますし、客観的視点で次の会社を選べるので転職にも成功しやすくなります。 上司や同僚に相談する 今の気持ちや悩みを、上司・同僚・人事などに相談してみるのも重要です。相談する際は愚痴や不満を言いすぎないように注意し、事実と意思ベースで話を進めましょう。 問題に感じていることを打ち明けると、第三者視点のアドバイスが聞けたり、会社側から改善提案やサポートが得られたりする可能性があります。 また、本当に退職することになった場合でも、事前に相談していると話が円滑に進みやすく、退職トラブルに発展しにくいです。 キャリアプランを再設定する 40代は自身のキャリアに行き詰まり感を感じやすく、退職を検討するときには働く目的や目標を見失っているケースが多いです。 今の会社を本当に辞めるにせよ転職するにせよ、このタイミングで「今後どうなりたいのか」を考え、キャリアプランを再設定しましょう。キャリアプランが明確になることで、「退職か転職か」という悩みの答えが見つかる場合もあります。 5年後、10年後どうなっていたいのかを具体的に想像し、そのうえで必要なスキルや今やるべきことを考えてみてください。 部署異動や転勤を検討する 会社や仕事そのものに大きな不満がない場合は、部署異動・転勤を検討してみるのもおすすめです。 部署異動や転勤ができれば、今の会社に留まりつつ新しい環境で働けます。特に、「仕事を辞めたい」と思う原因が今の職場独自の問題である場合、異動や転勤をすることで状況が好転しやすいです。 ただし、部署異動や転勤の希望は、出せば必ず通るというものではないため会社の状況もよく見極めましょう。 退職のシミュレーションや転職活動をしてみる 「今の仕事を辞めたあと」をイメージして、日常生活や転職先での働き方、お金のことなどを具体的にシミュレーションしておくのも大切です。 高い精度でシミュレーションできれば、経済的な計画を立てやすく、退職や転職に伴う複雑な手続きにもスムーズに対応できます。 また、並行して転職活動も始めていきましょう。「本当に辞めるかまだ決心がついていない」という場合でも、求人を見て他社を知ることで冷静な判断がしやすくなります。 キャリアコンサルティングを受ける 「仕事辞めたい!」と思っても、40代での退職はそう簡単に決心がつくものではありません。 お金の心配はもちろん、「辞めて後悔しないか」「転職に成功できるのか」という不安も膨らみやすく、なかなか答えを見つけられない40代も多いのではないでしょうか。 そんなときは、キャリアコンサルティングでプロのサポートを受けながら、じっくり自分と向き合うのがおすすめです。 キャリアコンサルティングでは、転職・退職だけに縛られない幅広い選択肢を一緒に検討してもらえます。たくさんの可能性の中から「本当に納得できる結論」にたどりつく足がかりとなるでしょう。 仕事を辞めたい40代に重要なのは、心の整理と事前の計画 丁寧に自分の気持ちを整理し、現実的な計画を立てて行動を積み重ねるのが、40代以降のキャリアを切り開くポイントです。40代で「仕事辞めたい」と感じたときは、その感情と正面から向き合い、自分のキャリアを見直してみましょう。 キャリア・コンサルティング・ラボでは、1回から気軽に悩みを相談できます。自己分析やキャリアの棚卸し、キャリアプランの設定も、プロと一緒ならよりスムーズにできるでしょう。 キャリアコンサルティングを有効活用しながら、自分らしい豊かなキャリアの実現を目指してください!

